1位を夢見ないで2位死守します~
よろしくお願いいたしますです
木綿のお問合せが増えています。
自宅で洗える天然素材、というところが一番の魅力でしょうか。
季節を問わず単衣でよい、というのも温暖化に則してると思います。
保湿、保温に優れ 濡れるほど強度を増すので洗濯が容易です。
アルカリに強いので藍染めとの相性が良いので藍絣が発展しました。
木綿は 産地、織り方により風合いが全く違うし
価格も 1万円以下から100万越えまで多彩です。
なので ご自分にあった木綿を探すのが大切です。
木綿は、延暦18年(799年)に
三河に漂着した外国船が伝えたとされていますが、
この時は、伝来した木綿の種子をまいてもうまく育ちませんでした。
鎌倉時代、室町時代には、国産の木綿がなく、全て舶来物の木綿製品が輸入されていました。
木綿の布はとても貴重な品であったのです。
15世紀の後半になると朝鮮から綿布が大量に輸入されるようになり、
16世紀には明からの綿布(唐木綿)の輸入が加わって、上流階級では木綿の着用が流行しました。
さらに南蛮貿易によって東南アジア諸国から縞木綿がもたらされ、
その中にはインド産のサントメ縞(唐桟)や
ベンガラ縞、セイラス縞などが含まれていました。
これらは近世日本の模様染や縞織の発達に大きな影響を与えたのです。
国内で木綿の栽培が始まるのは16世紀初め頃。
木綿は丈夫で耐久性にすぐれているため、戦国時代の武士たちは幕や旗差物、袴などの衣料や
船の帆などにも使われました。
需要の増加にともなって三河などで木綿栽培がはじまり、
またたく間に近畿・関東地方でも栽培されるようなったのです。
江戸初期には農民の着物も麻から木綿へと転換し、
江戸中期になるとほとんど全国的に木綿織物が生産されるようになって、
各地で特色のある銘柄木綿が生産されました。
暖かい地方を好むので東北には少なく また 絶えてしまった産地も多いのですが
山陰地方を中心に 出雲絣、倉吉絣、弓浜絣、広瀬絣、備後絣。
九州には 久留米絣、薩摩絣。
四国には 阿波しじら、土佐木綿、伊予絣。
兵庫の丹波布。愛知には知多木綿、松坂木綿、
静岡の遠州木綿、千葉の館山唐桟・・・・生活に密着した木綿たちがあります。
また工芸的作品として作家さんの手による
手紡ぎ糸、手括り絣、本藍染め草木染によるこだわりの作品も。
久しぶりに木綿を紹介しましょう。
弓浜絣の福良雀の帯です。
柄はたっぷり。太鼓裏以外はずーっと竹と福良雀。かわいいです^^
黄八丈に合わせたいな、と思ったのですが今手持ちに黄八丈がなかったので。。
玉虫正直さんのあごろ織に合わせました。
もちろん木綿に乗せてもよいので こんな薩摩木綿とかにも。
最後までお読み頂きありがとうございます。
下の「着物・和装・業者」というバナーか、「にほんブログ村」という文字をクリックして下さい。ブログ村ランキングページへ飛びますので、そうしたら1ポイント入ります。(inポイント)次にブログ村の「きものがたり」じざいやブログのところをクリックしてこのページに戻りますと、outポイントが付きます。










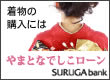 やまとなでしこローン
やまとなでしこローン
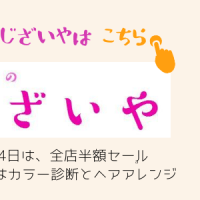











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます