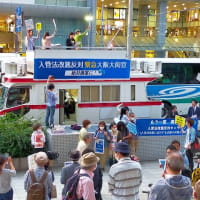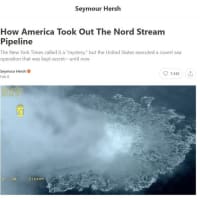1842年8月29日は何の日かご存じでしょうか。1840年6月28日、イギリスは中国(清)に対してアヘン戦争を仕掛けました。中国がイギリスのアヘンを拒絶したという理由で。8月29日はこの戦争が中国の敗北に終わって、屈辱的な香港島の割譲、賠償金の支払いなどを含む南京条約を結ばされた日です。帝国主義列強による州国の植民地化、中国が列強諸国に侵略され、半植民地状態にされていく状況はここから始まりました。
紅茶の返礼はアヘン──それが大英帝国のやり方
イギリスでは18世紀末に産業革命が始まりました。蒸気機関と機械化により、まずは紡績の分野で、以前よりずっとわずかな労働力で多くの製品が生み出されるようになりました。
これで人々の暮らしは楽になったでしょうか。いいえ。機械は24時間動くので、夜勤や長時間労働が当たり前のようになりました。そして、これまで成人の熟練労働者を必要としていた仕事に、未熟練労働者や子どもが導入されるようになり、熟練労働者は職を失っていきました。これまでなら父親が働いて家族の暮らしを支えていたところ、父親は失業し、その代わりに妻子がみんな働いてようやく父親が得ていた賃金を手にするということにもなりました。労働者の地位も不安定で、雇用は景気の浮沈次第でした。
このような産業構造の変化で、憂さを晴らすために庶民の間では深酒に浸る者も増えていきました。そうした中、酒よりも紅茶の方が体によいと、紅茶を飲む習慣を庶民の間に広めようという動きが起こりました。1837年に即位したヴィクトリア女王も率先してそのキャンペーンに努めました。かくして元々上流階級の贅沢な嗜好品であった紅茶が庶民の間にも広がっていきました。そして、この紅茶は主として中国からの輸入に頼っていました。
産業革命によって、イギリスでは自国で消費しきれないほどの大量の織物が生産されていきました。そして、それを売りさばくために、飽くことを知らない貪欲さで世界中に販路を求めていきました。
イギリスは植民地のインドに対して、工場で作った安価な綿製品を大量に売りつけ、手作業を主としていた現地の綿産業に壊滅的な打撃を与えました。
膨大な人口を抱える中国に対してもイギリスは狙いをつけていました。しかし、自前で織物を生産している中国にとって、イギリスの綿製品はそこまで必要のないものでした。逆に紅茶ブームとなったイギリスは中国の茶を大量購入せざるをえなくなり、その支払いのために、銀(当時の主要な貿易通貨)がどんどん中国に流れていきました。
そこでイギリスは卑劣な手段を考えつきました。綿産業が衰退したインドでケシの栽培を奨励し、そこから生み出されるアヘンを中国に密輸入させたのです。アヘンは強い依存性のある麻薬です。ひとたび吸引の習慣が身につけば、禁断症状にさいなまれ、やめるにやめられなくなってしまいます。心身を蝕むことがわかっていても、入手のためにお金を惜しまなくなります。こうして、イギリスはマフィア顔負けのやり方で、中国から銀を手に入れていきました。
中国ではアヘン中毒者の増加に加えて、銀の流出による国内の経済の混乱がおきました。こうした状況を見過ごすわけにはいかないと、皇帝は、アヘン追放の急先鋒であった林則徐を大臣に取り立て、彼にアヘンの厳格な取り締まりを命じました。彼は商人たちにアヘン持込禁止の誓約書を要求し、それを拒否したイギリス商人のアヘンを没収し処分しました。
中国にとっては、人々の生命と健康、財産、そして主権を守るための当然の処置であったわけですが、イギリスはこれに逆恨みをし、1839年10月1日に、閣議で中国出兵を決定しました。 翌年1月、ヴィクトリア女王は議会で、中国で起こった出来事は「臣民の利益と王室の尊厳に関わる事件」だとする演説をおこないました。一方、野党からはアヘンの保護のための戦争は「不義の戦争」だという批判もありましたが、結局は僅差で出兵費用が承認されてしまいました。
そして、6月28日、派遣された軍隊が広州沖に現れました。これがアヘン戦争の始まりです。 イギリスの近代化された艦隊に対して、中国の船は昔ながらの木造帆船でした。海軍のこの差が戦争の帰趨を分けました。中国は沿岸部の都市を次々と占領され、南京にまで迫られ、政府は戦意を失いました。
この結果、1842年に結ばれた南京条約で、中国は莫大な賠償金の支払い、従来の許可制の貿易制度の廃止、貿易港の増加などを約束させられました。香港島がイギリスに割譲されたのも、この条約の結果でした。 その翌年、さらに治外法権などの不平等条項が追加されました。フランスやアメリカも、どさくさに紛れてイギリスと同じ不平等条約を中国に押しつけました。
このアヘン戦争以来、中国が列強諸国の半植民地状態となっていく長い苦難の時代が始まりました。
勝てる相手になら、いちゃもんをつけてみる
南京条約で多くの権益を獲得したイギリスですが、それだけでは満足せず、さらなる戦利品を得るために武力行使の準備をしていました。
そんな中、1856年10月8日、中国の役人が中国船アロー号を海賊船の嫌疑で臨検し、乗務員を逮捕するという事件が起きました。アロー号は以前はイギリス船籍の船でしたが、この時点でその期限は終了していました。にもかかわらず、イギリスはこの臨検が不当であり、掲げられていた(?)英国旗が毀損されたという言いがかりをつけました。そして、10月23日に英海軍による軍事行動が広州で始まりました。
イギリスは本格的な軍隊を派遣し、さらに、フランスにも同調を求めました。この年の2月29日にはフランス人宣教師が逮捕・処刑されたという事件があり、フランスはこれを理由としてイギリスと連合軍を結成しました。
これはアロー戦争、あるいは第二次アヘン戦争とも呼ばれています。英仏連合軍の猛攻に清はまたしても敗北し、中国は1858年に天津条約を、1860年に北京条約を締結させられました。
これらの条約によって、香港島の対岸の九龍半島南部をもイギリスに割譲することになりました。さらには仲介に入ったロシアにも沿海州の領有を認めさせられました。中国にとっては、まさに踏んだり蹴ったりの状況です。
とはいえ対立物を生み出すのが歴史の鉄則──中国革命のはじまり太平天国
アヘン戦争後の状況で最も苦しむことになったのは、下層の民衆でした。清の政府は戦費と賠償金の支払いのため、人々に重税をかけました。銀不足による銀の高騰も人々を苦しめました。税金は銀で納めなければならないという決まりがあったからです。
そんな中、洪秀全という人物がキリスト教の影響を受け、拝上帝会という組織を立ち上げました。
中国におけるキリスト教の宣教師は、多くの場合、欧米の支配の手先としての役割を果たし、民衆から嫌われていました。その一方で、神の前の平等を説く思想は、洪秀全のような清のあり方に不満を抱く者の心をつかみ、やがては貧しく虐げられた人々を行動に駆り立てる大きな力となりました。
似たようなことが16世紀のドイツで起こりました。1624年から25年にかけて30万人もの貧しい農民たちが領主に対して反乱を起こしました。それは「ドイツ農民戦争」と呼ばれ、この主要な指導者は宗教改革者のトマス・ミュンツァーでした。
洪秀全は地上の天国を目指し、男女平等の土地分配や富の共有など画期的な政策を掲げて、1850年に清に対する武装蜂起を開始しました。
最初に集まったのは1万人ほどの男女の信者でしたが、清の軍隊に勝利を重ねていきます。1851年に「太平天国」建国を宣言し、各地を転々としながら人々を結集し、1853年には南京を占領して太平天国の首都としました。そこには数百万人もの人々が集まりました。
当初、欧米列強は太平天国に対して中立の立場をとっていました。それは太平天国がキリスト教の集団であると見なしたこと、そして内乱によって清の力が弱まることは中国支配を進める上で、好都合だと考えたからでした。ところが、太平天国の指導者は、アロー戦争の後に結ばれた条約を批判し出しました。ここから、欧米列強は、太平天国を中国支配の障害物と認識し、キリスト教とは無関係の“邪教”の徒であると評価を変えました。 清の政府と欧米列強の利害は一致し、その連合軍によって、太平天国は1864年に壊滅させられました。しかし、14年にわたって中国の南半分に大きな影響を与えた太平天国に関する記憶は、直接体験した人はもちろん、後の世代の人々の間にもずっと残ることになります。
辛亥革命の中心人物、中華民国「建国の父」孫文は、太平天国壊滅から2年後に生まれましたが、太平天国を描いた文学で育ち、その物語に大いに傾倒しました。
後に中国人民解放軍の元帥となる朱徳も同様です。彼は、壊滅から22年後に貧しい農民の家に生まれたのですが、彼が幼い頃、村を訪れる旅の職人たちの中に太平軍の兵士だった者がいました。その職人は、太平天国が貧民解放のためにいかに正々堂々と闘ったか、清朝や欧米列強がいかに卑劣であったか、そして、殺されたといわれる指導者は実は生き延びていた、あるいは幽霊となって今もさまよい歩いている、というような伝説を、せがまれるままに語ったのでした。そのことは幼い朱徳の心に深い印象を刻みつけ、後に八路軍(人民解放軍の前身)を組織した時も、民衆を大切にするその規範を軍の規律に取り入れたのでした。
孫文や朱徳の体験は、ほんの一例にすぎません。中国の人口の80%以上を占める大衆は、太平天国の人々を英雄とたたえる、このような民間伝承や文学に親しんだのでした。それは、太平天国を無頼の徒とする清朝政府の公式見解とは真逆の観点でした。
中国が、辛亥革命による中華民国の成立を経て、さらに中華人民共和国の建国に至った原動力の一つとして、太平天国は今もなお生き続けています。