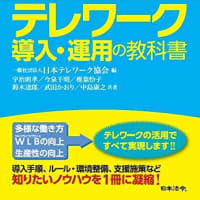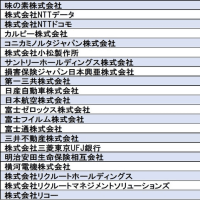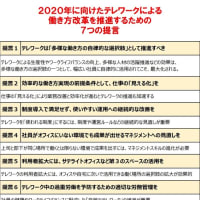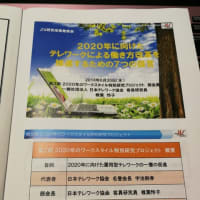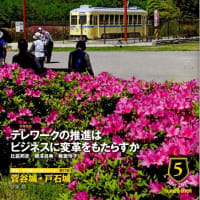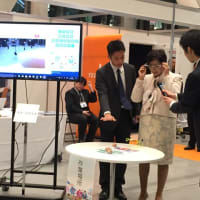今年も残すところあと2ヶ月となりました。
2018年の新年会の予定も入り始め、年の瀬感を味わっています。
さて、先日発行された内閣府のメールマガジンにコラムを掲載していただきました。
このような機会をいただけるとは、大変ありがたいことです。
自分自身、外部サービスをもっと上手に取り入れたいと思いながら書きました。
----------------------------------------------------------------
◆◇カエル!ジャパン通信 Vol.97◆◇
2017 年 10月 31日 内閣府 仕事と生活の調和推進室 発行
濃い緑色、みずみずしい生命力を放っていた木々の葉っぱも、燃えるような紅い色に衣替え。私たちの目を楽しませてくれますね。色彩心理学によると、紅=赤は明るさや強い行動力を、一方、日本人が1番好きな色と言われる青は清潔さや誠実さを連想させるのだそうです。
さて、企業理念の象徴であるロゴマーク。実はこの赤と青の2色で全体の8割を占めるとか。色に込めた企業理念。実現するには、企業を支える社員のワーク・ライフ・バランスに対する思いやりは欠かせませんね。
今回のコラムの寄稿者は、働き方コンサルタントであり、テレワークの研究者、キャリアカウンセラー、女子大の非常勤講師として活動している椎葉怜子さん。やりがいのある仕事と家庭の両立のための提言をお寄せいただきました。
-----------------------------------------------------------------
---■◇コラム◇■---
やりがいのある仕事と家庭の両立は本当に可能か
/株式会社ルシーダ 代表取締役社長/一般社団法人日本テレワーク協会
客員研究員 椎葉怜子
子どもができると生活が激変し、時間制約のある働き方が始まります。家にいても朝晩の「6時から9時」は、子どもの食事や着替えのお世話、保育園の送迎、食器洗いや洗濯などの家事で息をつく暇もありません。特に、子どもが小さいうちは体調を崩して保育園を休むことが多く、育児と仕事の両立は毎日が綱渡りです。
キャリアカウンセリングの現場では、ワーキングマザーの方々から「両立の苦労をこんなにしてまで今の仕事に続ける価値があるだろうか?」、「時間制約がある中、どうやったらキャリアアップできるだろうか?」という相談を受けます。育児と仕事をかろうじて両立できたとしても、働き方に悩みを抱えるワーキングマザーは少なくありません。
やりがいのある仕事と家庭を両立するには、今までの働き方を子育てに合わせて大きく見直したり、会社の両立支援制度や自治体、民間企業のサービスを活用したりするなど、様々な工夫やサポートが必要です。最近の傾向として、家事代行サービス(お惣菜づくり・掃除など)や育児サポート(ベビーシッター・病児保育など)を上手に取り入れて、仕事や子どもとの「時間」を捻出するワーキングマザーが増えているように感じます。
こうした取組に加え、男性も早く帰宅して妻と一緒に育児や家事を担う「男性の家庭進出」や通勤や移動時間を有効に活用できるテレワークの普及がポイントになります。家事代行や育児サポートサービスを活用できたとしても、男性の長時間労働が変わらない限り、女性への家事・育児の偏りが解決しないからです。企業のテレワーク導入率は16.2%(2015年)にとどまります。テレワークの利用を育児介護中の社員に限定する企業が多くみられますが、働き方改革を推進するためには幅広い社員への適用が必要です。
より多くの女性がやりがいのある仕事と家庭を両立できるようになるには、個人や家庭単位での努力のほかに、社会全体での働き方改革の取組が欠かせません。働き方改革が実現すれば、生産性の向上や多様で柔軟な働き方が可能になるといわれています。育児や介護などのライフイベントを迎えても、やりがいをもって働き続けられる社会を目指しましょう。
----------------------------------------------------------------
メルマガ全文は こちら
2018年の新年会の予定も入り始め、年の瀬感を味わっています。
さて、先日発行された内閣府のメールマガジンにコラムを掲載していただきました。
このような機会をいただけるとは、大変ありがたいことです。
自分自身、外部サービスをもっと上手に取り入れたいと思いながら書きました。
----------------------------------------------------------------
◆◇カエル!ジャパン通信 Vol.97◆◇
2017 年 10月 31日 内閣府 仕事と生活の調和推進室 発行
濃い緑色、みずみずしい生命力を放っていた木々の葉っぱも、燃えるような紅い色に衣替え。私たちの目を楽しませてくれますね。色彩心理学によると、紅=赤は明るさや強い行動力を、一方、日本人が1番好きな色と言われる青は清潔さや誠実さを連想させるのだそうです。
さて、企業理念の象徴であるロゴマーク。実はこの赤と青の2色で全体の8割を占めるとか。色に込めた企業理念。実現するには、企業を支える社員のワーク・ライフ・バランスに対する思いやりは欠かせませんね。
今回のコラムの寄稿者は、働き方コンサルタントであり、テレワークの研究者、キャリアカウンセラー、女子大の非常勤講師として活動している椎葉怜子さん。やりがいのある仕事と家庭の両立のための提言をお寄せいただきました。
-----------------------------------------------------------------
---■◇コラム◇■---
やりがいのある仕事と家庭の両立は本当に可能か
/株式会社ルシーダ 代表取締役社長/一般社団法人日本テレワーク協会
客員研究員 椎葉怜子
子どもができると生活が激変し、時間制約のある働き方が始まります。家にいても朝晩の「6時から9時」は、子どもの食事や着替えのお世話、保育園の送迎、食器洗いや洗濯などの家事で息をつく暇もありません。特に、子どもが小さいうちは体調を崩して保育園を休むことが多く、育児と仕事の両立は毎日が綱渡りです。
キャリアカウンセリングの現場では、ワーキングマザーの方々から「両立の苦労をこんなにしてまで今の仕事に続ける価値があるだろうか?」、「時間制約がある中、どうやったらキャリアアップできるだろうか?」という相談を受けます。育児と仕事をかろうじて両立できたとしても、働き方に悩みを抱えるワーキングマザーは少なくありません。
やりがいのある仕事と家庭を両立するには、今までの働き方を子育てに合わせて大きく見直したり、会社の両立支援制度や自治体、民間企業のサービスを活用したりするなど、様々な工夫やサポートが必要です。最近の傾向として、家事代行サービス(お惣菜づくり・掃除など)や育児サポート(ベビーシッター・病児保育など)を上手に取り入れて、仕事や子どもとの「時間」を捻出するワーキングマザーが増えているように感じます。
こうした取組に加え、男性も早く帰宅して妻と一緒に育児や家事を担う「男性の家庭進出」や通勤や移動時間を有効に活用できるテレワークの普及がポイントになります。家事代行や育児サポートサービスを活用できたとしても、男性の長時間労働が変わらない限り、女性への家事・育児の偏りが解決しないからです。企業のテレワーク導入率は16.2%(2015年)にとどまります。テレワークの利用を育児介護中の社員に限定する企業が多くみられますが、働き方改革を推進するためには幅広い社員への適用が必要です。
より多くの女性がやりがいのある仕事と家庭を両立できるようになるには、個人や家庭単位での努力のほかに、社会全体での働き方改革の取組が欠かせません。働き方改革が実現すれば、生産性の向上や多様で柔軟な働き方が可能になるといわれています。育児や介護などのライフイベントを迎えても、やりがいをもって働き続けられる社会を目指しましょう。
----------------------------------------------------------------
メルマガ全文は こちら