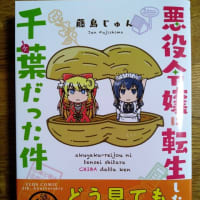新田次郎著。
実はこの本を読み始めて2か月近くなる。
もともと私の読書は、電車の中で読むことが多い。
しかし電車に乗るのは、平日1日20分間だ。
ところがこの本、いつも読んでいる小説よりも行間が狭いらしく、電車内で読むと酔ってしまう。
そのため、1日5分くらいしか読めなかったり、全く開けない日も多かった。
話は面白いのに全然進まない…。
そこで今日、思いっきり読んでしまおうと思いついた。
話は、明治40年、主人公・柴崎芳太郎氏が劔岳山頂に三角点設置をする内容だ。
明治40年とは、1907年のことだ。
NHK朝の連続テレビ小説「花子とアン」の現在放映しているシーンくらいの時代だ。
今、私は登山を楽しんでいるが、それはゴアテックスやビブラム、シャーミス、ジオラインなどの素晴らしい高性能ギアのおかげだ。
明治40年というは100年ちょっと前なのだけれど、まだ化学繊維が開発されていない。
したがってテントやウェアも綿製品が中心だ。
ゴアテックスなんてないから、天幕の内側に桐油紙を張って雨をしのいだという。
測量の記録も、PCどころか電卓もないので紙に書いたものばかりだ。
江戸時代、伊能忠敬が精巧な日本地図を作り上げたとは言われているが、明治40年にはまだ立山周辺は地図の空白地帯があったのだ。
レジャーとしての登山は地図が無ければできない。
登山道や道標があれば登れるには登れるけれど、先人がその整備をしていなければ、そもそも地図なし登山なんてできない。
私は地図が好きな人間だ。
小学生の時、初めて手にした地図帳が好きだったこともある。
行ったことが無い場所でも地図帳で見れば、その地理が何となく知ることができたからだ。
わくわく感のある資料の1つといえよう。
その地図1つ1つが誰かが測量したものを元に作られているのだと思うと、それにロマンを感じてしまうという感じだ。
そのロマンを「劔岳点の記」に感じてしまうのだ。
もっとも新田次郎氏は、富士山レーダー建設責任者としての公務員の側面の方も大変ロマンを感じる。