随意契約については、芽室町は今のところホームページでの公開は、していませんが、
行政の透明性確保の為には欠かすことができない大事な事だと考えます。
役場内部では、監査があり監査委員には、資料提供しているようです。
キチンと情報開示できる体制は整っているのですから、ホームページで公開すべきと考えます。
データをホームページに掲載するのに金も手間もそんなにかかりらないと思います。
http://zuikei.seesaa.net/article/441142671.html?seesaa_related=category
解りやすい解説がすばらしいので、ここから引用
官公庁の運営財源は国民や市民からの税金で賄われており、その使い道は常に公開し、使い方について説明責任が求められている。特に契約手続きについては、官公庁が国民などの貴重な税金を使い特定の企業と契約するわけだから、何故その企業と契約するのかを客観的に説明する必要がある。その説明資料として随意契約理由書が求められている。
価格競争を原則とする一般競争入札であれば、各社の入札書のうち一番安価な入札金額を提示した企業と契約するのだから、選定理由書は必要ない。あえて選定理由を書けと言われても、「一番安価だから」という、官公庁の会計法令(契約手続き)の基本原則によるものであり、説明するまでもないことである。契約関係書類に綴られている入札公告や各社の入札書を見れば一目瞭然である。
随意契約理由書が必要な理由として、次の規定を見てみよう。予決令第102条の4第3号である。この規定が随意契約の代表的な根拠規定である。
第百二条の四
三 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。
この条文を詳しく考えよう。
「契約の性質若しくは目的」
性質と目的とは分けて考える必要はなく、契約の内容と考える。
「競争を許さない場合」この部分が重要になるので、詳しく解説する。
「競争が出来ない場合」でなく「競争を許さない場合」と表現されていることに注意が必要だ。国語の授業的な基本的な言葉の解釈になるが、出来る、出来ない、という言葉は自分の意思により行おうとするが、その結果、出来る、出来ないという結論になる。
一方、「許さない場合」とは、やろうとしたけど出来ないという状況ではなく、意図的に「しない、させない」という強い否定の意志が内在している。官公庁側の発注者が、契約の基本原則である競争手続きを否定するという意思が加わっているのである。
簡単に言うと、「競争を許さない場合」とは、最初から競争性を確保しない恣意的な契約手続きを行うものであり、競争を排除するのだから、それ相応の理由が必要になるということである。
逆の言い方をすれば、競争性を確保した契約手続き(同一条件で複数の企業と交渉した結果1社になった)であれば、それらの書類を保存することにより随意契約理由書は不要であることは言うまでもない。(契約予定金額によっては公告などの手続きは必須であるが)
近年では、価格競争だけでなく総合評価方式やコンペ方式(企画提案型競争)による競争も行われており、これらは当然ながら「随意契約理由書」は必要ない。結果的に一社になったわけでもなく、競争原理を導入した結果一社になったのである。
基本コンセプト
「透明入札・透明契約」制度は、従来の入札や随意契約という制度とは全く異なる制度です。官公庁などの契約を発注する側、民間企業などの契約を受注する側、双方にとって公平でオープンでありメリットのあるものです。全ての契約手続の内容を一般公開(透明化)し契約実務担当者の恣意的な発注を除外する方法です。
近年のインターネット環境の普及により可能となる手続きですが、インターネットが存在しない時代の既存の法体系を全て見直し改正する必要があります。
方法
1.インターネットのWEB上で「透明入札・透明契約」専用サイトを構築し、国や地方自治体などの官公庁の発注情報を原則として自由に掲載します。(掲載のためのルールは最小限とします。)
官公庁等の発注者側は、発注しようとする一定規模以上の契約内容をインターネット上に例外なく公開します。(例えば予定金額50万円以上の契約すべてなど)
ただし、ここで公開の方法などを細かくルール化し規定してしまうと、実際の利用が煩雑になるので、原則として自由に記載することを原則とします。また、掲載情報の中止や内容の変更も随時可能とします。
2.申込、見積金額の公開(企業名、金額、見積の積算内訳を一般公開)
受注希望企業は、WEB上で官公庁側が掲載した発注情報を見て、見積書を添付して申し込みます。内訳が記載された見積書は自動的に一般公開されます。つまり、見積(入札)の状況がリアルタイムで一般公開されます。
見積金額の内訳明細書の一般公開も義務付けます。物品購入の発注情報であれば値引率や値引額あるいはオープン価格が明確になるように、工事や製造であれば製造原価や利益相当額の諸経費などが明確に判明する形式で掲載します。実際には見積金額をWEB上に入力し、積算内訳はPDFファイルなどをアップロードします。(これはリバースオークションに似ています、オークションやせり売りなどのイメージですが、積算内訳までもが公開されます
3.契約予定者の決定
一定期間(見積の積算に必要な期間、2週間など発注者が任意に設定する。)経過後、最安値の企業が契約予定者となり、次の段階として契約審査手続きへと進みます。
4.契約公開審査
契約予定者となった企業は、発注者側、見積に参加したライバル企業からの審査を経ます。
契約審査期間(5日間程度など、契約内容によって発注者側が任意に期間設定可能とします。)を設け、この間に、発注者や参加したライバル企業は契約予定者に対して、見積金額についての疑義などをWEB上で公開し質問します。匿名ではなく実名で回答期限を設けて質問します。
契約予定者は、WEB上で公開形式で回答の義務を負います。契約予定者が期限までに回答しない場合は自動的に排除され、次順位者の企業が契約予定者になります。回答しない契約予定者はペナルティとして一定期間(3ヶ月程度)他の契約に参加できなくなります。
質問した企業は、回答を見て、納得すれば回答承諾ボタンを押さなければなりません。回答承諾を故意に行わない企業は同様に一定期間(6ヶ月など長期)参加出来ないペナルティを負います。ここは質問者の方に重い責任を課します。質問や回答に相手を中傷するような批判的な内容を行なった企業はペナルティ(1年間参加禁止)を負い、企業の評価ランクに履歴が残ります。内容が不明確などの場合は質問に対して1回のみ再質問可能とします。
「透明入札・透明契約」に参加しようとする企業は事前に簡単な審査(現在の全省庁統一資格を改良)を受け、固有のIDとパスワードを持ちWEB上で参加します。
質問数は、項目数5位内、1回のみ、あるいは文字数の制限などを発注者側で任意に設定可能とします。デフォルト設定もしておきます。
質問や回答の混乱を避けるため、回答しない企業は、説明責任を負わなかったペナルティとして一定期間、他の契約に参加出来ません。さらに、透明契約制度を用いて契約を行った企業は、契約締結後であっても後日過度の利益を得ていることが外部から指摘され、それに反証出来なかった場合は当該金額の返還義務(利息や損害賠償は含まない。)を負わせることを法律で義務付けます。遡及期間は5年間とします。
最後に発注者は、質問や回答の内容を見てから、正式発注とするか検討志、内容的に曖昧で不安があるなら契約中止を任意に選択できます。契約を中止とした理由は必要ありません。ここで明確な理由を求めてしまうと効率的な契約制度になりません。発注者は何時でも自由に中止できるようにし簡単なシステムとします。
5.契約締結手続き
契約公開審査期間経過後、自動的に正式な契約が締結されます。
以上が「透明入札・透明契約」の基本的な仕組みです。
すべてがWEB上で一般公開され、第三者が常に監視できる仕組みを構築します。会計検査院へも質問回答部分で審査を義務付ければ、「透明入札・透明契約」による契約については、その後の会計実地検査を不要とすることも可能でしょう。
「透明入札・透明契約」のメリットは、発注者側には一切業務負担がなく、参加しようとする民間企業は営業行為が不要で最小限の資格(事前登録)さえあれば自由に参加でき、適正な利益が確保された正常な契約であるかどうか、契約金額の内容までもチェック可能なことです。不当利益の排除、不当廉売の排除も可能となります。
また、大手企業などの1社に契約が集中することを防ぐために、連続入札の禁止規定も制定します。例えば、1千万円以上の契約を受注した場合は、その後、2週間程度は複数の企業が参加する他の案件に参加できないなどを規定し、広く入札参加機会を確保します。WEB上でIDと契約金額を自動監視し制限します。
「透明入札・透明契約」制度を導入すれば、全てが公開されてしまうので、談合や癒着などは物理的に不可能(というか談合や癒着の意味がなくなります。契約後であっても不当な利益は5年間の返還義務を負うのですから。)となります。発注者側も予定価格の作成や入札手続きなどの負担がなくなり、発注者にとっても受注者にとっても完全に手続きが公開され、メリットのある制度です。
インターネットが爆発的に普及・発展し、情報公開が当然のようになった現代において、昭和初期の予定価格や入札などの契約制度、会計検査院のあり方さえも見直す時期と考えています。
現行の会計法令に基づく入札や契約手続からの移行措置ですが、移行措置は不要となるように「透明入札・透明契約」を構築します。つまり、現行の制度はそのまま残し、さらに「透明入札・透明契約」も可能とするのです。両方とも利用できるようにし、「透明入札・透明契約」制度の方を使いやすい便利なものとすれば自然と現行制度を利用する人はいなくなるので、現行制度を廃止する必要もなくなります。
最後に、この「透明入札・透明契約」制度の構築で重要な課題は、専用サイトの構築、保守管理を誰が担当するか、会計法令等の改正案を誰が担当するかです。内閣府あるいは会計検査院でしょうか。この制度構築による費用効果は、現在の契約手続や入札手続きの労力を想定すれば人件費ベースで年間400億円ほど節約できます。
(参考 人件費の試算)
会計部門の公務員数(総務省資料から抜粋)
地方公務員36万人(全体280万人)全体の12%が会計部門
国家公務員 8万人 (全体64万人)全体の12%と仮定
会計部門44万人の10%=5万人が契約実務担当者として仮定
業務量が2ヶ月分削減
平均給与月額40万円(契約を担当するのはベテラン係員のため)
5万人×40万円×2ヶ月=年間400億円
(実際には2~3倍ほどになると思いますが、実数のデータがないので仮定として少なく見積もっています。)
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/tempimg/130126134344201704261406255f.pdf
都城市なぜ随意契約でなければいけないのかについて理由を市民に公開しています

京都市ホームページから
随意契約内容の公表について 京都市の随意契約のうち,次の契約を公表しています。
1 対象契約 ⑴ 契約金額が500万円以上の物品等の調達に係る契約(物件の購入,賃借,委託等)
⑵ 契約金額が250万円を超える工事請負及び測量,設計等の委託に係る契約
2 公表する内容
⑴ 件名
⑵ 契約を所管する室又は課
⑶ 契約締結日,種別及び概要(工事にあっては,工事の名称,場所,種別及び概要)
⑷ 履行期間
⑸ 契約の相手方の住所,商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称 及び代表者名)
⑹ 契約金額(税込み)
⑺ 契約内容
⑻ 随意契約の理由
⑼ 根拠法令
⑽ 契約の相手方の選定理由
3 閲覧 契約課執務室内でも閲覧に供しています。
4 公表の時期 半期ごとに取りまとめて公表します。
5 公表の期間 公表の日の翌日から起算して1年が経過する日の属する年度の末日まで











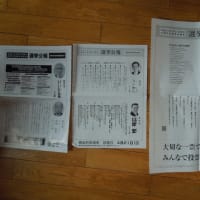

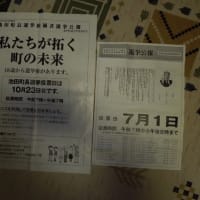

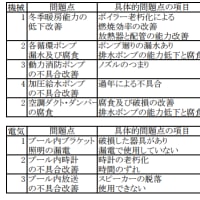
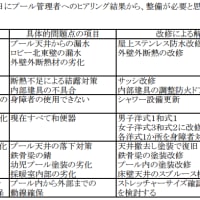
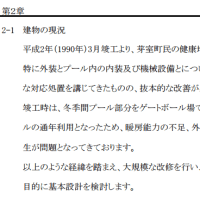


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます