http://www.kosonippon.org/project/detail.php?m_category_cd=5&m_project_cd=364 引用先
報告】「地方の工夫が国の財政を救う!」~長野県栄村、下條村現場レポート~
2004/11/24(水)更新
「三位一体改革」や「補助金3兆円の削減」という言葉がたびたびマスコミ等で取り上げられています。その多くは、国と地方との間の、お金の取り合いのような報道ぶりです。しかし問題の本質は、「補助金」の背後にある国のコントロールをいかに取り除くかです。
これまで国は、補助金や交付税をえさにして、地方をコントロールし、そして、地方はこれに依存してきました。その結果、地方はどこも同じ“金太郎飴”になり、必要のない行政運営の積み重ねで、膨大な財政赤字が積み上がりました。
しかし、その中で危機感を持って行政を運営し、お金がないからこそ工夫が生まれている村があります。この村の取り組みを紹介します。
長野県栄村
●長野県栄村~現場は改革のアイデアの宝庫!~
長野県栄村の高橋彦芳村長は市町村合併をしないことを宣言し、以来、村が持続可能な行政運営を行えるように、行政コストを削減し、ユニークな政策を行っています。
それらの政策の中で、補助金をもらわずに(国の関与なしに)行っている村独自の道路整備とは、どのような中身でどのくらいのコストで行っているのかを、栄村で現地調査しました。そして、補助事業との比較を試みました。
●村長の思い、村民の反応
<高橋彦芳村長> 
「国は農山村でも都市並みの村づくりをやれと言ってきた。そのためのカネは交付税と過疎債。これは『本物』ではないと思いながら大バカになってやってきた。しかし、官のつくる公共事業のモノサシは栄村のような山村には全く合わない。暮らしの知恵を活かしながら、栄村らしく生きていくことが必要」
<広瀬房子さん(薬局経営)>
「(栄村独自の政策によって)視察が増え、村全体が引き締まって良いと思う。若い人が少なくなって村が続いていくのか不安だけど、今は私のような高齢者にとってはとても住みやすい」
●「道直し」
国の補助を受けない村道や農道の改良事業。村の予算と受益者負担(用地費の3割、材料費の25%を集落で負担)で行い、村の臨時職員が施工します。
村道が国庫補助の対象になるには道路を2車線以上にするなどの条件がありますが、集落内の生活道路は機械除雪が行える幅(3.5m)さえ確保できれば良く、国庫補助の対象に合わせた規格にするとかえって高くつくため補助事業では行っていません。
具体的に見ると、栄村の道直しは整備距離1m当り約1.9万円。それに対し国の道路構造令・補助基準に従った場合は、建設会社へのヒアリングによると約11.1万円かかります。簡易な道路整備であれば、栄村は通常の1/6のコストで行っていることになります。補助事業で行うと50%の国庫補助がつきますが、それでも栄村独自で道路整備を行う方が負担額は1/3になるのです。
補助事業の場合、国が一律に決めることで「どんな地域、状況でも問題ない」よう基準が決められ、多くの場合過剰な仕様になり高くなってしまいます。栄村の道直しは、国が決めた基準(道路構造令)に従わなくて良いため、国や県へ報告するための設計や測量にかかる費用が不要になったり、原材料費が安くすむことが大きな原因です。特に原材料費は、道路構造令や補助基準に従った場合に比べて、栄村の道直しの方が1/14にも削減されています。
以上のことからも、車道や路肩の幅など、現場の必要性と判断、責任をもっと生かすべきだと言えます。全国でこのような工夫をすれば、税金の無駄使いが相当減るのではないでしょうか。
●「道直し」以外の栄村の創意工夫による主な事業
「田直し」:補助基準に満たない小さな田を拡大する事業。農家と村が10a当り20万円ずつ負担し、その費用の中から機械、作業員(1名)の費用を賄う(1時間8500円)。
「下駄ばきヘルパー」:村が講座を開いて160名のヘルパー資格者を作り、集落ごとに班を作って介護サービスを提供。農山村部特有のコミュニティーを生かした手法。村の雇用拡大にも寄与。
「雪害対策」:冬期間、雪害対策救助員を15名雇い高齢世帯の屋根の雪降ろしを行う。申請に基づいて民生委員が審査、無料と有料に分け村長が決定。
●最後に
栄村で行われている政策は、これまでマスコミ等で「国からのお金はなくても行政運営ができる」として取り上げられることが多くありました。しかし実状は補助金をもらうことのできない事業、あるいはもらうとむしろ高くつく事業を、いかにして低コストで行うかを追求して生まれたものであり、冒頭にも述べたように現行制度の中で「国のコントロール付きの補助金は無駄も多いし、要らないが、お金は必要」なのです。このことに留意し、今後このような努力している自治体が報われる仕組みを早急に作らなければなりません。
---------------------------------------------------------------------
長野県下條村
●「建設資材支給事業」
栄村の道直しと同様、国の補助を受けない村道や農道の改良事業のことを言います。村は整備に必要な材料を支給するだけで、実際の施工は集落の住民が行います。
この事業は国庫補助を受けず、国からの関与は一切受けていません。国の関与を受けて行った場合とは、事業規模や周辺整備の違いがあり一概に比較はできないものの、結果として原材料費は栄村の道直しと同規模の1/8に抑えられ、集落の住民がすべての施工を行うため、人件費や舗装代は無料。総事業費では1/32になります。
●下條村の創意工夫による主な事業
栄村と同じく合併をしないことを決めた下條村では、道路の建設資材支給事業だけでなく、様々な行政のスリム化政策を行い、実績をあげています。
○職員改革
役場の業務が忙しい12月に、職員全員を交代でホームセンターでの研修を実施。民間企業の方が更に忙しいことを実感させる。また、職員の嘱託化、新規雇用カット、係長制廃止、3保育所の統合など行政のスリム化を進め、人口当たりの職員割合が全国平均に比べて4割も少ない。
○若年対策
若者向けの安い村営住宅の建設、中学生までの医療費無料化を実施。このことが一因となって、村の人口が平成2年に比べて300人以上増加、生涯出生率は1.97で県内第1位(全国の出生率は1.36)、若年人口率が17.3%で県内第3位。
○合併処理浄化槽
汚水処理において、大部分の自治体が公共下水か農業集落排水を選んでいた時代に、下條村はコストの面を考えて合併処理浄化槽を選択。結果、公共下水・農業集落排水で想定した事業費の約1/6に削減。汚水処理の人口普及率は全国で76%のところ、下條村は96%まで整備。合併処理浄化槽の問題点とされていた水質についても、これまで苦情は1度も上がっていない。なお、全国的な汚水処理の種類別人口普及率は、公共下水が66%、合併処理浄化槽が8%、農業集落排水が2%。
○財政の健全化
最も厳しい前提条件に基づいて財政見通しを平成34年度まで試算。その状況下で行政運営できるよう徹底した財政の緊縮を行い、財政構造の長期安定性を示す「起債制限比率」が1.7%で県内1位(全国平均は8.7%)。また平成15年度の基金残高が22.9億円。当初予定より3.7億円多く、1人当りの基金残高は約55万円(全国平均は30万円)。
※起債制限比率:財政の中に占める、地方交付税措置されていない公債(純粋な借金)の割合。15%以上で警告、20%以上で一般単独事業債と厚生福祉施設事業債の発行停止、30%以上で一般事業債の発行が停止
●伊藤喜平 下條村長 
「これまで行政にはコスト意識があまりにもなさ過ぎた。今回の合併論議は行政が自分の市町村の状況を真剣に考えるようになったという意味で非常にプラスになった。国の借金を返すのに地方の財政が減るのは仕方ない。その代わり、国は地方の細かいことを決めるよりも、どのくらい減るのかなど大枠だけを決めていれば良い」
●最後に
「平成の大合併」により、市町村の数はこの11月1日で3000を下回った。ともに人口が5000人未満の栄村、下條村は国の方針に従わなかった「造反組」と言えるが、両村のヒアリングを通じて、小さな村でも生き残っていく術は十分にあり、地方の財政危機の観点だけでの合併論は誤っていることを実感した。
今後は、国の方針に従わないから「切る」のではなく、両村で行われている創意工夫を更に生かすことのできる環境整備が必要である。











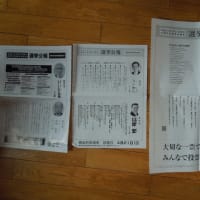

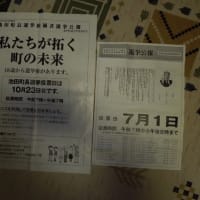

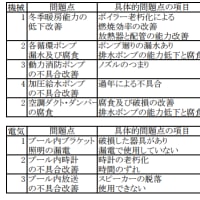
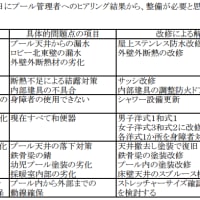
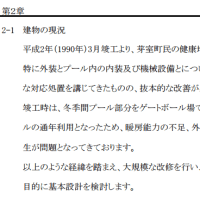


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます