2017年8月26日投稿
紋別市の上渚滑地区に、自治体が建設費の助成を行う事でセイコーマートを誘致する事を決めた。
コンビニ出店には2000人程度の商圏人口が必要
出店費用約1億のうち3500万を補助
自治体の支援次第では商圏人口400人規模のエリアでも出店可能らしい

http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/docs/2016081800017/
なかとんべつライドシェア(相乗り)事業実証実験
中頓別町では、ボランティア町民ドライバーの自家用車を利用した
ライドシェアの実証実験「なかとんべつライドシェア」を8月24日より実施します!
これは、中頓別町の生活をより便利に、豊かにするための取り組みです。
町内のお出かけやお買物などの際に、ぜひご乗車下さい!
運行時間は365日、8:00-24:00までご利用いただけます。(時間帯によっては配車が出来ない場合もありますので、ご了承下さい。)
タクシー事業者の撤退で公共交通空白地に
京丹後市は日本海に面した京都府の最北端にあり、峰山町、大宮町など6町が合併して2004年に誕生した。人口は約5万7000人。天女の羽衣伝説や丹後ちりめんの産地として知られるが、人口は1970年から一貫して減少している。
丹後町は市内の最北部にあり、人口約5500人。そのうちのざっと4割を65歳以上の高齢者が占めている。「間人(たいざ)ガニ」と呼ばれるズワイガニの産地だが、過疎と高齢化の進行が深刻さを増している。
もともと公共交通の発達した地域ではなかったが、2008年にタクシー事業者が撤退した。このため、2014年から小型の市営デマンドバスが運行しているものの、利用には事前の予約が必要なうえ、乗車できる曜日や地域も限定されている。住民の間からはもっと利用しやすい新たな交通手段を求める声が上がっていた。
さらに、市は訪日外国人観光客の誘致に力を入れているが、現在の公共交通は外国語やクレジットカードによる支払いに対応できていない。そこで45言語に対応し、クレジットカード決済機能を持つUberのアプリに白羽の矢が立った。
Uber日本法人の高橋正巳社長は記者会見で「公共交通の補完的な役割を果たしたい」と述べた。京丹後市企画政策課は「何としても過疎地の住民の足を確保したかった」と狙いを語っている。
過疎地の新交通手段確保が自治体の急務
しかし、Uberのライドシェアに対しては、日本の規制が厳しい。Uberは世界70の国と地域で自家用車の配車事業を展開しているが、国内での事業展開は東京都心部でのハイヤー、タクシー配車に限定されてきた。
2015年2月に福岡県で実施された配車実験は、運転手への報酬に違法の恐れがあるとして国交省から行政指導を受け、中止された。今年2月には富山県南砺市と無償の実証実験計画を合同発表したものの、市議会などから批判が出て、市が予算を取り下げる騒ぎに発展している。
タクシー業界を中心に反対の声も根強い。全国ハイヤー・タクシー連合会は「京丹後のケースは別にして、白タク行為は容認できない。事故時の対応や安全性には疑問を感じる」と警戒感を隠さない。Uberに出資したトヨタ自動車も規制などの状況を考慮し、国内を協力の対象外としている。
シェアリングエコノミー企業は利用者間のマッチングに徹することが多く、サービスの質や安全性を担保する仕組みが既存業界より弱い。こうした点は急ぎ改善しなければならないだろう。
ただ、過疎地の人口減少は今後も進み、高齢化の進行とともに交通難民がさらに増えると予想されている。それぞれの地域事情に合う効率的な新しい交通手段の確保は待ったなしの課題だ。新たな交通手段としてライドシェアに対する自治体の関心は高まっている。
全国では自家用車による搬送以外にも、乗り合いタクシーの運行、住民団体によるバス運行などさまざまな移動手段が模索されている。それぞれの地域に合った過疎地の足は何なのか、各自治体は真剣に考える時期に来ているのではないだろうか。











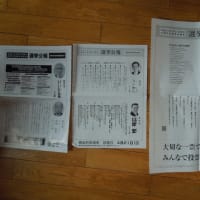

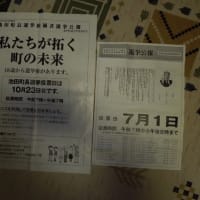

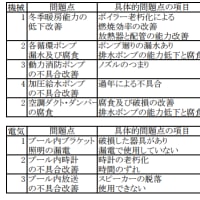
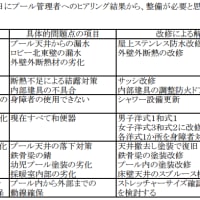
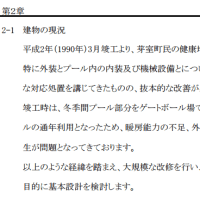


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます