| ●青木 定之 1 芽室町斎場の将来構想について 本町の斎場は、市街地から14kmの距離にあり、狭隘化に加え老朽化し、町民の利便性の低下を招いている実態にある。
最近の葬儀の実態にも鑑み、町民の利便性を考慮し、計画的に斎場の移転を進めるべきと考えるが、町長の見解を伺います。 2 入居者にやさしい公営住宅について 新年度に借り上げる公営住宅は、1棟当たりの入居戸数が多いものがある。
今後、入居戸数の多い借り上げ公営住宅においては、入居者の交流の場(憩いの集会室)を設けるべきと考えるが、町長の見解を伺います。 |
|||||||||||||
| ●吉田 敏郎 1 役場庁舎建設基本構想について 町が策定する役場庁舎建設基本構想は、3月上旬にも確定とのことであるが、町民に対しての情報量も極めて乏しく、拙速に進めていると考える。
このことから次の5点について町長の見解を伺います。
|
|||||||||||||
| ●橋 仁美 1 生活保護基準の引き下げと本町の対応について 国において、生活保護基準が平成25年8月から引き下げられることが決定しているが、これを基に生活支援制度な どの様々な基準が定められている。
したがって、生活保護基準の引き下げにより、本町においても様々な影響が表れると危惧されることから、次の2点について伺います。
2 乳幼児医療費助成の拡大について 乳幼児医療費助成については、本町においても徐々に拡大し、第4期芽室町総合計画後期実施計画にも拡大が盛り込まれ、一定の評価ができるところである。
しかしながら、本町の現在の助成基準は十勝管内で最も低い状況にあり、さらに、平成25年度当初予算案にも、盛り込まれていないことから、次の2点について伺います。
|
|||||||||||||
| ●常通 直人 1 居住環境の改善に向けた空き家対策について 本町の新耐震基準以前(昭和55年以前)に建築された住宅や店舗併設住宅は、中心市街地を含め、築30年以上の建物が30%以上現存していると言われています。
そのうちの「空き家」や「空き店舗」については、近くに管理できる人がいない場合が多く、夏場は庭などの管理不足で環境が良くないことや、冬場にかけても落雪など通行に支障をきたす問題なども生じています。 特に、長期間人が住んでいない建物は、老朽化が著しく、地震など災害が発生した際には倒壊し、近隣の住宅や住民への危険性も否定できないと考えます。 このようなことから、「空き家」や「空き店舗」には、防災上、生活環境上、景観上の3点から課題があると考えるが、町長の見解を伺います。 |
| ●小椋 孝雄 1 教職員住宅の管理について 平成24年4月現在、教職員住宅は37棟59戸となっています。 また、平成24年5月1日現在の教職員数は、小学校95名、中学校65名、計160名であり、教職員数に対する教員住宅のカバー率は36.9%ですが、今後の教職員住宅の管理について、次の5点について伺います。
|
|||||||||||||||||||
| ●中野 武彦 1 命を守るための防災対策について 近年の地球規模での気象変動により、災害に対する備えの重要性が増していることは言うまでもありません。
本町においては、昨年3月に「芽室町地域防災計画」が見直され、その実効性が求められるとともに、全町民への防災意識の向上対策と、今日起きるかもしれない大規模災害時の避難対策は、喫緊の課題であると考えることから、次の5点について伺います。
|
|||||||||||||||||||
| ●正村紀美子 1 母子保健事業の充実について 本町は、「安心して産み育てることができる子育て支援」を施策に掲げ、町全体による子育て支援体制の充実を図っている。
女性の社会進出が進み、働きながら出産・育児をする女性が年々増加している傾向にある中で、妊娠・出産期の支援に関し、次の3点について町長の見解を伺います。
2 町民が使いやすい情報公開コーナーのあり方について 町は、町政に関する情報を町民に提供するため、情報公開コーナーを設置し、町政資料の閲覧を行っている。 町民と町との協働のまちづくりを推進していくために、情報公開コーナーの充実が必要であると考え、次の3点について伺います。
3 図書館における情報収集のあり方について 図書館法第3条で、図書館は「地方行政資料の収集にも十分留意して、一般公衆の利用に供すること」とあり、図書館は行政資料の収集をし、町民に提供することが規定されている。
町は、平成11年に「芽室町情報条例」を制定し、役場第1庁舎1階ロビーに情報公開コーナーを設置したが、設置に伴い、それまで図書館で収集していた行政資料が一部収集対象から外れている状況にある。 そこで、図書館の情報収集のあり方に関して、次の2点について伺います。
|
|||||||||||||||||||
| ●梅津 伸子 1 TPP(環太平洋経済連携協定)交渉参加を許さない取組の強化について 2月に行われた安部晋三首相とアメリカ合衆国のオバマ大統領の会談以来、日本のTPP交渉参加に向けた動きが急速に強められています。
TPP交渉参加問題は全国民的な問題であり、特に本町においては基幹産業と地域社会の存亡に関わる一大事であると認識しています。 国民の食料基地としての役割を果たし、農業と地域社会を守り、発展させる上で町の果たす役割は重いものと考え、次の3点について町長の見解を伺います。
2 住宅の地震による倒壊被害から町民の生命を守ることについて 本町においては、地震による建築物の倒壊被害から住民の生命及び財産に対する被害を未然に防止するため、「芽室町耐震改修補助事業」を実施しています。
しかし、これまでの努力にも関わらず、住宅の耐震化が進まない状況にあります 。 そこで、補助制度等の利用促進のために、次の3点について町長の見解を伺います。
|
|











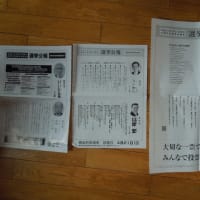

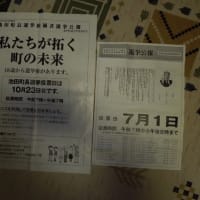

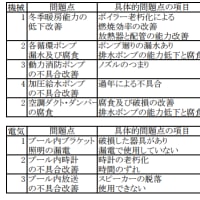
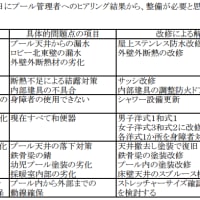
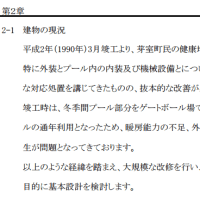


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます