土地利用や道路、公園など町の施設の配備、整備をまとめた計画書を作っていますが20年計画のなかで町の総合計画(13~17年度)との調整も兼ねて見直しをかけるという事です。
都市計画が専門の弘前大学教授 北原啓司氏の講話や委員(団体推薦委員7名、町民公募委員7名、役場課長7名)の委託状交付もありました。
北原氏のお話
住民のさまざまな視点をまちづくりに反映する
50年、100年後の次の世代の住民のために行う
町民公募委員7名
武藤氏(農協青年部)
宮本氏(写真家)
宮間氏(ハリ、整体)
坂本氏(保育士)
藤田氏(ホームヘルパー関係NPO)
風間氏(里山の保全に関心あり)
家内氏(会長に選出されました)
弘前大教育学部教授 北原啓司さん (ネットから引用)
2012年03月13日
|
防災対策の重要性を語る北原啓司教授=津市羽所町 |
◎弘前大教育学部教授 北原啓司さん(55)
◇◆地域を再編し住民守れ◆◇
――東日本大震災の復興に尽力されています。
岩手県北上市に昨年9月、「きたかみ震災復興ステーション」を立ち上げ、地元自治体や専門家、NPO法人関係者らと被災地の復興を後方支援しています。
三重も今後、大災害が起こりうる地域なので、ノウハウとネットワークを共有するため、三重大学の浅野聡准教授にもメンバーに入ってもらいました。
――専門はまちづくりですね。
大学入学当初は建築家になりたかった。勉強していくうちに、建造物が集まる集落に関心が向き、そうした空間を形作る人々の活動にも興味がわきました。
単なる建造物という空間(スペース)を、人々が快適に暮らす場所(プレース)に変えるためのマネジメントが「まちづくり」であり、さらに進めた「まち育て」だと考えています。これまで、震災被災地を含む東北各県のまちづくりに関わってきました。
――防災関連の講演会も多いとうかがいます。
私は伊勢市出身で、自宅から50メートル先には海がありました。ただ、子どもの頃の災害のイメージは、地震や津波よりも台風でした。伊勢 湾台風を経験したことも大きかった。宮城県に転居してからは、宮城県沖地震や十勝沖地震など、東北地方に被害をもたらした数々の地震を体験しました。まち づくりと災害は、どうしても切り離すことができません。
――では、防災面で重要なことは何ですか。
津波に関して言えば、これから巨大な堤防を造ることは難しい。被災地では、津波をかぶって価値が二束三文に下落した土地の処理が問題化し ています。海岸に面した危険度の高い土地は、行政がいったん買い上げるなどした後で住民に貸し付ければ、住民の損失は最小限に食い止められる。住民の財産 を守るという意味でも、地域を編集し直すことが求められています。
――三重でも東海、東南海、南海地震の危険性が指摘されています。
大きな被害に遭った三陸地方と、県内の沿岸部は地形的にも産業的にも非常によく似ている。もし、東日本大震災のような被害に遭った場合、地域の人たちの手で地域を復元することが重要になります。
「復興するぞ」という情熱だけで太刀打ちできるものではなく、災害に立ち向かえるノウハウと知識をもった人材を育てる必要があると思います。
――国は、延伸工事中の紀勢自動車道を避難場所として活用する方針です。
東日本大震災では、高規格道路が防災面で有効に機能することが分かりました。宮城県名取市などは、仙台東部道路を堤防の代わりに活用するほか、避難ビルを建設する方向で今後の防災対策を検討しています。(聞き手・安田琢典)
◎北原啓司さんの略歴 1956年、伊勢市村松町出身。専門は都市計画。小学校2年で宮城県岩沼市に転居し、仙台一高から東北大学工学部建 築学科に進み、同大学院工学研究科博士課程を修了。同大工学部助手を経て、94年に弘前大学教育学部助教授、2003年から教授。日本都市計画学会の防 災・復興問題特別研究委員会の復興まちづくり部会長や、国土交通省の「東日本大震災からの市街地復興手法検討委員会」委員を務める。











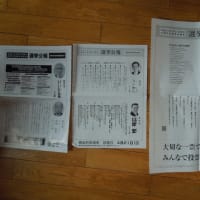

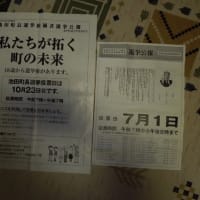

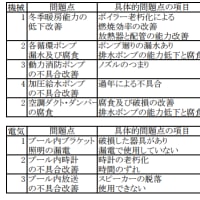
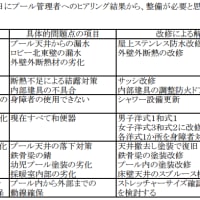
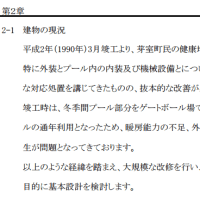


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます