議会基本条例を制定してから今日まで1回しか芽室議会では文章質問が行われませんでした。私で2番目です。
議員が、町政の課題に対して執行機関に改善を求める手段は
◆一般質問する
◆委員会で他の委員の賛同を求めて委員会の意見書などで執行側に要請する。
◆議員提案して他の議員の賛同を求め議会で議案作り、議会可決する。
◆文章質問する
◆担当課長に個別に改善を求める
さまざまな方法がありますが、今回の福祉分野での助成基準の緩和の提案は
こんな問題があることを町民に知ってもらう
対象者への個人的な利益誘導ではない
職員や町長も、町民議会サイドからのお願いに答える形式の方が動きやすい
こんな事を考えて文章での記録に残る形式(文章質問)を選択しました。
当然ですが、担当者や町長の対応もとても誠実でした。
平成28年7月13日、吉田敏郎議員から文書質問の提出がありましたので公表します】
〇文書質問とは? 以下、議会基本条例引用です。
(文書質問)
第15条 議員は、通年議会制度を活用し、休会中においても主体的・機動的な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができます。
2 議会は、文書質問の通告文及び町長等の回答文を、議会だより、議会ホームページ等により町民に公表します。
3 文書質問について必要な事項は、芽室町議会会議条例(平成24年条例第32号。以下「会議条例」といいます。)で定めます。
以上
芽室町議会2番目の文章質問です
〇質問項目:「身体障害者用自動車改造費助成制度の基準緩和について」
〇提出日:平成28年7月13日 質問者:吉田 敏郎議員
本町は、第4期芽室町総合計画の施策に「障がい者の自立支援と社会参加の促進」を掲げ、障がい福祉サービスの提供や相談支援などにより、障がいのある方の社会復帰や社会参加を促し、安心と生きがいを持って生活できることを目指しています。
本町における平成26年度の身体障害者手帳所持者人数は883人で、その中で重度障害者(1・2級、3級の内部障がい)は全体の約43%という状況です。これらの方への支援策の一つとして、身体障害者用自動車改造費助成制度があります。
これは「足や手が不自由でも自ら車を運転して社会復帰したい」 、「そのために自動車の一部を改造したい」という方々への支援策です。他市町村の制度を比較すると、本町の基準は極めてハードルの高い内容となっており、この基準を緩和して社会復帰を目指す方を増やすべきと考えることから、次の2点について町長の見解を伺います。
①本町の実施要綱上の基準では、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者」としています。この基準とサービス利用者数との関係性について、町はどのように評価しているか。
②全国の市町村では、「身体障害者手帳の交付を受けている市民」をはじめ、「1級から6級の上肢、下肢、体幹機能障害を有するもの」、「1級から4級の上肢、下肢、体幹機能障害を
有するもの」や、管内でも「身体障害者2級以上の者(上肢、下肢など細かな条件なし)」などを基準としているところもある。こうした実態を踏まえ、町は現行の基準を緩和し、より多くの障がいのある方の社会復帰と社会参加を促進すべきと考えるがいかがか。
〇答弁日:平成28年7月28日
〇答弁者:町長
吉田敏郎議員の「身体障害者用自動車改造費助成制度の基準緩和について」お答えします。
まず1点目、「本町の身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の基準とサービス利用者数との関係性について、町はどのように評価しているか」についてであります。
平成23年4月に施行した本要綱では、
助成対象者の基準について、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者」と定め、その解釈は、身体障害者手帳の総合等級が1級又は2級であっても、上肢、下肢、体幹機能障害の程度が2級以上でなければ助成対象外となるものであります。
管内における事業の実施状況をみますと、本町を含め15の市町村が実施しており、助成対象者の基準は、本町と同様の基準が2町、本町より緩和した基準が12市町村という状況であります。
ご質問の助成対象基準とサービス利用者数との関係性については、本町における過去3年間の利用実績は2件でありますが、十勝管内で、本町と同様の基準である池田町は1件、清水町は0件、本町より緩和した基準の帯広市18件、幕別町3件、音更町2件、士幌町1件、そして、利用実績がない市町村が8町であります。また、上記利用実績の合計27件の内1件が総合等級をもって助成対象と認められたものであります。
以上のことから、管内市町村においても本町同様にサービス利用者数は少ない状況であり、この実績をもって、本町の助成対象基準と利用者数の関係性を評価することは拙速であり、的確な評価とはならないと考えております。しかし、事業内容の周知という点では、住民への周知方法はさらにわかりやすく拡大するため、今後はホームページ等にも掲載するなど、対象となる方に広く活用していただけるよう努めてまいります。
次に2点目、「全国の市町村や管内の実態を踏まえ、町は現行の基準を緩和し、より多くの障がいのある方の社会復帰と社会参加を促進すべき」についてであります。
1点目で述べたとおり、管内では、本町を含めて15の市町村が本事業を実施しており、助成対象基準では、本町と同様の基準が2町、本町より緩和した基準が12市町村であります。この基準を緩和している市町村も、大きく2つに分類されます。
1つは、「身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢又は体幹に機能障害を有する者」とし、等級による制限は設けていない市町村が1町であります。
2つは、「身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者」で、上肢、下肢、体幹機能障害の程度が2級以上でなくても、身体障害者手帳の総合等級を加味し判断している市町村が、11市町村であります。
これら、管内市町村の助成対象者の基準と比較すると本町の総合等級を加味しない基準は厳しいものであり、それが利用の制限を生じてはいけないとも考えております。今年度、利用希望をお持ちの障がいのある方から、相談をいただきました。その実情などを直接聴かせていただき、利用者ニーズに応えるとき、本町の基準は改正すべきと判断し、現在その早急な検討を進めております。
質問主意書の処理
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA%E5%95%8F%E4%B8%BB%E6%84%8F%E6%9B%B8 引用です
議長(衆議院議長・参議院議長)に提出され承認を受けた質問主意書は内閣に送られ、内閣は7日以内に文書(答弁書)によって答弁する。期間内に答弁できない場合はその理由と答弁できる期限を通知する。[1]ただし、非公式には、議院事務局に提出された直後に院内の内閣総務官室に仮転送されており、内閣総務官室は、質問の項目ごとに答弁の作成を担当する省庁の割振りを仮決めし、各省庁にその適否を照会する。
各省庁は、仮決めされた割振りに異議がある(所管の誤りがある、他省庁と共同でないと答弁できないなど)場合は、照会から60分以内にその旨申し立て、省庁間及び内閣総務官室との協議を経て、仮転送当日のうちに割振りを決定する。
事実上、議院事務局に対する質問主意書の提出に時間制限がないため、国会開会中は、全省庁において答弁書の作成に関与しうる立場にある職員(ひとつの課で数人~十数人程度)は、自省庁に割り振られ、あるいは自らが担当すべき主意書が提出されないことが確認できるまで待機を要求され、もし担当が決定すれば、国会法第75条の定める7日以内という答弁の期限に間に合わせるため、すぐに答弁案の作成に着手しなければならない。
答弁案の作成に対する省庁の関与には、
- 執筆(答弁案の作成、閣議請議手続など)
- 合議(他省庁の作成した答弁案の内容確認、修正など)
- メモ出し(他省庁の答弁案作成に必要な資料の提供、答弁案の内容確認、修正など)
の各形態がある。答弁作成が複数省庁にまたがる場合は、最も質問主意書の主題と関係が深いか答弁の重要な部分を担当することとなった省庁が、全体の取りまとめを行う。
作成された答弁案は、原則として、仮転送から2ないし3日(営業日ではなく、休日・祝日を含む暦日。以下同じ)で、執筆した各省庁の法令担当課及び内閣法制局において、質問に対する適確さ、現行法令との整合性、用語・用字などにわたる審査と修正を終了する必要がある。その後、内閣総務官室、与党国会対策委員長への内容説明などののち、仮転送から6ないし7日後の閣議決定を経て、正式な答弁書として提出議院の議長に提出される。
質問主意書の提出数は増えてきているものの、答弁書の延期はほとんどなくなっている。これによりスピーディーなやり取りができるようになったと言われる反面、答弁内容が不十分になったとの声も出ている。[1]
制度の実態[編集]
制度に関する議論[編集]
この制度は、通常の国会質疑の場でなくとも政府の見解を質したり情報提供を求めたりすることができ、議席の少ない野党や無所属議員にとって有用な政治活動の手段であると評価されることが多く、実際にこの制度を積極的に利用する野党が増えている。質問時間が不足しがちな少数政党や無所属の議員は、質問主意書をもって国会審議を補っているという側面もある。また、質問主意書によって政府見解が明確になったり、政府の問題が明らかとなったりするメリットもあるとされる。[2]また長妻昭は自身の公式サイトに、質問主意書が「野党議員にとっては、巨大な行政機構をチェック・是正出来る武器(国会法74条、75条)」で、「本質問主意書がきっかけで是正された事項も数多い」と記している[3]。2005年度は新党大地の鈴木宗男衆議院議員がこの制度を利用し外務省内のセクハラ事件などの情報を引き出した。
外務省におけるワインの購入に関する質問主意書
外務省におけるワインの購入に関する質問主意書
一 外務省の国内施設(例えば飯倉公館)にワイン貯蔵庫が存在するか。存在するならばその場所と貯蔵ワインの数を明らかにされたい。
二 平成十七年度のワイン購入経費が予算計上されているか。されているならばいくらか。
三 平成元年から平成十六年まで、毎年のワイン購入にあてられた総額と本数如何。
四 平成十七年三月十一日付内閣参質一六二第七号で、「外務省は、諸外国の要人の接遇等に資するため、質、価格等に関する情報や想定される使用の機会等を勘案して、ワイン等種類を選定し、購入している」とした上で平成十四年以降平成十七年三月七日までに「外務本省において購入したワインは、合計で千六十四本、九百九十五万五千七百三十八円である」と答弁しているが、当該ワインは全て日本国内で購入されたか。それとも外国で購入されたものもあるか。当該ワインを購入した際の領収書等の証拠書類は外務省に保存されているか。
右質問する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるワインの購入に関する質問に対する答弁書
一について
外務省においては、飯倉別館のワイン貯蔵庫において約八千本のワインを保存している。
二について
平成十七年度において、ワインの購入のための予算は、単独の項目として計上されていない。
三について
確認できる範囲では、平成十二年から平成十六年までに外務本省において購入したワインは合計で二千
百七十七本であり、その総額は千六百四十四万三千三十八円である。
四について
お尋ねの「当該ワイン」はすべて日本国内で購入されており、その証拠書類は保存されている
| <form id="likeStory_S:_I510350735680867:1043758772340058" class="_523u embeddedForm" action="https://www.facebook.com/plugins/confirm/post/like/sentry/glyph-button/" method="post">
16
</form> |
コメントする
|
1
|













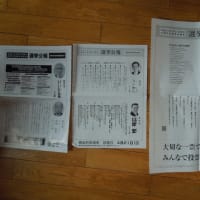

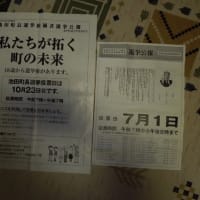

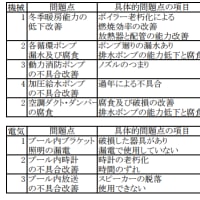
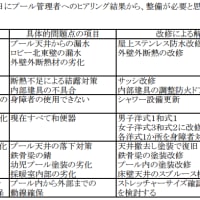
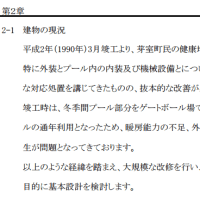


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます