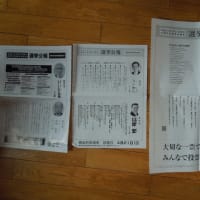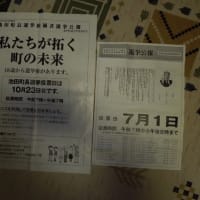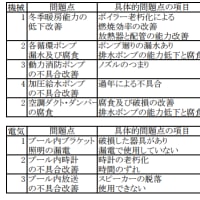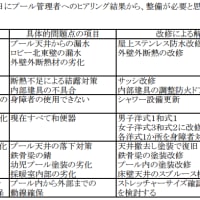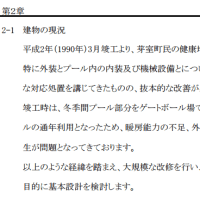2016年12月14日 一般質問しました
1 職員給与費
における「自
己所有に属す
る住居手当」
について
2 職員給与費
における「時
間外手当につ
いて」
3 町民に身近
に感じていた
だける職員像
を目指し、工
夫をすべき
国家公務員に対するこの手当は、平成21 年8月25 日付人事院勧告に基づき廃止されました。
人事院は、地方公共団体においても廃止を基本とした見直しを行うことを求め北海道人事委員会も平成21 年10 月9日付で廃止を勧告し、北海道はこれに従い同年2月に廃止、帯広市においても自己所有に属する住宅手当を廃止しました。
行財政改革の視点や官民格差、町民感情の面からも、自己所有に属する住居手当を廃止すべきと考え、平成25 年12月議会の一般質問において町長の見解を伺い、「国に準拠していない手当だが地域の実情・特殊性も鑑みた中で町独自の考えで支給をしている。町の財政的な負担を考慮し、
現在職員住宅の整備を行わず、職員が町内に自己所有住宅を持つことで定住人口の確保、固定資産税や住民税等の税収増のほか、地域社会のさまざまな担い手として、その活躍を期待しているものである。
しかしながら、今後においては道内・管内の情勢など総合的に勘案しながら、住居手当については再考すべき時期にあると考えている。」との答弁がありましたが、その後3年が経過した現在までの検討状況について伺います。
このことについても、一般質問の答弁では、「本町の時間外勤務の現状については、近年、時間外手当が増加傾向にあることは十分認識している。選挙事務や災害等、予測ができない突発的な業務のほか、その年度に限定される臨時的業務や病気休暇者の対応に伴う一時的な時間外勤務の増加が考えられる。全体的要因としては、職員の退職に伴う新規
採用職員の増加による影響がある。これが長期化することは、職員の健康保持、労働意欲や活力の維持に影響を及ぼすものと考え、今後も職員の適正な人員配置と並行した行政事務能力の向上が必要と考えている。業務量に見合った必要最小限の職員数を維持しながら、適正な定数管理と均衡を確保することが重要と考えている。適正な人員配置を行うた
め、毎年実施する業務量調査の精度を高め、業務量に応じた適正な人員配置を行うとともに、管理職による課内業務の適正な分担や職員の流動化等を含めたマネジメントの強化、新規採用職員の行政経験と研修の充実などの総合力をもって、業務能率の向上と効率化に努めることが時間外勤務を徐々に減少させる抜本的対策と考えている。職員が一丸となり、職場全体として時間外勤務の削減に取り組んでまいりたいと考えている。」と答弁をいただきました。
この答弁から3年が経過しますが、その後の時間外勤務手当支給実績では削減されておらず、この問題に対する課題と今後の対策について見解を伺います。
平成27 年9月議会の一般質問において、職員ガイドを発行すべきと提案しましたが、「現時点で発行する考えはなく、若手担当職員の紹介写真を掲載するなどし、工夫をしているところです。」との答弁をいただきました。
しかし、掲載の回数も少なく、誰が職員だかわからないとの声も相変らずよく聞きます。
顔と名前がわかる職員ガイドが欲しいとの町民の要望が多いことから、再度町長の見解を伺います。
持ち家手当てとは何か?
http://www.j-cast.com/2012/01/24119796.html?p=all ここから引用です
国家公務員については、総務省が2009年12月、人事院の勧告に基づいて「持ち家手当」を廃止している。
手当の目的はもともと、畳の張り替えなど住宅を維持するための修繕費を補助することにあった。しかし、人事院が2003年に全国調査をしたところ、この目的を挙げる民間企業が19.4%と過半数にも達しておらず、存在意義が薄れたとの判断から廃止を勧告していた。
人事院の給与第3課では、公務員については、生活費補助としてはすでに扶養手当があり、持ち家は財産になるので賃貸との均衡は考慮する必要はないと指摘する。つまり、持ち家手当の存在意義は、公務員の場合は、修繕費補助ぐらいしか見当たらないということだ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391818.pdf
全地方公共団体の8割以上の団体(1,492団体/1,788団体、83.4%)
が、自宅に係る住居手当を廃止している。
自宅に係る住居手当の制度のある団体は296団体(16.6%)
北 海 道 118 178 最近の3年で 440団体が廃止
自宅に係る住居手当の制度がない道内市町村(H27.4.1現在)
函館市 小樽市 帯広市 夕張市 留萌市 苫小牧市 美唄市 芦別市
江別市 赤平市 士別市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市
北斗市 松前町 福島町 七飯町 鹿部町 森町 長万部町 江差町
乙部町 奥尻町 せたな町 島牧村 黒松内町 蘭越町 ニセコ町
真狩村
倶知安町 共和町 岩内町 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 赤井川村
上富良野町 中富良野町 占冠村 増毛町 小平町 苫前町 斜里町
清里町
西興部村 大空町 豊浦町 壮瞥町 白老町 厚真町 洞爺湖町 安平町
えりも町 音更町 厚岸町 羅臼町 計60団体
町の考え
まず持家を廃止するとすれば、どのくらいの住宅の建設戸数が必要なのかだとか、職員住宅のですね。さっき言いました職員も180人、一般行政職員だけでいますから、その中でどのくらいの職員住宅を持てばいいのかだとか、その職員住宅を持った場合のランニングコストあるいはイニシャルコストは持家手当とどう違いが出るのかだとか、いろんなことを検証していかなければなりません
正当性がなく国民の批判を受け廃止した「持ち家手当」を継続する理由
止めるなら職員住宅を整備しなくてはならない 持ち家手当年間約2000万円のほうが安い
吉田の考え
公務員は田舎では1番良い待遇の就職先で「持ち家手当」を止めた道内60町村でも就職希望者は減っていません。役場庁舎建てるのも大変なのに更に職員の住宅整備を進める自治体などきいたことがありません。町民の理解が得られるとは到底考えられません。
国の言い分です
http://www.soumu.go.jp/main_content/000388465.pdf
本日の閣議において、国家公務員の給与改定に関する取扱いが決定されました。この決定を受け、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて、地方公共団体に対して12月4日付けで別添のとおり通知しましたのでお知らせいたします。
地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知
各地方公共団体においては、地方公務員の給与改定等を行うに当たって、別紙閣議
決定の趣旨に沿って、特に下記事項に留意の上、適切に対処されるよう要請いたしま
す。
地方公営企業に従事する職員の給与改定等に当たっても、これらの事項を十分勘案
の上、適切に対処されるようお願いします。
6 諸手当の在り方については、一般行政職のみならず職種全般について不断に点検
し、制度の趣旨に合致しないものや不適正な支給方法については、その適正化を図
ること。
また、自宅に係る住居手当については、国においては平成21年12月に廃止された
ことを踏まえ、地方公共団体においても、速やかに見直しを行うこと。
他の町の時間外勤務手当の実績 最新の各町のホームページから抜粋しました
新得 一般会計職員数115人 年間総額1986万 1人当たり 173000円
清水147人 2736万 186000円
芽室156人 5582万 358000円
音更 241人 1億4074万 583000円
幕別220人 8323万 378000円
本別 151人 3927万 26万
鹿追133人 3463万 26万
芽室町 時間外勤務 平成27年度実績
役場 26、778時間 63、279、634円 6300万 時給2363円
病院 5、549時間 47、309、118円 4700万 時給8525円
全体 32、327時間 110、588、752円 (総額で 約 1億1000万円)
役場部門 27年 6328万 746万増加
26年 5582万 115万増加
25年 5467万
清水町議会議事録から
職員の持ち家手当についてをお尋ねしたいと思います。
十勝毎日新聞の1月26日付でありました。十勝管内1市18町村の持ち家手当の状況が大きく報じられておりました。帯広市は平成24年度限りで廃止を決めました。何らかのかたちで検討している町村が複数あり、今後、見直しの検討を始める町村が増えたそうだという記事でございました。これは、清水町の住民に取りましても、関心の高い記事でありましたが、いまだに何の動きも見えませんのでお尋ねさせていただきます。
そもそも、持ち家手当というものはなんなのでしょうか。また、持ち家手当については、清水町においてどのような内容になっておりますか。この持ち家手当の廃止要請が国からあったということですが、清水町も例外ではないと思います。それは事実ですか、また、それはいつ頃ですか。事実だとすれば廃止できない理由はなんでしょうか。いまだ条例改正が提出されないでいるということは、新年度も予算が計上されてきております。続けるお考えでいるのでしょうか。
国・道も廃止をしており、帯広市も新年度から廃止ということでありますので、町民視線というものは非常に厳しいものがあり、住民感情として理解できないわけであります。この職員の持ち家手当をどのように考えていらっしゃるのか、ご説明いただきたいと思います。
次○議長(加来良明) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) 職員の持ち家にかかわる、住居手当のご質問ですが、ご指摘のとおり、人事院勧告に基づき、国家公務員は平成21年から廃止をしたところでございます。各地方自治団体に対しましても給与制度は、国家公務員の給与制度が基本として決定されるべきものから、地方公共団体におきましても、廃止を基本として見直しを行うようにということの要請がきているところであります。
本町には、地域事情としてもありますけれども、今まで他の町村もそうでありますけれども、国や北海道庁の職員や北海道の職員と違い、職員住宅を整備していないということもあります。以前はあったんでありますけれど、持ち家を建設することを推進して定住を図ってもらうということと、建てることによりまして、財源である固定資産税が賦課されるわけでありますので、それを期待しているということでそれぞれ住宅手当を支給してきたわけであります。今回、そういうことで廃止をすべきではないかというお話でございますので、我々もそのことについての議論をさせていただいているところであります。
帯広市は、借家の手当について従来どおり出しておりまして、合意になったのは、借家の手当を上げたということでありまして、自宅を建設しているところについては廃止というかたちになったところであります。そういうような状況でありますから、住民感情から見てもこの問題については取らざるをえなく、検討していくということにしたいと思いますので、平成25年度につきましては、このままにさせていただきまして、平成25年度中に結論を経ていきたいと思っております。町村会とも、この議論をしていかなければならないと思っているしだいでございます。
現在、参考までに、一般職158名のうち91名、借家が34名ということになっております。そういうような状況で推移しているところであります。


3年前の吉田の一般質問です
◆4番(青木定之) 終わります。
○議長(広瀬重雄) 以上で青木定之議員の質問を終わります。
次に、吉田敏郎議員の質問を許します。
吉田議員。
◆2番(吉田敏郎) 通告に基づきまして、1項目2つの質問をいたします。
職員給与費における「自己所有に属する住居手当」と「時間外手当」について。
本町では、平成24年度において「自己所有に属する住居手当(いわゆる持ち家手当)」が133人に対して月額1万3,000円、総額約2,071万円が支給されています。国家公務員に対するこの手当は、平成21年8月25日付人事院勧告に基づき廃止されました。人事院は、地方公共団体においても廃止を基本とした見直しを行うことを求めたところです。
これを受け、北海道人事委員会も平成21年10月9日付で廃止を勧告し、北海道はこれに従い同年2月に廃止、帯広市においても自己所有に属する住宅手当を廃止しました。人事院を設置していない市町村においては、人事院における官民給与の調査結果等を参考とする旨、総務省からも助言があることから、本町においても人事院勧告をもとに職員の給与を決定しているところであります。
国、地方ともに行財政を取り巻く環境は極めて厳しい中で、本町においても徹底した行財政改革に取組み、分権型社会にふさわしい行財政体制の整備に努める必要があると考えます。このことから、行財政改革の視点や官民格差、町民感情の面からも、「自己所有に属する住居手当」を廃止すべきと考えますが、町長の見解を伺います。
もう一つは、時間外勤務であります。
時間外勤務は、課長等の命令者の命令により発生し、業務の緊急性等を考慮の上、命令が行われます。平成24年度の時間外勤務手当は、253人の正職員に総額約1億1,000万円が支給されています。業務量に基づく適切な人員配置や代休の取得促進を行い、職員の健康管理のためにも時間外勤務の削減を目指すべきと考えることから、次の3点について伺います。
1、本町の時間外勤務の現状についてどのように考えていますか、見解を伺います。
2、時間外勤務の削減のための課題についてどのように考えているのか、見解を伺います。
3、職員の増員か業務のアウトソーシング等による業務量の削減以外に抜本的な対策がないと考えますが、見解を伺います。
以上、1回目の私の質問といたします。
○議長(広瀬重雄) 吉田議員の質問に答弁を求めます。
宮西町長。
◎町長(宮西義憲) 吉田敏郎議員の職員給与費における「自己所有に属する住居手当」と「時間外手当」についての1点目、「自己所有に属する住居手当を廃止すべき」との考えに対する見解についてであります。
職員の給料・手当は、これまでも人事院勧告を基本に職員団体の合意を得、改正にあっては議会の議決を経ているところであります。その中で、吉田議員御指摘のように、「自己所有に属する住居手当」、いわゆる持ち家手当は国に準拠していない手当であります。そのため、国家公務員や北海道職員との職場環境や住宅環境の違い、地域の実情・特殊性も鑑みた中で町独自の考えで支給をしているところであります。
その経緯は、国や北海道では市町村と異なり、人事異動により勤務地が変わる環境にあり、それに伴い、多くの職員住宅を整備し、職員の住宅環境を保持しているところであります。また、平成21年、人事院が廃止を勧告した新築・購入後5年に限り支給される住居手当の主な廃止理由は、財形持家個人融資の利用者が大幅に減少したことから、国家公務員の持ち家に対する依存度が低いと判断されたものであります。
芽室町では、町の財政的な負担を考慮し、現在職員住宅の整備を行わず、職員が町内に自己所有住宅を持つことで定住人口の確保、固定資産税や住民税等の税収増のほか、地域社会のさまざまな担い手として、その活躍を期待しているものであります。また、住宅手当全体を見ますと、平成24年度の持家手当は133人に対し、約2,071万円の支給、また借家手当については86人に対して約2,463万円の支給であり、1人当たりを単純に比較しますと、借家手当は月平均約2万3,800円、持家手当は月1万3,000円と1万円程度低くなっております。また、借家手当は家賃の補助として支給するのに対し、持家手当は住宅の維持管理費用の補填の意味合いを含め、支給しているものであります。
しかしながら、御指摘のとおり近傍類似市町村にもいろいろな動向があり、今後においては道内・管内の情勢など総合的に勘案しながら、住居手当については再考すべき時期にあると考えております。
次に、2点目の「時間外勤務手当」についてお答えします。
①の本町の時間外勤務の現状についての見解でありますが、近年、時間外手当が増加傾向にあることは十分認識しております。年度によっては、選挙事務や災害等、予測ができない突発的な業務のほか、平成24年度では第4期芽室町総合計画・後期実施計画策定事務のように、その年度に限定される臨時的業務や病気休暇者の対応に伴う一時的な時間外勤務の増加が考えられます。このほか、全体的要因としては、職員の退職に伴う新規採用職員の増加による影響があると考えております。
平成21年度に特別養護老人ホーム民営化で配置転換した職員を含め、ここ5年間で事務系職員は退職者補充として69名を新たに採用したところであり、事務系職員の4割近くが5年以内に変わっている状況にあります。これが災害、選挙、除雪を除いた一般会計職員1人当たりの時間外勤務平均時間が、平成20年度114時間、平成24年度153時間と39時間の増加となった要因の一つと考えております。
これが長期化することは、職員の健康保持、労働意欲や活力の維持に影響を及ぼすものと考え、今後も職員の適正な人員配置と並行した行政事務能力の向上が必要と考えております。
②の時間外勤務の削減のための課題についてでありますが、①の答弁で申し上げたように現況分析からは、職員の適正な人員配置と並行して行政事務能力の向上が課題と考えております。
③の職員の増員かアウトソーシング等による業務量の削減以外に抜本的な対策がないと考えるがについての見解であります。
時間外勤務を削減するために職員を増員することは、経常経費が増え、財政の硬直化を進める原因となることから、業務量に見合った必要最小限の職員数を維持しながら、適正な定数管理と均衡を確保することが重要と考えております。また、アウトソーシングは行政サービスを恒常的に維持する上で、現在までも指定管理者制度や電算事務などの専門的分野で導入している状況にあります。
したがって、各課・係の適正な人員配置を行うため、1つ、毎年実施する業務量調査の精度を高め、2つ、業務量に応じた適正な人員配置を行うとともに、3つ、管理職による課内業務の適正な分担や職員の流動化等を含めたマネジメントの強化、4つに、新規採用職員の行政経験と研修の充実などの総合力をもって、業務能率の向上と効率化に努めることが時間外勤務を徐々に減少させる抜本的対策と考えております。
今後とも、私を含め職員が一丸となり、職場全体として時間外勤務の削減に取組んでまいりたいと考えていることを申し上げ、お答えといたします。
◆2番(吉田敏郎) それでは、最初の質問、持家手当のことで質問いたします。
御答弁で、職員住宅の整備は行わず、職員が町内に自己所有の住宅を持つことなどで税収増や定住人口の確保だとか、そういうことを期待して出しているという答弁でした。管内の持家手当の状況を見てみますと、帯広市は月額6,900円で、これはもう廃止されましたが、陸別は1万7,000円、足寄は1万6,000円、広尾町も1万5,000円、芽室町は1万3,000円なんです。どちらかというと帯広から遠い町が多く払っているという実態があると思います。
そんな中で、芽室町は非常に利便性も高いし、現に管内の中で人口も維持しているという実態の中、あえて手当を出すという必要性が薄くなったんではないかと私は考えますけれども、この件について町長はいかがお考えでしょうか。
◎町長(宮西義憲) 確かに、これは住居手当、特に持ち家に関する手当については、先ほど申し上げたとおり、それぞれの地域特性をベースにして金額を算定し、労使で確定し、議会の議決を得ているという流れをとっていますから、町村ごとにはそれぞれの事情があり、それぞれの違いが理由にあらわれている、これは事実であります。
ただ、帯広市から遠いから近いからということだけでなくて、いろんな要素があっての、そしていろんな経過があっての今日の金額の設定であると、こういう御理解をいただきたいわけですが、質問がありましたとおり芽室町は利便性が高いから、その必要性はないんではないかということで考えてまいりますと、今職員総数は公立芽室病院も含めますと300人ぐらいおります。病院だけで120人ぐらいでありますから、行政職員だけで180人ぐらいと。人口も増えているからいいんではないかということで考えてまいりますと、180人がこの町にいるかいないかで、その影響力は家族ともどもで考えていきますと、相当大きな影響はあるわけでありますから、私は決してそのようには考えていないということをお答えさせていただきます。
◆2番(吉田敏郎) 1回目の答弁の中で、この持家手当というのは住宅の維持管理費用の補填の意味合いも含めていますという内容でありましたけれども、この持家手当がそもそもどういうことで発生したかというと、畳の張りかえなどの住宅の維持の修繕費の補助なんだというようなことで手当がついたということを聞いております。
昔、公務員の給料は確かに民間と比べて安かったという一般的なイメージがあるんですが、その中での持家手当だったのではないかと。そして、今時代が変わりまして、公務員と民間ということでいいますと、やっぱり地域で一番高い職場が役所であるというようなことは、これはもう今は常識になっております。その中で、公務員の給与のことを考えますと、給料と手当、あとは退職金だとか、共済制度があるんですけれども、そういうトータルな中でこの手当というものも考えるべきと私は思うんですけれども、町長の見解を伺います。
◎町長(宮西義憲) 住居手当について、先ほど私、持家手当というのは住宅の維持管理費用の補填の意味合いも含めてあるんだよということを申し上げたのは、これは私が勝手に申し上げているのではなくて、これは国も持家手当を支給していたときの概念としては、まさしくこれでありまして、それが地方にも当然導入されている考え方だと、そういうことで申し上げたところであります。
それから、役所の給料が高い、高くないということで論争するつもりはございませんけれども、これは当然私たちも今までそういうことがあるから人事院勧告に基づいて、それぞれの給与改定を行ってきていると、こういうことでありますから、そのことに対してあえてコメントをすることはないと思っております。
ただ、一つだけわかっていただきたいのは、先ほど御質問がありました給料と手当をトータルで考えるべきだと、これは違っておりまして、それは給料の、例えば地方公務員法にも、ベースは労働基準法でありますけれども、地方公務員法にも給与に関する定めというのはたくさんあるわけでありますけれども、そ