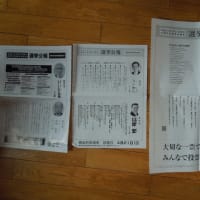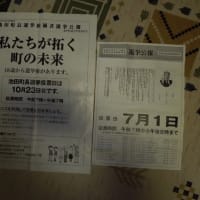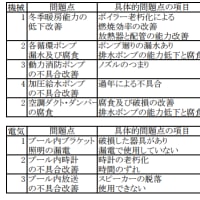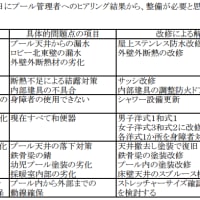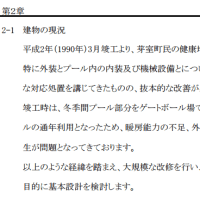オンブズマンとはどんなことをするのか分かりやすく解説しています
http://www.ombudsman.jp/data/meidaisai040605.pdf
・役所の無駄遣い
役所というのは本来、主権者たる住民の福祉・サービスのために税金を託されているは
ずなのであるが、役所の体質なのか、公私混同なのか、日本のお役所では税金を私物化す
るような使われ方が横行し、役所の赤字を増大させ、住民の怒りと不信頼の増大に一役買
っている。市民オンブズマンはこの十年余り、日本中の役所の無駄遣いを発見し、追及し、
その中止や費やした公費の返還を求めることに労力を注いできた。
官官接待
文字通り、官(役人)が官(役人)を接待すること。主に自治体(都道府県・市町村)
の役人と国家の役人が意見交換、親睦を深めるなどという理由で一席設ける。自治体が国
からより多く予算を得るために国の役人をもてなすというが、それは立派な収賄である。
さらに問題は、もてなす自治体の側がその費用をもつのだが、それは彼らの自腹ではな
く、自治体の公費、すなわち税金ということである(本来、訪客用のお茶代などに充てら
れる食糧費の名目で使われる)。
95 年、市民オンブズマンの追及によって明るみになった官
官接待に世論・マスコミは批判の集中砲火を浴びせたが、それはその税金での飲み食いが
あまりに常軌を逸していたからである。一夜で何 10 万円の飲食。6人で高級ワイン 10 数
本。芸者の花代、コンパニオン代なども公費で、二次会・三次会・タクシー代からタバコ
代まで全て公費 etc……。1993 年度の調査では全国の都道府県の食糧費はわかっただけで
も合計約23億円、推定年間約300億円が役人同士の飲み食いに費やされたとみられている。
さらに請求書を水増しして裏金作りが行われたケースも多数ある。
当初は「円滑な情報交換のために接待は必要」「日本の慣習」と開き直っていた役所や知
事・市町村長らも、あまりの批判の大きさやオンブズマンや住民たちからの相次ぐ返還請
求により、食糧費の大幅削減、官官接待の廃止の約束を余儀なくされた。2003 年のオンブ
ズマンの調査によれば、全国の都道府県の食糧費は一県あたり 1995 年には3億 8814 万円
から、2001 年度 8691 万円まで減額(78%の削減)されている。2/7 ページ
カラ出張
本来、役所の予算は一つ一つ使途目的が定められており、その目的外の使用は固く禁じ
られている。しかし、行きもしない出張をでっち上げて、そのための旅費(交通費・宿泊
費)をせしめてプールし、職員の飲食代などに充てるいわゆるカラ出張(典型的な裏金作
り)は全国の役所に見られる病理の一つである。この旅費も当然税金からなっている。
このカラ出張は話の内容は単純ながら、一応、支出書がつくられ、職場でも口裏合わせ
がなされるため、実際に「カラだ」と立証するのはなかなか難しい。それでも情報公開で
入手した支出書や報告書を丹念にチェックしてつじつまの合わないところを見つけ、追及
することで役所にカラ出張の事実を認めさせ、その後の改善や旅費の返還を確約させたケ
ースも多い。
「三重県の職員が阪神淡路大震災当日(当然、鉄道網はマヒ)に新幹線で神戸
を越えて九州に出張した(ことにした)」というのは語り草になっているが、他にも大雪で
運休した列車で出張、同一人物が同日に複数の場所に出張などというケースを発見して、
シラをきる役所を追いつめている。
また、実際に出張したには違いないが、訪問地が観光地や温泉ばかりで「一体何しに行っ
てきたんだ?」と言いたくなるケースも多々見られ、これらも追及の対象となっている。
1998 年までにオンブズマンのつかんだカラ出張、官官接待での不正支出は 436 億 6308
万円で、そのうち、303 億 8722 万を役所も返還を余儀なくされた。
・入札制度
談合
役所の行う事業はそのほとんどが税金でまかなわれており、同じことをするなら、より
安い費用であげようとすることは至極当然のことである。地方自治法にも「最小の経費で
最大の効果をあげるようにしなければならない」(2条⑭)とある。そのために利用される
のが入札制度であり、競争入札にかけることで、物品の納入や工事などを一番安く請け負
える業者と契約を結ぶことができる。
しかし、これは入札をする業者が互いに「自分が契約を取ろう」と競争関係にあること
が前提で、そうではなく入札を行う前に業者が寄り合って誰が落札するかを決めてしまう
なら、それよりも安い価格で入札する業者は誰もいないので役所はその決められた価格で
契約せざるをえなくなる。いわゆる談合である。
特に公共工事において、この談合が全国で日常茶飯事に行われ、結果、役所と住民は必
要以上に高い買い物をさせられている。この談合の摘発と中止・改善は市民オンブズマン
の大きなテーマの一つである。3/7 ページ
まず基本的な談合の流れを説明してお
こう。公共工事を行おうとする役所はその
工事がいくらかかるかを概算し、予定価格
を設定する。この予定価格はそれ以上の価
格では契約できないという上限価格であ
り、より高い価格で契約したい業者はこの
予定価格に限りなく近い価格を目指す。な
お、この予定価格は市販の算定ソフトなど
により、ある程度は予測可能である。ここ
で談合が行われるとしよう。その談合で契
約を取ると決めた業者(A業者とする)は
予定価格ギリギリの入札価格を設定し、他
の業者はそれより高い価格を入札価格に
設定する。これによりA業者の落札は確実
である。もし、A業者の入札価格が読み違
えて予定価格を上回った場合、誰も予定価
格以下の者はいないから、予定価格以下の
入札出るまで入札が二回目、三回目と仕切
りなおされる(複数回入札という)。談合
のとき、A業者は複数回入札になってもい
いように、二回目・三回目の入札時も他の
業者に自分より安い価格で入札しないよ
うに申し合わさせておく。こうして、どう
やってもA業者が落札・契約できるように
するのである。
さて、このような談合は秘密裏に行われ、
そこに参加した業者の内部告発などがな
い限り、摘発は難しい。そこで、オンブズ
マンはこの談合を明るみに出すべく、さま
ざまなツールを開発してきた。その一つが
一位不動の原則である。上で見てきたような談合が成立していなければ、第一回入札で一
位になった業者が第二回目以降も一位であることはきわめて難しい。他の業者がより安い
価格を設定するかもしれないからだ。しかし談合が成立している場合、例え何回目の入札
であろうと、A業者より安値で入札しないという了解ができているので、談合した業者は
何回入札しても不動の一位であり続けるのである。これが一位不動の原則であり、この原
今度の入札は
うちがとるからな!
予定価格以下のものが
無かったので、再度
入札を行います
入札の結果、
一番安い価格を入れた
A社さんが落札です
読み違ったけど
まあいいや
よしよし!
第二回入札
第一回入札
いいけど次は
うちに回しておくれ4/7 ページ
則が確認できる入札は、事前に談合が行われている疑いが格段に高いと言っていい。
また、談合が行われたときの入札の特徴として、予定価格にきわめて近い価格で落札さ
れることがあげられる。談合のない入札であれば落札したい業者は他の業者に負けないよ
うにできる限り安値で入札するので、予定価格の 60~70%以下の価格での落札もあり得る。
しかし、談合している業者は自分より安値で入札する業者がいないとあらかじめわかって
いるので、安心して予定価格ギリギリの価格で入札し、そしてその価格で落札・契約でき
るのである。つまり、その落札価格が予定価格に近ければ近いほど、談合の疑いが高くな
る。このように予定価格の 95%以上の価格で落札したなら、ほぼ間違いなく裏で談合が行
われていると判断できる。このような予定価格に対する落札価格の高さは落札率と呼ばれ、
それが高い(100%に近いほど)落札の疑いが高まるのである。
なお、予定価格の 70%で契約できる業者もいるのに、談合により落札率 95%の価格の業
者と契約させられるなら、その役所(の住民)は 25%も余計に高い買い物をさせられてい
るのであり、談合を駆除して適切な価格での公共工事が望まれる。
なお、オンブズマンの 2003 年の調査によれば、日本の全都道府県の1億円以上の公共事
業の落札率の平均は 95.24%であり、日本全国にいかに談合が蔓延し、そして国民が割を食
わされているかをうかがわせる。
さらに談合の問題としては、業者だけでなく、役所の職員が裏でつるんでいる(一部業
者にだけ予定価格を教える、入札前に業者を指名する etc)といったさらに悪質な官製談合
や、その地元の国会議員や地方議会議員が介入しているものもあって、その裏には役所の
OB がそれらの業者に天下る等の構造があり、問題は深刻である。
・議会・監査委員の問題
全国の市民オンブズマンに共有される標語にねむる議会に死んだ監査委員というものが
ある。本来、各自治体の地方議会と監査委員というチェック機関が役所の無駄遣いや不正
行為をしっかりチェックしていれば、市民オンブズマンの仕事などなくなるはずだ。
しかし実際には議会と監査委員はチェック機能を果たしていないどころか、役所を身内として
かばったり、市民からの追及や監査請求を握りつぶす役を積極的に演じているのである。
当然、市民オンブズマンの怒りの矛先はこれらに向かう。かくしてさまざまな調査により
地方議会と監査委員(とそれらの事務局)にもカラ出張や役所との接待関係があることを
オンブズマンは暴いてきた(同じ穴のムジナ!)。しかし、問題はそれだけにとどまらず、
これら機関の抱える病理は多岐にわたり、そして根深い。5/7 ページ
議員の特権
自治体の予算や条例の制定に関わり、役所のムダや不正を厳しくチェックする役目を期
待されている地方議会(都道府県議会・市町村議会)の議員さんたちにがんばって仕事を
してもらうためにも、彼らにさまざまな権限や身分の保障がなされなければならないのは
よくわかる。しかし、必要以上に手厚い報酬を議員たちが自分たちで決めて自分たちに支
払わせていたり、何に使ったかもよくわからない経費を役所に請求したりするなら、市民
は「何だそれは??」と思わざるを得ない。なぜなら、これらの報酬や経費も元はといえ
ばわれわれの税金なのだから。
政務調査費
地方議会の議員や彼らのつくる会派には議員の給料とは別に政務調査費が支給される。
これは議会での討議のための調査などの費用に使われるものなのだが、実際には何に使わ
れているよくわからないことが少なくない。精算に領収書を出さなくていいことにしてい
る役所(というかそのように自分たちで決めている議会)があるからだ。このようなとこ
ろでは議員が「調査に使いました」という言い値を(予算の限度内で)支給することにな
る。また領収書を提出させているところでも、その領収書の内容はきわめてあやしいこと
が多い。つじつま合わせとしか思えない計算表が多数見られている。愛知県瀬戸市の市議
会では「調査費の名目で『ハリー・ポッター』の単行本を購入」していた議員がいたこと
が明らかになり、一躍有名になったが、何に使ったか明らかにしている分、また律儀な方
なお、支給された政務調査費のうち、使われなかったものは返還が原則だが、この返還
がなされることはあまりない。みんな「使いきった」と言い張るからである。2003 年の統
一地方選挙の際、選挙の月は 10 数日しか議員活動ができる日がなかったにも関わらず、1
月(約 30 日分)の政務調査費をきれいに使いきった(よって返還0円)と申告する議員・
会派が相次ぎ、「一体何にどうやって使っているのか?」という謎はますます深まった。ち
なみに、政務調査費を選挙費用に充てるのはご法度である。
費用弁償
地方議会の議員が議会に出席した日には、その給料とは別に費用弁償が支給される。何
が「弁償」なのかといえば、「出席し、職務に要した費用を“弁償”する」という建前なの
だが、市民に立場から見れば、なぜ給料とは別にこのような出席手当のようなものが出る
のか説明がほしいところである。愛知県名古屋市では正規の議会だけでなく、市長の諮問
する市政調査会(通称部会)に出席しても費用弁償を支給し、さらにその市政調査会のな
い日すら、議会に登庁しただけでその日分の費用弁償を支給し、大いに問題になった。な
お、2004 年5月現在、名古屋市の費用弁償は1日1万円である。
その他にも、議員に認められている海外視察旅行も、自治体の政策に反映され、役に立
つ視察というよりも、勤続年数のある議員へのボーナスとしてとらえられていることが多
く、毎年決まって数人でヨーロッパの観光地へと行くものや、南極に視察に行く議員、オ
リンピック施設の視察という名目で試合観戦をしてくる議員などといった笑えないケース
が多数確認されている。さらに旅行後に提出する報告書もなく何の目的で何をしに行って
きたのかよくわからないケース、報告書を旅行代理店に代筆させるケースもある(請け負
う方も請け負う方だが)。
このような地方議会の不思議な世界はこれまで「議会は自治体の情報公開条例の適用範
囲外」という建前の下で厚いヴェールがかけられてきたが、市民オンブズマンや住民たち
の追及や抗議によって、議会にも情報公開が適用できるケースが多くなってきた。オンブ
ちゃんとそれだけの
仕事してくれてますか?7/7 ページ
ズマンでは情報公開度ランキングとは別に定期的に全国の地方議会に情報公開請求を行い、
議会透明度ランキングを行って、閉鎖的な議会、怪しげな特権を追及し続けている。
また最近問題になっている議員が自治体の職員に圧力をかけて、特定の業者を有利に取
り計らうようにさせるいわゆる口利きをどう摘発し、防止させるかも重要なテーマである。
監査委員改革
監査委員とは自治体の業務や財務全般を監査し、役所のムダや不正を摘発すべく自治体
に設置させる役所から独立した機関である。
その監査委員が「死んだ」とは言い過ぎでは・・・
と思われる方もいるかもしれないが、本来、市民から請求を受けて、役所の不正を調査し、
改善を促すはずの監査委員がまともにチェック機能を果たさず、むしろ、市民からの請求
を「役所に問題なし」と握りつぶしたり、門前払いさせるケースは枚挙にいとまがない。
これは特別悪い人が監査委員になっているからというより、監査委員自体がその役所の職
員OBや地方議会の議員で構成され、また監査委員の事務局の職員もその役所から出向者
で構成されている以上、身内である(あった)役所の職員を厳しく追求しにくいという構
造的な問題でもある。
しかし、だからといって行うべき仕事をしないことが当然許されるわけではなく、オン
ブズマンは監査委員自体の改善こそ役所問題の焦点として(今まで請求をムゲにされてき
た憤りも込めて)、本来不正を監視・追究する側にあるはずの監査委員やそこの職員がカラ
出張や官官接待をさかんに行っている実態を明るみにしてきた。
1999 年度より、このような監査委員のあり方を改めるべく、都道府県や政令市などに、
役所の外部から弁護士や会計士らを契約により監査委員に指名する包括的外部監査制度が
導入された。これは監査委員改革につながるものと期待されているが、オンブズマンでは
今後もチェックが必要として、全国の包括外部監査の「通信簿」づけを行い、緊張感ある
監査の実現・継続を求めている。
2004.6.5-6 名大祭配布資料
全国市民オンブズマン連絡会議