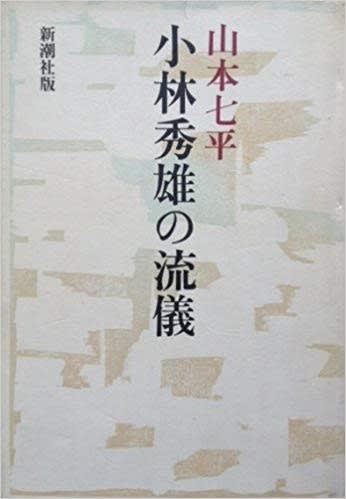
『小林秀雄の流儀』は、「山本学」と言われる山本七平の著作群の中にあっては、継子扱いにされている著作のようだ。そのことは主要著作を網羅した山本七平ライブラリー全16巻には収録されていないという事実に端的に表れている。山本を評価する文章でも、この『小林秀雄の流儀』に触れたものはほとんどないといった有様である。『小林秀雄の流儀』という著作は、「山本学」からは疎外され、排除されている。

にも関わらず文庫本では、PHP文庫、新潮文庫、そして文春学藝ライブラリーと趣を変えて三度も出版されているのは興味深い。恐らく小林秀雄論としての需要によるものであろう。



そして、これらの文庫に収録されている解説も、私には上滑りの文章ばかりで、この著作の精髄を捉えあぐねているように見える。それだけこの著作に入れ込んでいる私の読み方が異端的だとも言えるのだが、それは山本七平という著作家を考えるにあたっては、この本は決して外すことの出来ない最重要の著作、ある意味では自伝である『静かなる細き声』よりも、重要であるとさえ考えているからだ。
これはどういうことかというと、見てきたように橋爪大三郎氏なぞはその典型であるが、批判するにせよ賛美するにせよ、これまでなされてきたほとんどの山本七平に対する論考は、「山本学」とこの『小林秀雄の流儀』との接続がなされていないという点で、ピント外れも甚だしいと考えているからである。逆に言えば、これまで盲点であった「山本学」と『小林秀雄の流儀』との接続がなされることによって、山本七平という思想家の全人的総体的な理解が得られることになり、「山本学」に対しても新たな光を当てることになるという事である。
※ ※ ※
山本の著作を愛読していた私にとって、この本の出現は大げさでなく青天の霹靂であった。
一読、「ああ、そうだったのか!」という驚きとともにずしりとした感銘とも感慨ともつかぬものを受けとめることになったが、その読後感の軛から今現在も抜け出せずにいると言ってよい。それは、この本には小林に対する山本の肺腑の言葉が縷々綴られていたからである。訃に接し、”生き方の秘伝”を学んだ小林の思想に、一気呵成に分け入ってゆく山本の思考が直に綴られていたからである。そして、さらには、露には書かれていないが、小林の思想に対峙する山本の「思想劇」を読み取ることが出来るからである。幾分極端な言い方をすれば、この著作の奥深く隠されているこの「思想劇」こそが、この『小林秀雄の流儀』という著作を駆動する動力であり精髄であって、それが読み取れぬようではこの著作を読んだことにはならないとさえ考えている。
山本は、小林の死に際して原稿依頼を受けた時の衝撃から書き起こしている。
<またいやな声がする。「お前はまさか、それをもう小林秀雄が絶対に読まないと思って、『いいですよ』と言ったのではあるまいな」と。>
<お前は何でそんな衝撃を受けている。・・・衝撃を受けていないとは言わせない。今まで原稿の依頼を受けて、そんな状態になったことが一度でもあったか」と。>
<ある人間からその人の生き方の秘伝とも言うべきものを探り出し、否、探り出したと信じ、その秘伝によって生きてきたと思っている人間には、その存在は「あ、若いときちょっと影響を受けたけどね」と言える対象ではない。>
<だが生み出した人間はそれによって生きている。そしてこの生きているというのが、こういう読者にとっては相当にやっかいな問題だから、生きている限り、何も言いたくないのである。
人がもし、自分に関心のあることにしか目を向けず、言いたいことしか言わず、書きたいことだけを書いて現実に生活していけたら、それはもっとも贅沢な生活だ。そういう生活をした人間がいたら、それは、超一流の生活者であろう。そして私にとっての小林秀雄とは、耐えられぬほどの羨望の的であった。・・・
彼の書いたものは本となって一人歩きをしている。それを徹底的に読めばそれを生み出した人間がわかるはずだ。読者はどう本を読んでもよい。それが読者の特権なら、その特権を徹底的に行使すればよいのだ。私はそれを実行した。否、少なくとも実行したつもりであった。・・・
何を読んだのか、その時点までの彼の作品は全部読んだのだろう。徹底的に読み返し読み返し、暗記するまで読んだはずだ。では今も覚えているか。全部忘れた。否、忘れようと努めた。それでいいのだろう。>
<新潮社から話があったとき受けた衝撃は何だったのだろう。おそらく忘れたことにしていたものが、実は忘れていなかったからである。別の表現を使えば「図星をさされた」のだ。>
<さまざまな出版社が「小林秀雄との対談」の企画をわたしのところに持ち込んで来た。私はいつも生返事をしていた。なぜ、生返事をしたかを自らに問うまい。問うたところで意味はないことだ。小林秀雄は死んだ。会うことは永久にないし、この文章も読むこともない。それでよいのであろう。>
そして、この後に続く小林の思想に一気呵成に分け入ってゆく山本の文章は、要約のできない緊密な文章で、ぜひ全文を読んでいただきたいが、これまで山本七平以外に誰一人として出来なかった小林の思想の深みに分け入っている文章で、そこには幾つもの独創的な読みが散りばめられている。
例えば、小林には「ドストエフスキーの生活」と言う長編評論があるが、この題名に違和感を抱いた人もいるだろう。一般的には、「ドストエフスキーの生涯」とか「ドストエフスキーの一生」といった題名を付けるのが普通であろうが、なぜ「ドストエフスキーの生活」なのであろうか。これを山本はこのように紐解いている。
<というのは、宣長が極力「上代人になって上代人の目」で見ようとしているように、小林秀雄は「宣長になって宣長の目」で見ようとしている。いわば、宣長と小林秀雄の間には「常套的な意味合いでは、作家批評家の別はない」という状態をさす。確かにこれも批評の方法である。そしてそれが出来るのは「言葉と実感」「思想と現実(生活)」を共有しうるからだが、ドストエフスキーでははじめからそれが不可能なことを彼は良く知っている。知っているが故に『生活』と『作品』という腑分けをしている訳であろう。・・・・そのやり方は、「小林秀雄とラスコーリニコフ」で記したから再説しないが、端的に言えばそれは「敵を狙う」という態度であっても、決して「宣長になって宣長の目」で見ようという態度ではない。小林秀雄の聖書やドストエフスキーに対する接し方は非常に用心深く、氏自身の言葉を借りれば、あらゆる方法で正確に狙い、対象を「射止めようと」としているのである。>
つまり、山本によれば、「内部感覚」により小林には比較文化的な視点があって、作品の基盤である文化的な土壌の異なる言わばアウェーの対象に対しては、批評方法として異なるアプローチを取っていた。そういった文化的な土壌の異なる対象に対しては「思想と実生活」というベルクソン直伝の二元論的方法論においては、「思想(作品)」を語る前に、それとは別に「(実)生活」を考察しておく必要があり、それが「ドストエフスキーの生活」であったという解釈である。
そして、山本の独創性は、小林がそもそもなぜ『本居宣長』書いたのかを、これほど的確明確に説明した批評はないという点に端的に表れていると言わなければならない。これまで多くの小林秀雄論を読んできた経験から言えば、これまでこの点に言及した読むに堪える文章は、皆無といった現状の体たらくであるが、例えば、後で述べる山本の理解とこの松岡正剛氏のシニカルな理解とを対比して読み比べてみれば、小林の問題意識をどちらが的確に射抜いているのかは、言うまでもないであろう。
→千夜千冊992夜 小林秀雄 本居宣長
<さあ、どうするか。小林にとっては人格はともかくも、無意識そのものを相手にする気など、ない。石川とちがって、小林は宣長が「無意識の名優」だとも見たくない。
しかし、宣長は自己には毫もこだわらない。自己が一気に日本大ないしは日本小になっていて、そこにしか「まごころ」がないと言っている。しかも宣長は、そういう見方だけが学問や思想をひらく唯一の方法だと考えた。
一方、小林は正直に告白しているのだが、他の思想家にくらべても、宣長の学問的方法にはそうとうの、いや抜群卓抜な説得力があると感じている。けれども、それがすべて日本の思想の根幹であると言われると、困る。
こうして小林が格闘することになったのだ。自問し、自答することになったのである。
小林の『本居宣長』は、小林が自己に問うて自己に答えようとするその自問自答が、つねに宣長を介在させながら進むところが、興味深い。>
松岡氏は「つねに宣長を介在させながら」「小林が自己に問うて自己に答えようとするその自問自答が、興味深い」と述べているが、氏の理解も基本的には、前に述べたような「宣長をダシにして自分語りをしただけだ」といった理解、その一変奏だと言ってよいだろう。
次に本意ではないが、山本の文章を抜き出してみよう。
<「私達は、みな生ま身の俳優となって戦争という一大悲劇を演じたのであった。それは、後になって清算すれば事が済む様な一政治的事件ではなかったのである。・・・・
日が経つにつれて、日本の演じた悲劇の運命的性格、精神史的な顔が明らかになって行くであろう。もしそういう事が起こらなければ、日本の文化にはもう命がないであろう。」
一体この「悲劇の運命的性格、精神史的な顔」とは、どのような性格で、どのような顔なのであろうか。私はそれを、まず明恵上人、北条泰時、玉崎闇斎、浅見絅斎、栗山潜鋒 、三宅観瀾などに求めようとした。小林秀雄は、確かに明恵上人も闇斎も絅斎も取り上げてはいるが、彼の求めた顔と性格は、中江藤樹、熊沢蕃山、伊藤仁斎、荻生徂徠、そして本居宣長であった。一体なぜこれらにそれを求めて、それが本居宣長で帰結したのか。>
<宣長は「古学の世界」を「古学の目」で見、小林秀雄は宣長の目で宣長を見る、ということは宣長が獲得したと信じた「古学の目」で見ている「上代人の世界」を、宣長を見つつ見ているという事である。そしてそこに小林秀雄が見たものは、まさに日本文化そのもの、いわば「その運命的性格と精神史的な顔」である。>
<「漢字漢文の模倣は、自信を持って、徹底的に行われた。・・・・
何故なら、文字と言えば、漢字の他に考えられなかった日本人にとっては、恐らくこれは、漢字によってわが身が実験されるということでもあったからだ。従って、実験を重ね、漢字の扱いに熟練するというそのことが、漢字は日本語を書く為に作られた文字ではない、という意識を磨ぐ事でもあった。口誦のうちに生きていた古語が、漢字で捕らえられて、漢文の格に書かれると、変質して死んで了うという、苦しい意識が目覚める。どうしたらよいか。
この日本語に対する、日本人の最初の反省が『古事記』を書かせた。日本の歴史は、外国文明の模倣によって始まったのではない、模倣の意味を問い、その答えを見つけたところに始まった、『古事記』はそれを証している、言ってみれば、宣長は、そう見ていた」
大分長く引用したが、それは、私にはこれが小林秀雄の自伝のように思えるからだ。>
<「文学は翻訳で読み、音楽はレコードで聞き、絵は複製で見る。誰も彼もが、そうして来たのだ。少なくとも、凡そ近代芸術に関する僕等の最初の開眼は、そういう経験に頼ってなされたのである。翻訳文化と言う軽蔑的な言葉が屡々人の口に上る。尤もな言い分であるが、尤も過ぎれば嘘になる。近代の日本文化が翻訳文化であるという事と、僕らの喜びも悲しみもその中にしかあり得なかったし、現在も未だないという事とは違うのである」(「ゴッホの手紙」序)。この言葉は、「日本の歴史は、外国文明の模倣によって始まったのではない、模倣の意味を問い、その答えを見つけたところに始まった」という言葉に通ずるであろう。そして「知識人は、自国の口頭言語の伝統から、意識して一応離れてはみたのだが、伝統の方で、彼を離さなかった」ように、小林秀雄をも離さなかった。否、離すはずがない。>
<小林秀雄はおそらく『本居宣長』において、自分という本体に出合ったであろう。>
<二十余年ぶりに小林秀雄の著作を手に取った私の動機は少々不純なものであった。否、出版屋としては純粋と言うべきかも知れない。私が驚いたのは、『本居宣長』という書名の四千円(当時)の本が、十万部も売れたということだ。これは社会に衝撃を与えたという事だが、その理由が何であるかを問うてみたかったのだ。というのは、宣長は戦後の社会の興味の対象ではあり得ない。否むしろ否定的存在だったこともあるはずだ。さらに大冊でしかも読みやすい内容ではなさそうで、そのうえ高価である。さらに悪いことに、いわゆる”専門書”ではない。これは出版社にとって最も危険な出版物のはずだ。ではなぜこれが衝撃を与え得たのか。それを探るべく読み、今回読み返してつくづく感じたことは、この本が、日本文化の基本的な問題を、「もしそういう事が起らならければ、日本の文化にはもう命がない」という、まさにその問題を正面から取り上げているからだ。「模倣の意味を問い、その答えを見つけ」ること。それはまさに、過去を語りながら未来を創出することだからである。>
これらの文章で山本が告白していることは、「日本文化の運命的性格と精神史的な顔」という問題、言い換えれば「外国文明の模倣の意味を問い、その答えを見つけなければ、日本の文化にはもう命がない」という課題を小林秀雄から受け取ったという事である。
さらに別の言い方をすれば、日本文化のユニバーサル・モーターとは何かという思想的課題を小林から受け取ったという事である。「山本学」とは、この課題に対する山本の答えに他ならない。









