住所は今里郷495-2。明治12(1879)年の大曽教会設立には真手ノ浦まで含まれていたものと思われる。当時のキリシタンの戸数は片手で数えられる程度しか居なかったのではないかと云われています。
明治30(1897)年、五島列島が上、中、下の3つに小教区が別けられて以来ずっと、真手ノ浦の信徒は桐小教区に属していたが、昭和50年(1975)2月9日真手ノ浦小教区として分離独立した。桐までは、舟で行くにも徒歩で山道をいくつも越えるのも大変難儀な距離。道路も自動車も無かった当時の神父様達は大変だったと思います。
信徒の数が増えてからは宿老宅などを家御堂として使用していたものと思われますが、昭和31年に教会建立。
昭和20年代は戦後の混乱期、上五島はどこの地域でも復員や戦前に職を求めて本土へ出て行っていた人達がいっせいに帰省した為、古いお御堂が手狭になったり、お御堂が無かった地区では教会建設に迫られた頃です。
天井は折上天井。
祭壇はシンプル。古い教会の祭壇は、仏様関連の物を造るのが本職の職人さんが造っていたそうなのだけど、昭和30年頃には職人さんがいなかったのかも知れません。
当初は玄関に扉がつけられていたのですが、改修工事の際、伝統的な玄関に直されました。
真手ノ浦天主堂を投稿するにあたって、タイトルを「天国と地獄」にしようかと迷いました。
市町村合併前はここは旧若松町との町境。
真手ノ浦の向こうは高仏。キリシタン大名時代は南蛮寺が建っていたという由緒正しき場所なのだけど、弾圧時代は眼を覆いたくなるような拷問や弾圧が繰り返されて、殆どのキリシタンが神道祭にコロンでしまった。
旧有川町と旧青方村の上郷地区(青砂ヶ浦と冷水)のキリシタンは、一度はコロンだけれども禁教令の高札が外されたと同時にカトリックに帰依してしまったが、一度コロンでしまった若松のキリシタンは二度と帰依する事はありませんでした。
一般平民にも苗字がつけられた時、若松の役人達は軽蔑や差別の意味を込めて、キリシタンには下口、下村、下窄、下崎、下山、下川といったように苗字の頭に下をつけたと伝えられています。
新上五島町(長崎県)の教会















真手ノ浦天主堂 




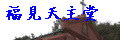
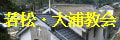


 鯛ノ浦天主堂
鯛ノ浦天主堂

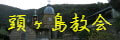
廃墟になった教会














