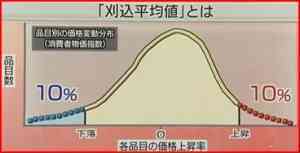■マーケット
消費税増税めぐり市場動揺
きょう財務省が4月の貿易統計を発表しました。貿易統計によりますと、原油安の影響を受けて貿易収支はおよそ8,000億円の黒字でした。このことをうけて、為替市場では円高ドル安が進行。日経平均株価の下げ幅は一時300円を超えました。また、週末に開かれていたG7=財務相・中央銀行総裁会議で、目立った成果がなかったことや、麻生財務大臣がアメリカのルー財務長官との会談で“消費税増税を予定通り行う”との意向を示したことも株式相場に影響を与えています。大和証券のシニアストラテジストの石黒英之氏は「増税は先送りするだろうという期待が株式相場の下支え要因になっていたが、“増税するのでは”との懸念が出てきてこれから1~2週間株式相場の重しになるだろう」と話しました。
女性専用ライドシェアに意外なハードル
スマホアプリなどを通じて一般人のドライバーが運転する車を利用するライドシェア。その代表格ウーバーが生まれたアメリカでは、車内のドライバーと客の間で暴力事件などのトラブルが発生していて、安全面での不安を声にする人が少なくありません。そうしたニーズに応えた新サービスがボストンで始まろうとしています。サービスの名称は「セーフハー」特徴はドライバーも客も女性専用で男性は乗車できないというものです。サービスの発案者は元々ユーバーのドライバーでした。ある日客として乗せた男が車内で大声を上げて騒ぎ出し身の危険を感じたときに「女性専用」というコンセプトを思いつきました。しかし、このサービス、性別による差別を禁止した法律に引っかかるという指摘もあります。
《ダーリアル・ドゥルスキー弁護士》
「雇用上の性差別を禁止する法律がある。客を車に乗せるという公共の空間で差別が法律で禁止されていてどんな客でも乗車を拒否できない。このサービスは潜在的な問題を抱えている。」
安全へのニーズと公平を求める法律の間に挟まったこのサービスが軌道に乗るかはこれからです。
■【コメンテーター】梅澤高明氏(A.T. カーニー 日本法人会長)
・楽観できない出走率・今がラストチャンス
「これ自体は喜ばしい事だが、楽観はできない。何故ならば人口のボリュームゾーンである団塊ジュニアの世代が今40代前半。今はまだ子供が産めるが数年するとほとんど子供を産まない世代になってしまう。そう考えると少子化対策は今がラストチャンスかもしれない。今手を打つべきは社会保障費のシニアから子育て世代への大胆なシフト。話題になっている保育園の拡充や児童手当の拡充にしても原資が必要なので、社会保障費の見直しが根っこにある課題。GDP比で言うと家族向けの社会保障費は日本は1.25%。少子化対策に成功して出生率2.0に戻したフランスは2.85%。これは大きな差で、ここの所にどれだけ手を打てるかが今求められている、数兆円規模で子育て世代へ大胆にシフトできれば、若い人達がストレスなく産む事ができる。」
・新ライドシェアサービス・安全確保は?
--ドライバーも乗客も安全を確保できる仕組みについて
「もしかしたウーバーではもうやっているかもしれないが、ドライバーも乗客を毎回評価しドライバーも乗客を選べるという仕組みでも安全を確保することは可能ではないか。客がドライバーをレイティングし、ドライバーも客をレイティングすることでドライバーも乗客に対する選択権を与える。今後は個人の車でも社内カメラは必需品になっていくだろう」
・地銀が地方創生の推進役を
--伊勢志摩地域で地銀の105銀行が融資だけではない2人3脚の事業を行っている件について
「政府も地方創成の主役として地域金融機関に期待をするという方針を出している。山形銀行は2012年から地域の経済をどう底上げするか経営戦略の2本柱の一つに掲げて地域の成長と自己の収益の拡大と掲げ、地域創成に関わる選任6人のチームを立ち上げお金も出す・人も出す・企画も出すと取り組んでいる。地銀はその地方でのネットワークに強く、地域で一番優秀な人材層も集まっていてお金もありビジネスの関係も情報もある。いろんな動き方ができるので地域の経済を支える役割として重要な役割をしてほしい」
■ニュース
沖縄 女性遺棄事件受け 翁長知事が総理と会談
沖縄県でアメリカ軍関係者の男が、20歳の女性の遺体を遺棄したとして逮捕された事件で、きょう被害者の父親が事件後初めて遺体発見現場を訪れ、花を手向けました。この事件をうけ、沖縄県の翁長知事はきょう、安倍総理大臣と会談し、日米地位協定の改定などを求めました。安倍総理は26日に伊勢志摩サミットに合わせて行われる日米首脳会談でこの事件について取り上げる方針を伝えました。オバマ大統領の歴史的な被爆地広島の訪問を控え、日米同盟の強さを国内外にアピールする絶好の機会と期待が高まっていましたが、日本は一転してアメリカ側に抗議することになります。この事件を受けて沖縄県では来月数万人規模の抗議集会が開かれる予定です。アメリカのケネディ駐日大使は近く沖縄県を訪問する方向で調整しています。
サミット効果を狙い動く地銀
イトーヨーカドーアリオ川口店で伊勢志摩サミットの開催を記念した三重県フェアが始まりました。全国150店舗でも25日から開催されます。三重県産の真鯛や地元の有名ホテルで作られたチーズケーキなど200の品が揃いました。実はこのフェアを仕掛けたのは、三重県を地盤とした百五銀行です。イトーヨーカ堂が三重に店舗を持っていないため、百五銀行が地元企業との橋渡しをして豊富な品揃えが実現しました。地元三重県で百五銀行は、すでにサミット終了後を見据えて動いています。伊勢神宮に隣接する「おはらい町」は、地方創生部が最も力を入れる地域です。地元の蜂蜜専門店に出資し、売り上げを伸ばすなど、店の魅力を発掘することでリピーターを増やそうとしています。また、増加する外国人観光客に対応し、スマホをかざすと外国語が表示されるQRコードの導入も先導しています。こうした取り組みがサミット効果の持続につながるでしょうか?
【サミットに賭ける地銀の挑戦】
26日に始まる伊勢志摩サミットを地元経済の利益に繋げようと、地元では地方銀行が積極的な動きを見せている。その挑戦を追った。
【真鯛!プリン!真珠!三重県フェアの仕掛け人は?】
今日からイトーヨーカドーアリオ川口店で始まったのは、伊勢志摩サミットの開催を記念した三重県フェア。三重県の鈴木英敬知事も出席して、イトーヨーカ堂ではこの店を皮切りに全国150店舗で三重県フェアを開催する。店内には多くの三重の特産品がある。伊勢神宮にも奉納されている三重県産の真鯛に糀屋・糀プリン、鳥羽国際ホテルチーズケーキ、真珠のアクセサリーなど200もの品が揃った。このフェアを仕掛けたのは三重県を地盤とする地方銀行の百五銀行だ。イトーヨーカ堂は三重に店舗を持っていないが百五銀行が地元企業との橋渡しをし、豊富な品ぞろえを実現した。
《百五銀行/伊藤歳恭頭取》
「融資や預金が増えるのは結果として有り難いですけれども、やはり地域の企業全てが幸せになることが私どもの仕事だと思っていますから、その為にできることは何でもする。」
【サミット効果をつなげ!地方銀行の挑戦】
三重県津市にある百五銀行本社地域創生部は、サミット効果を取り込むため今年4月に体制を強化し、これまでの地域創成室から「部」に格上げした。その地域創成部の一人、水谷守孝さんは、伊勢志摩サミット開会が迫る中、既に終了後を見据えていた。
《水谷守孝さん》
「熱が冷めると次の話題に行ってしまうと思うので、ポストサミットとうところでどういう政策を打つかが重要だと思う。」
伊勢神宮に隣接する商店街おはらい町は、地域創生部が最も力を入れる地域だ。伊勢神宮はサミット開催の決定で外国人観光客の数が1年前より約40%増加し、この商店街にも大きな経済効果が出ている。商店街で人気の蜂蜜専門店・松治郎の舗(みせ)は去年、百五銀行が出資する官民ファンドから約1000万円の出資を受けると、店舗を改装しスイートポテトなどテイクアウト商品を拡充した。テイクアウト商品は大ヒットし、店の売り上げは35%増加した。水谷はこうした店の魅力を発掘する事でリピーターを増やそうと考えている。三重県では今後、人口減少が深刻化すると懸念されている。県の観光の象徴であるこの商店街が活性化すれば地域経済が活性化するきっかけになると百五銀行は考えている。さらに百五銀行はスマートフォンをかざすと外国語のメニュー表示が出るQRコードの導入を商店街の店舗に呼びかけていて、伊勢神宮のバス停やATMなどにも設置された。
《百五銀行本社地域創生部/水谷守孝さん》
「(外国人の)満足度を高めて、SNSで発信してもらえれば、次の人が来る。サミット後には五輪もある。その時に三重県を選んでもらうことも今から続けていく必要がある。」
予算3兆円 高速道路大改修
静岡県の東名高速道路。開通から47年経過した高架橋で、道路の床部分、「床版」を一新する工事が実施されていました。本格始動した、東名高速の大規模改修プロジェクト。全国の高速道路の4割が開通後30年以上経過したいま、凍結防止剤の塩分で鉄筋がさびたり、大型車両の交通量の急増で道路に負担がかかったりなどによって、老朽化が進んでいます。NEXCO東日本・中日本・西日本3社は、15年かけて大改修に乗り出します。総事業費はあわせて3兆円規模。高速道路の利用料金ですべての費用を賄う計画で、10年で回収できる見込みです。一連の工事は長期間に及ぶため、利用者に配慮した工夫も。一部の資材は、工事現場でコンクリートを打つのではなく、あらかじめ工場でつくることで、現場での作業量を抑えて工期を減らすものにしています。さらに、現場周辺で、路肩を1つの車線として活用し、渋滞を起こりにくくします。
巨大すぎるペット売り場
東京・荒川区に今週オープンする「ロイヤルホームセンター」。ここの目玉は、全3フロアの内、最上階の約8割を使った「巨大ペット売り場」です。子犬と子猫だけでも約40種類。他にもフクロウにハリネズミなど120種類以上の生き物を買うことができます。さらに、ペット用品は約1万アイテムを揃えました。実は、ペット用品の市場は拡大傾向にあります。ペットフードの出荷額は、2,789億円と2年連続で増加しています。さらに「ペット」関連の物だけ売るのが狙いではありません。「ペット売り場」のすぐ隣には、ゴルフ用品売り場や子供の文房具売り場、そして2階へ降りると洗剤もあります。ペットを目当てに来た家族全体のついで買いで、ホームセンター全体の売り上げアップを狙っています。
日本橋三越が大規模改装
三越伊勢丹ホールディングスは、旗艦店の三越日本橋本店を大規模改装し、2018年春に新装オープンすると発表しました。衣料品の売り場を縮小する一方で、茶器や呉服など日本文化に関わる商品や、絵画などの品揃えを増やし、文化を発信する新しい形の百貨店を目指します。改装のデザインは、建築家の隈研吾氏が手がけます。
ファーストキッチンを売却
サントリーホールディングスは完全子会社であるハンバーガーチェーンの「ファーストキッチン」の全株式を売却することを明らかにしました。売却先は同じくハンバーガーチェーンを運営する「ウェンディ―ズ・ジャパン」で、売却額は公表していません。サントリーは2014年にアメリカのビーム社を1兆6,500億円で買収するなど酒類や清涼飲料といった中核事業に経営資源を集中させる動きを強めています。
出生率微増1.46に
一人の女性が生涯に産む子供の数を示す出生率が去年は1.46と、前の年をわずかに上回ったことが厚生労働省の調査でわかりました。これは、1994年以来21年ぶりの高い水準です。厚労省ではこの理由について「2、3年前には経済環境が好転したため、子供を産もうと考える人が増えたのではないか」としています。一方で、生まれた人の数から死亡した人の数を引いた人口の減少数は過去最大となりました。
5月の景気判断据え置き
政府はきょう、5月の月例経済報告を発表し、「このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」として、景気の基調判断を2ヵ月連続で据え置きました。項目別では、住宅建設の判断を引き上げた一方、企業収益は引き下げました。また政府は、熊本地震による被害額が、熊本、大分両県あわせて2兆4,000億から4兆6,000億円にのぼるとの試算を、初めて公表しました。
東芝 2,399億円減資
経営再建中の東芝は資本金を4,399億円から2,399億円減らし、2,000億円とすることを発表しました。構造改革に伴うリストラ費用の計上やアメリカの原子力事業の子会社の資産価値を見直したことで損失が膨らんでいたため、資本金を取り崩し、財務の改善を図ります。
サラリーマン川柳トップ10
第一生命は、29回目となったサラリーマン川柳コンクールのトップ10を発表しました。今回の応募総数は、3万9,551句。時代を映す、旬のワードを盛り込んだ川柳が多くランクインしました。1位となったのは、無人航空機の「ドローン」と姿をくらます「ドロン」を掛けた一句でした。
■【ロングセラー研究所】オタフクお好みソース
発売開始から今年で64年。現在、日本でいちばん売れているソースが「オタフクお好みソース」だ。オタフクソースの前身である広島の「佐々木商店」は、1950年、ウスターソースの販売を開始。しかし、当時市内で増えていたお好み焼き屋を訪ねると、ウスターソースでは、お好み焼きにかけると鉄板からすぐ流れ落ち、かつ、かけ過ぎると塩辛くなるという問題点があった。それを克服しようと、甘くてドロッとしたソースを開発したのが誕生のきっかけだ。その味を支えているのは、中東原産の「ある果実」。さらに、「お好みソース」を普及させるために、オタフクが現在も続けている「ある取り組み」を取材した。
取材先 ・オタフクソース ・広島焼HIDE坊
■【トレたま】“読める”留守電
留守番電話メッセージをすぐに自動で文字に起こして画面に送るスマホアプリ。実際に試すと名前が間違った以外はすべて正確に9秒で文字になった。タイピング練習ソフトで有名なソースネクストの松田憲幸社長は「メッセージをわざわざ電話確認しなければいけない、確認できる環境にいないケースが多い。」と開発のきっかけを語る。1977年・電電公社が始めた留守電サービス、40年もセンターに問い合わせて留守電を聞くというシステムがあまり変わっておらず、松田社長は開発に至った。
【商品名】スマート留守電
【商品の特徴】自動で留守電メッセージをテキスト化し通知するスマホアプリ
【企業名】ソースネクスト
【住所】東京都港区虎ノ門3-8-21虎ノ門33森ビル6階
【価格】290円(税抜き・iOS版除く)
【発売日】5月23日
【トレたまキャスター】北村まあさ



















 伸びが見込まれています。日本からもソフトバンクが登録ユーザー数2500万人を超えるインド大手通販サイト運営のスナップディールに約670億円を出資し、インドでの足場を築く動きが出ています。
伸びが見込まれています。日本からもソフトバンクが登録ユーザー数2500万人を超えるインド大手通販サイト運営のスナップディールに約670億円を出資し、インドでの足場を築く動きが出ています。