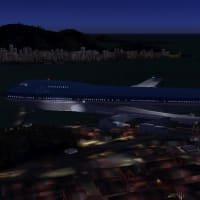たかが離陸、されど離陸... でも事故は向こう側からやってくる。
昨日、ニュースをみていると、123便の事故から21年もたったのかな...
と思い出させてくれる。
でも、FSだって、本物だと、間違いなく大事故になる行為を、
みなさん経験しているはずだ。
とにかく、過去の事故の半分は着陸時に発生している。
確かに、皆さんもご周知のとうり、着陸は大変難しい。
でも、これは技能的要素もあるので、あえて今日は外す。
ということで、今日は、また離陸の話だ。
手順を追ってみよう。
まず、運行計画書を作成する段階から始まる。
飛行機は省エネの意味もあるが、なるべく余計な燃料を積まないよう、計画する。
これにも、いろいろ理由があるが...
さて、この際、打ち合わせがあり、滑走路の工事ゃVORの停波情報、気象情報、
などの再確認が、行われる。
実は、この打ち合わせに穴がある。
滑走路の工事情報の不確認による大事故が、何度も発生している。
あと、離陸にのみ考えるのなら、燃料はなるべく少ない方が良い。
滑走距離が短くなるためだ。
でも、このことを無視して短い滑走路長で、離陸しようとして、
失敗した事故例がある。
さらに、ターミナルをはずれ誘導路を走行中にも、
気をつけなければいけない。
悪天候状態であったが、誘導路上でジャンボ機同士が衝突して、
現状で世界最悪の事故になった。
誘導路から、滑走路に入る際、管制から離陸許可を取ることになるが、
これとて安心できない。
管制から離陸許可を得て進入した、滑走路に着陸機が進入。
両機は滑走路上で激突という痛ましい事故が発生している。
起きた原因は管制塔から、この滑走路が見えないにも関わらず、
離着陸許可をだしてたというお粗末なものだった。
(滑走路の端でスポッターされている方ならお気づきかも知れないが、
滑走路進入前に、着陸機が無いことを副機長サンが頭をさげて確認
されている光景を良く見る。
管制官の指示は、かなり重要だが、ルール上では最終的な判断は
機長が下すことになっている。)
さて、離陸だ。
ここで、フラップの設定を忘れて離陸しようとしたジャンボがある。
もちろん、離陸に失敗。大破して大事故になった。
この事故以来、フラップをいれずに離陸しようとすると、操縦席では警報音が
鳴るそうだ。
さらに,離陸滑走中、V1を超えてから止まろうとした飛行機もあった。
(国内で発生した大事故だ!)
パイロットの常識として、エンジンがどんな状態でもV1を超えると
オーバーランによる機体の大破が待っているので、
何が何でも、離陸しなさいということになっている。
V1というのは、それくらい重要なのだ。
最後に、操縦桿を引いて機体を持ち上げるが、これとて気をぬけない。
最近の機体は、長胴型の機体が多いので、機体のお尻が滑走路に
当たりやすいのだ。
なので、離陸時は、かなり浅く操縦桿を引かなければいけない。
123便の事故だって、元を正せば、着陸時であったが、このシリモチ事故による、
圧力隔壁の修理によって、発生したのだ。
これらは、FSでも十分経験できる話だが、
本物では、絶対あってはいけない行為なのだ。
航空機事故で犠牲になられた方の、ご冥福をお祈りする。