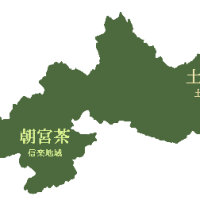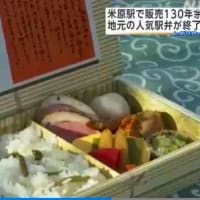単独での維持が困難となっている近江鉄道(本社・彦根市)を巡り、県や沿線市町などでつくる近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会が3月25日(水)、東近江市内で開かれた。
近江鉄道線の存廃について、「地域や年代を問わず、幅広く利用されている不可欠な地域公共交通。福祉や医療、教育のさまざまな分野で多面的な効果を発揮している」として、全線存続で合意した。
今後、自治体などがレールや駅を所有・管理し、近江鉄道が運行を担う「上下分離方式」などといった今後の運営方式と、自治体の財政負担を議論する。
この日は、沿線住民や事業所を対象に行ったアンケート結果のほか、近江鉄道線が持つ交通分野以外の、医療や福祉への多面的な効果を分析して報告した。
効果分析では、近江鉄道が廃止した場合に、分野別に必要となる費用を試算。通院や通学目的のバスやタクシーの運行や、自動車利用が増えることで混雑緩和のための道路整備などが必要になり、代替施策の実施は、近江鉄道線を存続させる場合よりも追加で12億円の費用がかかるとした。
報告を踏まえ、三日月大造知事が出席者の意見を取りまとめ、近江鉄道は「地域にとって欠くことのできない社会資本であり、安全の確保を最優先に、利便性やサービスを向上させることで、価値や役割はさらに高まる」などとして、全線存続で合意した。
◆廃線「通学できず」3割
協議会では、1~2月に沿線五市五町の住民ら1万3700人を対象に実施した、アンケート結果の報告もあった。
対象は駅から原則2km圏内の住民や、駅から徒歩十分程度の事業所の従業員、沿線の学校で学ぶ生徒ら。利用状況、目的、利用したくなる改善点などを尋ね、合計8200人から回答を得た。
利用状況では、沿線高校の生徒の2割が通学で利用し、そのうちの3割は近江鉄道が使えなくなると通学できなくなると回答。通学手段としての必要性が共有された一方、一部の出席者からは「使えなくなったら他校に行くだろう」との冷静な意見もあった。
改善点としては、運行本数の増加や運賃の値下げ、他の路線との乗り継ぎといった声が多く、「潜在的な利用者は相当数見込まれ、利便性を高めることで利用者は増やせる」との認識が示された。
関西大経済学部の宇都宮浄人教授は「回収率が高く、信頼できる結果だ。(自家用車を利用できないなど)いざというときのオプションとしての価値が、くっきり表れている」と講評した。
<中日新聞より>