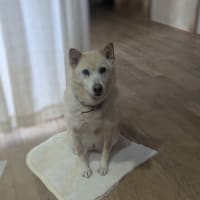※非常勤講師を勤めております前橋国際大学での授業内容を、問題のない部分のみ、ブログ上にアップすることに致しました(資料は大学のLMS上にアップしていますが、引用文など少し長めの文章を載せたものは、スマホの画面ではかなり読みにくいため。ブログ記事であればスマホ上でも何とか読めるだろうと思うので)。
今回は概要を紹介します。
本講義では、花や植物のイメージに着目して、日本文学を読み解きます。
各回概要
1週目…ガイダンス・概要
2週目…『古事記』(石長比売と木花咲耶姫)と『万葉集』(植物のイメージ)
3週目…『源氏物語』の植物と子供の比喩、季節
4週目…『紫式部集』における女性同士の絆
5週目…稚児物語『秋の夜長物語』における植物のイメージ
6週目…『御伽草子』の植物
7週目…近世文学における花のイメージ
8週目…夏目漱石『それから』
9週目…尾崎翠『第七官界彷徨』
10週目…野溝七生子『山梔』
11週目…石井桃子『幻の朱い実』
12週目…まとめ
花にはいろいろなものが喩えられます。
例えば、何年か前に『世界にひとつだけの花』という歌が流行したと思います。
この「花」って何でしょう。
「ナンバーワン」じゃなくてもいい、特別な「オンリーワン」と歌っているわけなので、特別なその人にしかない「個性」を喩えているようにも読めます。
ですがこれ、「花屋の店先」で売られている花なんですよね。
だから、「商品価値」とか、労働力が売れる価値を喩えているようにも見える。
そして花というのは見かけの華やかな美しいものなので、アイドルとしての魅力を喩えているようにも見えるし、花の中で受粉が起こって実や種ができるので、性的な価値かもしれません。
また、女性が花に喩えられることが多いので、女性ではなく男性アイドル集団が歌うことの意味を考えてみても面白いかもしれない。
こんな風に、「花」のイメージを考えることで、いろんなものが見えてきます。
近代以前の文学作品における、花・植物のイメージ
近代以前の花は、生殖や繁栄の比喩となることが多いです。
例えば『源氏物語』では、掛詞から、撫子の花や岩根の松が子供に喩えられます。
『源氏物語』における植物と子供
(例1)藤壺中宮が若宮(のちの冷泉院、実は源氏との子供)出産後、前栽の常夏に付けて、源氏が撫子の花に若宮を重ねる歌をよこす。
(源氏)よそへつゝ見るに心はなぐさまで露けさまさるなでしこの花
花に咲かなんと思ひたまへしも、かひなき世に侍りければ。
とあり。さりぬべきひまにやありけむ、御覧ぜさせて、「たゞ塵ばかり、この花びらに」と聞こゆるを、わが御心にも、ものいとあはれにおぼし知らるゝほどにて、
(藤壺)袖ぬるゝ露のゆかりと思ふにもなほうとまれぬやまとなてしこ(紅葉賀、1巻254頁)
【口語訳】(源氏)「(撫子の花と若宮を)なずらえて(=たとえて)見るにつけても、心は慰められないで、撫子が露に濡れるように、涙がちになる撫子の花である。
(若宮が)花と咲いてほしい(=成長してほしい、繁栄してほしい)と思い申し上げていたことも、甲斐のない世の中でしたので。」
とある。そのような機会があったのか、ご覧にならせて、(王命婦=源氏を手引きした藤壺の女房)「ただ塵ばかりでも(引歌あり)この花びらに(お返事を)」と申し上げるのにつけて、藤壺自身の御心にも、ものがたいへん悲しく思い知られる頃であったので、
(藤壺)「袖が濡れる露と縁があるように、涙を誘うものであるにつけても、やはり疎ましく思われた/思われないやまとなでしこである」
藤壺の生んだ若宮は、表向きは桐壺帝の子と言うことになっていますが、実は源氏の子供です。
「撫子の花」は「撫でし子」との掛詞によって、子供(若宮)を喩えています。
「うとまれぬ」の「ぬ」は文法的には打消とも完了とも取れ、解釈が分かれる部分ですが、現行の注釈書では玉上琢弥『源氏物語評釈』以外のほとんどが完了の意味で取っており、ツベタナ・クリステワ「涙と袖:平安朝の詩学」が打消の解釈を提唱し、藤壺歌を本歌取りした俊成女の歌「咲けば散る花の憂き世と思ふにも猶うとまれぬ山桜かな」(『続古今集』春下、122、「洞院摂政百首歌に、花」)などを証歌としました。その上で「掛詞的に」完了、打消の両方の意味があると解釈することを提案しています(石川九楊責任編集『文学』第二号、京都精華大学文字文明研究所/ミネルヴァ書房、2004年1月)。
(例2)源氏が若君(実は柏木の子供)のことで女三の宮に嫌味
(源氏)「たが世にか種はまきしと人とはゞいかゞいはねの松はこたへん
あはれなり」(柏木、4巻30~31頁)
【口語訳】(源氏)「誰の世にまいた種か(=誰の子供か)と人が尋ねたら、どのようにものを言わない岩根の松のようにものを言わない子供は答えるだろうか。
可哀想だ」
女三の宮が生んだ若君は、源氏との子供と言うことになっていますが、女三の宮にずっと憧れていた柏木という登場人物が、密通してできた子供です。
ここでは、「岩根」と「言わね」を掛け、さらに「いわねの松」に若君を喩えています。
「種をまく」は子供をつくることの比喩で、実は柏木との密通の結果である子供について、誰の子なのか、とほのめかすものです。
ただし、他者から与えられた花・植物のイメージに対し、喩えられた女性自身の行動や言動がずれて行く場面もあります。
例えば『源氏物語』女三の宮は、春(桜や柳)のイメージを与えられますが、本人は春に消える「淡雪」に自分を喩え、自分がいる場所は春の来ない「谷」と言っています。
『源氏物語』女三の宮と季節
(例1)女三の宮と源氏の結婚当初の場面。女三の宮の父朱雀院(源氏の兄)のたっての願いで、女三の宮と源氏は結婚した。それまで紫の上は事実上の正妻に準じるような扱いであったが、紫の上より身分の高い女三の宮が正妻として入って来た状態。女三の宮も紫の上も、六条院(源氏の邸宅で、春、夏、秋、冬の四つの町に分かれている)の春の町にいる。
源氏は三日間女三の宮方に渡るものの、三日目は紫の上を夢に見てまだ暗いうちに帰ってしまう。その日は一日紫の上のところで過ごし、その夜訪れない言い訳に「けさの雪に心地あやまりて」(体調が悪いので)という文を送る(若菜上、3巻245頁)。その翌朝の源氏と女三の宮とのやり取り。
中道をへだつるほどはなけれども心みだるゝけさのあは雪
梅につけ給へり。(中略)
御返り、すこし程経る心地すれば、入り給ひて、女君に花見せたてまつり給ふ。「花と言はば、かくこそ匂はまほしけれな。桜に移しては、また塵ばかりも心分くる方なくやあらまし」などのたまふ。(中略)。
はかなくてうはの空にぞ消えぬべき風にたゞよふ春のあは雪(若菜上、4巻245~246頁)
【口語訳】(源氏)中の道を隔てたというほどではないけれども、淡雪が乱れて降るように、心が乱れる今朝の淡雪である(今日は行きません)。
梅につけてお贈りになる。(中略)
お返事が少し時間が経つような気がするので、中に入って、女君(紫の上)に花(梅の花)をご覧に入れなさる。「花といえば、このように匂ってほしいものであるよ。(梅の香りを)桜に移したならば、また塵ほども心を分ける方向はないだろう(他の女性に浮気することなどない)」などおっしゃる。(中略)
(女三の宮)(あなたの訪れが)はかなくて上空に消えてしまいそうな、風に漂う春の淡雪(のような自分)である。
ここでは、源氏の贈歌、女三の宮の答歌ともに、『後撰和歌集』巻第八 冬
雪の少し降る日、女につかはしける 藤原かげもと
479 かつ消えて空に乱るゝ泡雪は物思ふ人の心なりけり
を引いています。
女三の宮の歌については、乳母が詠んだ歌という説もありますが、女三の宮歌として提示されていることが重要でしょう。
女三の宮歌では、淡雪は女三の宮を喩えるものですが、雪は春に消えるものです。
女三の宮は六条院の春の町におり、源氏の紫の上に対する言葉のなかでは梅の花に喩えられることもあるのですが、女三の宮自身の歌のなかでは春に消える淡雪なのです。
(例2)紫の上死後の幻巻の場面。春、源氏が女三の宮方を訪れる。源氏は心穏やかに仏道修行する女三の宮をうらやましいと思う一方で、やはり女三の宮を心の浅いものと軽く見ているため、女三の宮にすら出家が遅れてしまったことを悔しく思う。仏前の花が夕日に映えて美しい。源氏は春に心を寄せていた紫の上の不在を嘆く。
「(略)。植ゑし人なき春とも知らず顔にて、常よりもにほひ重ねたるこそあはれに侍れ」とのたまふ。御いらへに、「谷には春も」と、何心もなく聞こえ給ふを、言しもこそあれ、心うくも、とおぼさるゝにつけても (幻、4巻194頁)
【口語訳】(源氏)「花を植えた人のない春とも知らないで、いつもよりも美しく咲き誇っている様子が「あはれ」です」とおっしゃる。お返事に、(女三の宮は)「谷には春も」と、他意なく申し上げなさるのを、よりによってそんなことをと、(源氏は)お思いになるにつけても
女三の宮の言葉は、『古今和歌集』巻第十八 雑歌下の、
時なりける人の、にはかに時なくなりて歎くを見て、みづからの歎きもなく喜びもなきことを思ひてよめる 清原深養父
967 光なき谷には春もよそなれば咲きてとく散る物思ひもなし
を引いています。
春の風景を前にし、六条院の春の町にいながら、自分の入る場所を、光のない、春の来ない谷に喩えているのです。
☆近代以前の文学作品における、花・植物のイメージ=生殖や繁栄の比喩
☆ただし、そこからずれる部分もある(本講義ではずれる部分に特に注目する)。
近代以降
近代以降になると、花は、「生殖を禁じられた」存在である少女の比喩として用いられるようになります。生殖や繁栄を象徴することの多かった花が、「生殖を禁じられた」少女の比喩となることで、そのイメージはどう変容するでしょうか。
まず、「少女」の定義や、花と「少女」の結びつきについて簡単に見ておきましょう。
少女とは?
本田和子が、女学校によって女学生の集団が出現、「明治三十年代に簇出した少女雑誌群」が「少女共同幻想体」の成立に関与した(『女学生の系譜:彩色される明治』青土社、1990年)、
大塚英志が、
明治三〇年代、女学校という学校制度と女性雑誌というメディアによって二重に囲い込まれる形で〈少女〉は誕生する(『少女雑誌論』東京書籍、1991年)
今田絵里香が、「「少女」は経済力とともに、西欧文化と教養主義的な文化という新時代に光輝を放つ文化を込められた」者であり(「「少女」の誕生:少女雑誌以前」『「少女」の社会史』勁草書房、2007年。初出『教育学研究』2004年6月)、「女学校に通い、少女雑誌を買い与えられていた女子」、
修身教科書に登場するのは「女子」、高等女学校に存在するのは「女学生」であり、「少女」ではない。(中略)「少女」というジェンダー・アイデンティティを創出し、それに独特の意味を与え、非常にポジティヴな語としてきらびやかに装飾したのはほかでもない少女雑誌であった(同書「序章」)
と指摘するように、純潔規範を課せられ、社会的再生産のシステムから疎外される存在であり、学校制度の整備と教養主義とともに発生したこと、「少女」イメージには少女雑誌が大きく関わることが指摘されています。
少女と園芸
このような少女と花の関わりについて、渡部周子は、「少女は、園芸を通して新たな生命を育み、愛護することを学ぶことが可能だと考えられていた」(「実践教育としての「園芸」:ケア役割の予行」『〈少女〉像の誕生 :近代日本における「少女」規範の形成 』新泉社、2007年)ことを指摘し、さらに園芸が、
明治末期から大正・昭和における少女の教育に波及した際には、(中略)、将来の良妻賢母となる少女たちの身体を純潔のままに保持するうえでの教化の象徴として、機能する(同書「白百合に象徴される規範としての「少女」像」)
こと、特に白百合の花について、「明治期の浪漫主義者」において、「恋愛(プラトニック・ラブ)の対象となる純潔な女性」および、「女性への思慕の念を通して喚起された芸術創造を象徴した」(同書「浪漫主義文学と美術における「少女」像」)と指摘しています。
つまり、少女は「生殖を禁じられた」存在ではあるけれども、その純血性を保持しつつ、将来の愛や子育てといったものを担う情緒を育成する目的で、園芸が使われた、と言うのです。
ですが、将来妻になんかならない、子供なんか作らない、一生少女でいたいという志向に、花が喩えられることもあります。
(例1)野溝七生子『山梔』(1924年)…一生結婚しない、子供も作らないという少女の比喩に白百合や山梔
「昔、昔希臘とトロイが、戦争をしました。そんなお話さ。」
(中略)
「オリムピヤの野に、百合がたくさんたくさん、咲いてゐました。そこにある百合よ。この百合さ。それから、希臘の年若い将軍が、たそがれの野を、真一文字に疾走を続けてゐました。将軍の故里の街では、母さんが門に立つて、その子がもたらして帰る戦勝の便りを、今か今かと待つてゐました。(中略)美しい処女が、(中略)愛人の帰りを待つてゐたのでした。(中略)ああそこに、愛する処女がと思つた時、将軍の膝はくづをれて、はたと百合の花叢の中に、倒れてしまひました。(中略)身動きに槍の石突が、大きな百合の花に触れて、明星の影乍らに将軍の唇に、涙のやうな露がかゝつたのです。彼は、意識をとり戻しました。その処女だと思ふ、百合の花を、鎧の胸甲深く膚に納めて、将軍は、再び立つて、その疾走を続けました。そして故里の門に待つ、なつかしいお母さんの腕に瀕死の身を投げかけて、『勝つたのです。』と只一言、その儘瞼は深く閉ぢられてしまつたのです。(中略)、あゝ将軍の、蒼い瞼は再び、処女を見ることは出来ませんでした。美しいとび色の、長い睫毛を濡らして、処女の涙は将軍の上に散りました。あの、その、この百合の露のやうに。」
阿字子は、さう云つて、空を見て、百合を指して微笑した。(241~242頁)
これは、一生結婚せずに生きていくことを望む女主人公の阿字子が、兄夫婦との関係が悪くなり、家を出る直前、妹の空に語った物語です。ギリシャ神話を下敷きにしていますが、阿字子が自分で作った物語という設定です。
この物語の中で、阿字子はこれから家を出ようとしていることから将軍で、白百合=処女が妹の空を喩えていると思われます。ですので、白百合は直接的に女主人公を喩えるものではないのですが、妹との少女同士の関係が、白百合を通して語られていると見ることもできます。
あるいは、植物の比喩を通して、ちょっと不思議な恋愛が描かれることもあります。
(例2)尾崎翠『第七官界彷徨』(1931年)…蘚が花粉を飛ばす
・「分裂心理学」を研究する兄の一助、蘚の受粉を研究する二助、音楽学校の受験勉強をする従妹の三五郎と、「第七官にひびく」詩を書こうと思っている町子が同居する、「秋から冬にかけての短い期間」の物語。「変な家庭の一員としてすごし」、「ひとつの恋をしたようである」(127頁)とあるが、その「恋」はどうにもぼんやりしている。
(二助)「床の間には恋愛期に入った蘚の鉢をひとつずつ移していくんだ。(中略)僕の勉強部屋は、ああ、蘚の花粉でむせっぽいまでの恋愛部屋となるであろう」(177~178頁)
ここでは、植物が「恋愛」している、との表現が用いられていますが、胞子で殖えるはずの蘚が「受粉」しているのです。
こんな感じで、近代以降の文学については、近代以降に「生殖を禁じられた」存在である少女の比喩として用いられたことによるイメージの変容を見ていきたいと思います。
次回は、『古事記』や『万葉集』における、花のイメージを見ていきます。
※引用は、『新日本古典文学大系 源氏物語』(岩波書店)、『新日本古典文学大系 後撰和歌集』(岩波書店)、『新編日本古典文学全集 古今和歌集』(小学館)、『野溝七生子作品集』(1983年、立風書房)、尾崎翠『第七官界彷徨』(創樹社、1980年)による。
→第2回
今回は概要を紹介します。
本講義では、花や植物のイメージに着目して、日本文学を読み解きます。
各回概要
1週目…ガイダンス・概要
2週目…『古事記』(石長比売と木花咲耶姫)と『万葉集』(植物のイメージ)
3週目…『源氏物語』の植物と子供の比喩、季節
4週目…『紫式部集』における女性同士の絆
5週目…稚児物語『秋の夜長物語』における植物のイメージ
6週目…『御伽草子』の植物
7週目…近世文学における花のイメージ
8週目…夏目漱石『それから』
9週目…尾崎翠『第七官界彷徨』
10週目…野溝七生子『山梔』
11週目…石井桃子『幻の朱い実』
12週目…まとめ
花にはいろいろなものが喩えられます。
例えば、何年か前に『世界にひとつだけの花』という歌が流行したと思います。
この「花」って何でしょう。
「ナンバーワン」じゃなくてもいい、特別な「オンリーワン」と歌っているわけなので、特別なその人にしかない「個性」を喩えているようにも読めます。
ですがこれ、「花屋の店先」で売られている花なんですよね。
だから、「商品価値」とか、労働力が売れる価値を喩えているようにも見える。
そして花というのは見かけの華やかな美しいものなので、アイドルとしての魅力を喩えているようにも見えるし、花の中で受粉が起こって実や種ができるので、性的な価値かもしれません。
また、女性が花に喩えられることが多いので、女性ではなく男性アイドル集団が歌うことの意味を考えてみても面白いかもしれない。
こんな風に、「花」のイメージを考えることで、いろんなものが見えてきます。
近代以前の文学作品における、花・植物のイメージ
近代以前の花は、生殖や繁栄の比喩となることが多いです。
例えば『源氏物語』では、掛詞から、撫子の花や岩根の松が子供に喩えられます。
『源氏物語』における植物と子供
(例1)藤壺中宮が若宮(のちの冷泉院、実は源氏との子供)出産後、前栽の常夏に付けて、源氏が撫子の花に若宮を重ねる歌をよこす。
(源氏)よそへつゝ見るに心はなぐさまで露けさまさるなでしこの花
花に咲かなんと思ひたまへしも、かひなき世に侍りければ。
とあり。さりぬべきひまにやありけむ、御覧ぜさせて、「たゞ塵ばかり、この花びらに」と聞こゆるを、わが御心にも、ものいとあはれにおぼし知らるゝほどにて、
(藤壺)袖ぬるゝ露のゆかりと思ふにもなほうとまれぬやまとなてしこ(紅葉賀、1巻254頁)
【口語訳】(源氏)「(撫子の花と若宮を)なずらえて(=たとえて)見るにつけても、心は慰められないで、撫子が露に濡れるように、涙がちになる撫子の花である。
(若宮が)花と咲いてほしい(=成長してほしい、繁栄してほしい)と思い申し上げていたことも、甲斐のない世の中でしたので。」
とある。そのような機会があったのか、ご覧にならせて、(王命婦=源氏を手引きした藤壺の女房)「ただ塵ばかりでも(引歌あり)この花びらに(お返事を)」と申し上げるのにつけて、藤壺自身の御心にも、ものがたいへん悲しく思い知られる頃であったので、
(藤壺)「袖が濡れる露と縁があるように、涙を誘うものであるにつけても、やはり疎ましく思われた/思われないやまとなでしこである」
藤壺の生んだ若宮は、表向きは桐壺帝の子と言うことになっていますが、実は源氏の子供です。
「撫子の花」は「撫でし子」との掛詞によって、子供(若宮)を喩えています。
「うとまれぬ」の「ぬ」は文法的には打消とも完了とも取れ、解釈が分かれる部分ですが、現行の注釈書では玉上琢弥『源氏物語評釈』以外のほとんどが完了の意味で取っており、ツベタナ・クリステワ「涙と袖:平安朝の詩学」が打消の解釈を提唱し、藤壺歌を本歌取りした俊成女の歌「咲けば散る花の憂き世と思ふにも猶うとまれぬ山桜かな」(『続古今集』春下、122、「洞院摂政百首歌に、花」)などを証歌としました。その上で「掛詞的に」完了、打消の両方の意味があると解釈することを提案しています(石川九楊責任編集『文学』第二号、京都精華大学文字文明研究所/ミネルヴァ書房、2004年1月)。
(例2)源氏が若君(実は柏木の子供)のことで女三の宮に嫌味
(源氏)「たが世にか種はまきしと人とはゞいかゞいはねの松はこたへん
あはれなり」(柏木、4巻30~31頁)
【口語訳】(源氏)「誰の世にまいた種か(=誰の子供か)と人が尋ねたら、どのようにものを言わない岩根の松のようにものを言わない子供は答えるだろうか。
可哀想だ」
女三の宮が生んだ若君は、源氏との子供と言うことになっていますが、女三の宮にずっと憧れていた柏木という登場人物が、密通してできた子供です。
ここでは、「岩根」と「言わね」を掛け、さらに「いわねの松」に若君を喩えています。
「種をまく」は子供をつくることの比喩で、実は柏木との密通の結果である子供について、誰の子なのか、とほのめかすものです。
ただし、他者から与えられた花・植物のイメージに対し、喩えられた女性自身の行動や言動がずれて行く場面もあります。
例えば『源氏物語』女三の宮は、春(桜や柳)のイメージを与えられますが、本人は春に消える「淡雪」に自分を喩え、自分がいる場所は春の来ない「谷」と言っています。
『源氏物語』女三の宮と季節
(例1)女三の宮と源氏の結婚当初の場面。女三の宮の父朱雀院(源氏の兄)のたっての願いで、女三の宮と源氏は結婚した。それまで紫の上は事実上の正妻に準じるような扱いであったが、紫の上より身分の高い女三の宮が正妻として入って来た状態。女三の宮も紫の上も、六条院(源氏の邸宅で、春、夏、秋、冬の四つの町に分かれている)の春の町にいる。
源氏は三日間女三の宮方に渡るものの、三日目は紫の上を夢に見てまだ暗いうちに帰ってしまう。その日は一日紫の上のところで過ごし、その夜訪れない言い訳に「けさの雪に心地あやまりて」(体調が悪いので)という文を送る(若菜上、3巻245頁)。その翌朝の源氏と女三の宮とのやり取り。
中道をへだつるほどはなけれども心みだるゝけさのあは雪
梅につけ給へり。(中略)
御返り、すこし程経る心地すれば、入り給ひて、女君に花見せたてまつり給ふ。「花と言はば、かくこそ匂はまほしけれな。桜に移しては、また塵ばかりも心分くる方なくやあらまし」などのたまふ。(中略)。
はかなくてうはの空にぞ消えぬべき風にたゞよふ春のあは雪(若菜上、4巻245~246頁)
【口語訳】(源氏)中の道を隔てたというほどではないけれども、淡雪が乱れて降るように、心が乱れる今朝の淡雪である(今日は行きません)。
梅につけてお贈りになる。(中略)
お返事が少し時間が経つような気がするので、中に入って、女君(紫の上)に花(梅の花)をご覧に入れなさる。「花といえば、このように匂ってほしいものであるよ。(梅の香りを)桜に移したならば、また塵ほども心を分ける方向はないだろう(他の女性に浮気することなどない)」などおっしゃる。(中略)
(女三の宮)(あなたの訪れが)はかなくて上空に消えてしまいそうな、風に漂う春の淡雪(のような自分)である。
ここでは、源氏の贈歌、女三の宮の答歌ともに、『後撰和歌集』巻第八 冬
雪の少し降る日、女につかはしける 藤原かげもと
479 かつ消えて空に乱るゝ泡雪は物思ふ人の心なりけり
を引いています。
女三の宮の歌については、乳母が詠んだ歌という説もありますが、女三の宮歌として提示されていることが重要でしょう。
女三の宮歌では、淡雪は女三の宮を喩えるものですが、雪は春に消えるものです。
女三の宮は六条院の春の町におり、源氏の紫の上に対する言葉のなかでは梅の花に喩えられることもあるのですが、女三の宮自身の歌のなかでは春に消える淡雪なのです。
(例2)紫の上死後の幻巻の場面。春、源氏が女三の宮方を訪れる。源氏は心穏やかに仏道修行する女三の宮をうらやましいと思う一方で、やはり女三の宮を心の浅いものと軽く見ているため、女三の宮にすら出家が遅れてしまったことを悔しく思う。仏前の花が夕日に映えて美しい。源氏は春に心を寄せていた紫の上の不在を嘆く。
「(略)。植ゑし人なき春とも知らず顔にて、常よりもにほひ重ねたるこそあはれに侍れ」とのたまふ。御いらへに、「谷には春も」と、何心もなく聞こえ給ふを、言しもこそあれ、心うくも、とおぼさるゝにつけても (幻、4巻194頁)
【口語訳】(源氏)「花を植えた人のない春とも知らないで、いつもよりも美しく咲き誇っている様子が「あはれ」です」とおっしゃる。お返事に、(女三の宮は)「谷には春も」と、他意なく申し上げなさるのを、よりによってそんなことをと、(源氏は)お思いになるにつけても
女三の宮の言葉は、『古今和歌集』巻第十八 雑歌下の、
時なりける人の、にはかに時なくなりて歎くを見て、みづからの歎きもなく喜びもなきことを思ひてよめる 清原深養父
967 光なき谷には春もよそなれば咲きてとく散る物思ひもなし
を引いています。
春の風景を前にし、六条院の春の町にいながら、自分の入る場所を、光のない、春の来ない谷に喩えているのです。
☆近代以前の文学作品における、花・植物のイメージ=生殖や繁栄の比喩
☆ただし、そこからずれる部分もある(本講義ではずれる部分に特に注目する)。
近代以降
近代以降になると、花は、「生殖を禁じられた」存在である少女の比喩として用いられるようになります。生殖や繁栄を象徴することの多かった花が、「生殖を禁じられた」少女の比喩となることで、そのイメージはどう変容するでしょうか。
まず、「少女」の定義や、花と「少女」の結びつきについて簡単に見ておきましょう。
少女とは?
本田和子が、女学校によって女学生の集団が出現、「明治三十年代に簇出した少女雑誌群」が「少女共同幻想体」の成立に関与した(『女学生の系譜:彩色される明治』青土社、1990年)、
大塚英志が、
明治三〇年代、女学校という学校制度と女性雑誌というメディアによって二重に囲い込まれる形で〈少女〉は誕生する(『少女雑誌論』東京書籍、1991年)
今田絵里香が、「「少女」は経済力とともに、西欧文化と教養主義的な文化という新時代に光輝を放つ文化を込められた」者であり(「「少女」の誕生:少女雑誌以前」『「少女」の社会史』勁草書房、2007年。初出『教育学研究』2004年6月)、「女学校に通い、少女雑誌を買い与えられていた女子」、
修身教科書に登場するのは「女子」、高等女学校に存在するのは「女学生」であり、「少女」ではない。(中略)「少女」というジェンダー・アイデンティティを創出し、それに独特の意味を与え、非常にポジティヴな語としてきらびやかに装飾したのはほかでもない少女雑誌であった(同書「序章」)
と指摘するように、純潔規範を課せられ、社会的再生産のシステムから疎外される存在であり、学校制度の整備と教養主義とともに発生したこと、「少女」イメージには少女雑誌が大きく関わることが指摘されています。
少女と園芸
このような少女と花の関わりについて、渡部周子は、「少女は、園芸を通して新たな生命を育み、愛護することを学ぶことが可能だと考えられていた」(「実践教育としての「園芸」:ケア役割の予行」『〈少女〉像の誕生 :近代日本における「少女」規範の形成 』新泉社、2007年)ことを指摘し、さらに園芸が、
明治末期から大正・昭和における少女の教育に波及した際には、(中略)、将来の良妻賢母となる少女たちの身体を純潔のままに保持するうえでの教化の象徴として、機能する(同書「白百合に象徴される規範としての「少女」像」)
こと、特に白百合の花について、「明治期の浪漫主義者」において、「恋愛(プラトニック・ラブ)の対象となる純潔な女性」および、「女性への思慕の念を通して喚起された芸術創造を象徴した」(同書「浪漫主義文学と美術における「少女」像」)と指摘しています。
つまり、少女は「生殖を禁じられた」存在ではあるけれども、その純血性を保持しつつ、将来の愛や子育てといったものを担う情緒を育成する目的で、園芸が使われた、と言うのです。
ですが、将来妻になんかならない、子供なんか作らない、一生少女でいたいという志向に、花が喩えられることもあります。
(例1)野溝七生子『山梔』(1924年)…一生結婚しない、子供も作らないという少女の比喩に白百合や山梔
「昔、昔希臘とトロイが、戦争をしました。そんなお話さ。」
(中略)
「オリムピヤの野に、百合がたくさんたくさん、咲いてゐました。そこにある百合よ。この百合さ。それから、希臘の年若い将軍が、たそがれの野を、真一文字に疾走を続けてゐました。将軍の故里の街では、母さんが門に立つて、その子がもたらして帰る戦勝の便りを、今か今かと待つてゐました。(中略)美しい処女が、(中略)愛人の帰りを待つてゐたのでした。(中略)ああそこに、愛する処女がと思つた時、将軍の膝はくづをれて、はたと百合の花叢の中に、倒れてしまひました。(中略)身動きに槍の石突が、大きな百合の花に触れて、明星の影乍らに将軍の唇に、涙のやうな露がかゝつたのです。彼は、意識をとり戻しました。その処女だと思ふ、百合の花を、鎧の胸甲深く膚に納めて、将軍は、再び立つて、その疾走を続けました。そして故里の門に待つ、なつかしいお母さんの腕に瀕死の身を投げかけて、『勝つたのです。』と只一言、その儘瞼は深く閉ぢられてしまつたのです。(中略)、あゝ将軍の、蒼い瞼は再び、処女を見ることは出来ませんでした。美しいとび色の、長い睫毛を濡らして、処女の涙は将軍の上に散りました。あの、その、この百合の露のやうに。」
阿字子は、さう云つて、空を見て、百合を指して微笑した。(241~242頁)
これは、一生結婚せずに生きていくことを望む女主人公の阿字子が、兄夫婦との関係が悪くなり、家を出る直前、妹の空に語った物語です。ギリシャ神話を下敷きにしていますが、阿字子が自分で作った物語という設定です。
この物語の中で、阿字子はこれから家を出ようとしていることから将軍で、白百合=処女が妹の空を喩えていると思われます。ですので、白百合は直接的に女主人公を喩えるものではないのですが、妹との少女同士の関係が、白百合を通して語られていると見ることもできます。
あるいは、植物の比喩を通して、ちょっと不思議な恋愛が描かれることもあります。
(例2)尾崎翠『第七官界彷徨』(1931年)…蘚が花粉を飛ばす
・「分裂心理学」を研究する兄の一助、蘚の受粉を研究する二助、音楽学校の受験勉強をする従妹の三五郎と、「第七官にひびく」詩を書こうと思っている町子が同居する、「秋から冬にかけての短い期間」の物語。「変な家庭の一員としてすごし」、「ひとつの恋をしたようである」(127頁)とあるが、その「恋」はどうにもぼんやりしている。
(二助)「床の間には恋愛期に入った蘚の鉢をひとつずつ移していくんだ。(中略)僕の勉強部屋は、ああ、蘚の花粉でむせっぽいまでの恋愛部屋となるであろう」(177~178頁)
ここでは、植物が「恋愛」している、との表現が用いられていますが、胞子で殖えるはずの蘚が「受粉」しているのです。
こんな感じで、近代以降の文学については、近代以降に「生殖を禁じられた」存在である少女の比喩として用いられたことによるイメージの変容を見ていきたいと思います。
次回は、『古事記』や『万葉集』における、花のイメージを見ていきます。
※引用は、『新日本古典文学大系 源氏物語』(岩波書店)、『新日本古典文学大系 後撰和歌集』(岩波書店)、『新編日本古典文学全集 古今和歌集』(小学館)、『野溝七生子作品集』(1983年、立風書房)、尾崎翠『第七官界彷徨』(創樹社、1980年)による。
→第2回