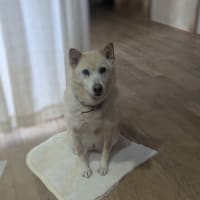アップロードしていたCunugiのサービスが4月24日で終了しますので、
こちらに記事を移しました。
* * * * * * * * *
私は去年(2021年)の春、初めてのお人形を迎えた。上半身はあばらが見えるほどに痩せて腕はないけれど、少し悲しげに見える顔立ちは整っていて可愛らしい。吸い込まれそうに大きな瞳は青のガラス、赤茶のまつげがきちんと生えていて、髪は白に近いブロンド、ビーズのついた白い衣装を着て、たくましい太ももから細くしまった足首まですっとのびた素晴らしい脚に、擦り切れた薔薇色のタイツと白いトゥシューズをはいている。手のひらに乗るほどの大きさの、お尻のかたちがとても良い。


人形作家・中川多理さんの作品で、『夜想』山尾悠子特集特装版(1)のためにつくられたものだ。小説『夢の棲む街』(2)に登場する、「薔薇色の脚」と呼ばれる踊り子たちをモチーフとしている。
山尾悠子は硬質華麗な文体と、言葉で完璧に構築された作品世界で知られる作家で、初期の代表作『夢の棲む街』は、架空の街を舞台とするカタストロフを描く小説である。
街は「浅い漏斗型」(10頁)で、底に当たる中心部分に「円形劇場」(9頁)がある円環構造をもつ。「街の噂を収集しそれを街中に広めること」を「仕事」とする「夢喰い虫」でありながら、「日暮れ時」に「街のうわさをささや」く(10頁)「〈夢喰い虫〉の儀式にもう数箇月間も参加できずにいた」「中途半端な存在」(11頁)である「バク」を語り手とする。
「薔薇色の脚」と呼ばれるのは、「太めの腰から伸びている適度に肉のついた腿とふくらはぎ、よく締まった足首」という「下半身とは対照的に上半身は全く無視され、筋肉は栄養失調と運動不足で萎えたように縮み」「骨格までもがひとまわり大きさが縮んでいるため、飢餓状態の子供ほどの大きさに干からびて」(13頁)いる、円形劇場の踊り子たちのこと。中川多理さんのお人形は、見事な下半身は小説のイメージそのままに、やせ細った上半身はそれでもぎりぎり美しいバランスに保たれている。
彼女たちはもともと、「演出家たち」が「狩り集め」てきた「街の乞食や浮浪者または街娼」であるが、「街の噂」によれば、演出家たちが「彼女たちの脚にコトバを吹き込むことによって」「薔薇色の脚」に創りあげられるのだという(13頁)。
彼女たちは、「知覚がまだ残っているのかどうか」「いつでも一言も言葉を発しなかった」(同)のだが、ある日集団失踪して捕獲されたのちに、ひとりが次のように告白する。
そして「踊り子を出せ」と叫ぶ観客たちへの対応を
と議論していた演出家たちは、舞台に上がり演説を始めるものの…。怒り狂った観客に撲殺されてしまう。すると、「直立していた〈脚〉の群れ」が唐突に「身震いし」、舞台に駆け上がる。脚たちは「一夜かけて踊り狂」い(15頁)、死んでしまうが、その様子を見ると、「上半身は下半身によって完全に吸収され尽くし」ていた(16頁)。
ところが物語末尾のカタストロフの瞬間に、この「脚」は、再び現れる。
異変が起こり、繰り返し「あのかた」の「顕現」が囁かれるある日、「あのかた」からの招待状が街の人々のもとに届く。街の人々や夢喰い虫たちが円形劇場に集まる中、「バク」は地下の楽屋が気になり、入り口の上蓋をこじ開けようとしながら、「あのかた」の名を大声で呼び、「中に、いるのか?」「本当は、いやしないんだろう!」(42頁)と言うが…。そのとき、大時計が深夜零時をさし、「機械仕掛の鐘の音」が鳴り終えると「同時にゼンマイの弾ける音がして、ぴたりと針が針が停止」する(同)。「地下で落盤が起きたらしく」(同)、円柱も硝子も崩壊し、座席は人々とともに中心に向かって雪崩落ちる。
* * * * * * * * *
「言葉と脚」の関係について考え始めたのは、いつのことだっただろうか。「きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ」(9頁)という書き出しの印象的な須賀敦子の美しいエッセイ『ユルスナールの靴』(3)には高校生の頃に出会い、感銘を受けたはずだったけれども、「靴」が言葉の比喩であることに気づいたのはずっと後、自分が言葉によってしか生きられないことを悟った頃だっただろう。
ポール・ヴァレリー(4)による比喩や、ヴィルヘルム・イェンゼンの『グラディーヴァ』(5)、ヴァルター・ベンヤミンの「遊歩者(フラヌール)」(6)まで…、ヨーロッパ文学においては、歩くことを文芸行為になぞらえる発想はなじみ深いものだろう。日本においても、例えば百人一首にも入っている有名な小式部内侍の歌「大江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立 」のような、「文」と「踏み」の掛詞は、そういうものの一つと言えなくもない。
とりわけ『夢の棲む街』における「薔薇色の脚」たちの舞踏、「コトバ」を吹き込まれたり、抜き取られたりする脚たちの舞踏が「言葉を超えて美しく」と言葉によって表現されることは、ヴァレリーによる、散文を歩行に、韻文を舞踏になぞらえる比喩を思わせる。
(中略)
『夢の棲む街』は小説という散文でありながら、街のかたち、街の噂、そして語りの構造が漏斗状の底にある円形劇場にすべてなだれ込むような円環構造が強調されているから、おそらくかなり意識的に、散文=歩行、詩=舞踏という比喩が踏まえられ、「薔薇色の脚」の舞踏を、一回きりの詩的な瞬間として描いている。
そしてもうひとつ考えたいのが、男性である演出家たちが、女性である街の女たちに、言葉を吹き込むという権力構造だ。それによって街の女たちは「薔薇色の脚」となり、自らの言葉も上半身も失ってしまう。小谷真理(9)は『夢の棲む街』を読んで、「かつてロートレックやドガが愛おしみつつ画布に描かずにはいられなかった」(9頁)「パリの踊り子たちの絵画」の「後ろ側」に「恐怖」を感じずにいられなくなった(10頁)ことを語っている。「特定の観客に奉仕されるべく生み出された被虐的な人工物」であり、「女とは観念的に描かれるとこういうかたちを採るのかもしれない」(9頁)と。今ではロートレックやドガの「踊り子」についても、(男性が)描き、(女性が)描かれる(ジェンダー不均衡な)権力構造を読み取ることは常識だろうけれど、その権力関係が、『夢の棲む街』のなかでは、「コトバ」をめぐる演出家たちと脚たちとの関係に描きこまれている。
思い返せば、何かを言葉や絵筆で描く行為だけでなく、私たち研究者が常日頃行っている、作品に対する解釈や研究も、対象を言葉で切り取り、言葉をあてはめる、暴力的で権力的な行為である。
須賀敦子『ユルスナールの靴』は、自分に「ぴったり」の言葉を探してさまよった著者の旅を、20世紀フランスの作家マルグリット・ユルスナールの人生と重ねつつ語るものだった。それは、まだ女性が学問をすることが珍しく、「言葉」が男性(だけ)のものであった時代に、自分のものとしての「言葉」を模索し、つくりだす行為でもある。
私にとっては何かの作品を対象とし、論文やエッセイを書くこともまた、『ユルスナールの靴』と同様に、「ぴったり」の言葉を模索する行為だった。
けれども、自分にとって「ぴったり」であることを求めるあまり、言葉を作品に無理やりあてはめてしまうと、それが研究でなくなってしまうばかりか、作品に対する暴力にもなる。シンデレラの義姉たちが、小さな靴に合わせて自分のかかとや足指を切り落としてしまったように、言葉に合わせて作品を切り落としてしまっては…。一方的に作品を切り刻み、作品の言葉を無視し、自分にとって都合のよいものに作り替え、作品を殺してしまったら、一方的に薔薇色の脚にコトバを吹き込んだ演出家たちが観客に撲殺され、脚たちに踏み潰されてしまったように、研究者としての死がもたらされる。
私は作品の声に耳を傾け、声に言葉を与え、寄り添い、時には一緒に踊るような研究者でありたい。
私は彼女と、いっしょに踊りたい。
*引用文は、『山尾悠子作品集成』(国書刊行会、1999年)、須賀敦子『ユルスナールの靴』(河出文庫、1998年)による。
1、ステュディオ・パラボリカ、2021年。
http://www.yaso-peyotl.com/archives/2021/03/yaso_yamao_tokusoban.html
2、初出、『SFマガジン』7(1976年)。現在最も入手しやすいのは、文庫版『増補 夢の遠近法 初期作品選』(ちくま文庫、2014年)、『新編 夢の棲む街』(ステュディオ・パラボリカ、2022年)
3、初出『文藝』1994年11月~1996年5月。
4、Paul Valéry[1871~1945]、「フランスの詩人・批評家。マラルメに師事し、純粋詩の理論を確立。詩「若きパルク」、評論「レオナルド=ダ=ビンチの方法序説」「バリエテ」など」("バレリー【Paul Valéry】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2021-06-07))。
5、イエンゼン(Jensen, Wilhelm[1837~1911]は「ドイツの作家」。「ポンペイを舞台にした小説」『グラディーヴァ』(Gradiva, 1903)は、「フロイトによって取り上げられ,その成果は精神分析の文学理論のさきがけとなった」("イェンゼン(Jensen, Wilhelm)", 岩波 世界人名大辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2021-06-07))。
「グラディーヴァ」とは、「歩み行く女」の意であり、右足のかかとをほとんど垂直に立てている特徴的な歩き方をする女を描いたレリーフが重要なモチーフとなり、そのレリーフにそっくりの容姿と歩き方をするヒロインが登場する。
6、ベンヤミン(Walter Benjamin[1892―1940])は「ドイツ・フランクフルト学派の批評家」。「フラヌールflâneur(遊歩者)」は、ベンヤミンが「19世紀の都市を考察するにあたって,重要なキーワードの一つとして」「注目した」、「現代の都市論に欠かせぬ基本的な概念」。「都市の生産的機能からへだてられ」ながら、「都市の自意識をもっとも鋭いかたちで表現する」存在であり、「娼婦や犯罪者など,都市のアンダーグラウンドに棲息する者たちのよき理解者でもあった」(前田愛、"遊民", 世界大百科事典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2021-06-07))。
7、「詩人の手帖」佐藤正彰訳(落合太郎、鈴木信太郎、渡辺一夫、佐藤正彰監修『ヴァレリー全集6 詩について』筑摩書房、1967年)。
8、同「詩話」
9、「脚と薔薇の日々」『山尾悠子作品集成』「栞」国書刊行会、1999年。
こちらに記事を移しました。
* * * * * * * * *
私は去年(2021年)の春、初めてのお人形を迎えた。上半身はあばらが見えるほどに痩せて腕はないけれど、少し悲しげに見える顔立ちは整っていて可愛らしい。吸い込まれそうに大きな瞳は青のガラス、赤茶のまつげがきちんと生えていて、髪は白に近いブロンド、ビーズのついた白い衣装を着て、たくましい太ももから細くしまった足首まですっとのびた素晴らしい脚に、擦り切れた薔薇色のタイツと白いトゥシューズをはいている。手のひらに乗るほどの大きさの、お尻のかたちがとても良い。


人形作家・中川多理さんの作品で、『夜想』山尾悠子特集特装版(1)のためにつくられたものだ。小説『夢の棲む街』(2)に登場する、「薔薇色の脚」と呼ばれる踊り子たちをモチーフとしている。
山尾悠子は硬質華麗な文体と、言葉で完璧に構築された作品世界で知られる作家で、初期の代表作『夢の棲む街』は、架空の街を舞台とするカタストロフを描く小説である。
街は「浅い漏斗型」(10頁)で、底に当たる中心部分に「円形劇場」(9頁)がある円環構造をもつ。「街の噂を収集しそれを街中に広めること」を「仕事」とする「夢喰い虫」でありながら、「日暮れ時」に「街のうわさをささや」く(10頁)「〈夢喰い虫〉の儀式にもう数箇月間も参加できずにいた」「中途半端な存在」(11頁)である「バク」を語り手とする。
「薔薇色の脚」と呼ばれるのは、「太めの腰から伸びている適度に肉のついた腿とふくらはぎ、よく締まった足首」という「下半身とは対照的に上半身は全く無視され、筋肉は栄養失調と運動不足で萎えたように縮み」「骨格までもがひとまわり大きさが縮んでいるため、飢餓状態の子供ほどの大きさに干からびて」(13頁)いる、円形劇場の踊り子たちのこと。中川多理さんのお人形は、見事な下半身は小説のイメージそのままに、やせ細った上半身はそれでもぎりぎり美しいバランスに保たれている。
彼女たちはもともと、「演出家たち」が「狩り集め」てきた「街の乞食や浮浪者または街娼」であるが、「街の噂」によれば、演出家たちが「彼女たちの脚にコトバを吹き込むことによって」「薔薇色の脚」に創りあげられるのだという(13頁)。
毎夜演出家たちは踊り子の足の裏に唇を押しあてて、薔薇色のコトバを吹き込む。ひとつのコトバが吹き込まれるたびに脚はその艶を増していくが、下半身が脂ののった魚の皮膚のような輝きを持つにつれて畸型の上半身は徐々に生気を失ってゆき(同)
彼女たちは、「知覚がまだ残っているのかどうか」「いつでも一言も言葉を発しなかった」(同)のだが、ある日集団失踪して捕獲されたのちに、ひとりが次のように告白する。
コトバがひとつ吹き込まれるたびに、私たちの脚は重くなる。私たちとて踊り子の端くれ、コトバのない世界の縁を、爪先立って踊ってみたい気があったのだ、と。それを聞いた演出家たちは怒り狂い、踊り子たちの脚からコトバを抜き取ってしまった(中略)が、そのとたんに脚たちは力を失い、死んだように動かなくなってしまったのだという。(14頁)
そして「踊り子を出せ」と叫ぶ観客たちへの対応を
今こそ我々が踊る時だ、と一人が叫んだ。
踊り子たちの〈脚〉はなくとも、我々のペン胼胝のある手や運動不足でむくんだ脚を、コトバは覆い隠してくれる筈だ!(12頁)
踊り子たちの〈脚〉はなくとも、我々のペン胼胝のある手や運動不足でむくんだ脚を、コトバは覆い隠してくれる筈だ!(12頁)
と議論していた演出家たちは、舞台に上がり演説を始めるものの…。怒り狂った観客に撲殺されてしまう。すると、「直立していた〈脚〉の群れ」が唐突に「身震いし」、舞台に駆け上がる。脚たちは「一夜かけて踊り狂」い(15頁)、死んでしまうが、その様子を見ると、「上半身は下半身によって完全に吸収され尽くし」ていた(16頁)。
(演出家たちの、引用者)撲殺屍体は、巨人の脚と化した踊り子たちの轟く足の裏に踏み潰され、血潮にまみれたわずかな肉片となって舞台の石造りの床にこびりついているだけなのだった。
こうして、この夜を最後に劇場の踊り子は死に絶え、その製造方法を知っていた演出家たちも全員死亡したため、再び街に〈薔薇色の脚〉の姿が見られることはなかった。しかしその夜死に至るまで踊り続けた脚の群れはあらゆる言葉を飛び越えて美しく、それはまさに光り輝くようだったという。(16~17頁)
こうして、この夜を最後に劇場の踊り子は死に絶え、その製造方法を知っていた演出家たちも全員死亡したため、再び街に〈薔薇色の脚〉の姿が見られることはなかった。しかしその夜死に至るまで踊り続けた脚の群れはあらゆる言葉を飛び越えて美しく、それはまさに光り輝くようだったという。(16~17頁)
ところが物語末尾のカタストロフの瞬間に、この「脚」は、再び現れる。
異変が起こり、繰り返し「あのかた」の「顕現」が囁かれるある日、「あのかた」からの招待状が街の人々のもとに届く。街の人々や夢喰い虫たちが円形劇場に集まる中、「バク」は地下の楽屋が気になり、入り口の上蓋をこじ開けようとしながら、「あのかた」の名を大声で呼び、「中に、いるのか?」「本当は、いやしないんだろう!」(42頁)と言うが…。そのとき、大時計が深夜零時をさし、「機械仕掛の鐘の音」が鳴り終えると「同時にゼンマイの弾ける音がして、ぴたりと針が針が停止」する(同)。「地下で落盤が起きたらしく」(同)、円柱も硝子も崩壊し、座席は人々とともに中心に向かって雪崩落ちる。
巨大な裸足の脚が、一撃で大地を踏み割ったようなある〈音〉が中空に轟いて、がん、と反響した音がその瞬間凝結し、同時にすべてが静止した。(43頁)
* * * * * * * * *
「言葉と脚」の関係について考え始めたのは、いつのことだっただろうか。「きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ」(9頁)という書き出しの印象的な須賀敦子の美しいエッセイ『ユルスナールの靴』(3)には高校生の頃に出会い、感銘を受けたはずだったけれども、「靴」が言葉の比喩であることに気づいたのはずっと後、自分が言葉によってしか生きられないことを悟った頃だっただろう。
ポール・ヴァレリー(4)による比喩や、ヴィルヘルム・イェンゼンの『グラディーヴァ』(5)、ヴァルター・ベンヤミンの「遊歩者(フラヌール)」(6)まで…、ヨーロッパ文学においては、歩くことを文芸行為になぞらえる発想はなじみ深いものだろう。日本においても、例えば百人一首にも入っている有名な小式部内侍の歌「大江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立 」のような、「文」と「踏み」の掛詞は、そういうものの一つと言えなくもない。
とりわけ『夢の棲む街』における「薔薇色の脚」たちの舞踏、「コトバ」を吹き込まれたり、抜き取られたりする脚たちの舞踏が「言葉を超えて美しく」と言葉によって表現されることは、ヴァレリーによる、散文を歩行に、韻文を舞踏になぞらえる比喩を思わせる。
散文から詩への、言葉から歌への、歩行から舞踏への推移。――同時に行為であり夢であるこの瞬間。(7)
歩行は散文と同じく常に明確な一対象を有します。それはある対照に向って進められる一行為であり、われわれの目的はその対象に辿り着くに在ります。
(中略)
舞踏と言えば全く別物です。それはいかにも一行為体系には違いないが、しかしそれらの行為自体のうちに己が窮極を有するものであります。舞踏はどこにも行きはしませぬ。(8)
『夢の棲む街』は小説という散文でありながら、街のかたち、街の噂、そして語りの構造が漏斗状の底にある円形劇場にすべてなだれ込むような円環構造が強調されているから、おそらくかなり意識的に、散文=歩行、詩=舞踏という比喩が踏まえられ、「薔薇色の脚」の舞踏を、一回きりの詩的な瞬間として描いている。
そしてもうひとつ考えたいのが、男性である演出家たちが、女性である街の女たちに、言葉を吹き込むという権力構造だ。それによって街の女たちは「薔薇色の脚」となり、自らの言葉も上半身も失ってしまう。小谷真理(9)は『夢の棲む街』を読んで、「かつてロートレックやドガが愛おしみつつ画布に描かずにはいられなかった」(9頁)「パリの踊り子たちの絵画」の「後ろ側」に「恐怖」を感じずにいられなくなった(10頁)ことを語っている。「特定の観客に奉仕されるべく生み出された被虐的な人工物」であり、「女とは観念的に描かれるとこういうかたちを採るのかもしれない」(9頁)と。今ではロートレックやドガの「踊り子」についても、(男性が)描き、(女性が)描かれる(ジェンダー不均衡な)権力構造を読み取ることは常識だろうけれど、その権力関係が、『夢の棲む街』のなかでは、「コトバ」をめぐる演出家たちと脚たちとの関係に描きこまれている。
思い返せば、何かを言葉や絵筆で描く行為だけでなく、私たち研究者が常日頃行っている、作品に対する解釈や研究も、対象を言葉で切り取り、言葉をあてはめる、暴力的で権力的な行為である。
須賀敦子『ユルスナールの靴』は、自分に「ぴったり」の言葉を探してさまよった著者の旅を、20世紀フランスの作家マルグリット・ユルスナールの人生と重ねつつ語るものだった。それは、まだ女性が学問をすることが珍しく、「言葉」が男性(だけ)のものであった時代に、自分のものとしての「言葉」を模索し、つくりだす行為でもある。
私にとっては何かの作品を対象とし、論文やエッセイを書くこともまた、『ユルスナールの靴』と同様に、「ぴったり」の言葉を模索する行為だった。
けれども、自分にとって「ぴったり」であることを求めるあまり、言葉を作品に無理やりあてはめてしまうと、それが研究でなくなってしまうばかりか、作品に対する暴力にもなる。シンデレラの義姉たちが、小さな靴に合わせて自分のかかとや足指を切り落としてしまったように、言葉に合わせて作品を切り落としてしまっては…。一方的に作品を切り刻み、作品の言葉を無視し、自分にとって都合のよいものに作り替え、作品を殺してしまったら、一方的に薔薇色の脚にコトバを吹き込んだ演出家たちが観客に撲殺され、脚たちに踏み潰されてしまったように、研究者としての死がもたらされる。
私は作品の声に耳を傾け、声に言葉を与え、寄り添い、時には一緒に踊るような研究者でありたい。
私は彼女と、いっしょに踊りたい。
*引用文は、『山尾悠子作品集成』(国書刊行会、1999年)、須賀敦子『ユルスナールの靴』(河出文庫、1998年)による。
1、ステュディオ・パラボリカ、2021年。
http://www.yaso-peyotl.com/archives/2021/03/yaso_yamao_tokusoban.html
2、初出、『SFマガジン』7(1976年)。現在最も入手しやすいのは、文庫版『増補 夢の遠近法 初期作品選』(ちくま文庫、2014年)、『新編 夢の棲む街』(ステュディオ・パラボリカ、2022年)
3、初出『文藝』1994年11月~1996年5月。
4、Paul Valéry[1871~1945]、「フランスの詩人・批評家。マラルメに師事し、純粋詩の理論を確立。詩「若きパルク」、評論「レオナルド=ダ=ビンチの方法序説」「バリエテ」など」("バレリー【Paul Valéry】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2021-06-07))。
5、イエンゼン(Jensen, Wilhelm[1837~1911]は「ドイツの作家」。「ポンペイを舞台にした小説」『グラディーヴァ』(Gradiva, 1903)は、「フロイトによって取り上げられ,その成果は精神分析の文学理論のさきがけとなった」("イェンゼン(Jensen, Wilhelm)", 岩波 世界人名大辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2021-06-07))。
「グラディーヴァ」とは、「歩み行く女」の意であり、右足のかかとをほとんど垂直に立てている特徴的な歩き方をする女を描いたレリーフが重要なモチーフとなり、そのレリーフにそっくりの容姿と歩き方をするヒロインが登場する。
6、ベンヤミン(Walter Benjamin[1892―1940])は「ドイツ・フランクフルト学派の批評家」。「フラヌールflâneur(遊歩者)」は、ベンヤミンが「19世紀の都市を考察するにあたって,重要なキーワードの一つとして」「注目した」、「現代の都市論に欠かせぬ基本的な概念」。「都市の生産的機能からへだてられ」ながら、「都市の自意識をもっとも鋭いかたちで表現する」存在であり、「娼婦や犯罪者など,都市のアンダーグラウンドに棲息する者たちのよき理解者でもあった」(前田愛、"遊民", 世界大百科事典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2021-06-07))。
7、「詩人の手帖」佐藤正彰訳(落合太郎、鈴木信太郎、渡辺一夫、佐藤正彰監修『ヴァレリー全集6 詩について』筑摩書房、1967年)。
8、同「詩話」
9、「脚と薔薇の日々」『山尾悠子作品集成』「栞」国書刊行会、1999年。