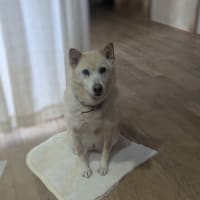こんにちは。久しぶりに本の話題です。
佐藤亜紀さんの新刊『スウィングしなけりゃ意味がない』(角川書店、2017年)について。かなり好評を博しております。
タイトルからも分かる通り、ジャズが重要なテーマとなっており、ハンブルクの空襲やナチスのユダヤ人政策など、様々な観点から考察することが可能です。…が、ご本人が参考文献もあげておりますし、そちらの方面からの考察は得意な方にお任せし、私は、湖や雨、空から降ってくるもの、空襲の炎などに注目して考察します(長くなりそうなので、今日は水のイメージのみ)。
******
1.水の都
言わずと知れた世紀末ロマン文学に、ローデンバッハの『死都ブリュージュ』がある。亡き妻に酷似した踊り子にのめり込む主人公が、最終的に彼女の首を絞めて殺すという、それだけと言えばそれだけの、しょうもないと言えばしょうもない話なのだが、霧と雨に降りこめられた陰鬱な都市ブリュージュの描き方が素晴らしい。それだけに、ブリュージュを殺した、として批判もされた。
本書『スウィングしなけりゃ意味がない』が舞台とするのは、第二次大戦中のハンブルク。ハンブルクは大きな湖アルスター湖を取り囲むように発展した、「ハンザ都市」「七百五十何年だかの歴史」(309頁)のある都市だ。ハンブルクのブルジョワである、語り手エディと仲間たちがはまるのは、「敵性音楽」であるジャズ。
消費と青春を謳歌する彼らの世界はあっけらかんと明るい。エディの家の「地下室の防火扉」を開け放った裏庭には、「アルスター湖から水を引き込んだフェーンタイヒの水面」(67頁)があり、仲間たちは芝生の上に置いたデッキチェアに座り、あるいはパンチを飲み、あるいは水面で戯れる。地下室からはジャズのレコードが流れる。
けれども戦況の進展とともに、ハンブルクは徐々に「死の都」として描かれるようになる。例えば空襲によって工場が焼けてしまった後、ふ抜けたようになってしまった両親に、エディが違和感を抱く場面。
「古い映画をまた見てるような気になる。子供の頃のぼくの家、みたいな。七十とかになってから、親が生きていた頃に撮ったフィルムを見てるみたいな」
しばらく黙り込んでから、死の都、とマックスは言う。「ここは死の都だ。ぼくはそう思ってる」
(中略)
「だいぶ前だね。何かが死んで、それで全部死んでしまった。もちろん、ぼくもとっくに死んでいる。それはちょっと辛い。ちょっとだけだけど。(中略)でもやっぱり死んでいるんだ」(253頁)
自分たちが青春を過ごした時代に回帰してしまったかのような両親について、「古い映画」を見ているみたいな気分になるというエディに対し、天才的なピアニストでジャズも弾くマックスは、「だいぶ前」からここを「死の都」だと思っていたと言う。マックスは八分の一ユダヤ人で、かつて両親を自動車事故で亡くし、二分の一ユダヤ人の祖母は、ユダヤ人と結婚しているために100パーセントのユダヤ人の扱いを受けるようになってしまった姪一家が当局に出頭を命じられた後、首を吊って自殺してしまった。
やがてそのような感慨を、エディも抱くようになる。空襲で両親が死んでしまった後。
死の都、とマックスが言ったもの――そのものではないとしても、ごく近い何かが目の前に現れる。確かに何かが死んだのを、ぼくは感じる。ハンブルクはもうぼくの知っていた町ではない。それどころか、ぼくの知っていたぼくも死んでいる。これは誰か別の人間か――でなければ死人のぼくだ。(261頁)
空襲で建物が破壊された街は、遠くどこまでも見渡せる。「近くで言うと、ランガーツークのむこうのマックスの家の二階の窓まで見て取れる。ほら、誰かがカーテンを開いた。あれは婆さんの寝室の窓だ」(262頁)。マックスの祖母は、すでに首を吊って亡くなっている。
海や湖、川などがあるとき、その向こう岸、つまり彼岸を死者の世界とするのがふつうの発想だろう。けれども、いつの間にか彼岸が生の世界、此岸が死者の世界へと変わってしまう。例えば海の向こう、イギリスに行くことを夢見たエディの両親は、海の向こうには行けずに空襲で亡くなってしまった。あるいは、ジャズ仲間の一人デュークとその恋人のエヴァについて。デュークは、警察とけんかしたかどで有罪になり、前線に出征することが決まったとき、出征する前にエヴァと結婚し、フリースラントの祖母の家を訪れた。そして「着いた翌日、夜が明ける前に」「祖母の家から姿を消した」(176頁)。「この国では生きてはいけない」(177頁)という「遺書」があり、「近所でボートが一艘盗まれて、後で干潟の沖合で発見された」(同)ために、自殺したものと見なされたが、「Vサインするチャーチル」(同)の落書きのある制服を祖母から見せられたエディは、デュークとエヴァが生きていて、国外に逃げ出したことを確信する。「陸路でもデンマークに潜り込むことは可能だ。海路で小さく迂回するならなおさら簡単だろう」(同)、「そこから半島を横切ってバルト海に出て、スウェーデンに渡る」(177~178頁)。海のこちら側の「この国」は生きていける場所ではなく、海の向こう側がむしろ、生の世界となっているのだ。しかもエヴァは、貧しくてまともな衣類を持っていなかったために、あんなにイギリスに行くことを夢見ていたエディの母のむかしの衣装をもらって着ていた。
それにしても、マックスがハンブルクを「死の都」だと思うようになったのはいつのことだろう。街が空襲でめちゃめちゃになったとき? 祖母が首を吊ったとき? 戦争が始まったとき? いや、それよりもっと前、「両親が自動車事故で死んだ時」「ヨットに乗って、閘門から川まで出して、海まで行って、戻って来た」(81頁)ときだろう。「以来、もう何も感じない」(同)。死のほんの手前まで行って、帰ってきたのだから。
だからマックスの音楽は、水のイメージ――ハンブルクの湖の、そして自分が死の手前まで行った海のイメージに満ちている。「風向きのせいで港の水位はひたひたと上がり、暗い雲が冷たい風と共に押し寄せ、雪さえちらつ」く夜、マックスは「雨の庭」を弾く。
こんな寒い晩に、北海からの風が海水をどんどん川を遡らせ港の水を押し上げる晩に、「雨の庭」。冷たい水位が上がっていく。靴の中までずぶ濡れだ。妙にきんきんと一番上の音を強調して響かせると、まるで氷が張るように「雨の庭」は一箇所で動かなくなる。異様な和音がピアノを揺さぶる。ピアノも自分にこんな音が出せるとは知らなくて泡を食うような音だ。
マックスはドビュッシーを、ぐいっ、とスウィングさせた。目が覚めたような気がした。幾つもの和音の下から、最高にホットなリズムを出現させた。(中略)
マックスは、徹頭徹尾、本気だった。(55頁)
マックスが天才的なのは、ピアノだけではない。ボートを操る技術も際立っている。例えば空襲の夜、火炎による風を避けるために帆をおろした船の中で、「マックスだけが炎に背を向け前方に目を据えたままおそろしく真面目な顔で舵を操っている」(244頁)、「マックスはゆっくりと確実に舵を入れながら、空気と水の一番柔らかい場所を手探りで切り裂く」(244~245頁)。エディの家が燃えた夜も、マックスは火が点いてしまったヨットに水をかけて消し、「不規則な波にひどく揺られながら湖に出」て、「暗いロンデルタイヒの水路に船を泊めて」「ウーレンホルストの炎のむこうで炎上するバルムベックへと吹く強風をやり過ごす」(257頁)。湖に浮かび、水と風の流れを読む技術に秀でたマックスは、水と縁が深い。マックスの祖母は「ハンブルクの白鳥」と呼ばれたというが、マックスもやはり「ハンブルクの白鳥」なのだ。
湖のイメージに注目したとき、何度も(水面下に)「潜る」という比喩が用いられることも重要だろう。エディと仲間たちは、非合法でジャズのレコードを作り、売りさばく商売を始めるのだが、それに関わって「潜る」(212頁)「Uボートする」(211頁)という表現が用いられるのだ。結局空襲があまりにひどくなり、レコードが売りさばけるような状況ではなくなったため、「Uボート」しないのだが。
続き
******
長くなりそうなのでひとまずここまで。続きはそのうち掲載します☆
☆おまけ☆
実家で一時預かり中の保護犬ちゃん、すくすく成長して15㎏くらいになってます。
→2020年1月2日に急逝しました。
譲渡会に行った時の写真。

 (右は、おんなじ保護主さんが保護しているわんちゃんです)
(右は、おんなじ保護主さんが保護しているわんちゃんです)
→保護主さんのブログです。おうちで暮らそう
佐藤亜紀さんの新刊『スウィングしなけりゃ意味がない』(角川書店、2017年)について。かなり好評を博しております。
タイトルからも分かる通り、ジャズが重要なテーマとなっており、ハンブルクの空襲やナチスのユダヤ人政策など、様々な観点から考察することが可能です。…が、ご本人が参考文献もあげておりますし、そちらの方面からの考察は得意な方にお任せし、私は、湖や雨、空から降ってくるもの、空襲の炎などに注目して考察します(長くなりそうなので、今日は水のイメージのみ)。
******
1.水の都
言わずと知れた世紀末ロマン文学に、ローデンバッハの『死都ブリュージュ』がある。亡き妻に酷似した踊り子にのめり込む主人公が、最終的に彼女の首を絞めて殺すという、それだけと言えばそれだけの、しょうもないと言えばしょうもない話なのだが、霧と雨に降りこめられた陰鬱な都市ブリュージュの描き方が素晴らしい。それだけに、ブリュージュを殺した、として批判もされた。
本書『スウィングしなけりゃ意味がない』が舞台とするのは、第二次大戦中のハンブルク。ハンブルクは大きな湖アルスター湖を取り囲むように発展した、「ハンザ都市」「七百五十何年だかの歴史」(309頁)のある都市だ。ハンブルクのブルジョワである、語り手エディと仲間たちがはまるのは、「敵性音楽」であるジャズ。
消費と青春を謳歌する彼らの世界はあっけらかんと明るい。エディの家の「地下室の防火扉」を開け放った裏庭には、「アルスター湖から水を引き込んだフェーンタイヒの水面」(67頁)があり、仲間たちは芝生の上に置いたデッキチェアに座り、あるいはパンチを飲み、あるいは水面で戯れる。地下室からはジャズのレコードが流れる。
けれども戦況の進展とともに、ハンブルクは徐々に「死の都」として描かれるようになる。例えば空襲によって工場が焼けてしまった後、ふ抜けたようになってしまった両親に、エディが違和感を抱く場面。
「古い映画をまた見てるような気になる。子供の頃のぼくの家、みたいな。七十とかになってから、親が生きていた頃に撮ったフィルムを見てるみたいな」
しばらく黙り込んでから、死の都、とマックスは言う。「ここは死の都だ。ぼくはそう思ってる」
(中略)
「だいぶ前だね。何かが死んで、それで全部死んでしまった。もちろん、ぼくもとっくに死んでいる。それはちょっと辛い。ちょっとだけだけど。(中略)でもやっぱり死んでいるんだ」(253頁)
自分たちが青春を過ごした時代に回帰してしまったかのような両親について、「古い映画」を見ているみたいな気分になるというエディに対し、天才的なピアニストでジャズも弾くマックスは、「だいぶ前」からここを「死の都」だと思っていたと言う。マックスは八分の一ユダヤ人で、かつて両親を自動車事故で亡くし、二分の一ユダヤ人の祖母は、ユダヤ人と結婚しているために100パーセントのユダヤ人の扱いを受けるようになってしまった姪一家が当局に出頭を命じられた後、首を吊って自殺してしまった。
やがてそのような感慨を、エディも抱くようになる。空襲で両親が死んでしまった後。
死の都、とマックスが言ったもの――そのものではないとしても、ごく近い何かが目の前に現れる。確かに何かが死んだのを、ぼくは感じる。ハンブルクはもうぼくの知っていた町ではない。それどころか、ぼくの知っていたぼくも死んでいる。これは誰か別の人間か――でなければ死人のぼくだ。(261頁)
空襲で建物が破壊された街は、遠くどこまでも見渡せる。「近くで言うと、ランガーツークのむこうのマックスの家の二階の窓まで見て取れる。ほら、誰かがカーテンを開いた。あれは婆さんの寝室の窓だ」(262頁)。マックスの祖母は、すでに首を吊って亡くなっている。
海や湖、川などがあるとき、その向こう岸、つまり彼岸を死者の世界とするのがふつうの発想だろう。けれども、いつの間にか彼岸が生の世界、此岸が死者の世界へと変わってしまう。例えば海の向こう、イギリスに行くことを夢見たエディの両親は、海の向こうには行けずに空襲で亡くなってしまった。あるいは、ジャズ仲間の一人デュークとその恋人のエヴァについて。デュークは、警察とけんかしたかどで有罪になり、前線に出征することが決まったとき、出征する前にエヴァと結婚し、フリースラントの祖母の家を訪れた。そして「着いた翌日、夜が明ける前に」「祖母の家から姿を消した」(176頁)。「この国では生きてはいけない」(177頁)という「遺書」があり、「近所でボートが一艘盗まれて、後で干潟の沖合で発見された」(同)ために、自殺したものと見なされたが、「Vサインするチャーチル」(同)の落書きのある制服を祖母から見せられたエディは、デュークとエヴァが生きていて、国外に逃げ出したことを確信する。「陸路でもデンマークに潜り込むことは可能だ。海路で小さく迂回するならなおさら簡単だろう」(同)、「そこから半島を横切ってバルト海に出て、スウェーデンに渡る」(177~178頁)。海のこちら側の「この国」は生きていける場所ではなく、海の向こう側がむしろ、生の世界となっているのだ。しかもエヴァは、貧しくてまともな衣類を持っていなかったために、あんなにイギリスに行くことを夢見ていたエディの母のむかしの衣装をもらって着ていた。
それにしても、マックスがハンブルクを「死の都」だと思うようになったのはいつのことだろう。街が空襲でめちゃめちゃになったとき? 祖母が首を吊ったとき? 戦争が始まったとき? いや、それよりもっと前、「両親が自動車事故で死んだ時」「ヨットに乗って、閘門から川まで出して、海まで行って、戻って来た」(81頁)ときだろう。「以来、もう何も感じない」(同)。死のほんの手前まで行って、帰ってきたのだから。
だからマックスの音楽は、水のイメージ――ハンブルクの湖の、そして自分が死の手前まで行った海のイメージに満ちている。「風向きのせいで港の水位はひたひたと上がり、暗い雲が冷たい風と共に押し寄せ、雪さえちらつ」く夜、マックスは「雨の庭」を弾く。
こんな寒い晩に、北海からの風が海水をどんどん川を遡らせ港の水を押し上げる晩に、「雨の庭」。冷たい水位が上がっていく。靴の中までずぶ濡れだ。妙にきんきんと一番上の音を強調して響かせると、まるで氷が張るように「雨の庭」は一箇所で動かなくなる。異様な和音がピアノを揺さぶる。ピアノも自分にこんな音が出せるとは知らなくて泡を食うような音だ。
マックスはドビュッシーを、ぐいっ、とスウィングさせた。目が覚めたような気がした。幾つもの和音の下から、最高にホットなリズムを出現させた。(中略)
マックスは、徹頭徹尾、本気だった。(55頁)
マックスが天才的なのは、ピアノだけではない。ボートを操る技術も際立っている。例えば空襲の夜、火炎による風を避けるために帆をおろした船の中で、「マックスだけが炎に背を向け前方に目を据えたままおそろしく真面目な顔で舵を操っている」(244頁)、「マックスはゆっくりと確実に舵を入れながら、空気と水の一番柔らかい場所を手探りで切り裂く」(244~245頁)。エディの家が燃えた夜も、マックスは火が点いてしまったヨットに水をかけて消し、「不規則な波にひどく揺られながら湖に出」て、「暗いロンデルタイヒの水路に船を泊めて」「ウーレンホルストの炎のむこうで炎上するバルムベックへと吹く強風をやり過ごす」(257頁)。湖に浮かび、水と風の流れを読む技術に秀でたマックスは、水と縁が深い。マックスの祖母は「ハンブルクの白鳥」と呼ばれたというが、マックスもやはり「ハンブルクの白鳥」なのだ。
湖のイメージに注目したとき、何度も(水面下に)「潜る」という比喩が用いられることも重要だろう。エディと仲間たちは、非合法でジャズのレコードを作り、売りさばく商売を始めるのだが、それに関わって「潜る」(212頁)「Uボートする」(211頁)という表現が用いられるのだ。結局空襲があまりにひどくなり、レコードが売りさばけるような状況ではなくなったため、「Uボート」しないのだが。
続き
******
長くなりそうなのでひとまずここまで。続きはそのうち掲載します☆
☆おまけ☆
→2020年1月2日に急逝しました。
譲渡会に行った時の写真。

 (右は、おんなじ保護主さんが保護しているわんちゃんです)
(右は、おんなじ保護主さんが保護しているわんちゃんです)→保護主さんのブログです。おうちで暮らそう