岡山からの帰り道に備前焼の伊部(いんべ)に立ち寄った。
私はコーヒーが飲めない。紅茶もたいして好きではない。
以前テレビ見た大阪空堀商店街のお茶屋さんが
飛び込みで来るタレントに煎茶腕でお茶を入れて飲ませていた。
煎茶は熱々ではなくぬるめがよいと言う。
私は夏でも冬でも熱々フウフウのお茶がよい。
恥ずかしながら、それこそが日本茶と思っていた。
テレビからも「こんなぬるくていいんですか?」と。
しかし一口飲むと一応にカルチャーショックを受けている。
実に旨そうだった。
それが気になり、私も煎茶腕で日本茶を入れて
カルチャーショックを受けたいと
備前焼の伊部(いんべ)に立ち寄ったのだ。
別に備前焼でなくてもよいのだが白のセラミックでは味気ない。
素人は素人らしく○○焼というブランドから入りたいのだ。
だから備前焼でも丹波焼でもたこ焼?でもよい。
とにかくブランド第一主義だ。
というわけで、たまたま岡山に来たので備前焼になった。
しかし備前焼は、とにかくシブイ。
私には似合わないが、ここはまず形から。
とはいえ焼き物はチンプンカンプン。選び方もわからない。
仕方ないので店の方に選んでもった。
たまたま接客してくれた女主人が話上手で、
彼女のお爺さんが作ったものをだしてくれた。

彼女によると備前焼では煎茶用の
小型の急須を作る職人が少ないらしい。
私の欲しいのは、注ぎ口の内側に茶こしがついている急須。
茶葉をこす為の小さな穴は、
すべてひとつひとつ人の手で開けられたもので
見ているだけで飽きない。これだけでも価値がある。
しかも金網の金属臭がない。

その備前焼の代表的な焼きは「胡麻(ごま)」「桟切(さんぎり)」
「火襷(ひだすき)」の三種と教えてくれた。
胡麻(ごま)とは、胡麻のような粒の模様。

桟切(さんぎり)とは、黒から灰青色などの色の変化が
模様となっている。

火襷(ひだすき)は、素地に藁を巻いて
火があたるのを避けてたところに藁の模様を残したもの。

彼女のお爺さんが作った煎茶腕の中から彼女の選んだ一品は
「胡麻」と「桟切」の二種が表れている。
火襷は全く違うので今回はなし。
彼女の勧めるままに煎茶腕と茶碗を2卓買うことにした。
彼女の助言を元に、まず鍋に水を張りコンロ点火。
沸騰する手前で火を止めそのまま冷めるまで放置。
こうすることで強度が増す(らしい)。
備前焼はピカピカした光沢は少なく
土の色合いが全面に押し出されシブイ、かつ地味だ。
しかし使えば使うほど光沢がでてきて
シブさがさらに増す(らしい)。
では試飲。
お湯を50度までさまし、たっぷり目に煎茶を入れた急須に注ぐ。
煎茶は阪急百貨店で買ってきた上等なお茶だ。
近くのイオンでオハギも購入し準備播但線。
出発進行!
まず一服目は、ぬるめ、ぬるめ。
さてお味はいかに・・
なんじゃこりゃ。これぞお茶。
甘くてほのかに渋味があり、奥が深い。
恥ずかしながら初めて舌が感じる味わいだ。
しかしぬるいなぁ。
二服目は一服目より少し熱めで・・旨い。
貧乏人の私にとっては二服目は最高だ。
私って今まで舌音痴だったのかと不安になる旨さだ。
三服目はさらに熱めで。
まだまだいける。味が深い。
私は日本酒が大好きだが年間70~80日は休肝日を設けている。
しかし今回の体験で日本茶があればあと10日は延長できそうだ(笑)
いゃ~参りました。
今後、コーヒーいりません(元々飲めないけど)。
今後、紅茶いりません(リプトンティーパックしか飲んだことないけど)。
やっぱりこれからは、日本人らしく、日本茶やね。
私はコーヒーが飲めない。紅茶もたいして好きではない。
以前テレビ見た大阪空堀商店街のお茶屋さんが
飛び込みで来るタレントに煎茶腕でお茶を入れて飲ませていた。
煎茶は熱々ではなくぬるめがよいと言う。
私は夏でも冬でも熱々フウフウのお茶がよい。
恥ずかしながら、それこそが日本茶と思っていた。
テレビからも「こんなぬるくていいんですか?」と。
しかし一口飲むと一応にカルチャーショックを受けている。
実に旨そうだった。
それが気になり、私も煎茶腕で日本茶を入れて
カルチャーショックを受けたいと
備前焼の伊部(いんべ)に立ち寄ったのだ。
別に備前焼でなくてもよいのだが白のセラミックでは味気ない。
素人は素人らしく○○焼というブランドから入りたいのだ。
だから備前焼でも丹波焼でもたこ焼?でもよい。
とにかくブランド第一主義だ。
というわけで、たまたま岡山に来たので備前焼になった。
しかし備前焼は、とにかくシブイ。
私には似合わないが、ここはまず形から。
とはいえ焼き物はチンプンカンプン。選び方もわからない。
仕方ないので店の方に選んでもった。
たまたま接客してくれた女主人が話上手で、
彼女のお爺さんが作ったものをだしてくれた。

彼女によると備前焼では煎茶用の
小型の急須を作る職人が少ないらしい。
私の欲しいのは、注ぎ口の内側に茶こしがついている急須。
茶葉をこす為の小さな穴は、
すべてひとつひとつ人の手で開けられたもので
見ているだけで飽きない。これだけでも価値がある。
しかも金網の金属臭がない。

その備前焼の代表的な焼きは「胡麻(ごま)」「桟切(さんぎり)」
「火襷(ひだすき)」の三種と教えてくれた。
胡麻(ごま)とは、胡麻のような粒の模様。

桟切(さんぎり)とは、黒から灰青色などの色の変化が
模様となっている。

火襷(ひだすき)は、素地に藁を巻いて
火があたるのを避けてたところに藁の模様を残したもの。

彼女のお爺さんが作った煎茶腕の中から彼女の選んだ一品は
「胡麻」と「桟切」の二種が表れている。
火襷は全く違うので今回はなし。
彼女の勧めるままに煎茶腕と茶碗を2卓買うことにした。
彼女の助言を元に、まず鍋に水を張りコンロ点火。
沸騰する手前で火を止めそのまま冷めるまで放置。
こうすることで強度が増す(らしい)。
備前焼はピカピカした光沢は少なく
土の色合いが全面に押し出されシブイ、かつ地味だ。
しかし使えば使うほど光沢がでてきて
シブさがさらに増す(らしい)。
では試飲。
お湯を50度までさまし、たっぷり目に煎茶を入れた急須に注ぐ。
煎茶は阪急百貨店で買ってきた上等なお茶だ。
近くのイオンでオハギも購入し準備播但線。
出発進行!
まず一服目は、ぬるめ、ぬるめ。
さてお味はいかに・・
なんじゃこりゃ。これぞお茶。
甘くてほのかに渋味があり、奥が深い。
恥ずかしながら初めて舌が感じる味わいだ。
しかしぬるいなぁ。
二服目は一服目より少し熱めで・・旨い。
貧乏人の私にとっては二服目は最高だ。
私って今まで舌音痴だったのかと不安になる旨さだ。
三服目はさらに熱めで。
まだまだいける。味が深い。
私は日本酒が大好きだが年間70~80日は休肝日を設けている。
しかし今回の体験で日本茶があればあと10日は延長できそうだ(笑)
いゃ~参りました。
今後、コーヒーいりません(元々飲めないけど)。
今後、紅茶いりません(リプトンティーパックしか飲んだことないけど)。
やっぱりこれからは、日本人らしく、日本茶やね。

















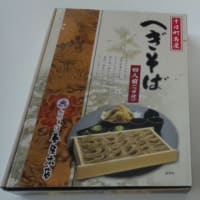


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます