だんじりとは鳴り物(大太鼓、半鐘、二丁鐘、小太鼓)を
叩く楽団を乗せた乗り物だ。
神さんが乗る神輿の後ろで鳴り物を鳴らして、
神さんが降臨・昇天しやすいように囃す。

5月5日は本宮。
この日の朝、神さんは神輿に降臨され、
その日一日限定で町民の無病息災や五穀豊穣などを祈ってくれる。
そして夜、昇天される。
一年に一度の来訪だ。
その前日の5月4日は宵宮。
いわば前夜祭で、だんじりは町中を練り歩き
「神さんが明日来られますよ」と鳴り物で告知する。
従って4日はまだ神さんは降臨していない。
神輿は神さんが乗る乗り物なので神社が管理するのに対して、
だんじりは氏子が管理する。氏子が裕福であればあるほど、
だんじりは、大きくきらびやかになる傾向にある。
ある意味いいかげんなので基本は口伝になる。
文書の記録が残っていないことが多いので定かではないが、
私のいる空区のだんじりが最も古いとされており、
江戸時代後期の作と言われている。
かっては住吉地区7台のだんじりの中で最も大きかったが、
7台のだんじりが入る長屋が本住吉神社の境内に建てられてからは
各区ともだんじり小屋にギリギリ入るサイズにまで巨大化させており、
空区のだんじりが一番と誇れなくなってきた。
今年も住之江区のだんじりが新調され、
ひときはきらびやかに巨大化している。
住吉地区には9つの区があるが、
これまでだんじりは7台しかなかった。
しかし昨年、反高林区が1台購入して今は8台に。
あと1台!
さて住吉地区の神社は本住吉神社だが、
あたまに本がつくのは住吉神社の大本営ということで、
大阪市住吉区にある住吉神社よりも古いとされている。
住吉神社は「住吉さん」の愛称で大阪市民に愛されており、
氏子も金持ちがうじゃうじゃいる。
金にモノをいわせて巨大な鳥居や太鼓橋を作るなど、
住吉神社が数段上に見える。
この論争には諸説あるが、本居宣長が
「本住吉神社が一番古い」と発表して一件落着かに見えたが
今なおくすぶり続けている。
しかし10年ほど前に行われた1800年祭は
住吉神社が2010年10月に対して
本住吉神社は2008年5月に行われている。
確かに我が本住吉神社の方が早く行われた。
日本書紀には神功皇后の三韓征伐からの帰途に船が進まなくなり
神託により住吉三神を祀ったと記されるのが当地であり
当社が住吉三神鎮祭の根源であると伝えられる。
そのために古くから「本住吉」と呼ばれるとしている。
このあと船は大阪市住吉区と堺の間を流れる大和川を遡り
樫原についたと思われることから、大阪湾を無事に渡れたことを
祈念して住吉区にも住吉神社を建立したと考えられる。
したがって元住吉神社の方が
2~3年早く建立されたと考えられるのだ。

私は5日も4日同様子供会の綱の中で叫んでいる。
しかし宮入は例年通り左前外側に陣取った。一方次女は右後ろ外側だ。
今年は経験の浅い曳き手が多く、
人数的には例年以上だが要領が分からず100%の力が発揮できていない。
それでも持ち時間内は、だんじりを落とすことなく回し続けた。
ただし例年の優美とはほど遠い。致し方ない。
数がいればきれいと舞うという訳ではない。
きれいに合わすにはだんじりを愛し、よく研究することが大切だ。
教本はないので口伝か見よう見まねになるが、暴れるのではない。
あくまでも神事なので舞わなければならない。
今年は経験の浅い曳き手が多く力任せだったが、
それでも皆さんとても良い汗をかいていた。
誰一人として休むことなくだんじりに触れていたいという
気持ちに包まれていた。と私は感じた。
我々の舞と鳴り物で、神さんは気持ちよく昇天されたかなぁ。
ありかとうございました。
叩く楽団を乗せた乗り物だ。
神さんが乗る神輿の後ろで鳴り物を鳴らして、
神さんが降臨・昇天しやすいように囃す。

5月5日は本宮。
この日の朝、神さんは神輿に降臨され、
その日一日限定で町民の無病息災や五穀豊穣などを祈ってくれる。
そして夜、昇天される。
一年に一度の来訪だ。
その前日の5月4日は宵宮。
いわば前夜祭で、だんじりは町中を練り歩き
「神さんが明日来られますよ」と鳴り物で告知する。
従って4日はまだ神さんは降臨していない。
神輿は神さんが乗る乗り物なので神社が管理するのに対して、
だんじりは氏子が管理する。氏子が裕福であればあるほど、
だんじりは、大きくきらびやかになる傾向にある。
ある意味いいかげんなので基本は口伝になる。
文書の記録が残っていないことが多いので定かではないが、
私のいる空区のだんじりが最も古いとされており、
江戸時代後期の作と言われている。
かっては住吉地区7台のだんじりの中で最も大きかったが、
7台のだんじりが入る長屋が本住吉神社の境内に建てられてからは
各区ともだんじり小屋にギリギリ入るサイズにまで巨大化させており、
空区のだんじりが一番と誇れなくなってきた。
今年も住之江区のだんじりが新調され、
ひときはきらびやかに巨大化している。
住吉地区には9つの区があるが、
これまでだんじりは7台しかなかった。
しかし昨年、反高林区が1台購入して今は8台に。
あと1台!
さて住吉地区の神社は本住吉神社だが、
あたまに本がつくのは住吉神社の大本営ということで、
大阪市住吉区にある住吉神社よりも古いとされている。
住吉神社は「住吉さん」の愛称で大阪市民に愛されており、
氏子も金持ちがうじゃうじゃいる。
金にモノをいわせて巨大な鳥居や太鼓橋を作るなど、
住吉神社が数段上に見える。
この論争には諸説あるが、本居宣長が
「本住吉神社が一番古い」と発表して一件落着かに見えたが
今なおくすぶり続けている。
しかし10年ほど前に行われた1800年祭は
住吉神社が2010年10月に対して
本住吉神社は2008年5月に行われている。
確かに我が本住吉神社の方が早く行われた。
日本書紀には神功皇后の三韓征伐からの帰途に船が進まなくなり
神託により住吉三神を祀ったと記されるのが当地であり
当社が住吉三神鎮祭の根源であると伝えられる。
そのために古くから「本住吉」と呼ばれるとしている。
このあと船は大阪市住吉区と堺の間を流れる大和川を遡り
樫原についたと思われることから、大阪湾を無事に渡れたことを
祈念して住吉区にも住吉神社を建立したと考えられる。
したがって元住吉神社の方が
2~3年早く建立されたと考えられるのだ。

私は5日も4日同様子供会の綱の中で叫んでいる。
しかし宮入は例年通り左前外側に陣取った。一方次女は右後ろ外側だ。
今年は経験の浅い曳き手が多く、
人数的には例年以上だが要領が分からず100%の力が発揮できていない。
それでも持ち時間内は、だんじりを落とすことなく回し続けた。
ただし例年の優美とはほど遠い。致し方ない。
数がいればきれいと舞うという訳ではない。
きれいに合わすにはだんじりを愛し、よく研究することが大切だ。
教本はないので口伝か見よう見まねになるが、暴れるのではない。
あくまでも神事なので舞わなければならない。
今年は経験の浅い曳き手が多く力任せだったが、
それでも皆さんとても良い汗をかいていた。
誰一人として休むことなくだんじりに触れていたいという
気持ちに包まれていた。と私は感じた。
我々の舞と鳴り物で、神さんは気持ちよく昇天されたかなぁ。
ありかとうございました。


















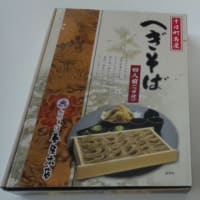

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます