ジャンボジェットは巨体ゆえに一旦失速するとその巨体を持て余してしまう。
どこかで必ず燃料補給をしなければ、ジャンボジェットといえども
飛び続けることはできない。
会社もまた、いつまでも右上がりの成長を続けられるわけではない。
むしろ失速を経験して、もう一度盛り返すようでなければ、
真の強い体質をつくることはできない。
映像作品を我が社に依頼するスポンサーのほとんどは一部上場企業である。
中小企業では費用対効果を考えると、
映像はお金がかかりすぎて選ばないからだ。
そんな上場企業が潰れるなんて考えられないが、
不景気の嵐に巻き込まれて、倒産したり買収されたりする。
オイルショック、そしてバブルの崩壊、さらにリーマンショックで、
私たちは有り得ない、あってはならない倒産劇の目撃者となってしまった。
私の同級生の中には安定を求めて銀行に入社したが、
銀行すら潰れてしまう。バブルの時代は本業そっちのけで、
株に投資し、一夜にして全てを失った企業もあった。
我が社のように本業を必死で貫いている会社でも、
いつ潰れてもおかしくない時代となっている。
仕事は回っていているのに資金がショートし
「なぜ?」と翻弄されている。

(監督だかプロデューサーだかよくわからないが
とにかくバイタリティー溢れる岡村 重昭氏が
作った中国・上海投資戦略ビデオ)
我が社は今から14年ほど前に、第一回目の苦境に立たされている。
会社となって2年目ぐらいの頃か…
私が中心になって仕事をしているので、
どうしてもご贔屓さんを中心に段取りしてしまう。
しかしある日ご贔屓さんが部署変更になり、
パタリと仕事が止まってしまったのだ。
そもそも小さな会社なので、仕事本数に限りがあるので、
ご贔屓さんを中心にシフトを組んでいた。だから大打撃を受けたのだ。
会社の蓄えはアッと言う間に底をつき、
社員の給料を遅配するわけにはいかず、
私の給料カットで凌ぐしかなかった。
家族4人暮らしの社長の給料が、25歳の新入社員の給料よりも
さらに5万円も安い月が続いた。
夜になると脂汗が出て1ヵ月で5キロ痩せた。
家の貯金も崩して社員の給料を払っていると、
生きているのがイヤになってくる。
一体どうなるのだろうかと、出口の見えない日々を過ごした。
仕事を求めて企画書を出すが、
お客さまに見透かされたのか一向に決まらない。
余裕がないと企画書にもチカラがなく、
プレゼンの言葉にも自信が漲らない。
スランプとは違う世界にどう立ち向かえばよいのか、途方に暮れた。
ジリ貧の生活が約1年続いたが、
元の数字に戻るは、それからさらに4年かかった。
もちろん急にV字回復したのではない。
私たちの商品は人貢の積み上げなので、単価が急に上ったり、
起死回生の新商品があるわけではない。
ただ一生懸命モノを作り上げ、ファンを増やし、仕事を増やすしか手がない。
数年かけて新たなファンを増やして、
少しずつ牛歩のごとく業績を上げていったのだ。
これから得た教訓は…
①顧客数を増やす。
②上得意に頼りすぎない。
③シリーズ(レギュラー)を持ちつつ、単発も大切にする。
④若い担当者を大切にし、共に成長する。
特に④は大切で、決定権者ばかりに目を向けがちだが、
その下につく若い担当者もいずれ決定権者になる。
彼らから頼りにされないと仕事は続かない。
また担当者は自分と同じ世代、
もしくは少し下の世代の方が会話しやすい。
だから我が社も常に若手を採用し、教育し続けねばならない。

(当社創業の頃のメンバーで今では森田取締役夫人の梶山 高子嬢。
1列目中央に梶山、その左横が私、右横はビデオの進行役
2列目は右から照明:大穂、カメラマン:河西、VE:溝岡
まだビデオの仕事がワンサカあった)
大企業は毎年新人を採用し、教育できるが、中小企業はそうはいかない。
しかしそういう準備を常にしておかねば、
今は良くても数年後には必ず失速する。
大好きな仕事をしてお金をいただけるのは大変ありがたい。
仕事があれば嫌な事も忘れられる。経営危機にすら気づかない。
作り手とはそういうものだ。自分の才能と心中する気でいる。
しかし会社である限りは、社員の幸せも考えねばならない。
社長とはそういうものだ。
第一回目の経営危機をなんとか乗り越えたが、
ここにきて業界の危機は加速し、同業者の倒産や解散が相次いでいる。
まず最初に、編集スタジオが倒れた。
というのもパソコンで編集できるようになったからだ。
1時間のスタジオ使用料を3~5万円も出さなくても、
100万円も出せば、パソコンの編集システムが組めるようになってしまった。
しかし誰が編集するのかという新たな問題が生まれる。監督がするしかない。
今までのギャラのままで編集というサービス残業が増える。
メカ音痴の高齢監督は仕事本数が減る。生活ができなくなり監督を止める。
そんな業界に見切りをつけ若手監督も転職する。
仕方がないので、プロダクションの若手が監督に昇格する。
駄作が生まれる。というマイナスの連鎖が始まる。
次に淘汰されたのは、撮影プロダクションや照明プロダクションだ。
カメラの性能が日進月歩で進化し、
小型・軽量・低消費電力・暗くても撮れる・高画質化に加えて低価格化。
この低価格化がネックとなり、
機材償却に失敗した撮影プロダクションが、まずイチヌケする。
残った会社も生き残りをかけ、人員を整理する。
ベテランの腕のいいカメラマンは首を切られ、
若手のカメラオペレーターがカメラマンと偽り、台頭する。
素人化で駄作が益々増える。
カメラの性能アップで、照明も不要になり、
照明マンを抱えていた会社は、潰れていった。
私がこの世界に入った頃には、
画面の横に出るテロップと呼ばれていた文字を専門に打つ会社もあり
1枚1000~1500円で、荒稼ぎをしていたが、今は影も形もない。
またフリップと呼ばれる表や、
まとめを整理したボードを専門に作っていた会社も
CG制作会社に形を変えていった。
ただし、テレビ番組では進行者が扱いやすいのでフリップを使うが、
PRの世界ではフリップは完全に姿を消した。
比較的生き残っているのは録音スタジオだ。
音は映像に比べアナログからデジタルになったのが早く
人員整理や機材の入れ替えが早くに行われていたことと、
映像作品には音が欠かせないこと、
また昨今のインディーズデビューで録音スタジオが練習場になったり、
CD制作の拠点になるなどして、
大阪にある数か所の録音スタジオも辛うじて生き残っている。
これとて怪しくなっているのが現状だ。

(盟友・山城 日出男氏率いるサウンドシード
録音レベルは高いので、ぜひご活用を!)
映像作品を見るには自分の時間を割き、
テレビもしくはスクリーンのある場所に身を起き、
それのみに集中しなければならない。
しかし携帯にしろ、アイパッドにしろ、
自分の居場所に合わせて、時を選ばず、
ナガラ族ができるハードの登場により、
もはや映像業界は、ビジネスモデルとしてはとっくに終わっているのだ。
この世界に身を置いたとて、身の破滅はあったとしても
大金持ちになる可能性は皆無である。
パソコンの進化により、音楽も書籍も時代の流れに併せて形を変えている。
インディーズ主体になり、音楽業界は変わらざるを得なくなった。
電子書籍が出て、出版業界も変わらざるを得なくなった。
映像業界も然り。
30年かかった変化が5年で起こる時代になってしまったのだ。
今の売上高を変えたくなければ、自分自身を変えていくしかない。
考えられる方法は2つ。
ひとつは業種・業態の変更。つまり映像業界から身を引き別業界になる。
もうひとつは特化。例えばプレハブ住宅全盛の中で生き残る宮大工のごとく。
他業種なら3つ目としてグローバル化という選択肢もあるが、
映像は文化なので、システムのグローバル化はできても、
制作のグローバル化は言葉の壁だけでは収まらない根深い難しさがある。

(坂本先生なら今の時代、どう生きるのですか?)
当社は零細企業にもかかわらず、少数ながら数年に1度は増員している。
基本的には中途採用はしない方針だ。大卒の新入社員を求めている。
専門学校生も悪くないが、この仕事をするには幼すぎる。
高校卒は学校側が心配して、送りこんでこないだろう。
当社の一番若手は、昨年4月入社だ。
1年半経ち、ようやく戦力になりつつあるが、まだまだモノ足らない。
それでも制作能力は、上昇機運にある。おそらくいま取引いただくと
我が社としては、かなり上質のものが上がる自信もあり
よそに頼むのはやめた方がいい!と断言できる。
おそらくこの5~6年はさらに上昇すると思う。
それとて、人件費を削減するため現状維持で
以降の採用をサボったり、会社としてのまとまりが希薄になると
たちまち急降下することになる。
会社経営とは大小にかかわらず、本当に大変である。
はてさて、当社は10年後をどう進むか!?今から考えねばならない。
どこかで必ず燃料補給をしなければ、ジャンボジェットといえども
飛び続けることはできない。
会社もまた、いつまでも右上がりの成長を続けられるわけではない。
むしろ失速を経験して、もう一度盛り返すようでなければ、
真の強い体質をつくることはできない。
映像作品を我が社に依頼するスポンサーのほとんどは一部上場企業である。
中小企業では費用対効果を考えると、
映像はお金がかかりすぎて選ばないからだ。
そんな上場企業が潰れるなんて考えられないが、
不景気の嵐に巻き込まれて、倒産したり買収されたりする。
オイルショック、そしてバブルの崩壊、さらにリーマンショックで、
私たちは有り得ない、あってはならない倒産劇の目撃者となってしまった。
私の同級生の中には安定を求めて銀行に入社したが、
銀行すら潰れてしまう。バブルの時代は本業そっちのけで、
株に投資し、一夜にして全てを失った企業もあった。
我が社のように本業を必死で貫いている会社でも、
いつ潰れてもおかしくない時代となっている。
仕事は回っていているのに資金がショートし
「なぜ?」と翻弄されている。

(監督だかプロデューサーだかよくわからないが
とにかくバイタリティー溢れる岡村 重昭氏が
作った中国・上海投資戦略ビデオ)
我が社は今から14年ほど前に、第一回目の苦境に立たされている。
会社となって2年目ぐらいの頃か…
私が中心になって仕事をしているので、
どうしてもご贔屓さんを中心に段取りしてしまう。
しかしある日ご贔屓さんが部署変更になり、
パタリと仕事が止まってしまったのだ。
そもそも小さな会社なので、仕事本数に限りがあるので、
ご贔屓さんを中心にシフトを組んでいた。だから大打撃を受けたのだ。
会社の蓄えはアッと言う間に底をつき、
社員の給料を遅配するわけにはいかず、
私の給料カットで凌ぐしかなかった。
家族4人暮らしの社長の給料が、25歳の新入社員の給料よりも
さらに5万円も安い月が続いた。
夜になると脂汗が出て1ヵ月で5キロ痩せた。
家の貯金も崩して社員の給料を払っていると、
生きているのがイヤになってくる。
一体どうなるのだろうかと、出口の見えない日々を過ごした。
仕事を求めて企画書を出すが、
お客さまに見透かされたのか一向に決まらない。
余裕がないと企画書にもチカラがなく、
プレゼンの言葉にも自信が漲らない。
スランプとは違う世界にどう立ち向かえばよいのか、途方に暮れた。
ジリ貧の生活が約1年続いたが、
元の数字に戻るは、それからさらに4年かかった。
もちろん急にV字回復したのではない。
私たちの商品は人貢の積み上げなので、単価が急に上ったり、
起死回生の新商品があるわけではない。
ただ一生懸命モノを作り上げ、ファンを増やし、仕事を増やすしか手がない。
数年かけて新たなファンを増やして、
少しずつ牛歩のごとく業績を上げていったのだ。
これから得た教訓は…
①顧客数を増やす。
②上得意に頼りすぎない。
③シリーズ(レギュラー)を持ちつつ、単発も大切にする。
④若い担当者を大切にし、共に成長する。
特に④は大切で、決定権者ばかりに目を向けがちだが、
その下につく若い担当者もいずれ決定権者になる。
彼らから頼りにされないと仕事は続かない。
また担当者は自分と同じ世代、
もしくは少し下の世代の方が会話しやすい。
だから我が社も常に若手を採用し、教育し続けねばならない。

(当社創業の頃のメンバーで今では森田取締役夫人の梶山 高子嬢。
1列目中央に梶山、その左横が私、右横はビデオの進行役
2列目は右から照明:大穂、カメラマン:河西、VE:溝岡
まだビデオの仕事がワンサカあった)
大企業は毎年新人を採用し、教育できるが、中小企業はそうはいかない。
しかしそういう準備を常にしておかねば、
今は良くても数年後には必ず失速する。
大好きな仕事をしてお金をいただけるのは大変ありがたい。
仕事があれば嫌な事も忘れられる。経営危機にすら気づかない。
作り手とはそういうものだ。自分の才能と心中する気でいる。
しかし会社である限りは、社員の幸せも考えねばならない。
社長とはそういうものだ。
第一回目の経営危機をなんとか乗り越えたが、
ここにきて業界の危機は加速し、同業者の倒産や解散が相次いでいる。
まず最初に、編集スタジオが倒れた。
というのもパソコンで編集できるようになったからだ。
1時間のスタジオ使用料を3~5万円も出さなくても、
100万円も出せば、パソコンの編集システムが組めるようになってしまった。
しかし誰が編集するのかという新たな問題が生まれる。監督がするしかない。
今までのギャラのままで編集というサービス残業が増える。
メカ音痴の高齢監督は仕事本数が減る。生活ができなくなり監督を止める。
そんな業界に見切りをつけ若手監督も転職する。
仕方がないので、プロダクションの若手が監督に昇格する。
駄作が生まれる。というマイナスの連鎖が始まる。
次に淘汰されたのは、撮影プロダクションや照明プロダクションだ。
カメラの性能が日進月歩で進化し、
小型・軽量・低消費電力・暗くても撮れる・高画質化に加えて低価格化。
この低価格化がネックとなり、
機材償却に失敗した撮影プロダクションが、まずイチヌケする。
残った会社も生き残りをかけ、人員を整理する。
ベテランの腕のいいカメラマンは首を切られ、
若手のカメラオペレーターがカメラマンと偽り、台頭する。
素人化で駄作が益々増える。
カメラの性能アップで、照明も不要になり、
照明マンを抱えていた会社は、潰れていった。
私がこの世界に入った頃には、
画面の横に出るテロップと呼ばれていた文字を専門に打つ会社もあり
1枚1000~1500円で、荒稼ぎをしていたが、今は影も形もない。
またフリップと呼ばれる表や、
まとめを整理したボードを専門に作っていた会社も
CG制作会社に形を変えていった。
ただし、テレビ番組では進行者が扱いやすいのでフリップを使うが、
PRの世界ではフリップは完全に姿を消した。
比較的生き残っているのは録音スタジオだ。
音は映像に比べアナログからデジタルになったのが早く
人員整理や機材の入れ替えが早くに行われていたことと、
映像作品には音が欠かせないこと、
また昨今のインディーズデビューで録音スタジオが練習場になったり、
CD制作の拠点になるなどして、
大阪にある数か所の録音スタジオも辛うじて生き残っている。
これとて怪しくなっているのが現状だ。

(盟友・山城 日出男氏率いるサウンドシード
録音レベルは高いので、ぜひご活用を!)
映像作品を見るには自分の時間を割き、
テレビもしくはスクリーンのある場所に身を起き、
それのみに集中しなければならない。
しかし携帯にしろ、アイパッドにしろ、
自分の居場所に合わせて、時を選ばず、
ナガラ族ができるハードの登場により、
もはや映像業界は、ビジネスモデルとしてはとっくに終わっているのだ。
この世界に身を置いたとて、身の破滅はあったとしても
大金持ちになる可能性は皆無である。
パソコンの進化により、音楽も書籍も時代の流れに併せて形を変えている。
インディーズ主体になり、音楽業界は変わらざるを得なくなった。
電子書籍が出て、出版業界も変わらざるを得なくなった。
映像業界も然り。
30年かかった変化が5年で起こる時代になってしまったのだ。
今の売上高を変えたくなければ、自分自身を変えていくしかない。
考えられる方法は2つ。
ひとつは業種・業態の変更。つまり映像業界から身を引き別業界になる。
もうひとつは特化。例えばプレハブ住宅全盛の中で生き残る宮大工のごとく。
他業種なら3つ目としてグローバル化という選択肢もあるが、
映像は文化なので、システムのグローバル化はできても、
制作のグローバル化は言葉の壁だけでは収まらない根深い難しさがある。

(坂本先生なら今の時代、どう生きるのですか?)
当社は零細企業にもかかわらず、少数ながら数年に1度は増員している。
基本的には中途採用はしない方針だ。大卒の新入社員を求めている。
専門学校生も悪くないが、この仕事をするには幼すぎる。
高校卒は学校側が心配して、送りこんでこないだろう。
当社の一番若手は、昨年4月入社だ。
1年半経ち、ようやく戦力になりつつあるが、まだまだモノ足らない。
それでも制作能力は、上昇機運にある。おそらくいま取引いただくと
我が社としては、かなり上質のものが上がる自信もあり
よそに頼むのはやめた方がいい!と断言できる。
おそらくこの5~6年はさらに上昇すると思う。
それとて、人件費を削減するため現状維持で
以降の採用をサボったり、会社としてのまとまりが希薄になると
たちまち急降下することになる。
会社経営とは大小にかかわらず、本当に大変である。
はてさて、当社は10年後をどう進むか!?今から考えねばならない。



















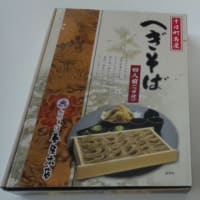
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます