
8月にイタリアのWEB雑誌XL Repubblicaに掲載されたMIKAのエッセイの和訳(日本語訳)。最初の段落から読者を引き込む文章力!自伝書いたら凄いだろうなと思わせる文才に恐れ入りました!私の訳は原文に忠実ではなく、文章として意味が分かりやすい様意訳してある部分があります。ご了承ください。
元サイト:http://xl.repubblica.it/dettaglio/80340
「イタリー、君を愛している」
イタリア、ボルディゲーラ、13歳のある夏の夜。短すぎるスボン、額には汗、その上サスペンダーは僕の首の後ろで擦れていた。その夜、僕はイタリアという国を憎むことに決めた。ここでは何もかもが困難を伴う。カフェでは無視され、居心地の悪い疎外感を味わい、そして姉や妹ばかりが注目を浴び・・・外国人女性は本当のイタリアを知らない。彼女たちの変わりに哀れな様相の13歳の少年に聞いてみるといい、彼だけが本当のイタリアを知っている。
育ち盛りの年月、僕たち家族はほとんどと言って良い位、毎年の夏休みを南フランスで過ごした。ロンドンからトヨタの白いエスティマに乗って。車にはぎゅうぎゅう詰めの荷物、枕、両親、僕の座席の下に隠したウサギを含む何匹かのペット、そして僕の4人の兄弟。車の床に座るのはそうしたいからではなく、それしか方法が無いから。車のトランクが閉まる限り、そして警察が僕たちを発見しない限り、僕たちは陰気なロンドンから太陽の国に向けて20時間の旅に出発した。今でも車の移動は僕の大好きな移動手段だし、ツアーの時だってそう。
大家族の一員であること、それは理論的には何もかもが困難を伴う。しかし実行はすべてがより簡単なんだ。僕たち家族はお金が無かったにもかかわらず、いつも誰かが冗談を言い、会話を始め、他愛の無い言い争いで楽しませてくれた。南フランスはいつだって僕らの目的地だった。旅行のコストが安かったからだ。僕たちは家族一緒に過ごし、ビーチへ行ったり、可能な限りイタリアまでドライブした。
ボルディゲーラ、そしてサンレモ通りが僕の最初のイタリアとの出会い。僕の母はイタリアの食べ物や人々を愛し、イタリアの人々もまた彼女を愛し返した。母の色鮮やかなドレスに丸々とした体型、そして取り巻く子供達の群れ。それは彼女を冷たい目で見るフランス人たちと違い、イタリアの人々に好意を持って受け入れられた。僕の姉妹はその可愛さと笑顔で人々の熱狂を誘い、一番下の弟は家族の中で唯一のチビでイタリアでは黙れとかダメとか言われないことを楽しんでいるようだった。父はローマに住んでいたことがありイタリア語に堪能だったし、何よりも彼には人を引き付ける魅力があった。魅力!それは13歳の僕に確実に無いものの一つだった。僕は無口なくせにいきなり感情を爆発させ、周りの人を不快にさせる無様な少年だったから。たぶん僕は周りから奇妙な少年、あるいは女々しい少年とみなされていたと思う。僕は大抵、短くしたズボン、サスペンダー、袖口のついた長袖シャツに蝶ネクタイというファッションで、自分で作った服を着ていた。僕は自分自身に違和感を感じ、そしてイタリア人も僕に違和感を感じているのを感じていた。僕は一人で道をぶらぶらし、行き当たったアイスクリーム屋全部の店でアイスクリームを注文した。馴れ馴れしいイタリア人の若い男は僕にとって凄く威圧的に思え、彼らに近づかないようにしていた。
僕が感じていたこの違和感が、僕を激しく音楽へのめりこませる原動力になる。音楽という世界の中で僕は何にでも、誰にでもなれた。僕は魅力的で、人々に注目してもらうことだって可能だった。音楽を介して僕は自分の居場所を見つけ、そして音楽を介してやっと、イタリアという国に受け入れられた。イタリアのライブほどボク自身がライブを楽しめる国は世界に少ししかない。ミラノ・フォーラム公演は前回のツアーで最も僕が誇りに思うライブだったし、それは僕の若いころのイタリアでの経験がどれほど強く僕に影響を与えてきたかを再確認させてくれた。
僕の2度目のイタリアとの出会いは、もう少し後だ。19の時、僕はロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックでオペラを専攻し、3年半バリトンを歌っていた。マルコ・カネパ教授のイタリア楽曲のクラスへ足を踏み入れた瞬間、僕はまるであの哀れな13歳の僕に引き戻されたような気がしたものだ。カネパ教授は強烈なイタリア訛の正直でざっくばらんな物言いの小柄な中年男性で、いつも赤いサスペンダーを着けオペラを愛していた。彼の授業を受けた3年半の間、僕が教授の前で歌ったのはたった5回だけ。それもいつも同じスカルラッティの「 ‘Gia il sole dal Gange’陽はすでにガンジス川から」で、僕の歌はそれはひどい代物だった。ポップシンガーの僕はオペラ歌手のふりをし、60歳のバリトン歌手みたいな声で歌ってたんだから。教授は自暴自棄になり、僕を「口の聞けない者」と呼んだ。教授の最後の授業の日、僕は彼に「いつの日かあなたは僕をミラノで見ることになる、しかもそれはスカラじゃない、スカラは僕には小さすぎるから」と告げたんだ。彼は僕を気でも狂ったかと思っただろう。
5年の歳月が経ち、僕はイタリアで初めてのライブであるミラノのアルカトラズのステージに立っていた。ショーの中程で僕は座り、静かな'Over My Shoulder'という曲を演り始めた。ハイトーンの長いパートを歌い終えた時、観客は騒々しいほどざわざわし始め、僕はてっきり観客が歌を気に入らなかったんだ、この後のショーをどうしようと気が遠くなるほど怖くなった。しかし本当はそうではなく観客は僕の歌を気に入ってくれて、僕に対する賞賛のざわめきだったんだ。あんな観客の反応は初めてだった。カネパ教授もびっくりだったろう。
僕のティーン時代のイタリア嫌いはそうして’好き’に変わったんだ。今ではイタリア人には「何か」があると分かった。「何か」が何を意味しようとね。彼らは他人が普通の物だと思う物の中に美と特別な何かを見いだすことが出来る。彼らは悲しみの中に美を見いだし、それを自ら公言することを恐れない。イタリア、君は僕にいつも思い出させてくれる、僕の家族のあの叫び声や笑い声、そしておんぼろエスティマのあの長い旅を。
元サイト:http://xl.repubblica.it/dettaglio/80340
「イタリー、君を愛している」
イタリア、ボルディゲーラ、13歳のある夏の夜。短すぎるスボン、額には汗、その上サスペンダーは僕の首の後ろで擦れていた。その夜、僕はイタリアという国を憎むことに決めた。ここでは何もかもが困難を伴う。カフェでは無視され、居心地の悪い疎外感を味わい、そして姉や妹ばかりが注目を浴び・・・外国人女性は本当のイタリアを知らない。彼女たちの変わりに哀れな様相の13歳の少年に聞いてみるといい、彼だけが本当のイタリアを知っている。
育ち盛りの年月、僕たち家族はほとんどと言って良い位、毎年の夏休みを南フランスで過ごした。ロンドンからトヨタの白いエスティマに乗って。車にはぎゅうぎゅう詰めの荷物、枕、両親、僕の座席の下に隠したウサギを含む何匹かのペット、そして僕の4人の兄弟。車の床に座るのはそうしたいからではなく、それしか方法が無いから。車のトランクが閉まる限り、そして警察が僕たちを発見しない限り、僕たちは陰気なロンドンから太陽の国に向けて20時間の旅に出発した。今でも車の移動は僕の大好きな移動手段だし、ツアーの時だってそう。
大家族の一員であること、それは理論的には何もかもが困難を伴う。しかし実行はすべてがより簡単なんだ。僕たち家族はお金が無かったにもかかわらず、いつも誰かが冗談を言い、会話を始め、他愛の無い言い争いで楽しませてくれた。南フランスはいつだって僕らの目的地だった。旅行のコストが安かったからだ。僕たちは家族一緒に過ごし、ビーチへ行ったり、可能な限りイタリアまでドライブした。
ボルディゲーラ、そしてサンレモ通りが僕の最初のイタリアとの出会い。僕の母はイタリアの食べ物や人々を愛し、イタリアの人々もまた彼女を愛し返した。母の色鮮やかなドレスに丸々とした体型、そして取り巻く子供達の群れ。それは彼女を冷たい目で見るフランス人たちと違い、イタリアの人々に好意を持って受け入れられた。僕の姉妹はその可愛さと笑顔で人々の熱狂を誘い、一番下の弟は家族の中で唯一のチビでイタリアでは黙れとかダメとか言われないことを楽しんでいるようだった。父はローマに住んでいたことがありイタリア語に堪能だったし、何よりも彼には人を引き付ける魅力があった。魅力!それは13歳の僕に確実に無いものの一つだった。僕は無口なくせにいきなり感情を爆発させ、周りの人を不快にさせる無様な少年だったから。たぶん僕は周りから奇妙な少年、あるいは女々しい少年とみなされていたと思う。僕は大抵、短くしたズボン、サスペンダー、袖口のついた長袖シャツに蝶ネクタイというファッションで、自分で作った服を着ていた。僕は自分自身に違和感を感じ、そしてイタリア人も僕に違和感を感じているのを感じていた。僕は一人で道をぶらぶらし、行き当たったアイスクリーム屋全部の店でアイスクリームを注文した。馴れ馴れしいイタリア人の若い男は僕にとって凄く威圧的に思え、彼らに近づかないようにしていた。
僕が感じていたこの違和感が、僕を激しく音楽へのめりこませる原動力になる。音楽という世界の中で僕は何にでも、誰にでもなれた。僕は魅力的で、人々に注目してもらうことだって可能だった。音楽を介して僕は自分の居場所を見つけ、そして音楽を介してやっと、イタリアという国に受け入れられた。イタリアのライブほどボク自身がライブを楽しめる国は世界に少ししかない。ミラノ・フォーラム公演は前回のツアーで最も僕が誇りに思うライブだったし、それは僕の若いころのイタリアでの経験がどれほど強く僕に影響を与えてきたかを再確認させてくれた。
僕の2度目のイタリアとの出会いは、もう少し後だ。19の時、僕はロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックでオペラを専攻し、3年半バリトンを歌っていた。マルコ・カネパ教授のイタリア楽曲のクラスへ足を踏み入れた瞬間、僕はまるであの哀れな13歳の僕に引き戻されたような気がしたものだ。カネパ教授は強烈なイタリア訛の正直でざっくばらんな物言いの小柄な中年男性で、いつも赤いサスペンダーを着けオペラを愛していた。彼の授業を受けた3年半の間、僕が教授の前で歌ったのはたった5回だけ。それもいつも同じスカルラッティの「 ‘Gia il sole dal Gange’陽はすでにガンジス川から」で、僕の歌はそれはひどい代物だった。ポップシンガーの僕はオペラ歌手のふりをし、60歳のバリトン歌手みたいな声で歌ってたんだから。教授は自暴自棄になり、僕を「口の聞けない者」と呼んだ。教授の最後の授業の日、僕は彼に「いつの日かあなたは僕をミラノで見ることになる、しかもそれはスカラじゃない、スカラは僕には小さすぎるから」と告げたんだ。彼は僕を気でも狂ったかと思っただろう。
5年の歳月が経ち、僕はイタリアで初めてのライブであるミラノのアルカトラズのステージに立っていた。ショーの中程で僕は座り、静かな'Over My Shoulder'という曲を演り始めた。ハイトーンの長いパートを歌い終えた時、観客は騒々しいほどざわざわし始め、僕はてっきり観客が歌を気に入らなかったんだ、この後のショーをどうしようと気が遠くなるほど怖くなった。しかし本当はそうではなく観客は僕の歌を気に入ってくれて、僕に対する賞賛のざわめきだったんだ。あんな観客の反応は初めてだった。カネパ教授もびっくりだったろう。
僕のティーン時代のイタリア嫌いはそうして’好き’に変わったんだ。今ではイタリア人には「何か」があると分かった。「何か」が何を意味しようとね。彼らは他人が普通の物だと思う物の中に美と特別な何かを見いだすことが出来る。彼らは悲しみの中に美を見いだし、それを自ら公言することを恐れない。イタリア、君は僕にいつも思い出させてくれる、僕の家族のあの叫び声や笑い声、そしておんぼろエスティマのあの長い旅を。












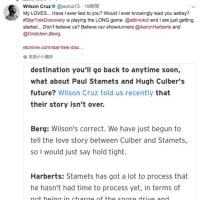


















読んでて泣きそうになっちゃった(涙)
やっぱりMIKAたんが大好きです。
MIKA、文章上手いですよね。
最初読んだ時は感情こみ上げてきて泣けてきそうになりましたよ!
なんだか人情味にあふれたエッセイです。
その原文の雰囲気を壊さない様訳すのが最大のポイントでした!
ではでは
MIKAちょっと、クリエイティブ能力高すぎ
どーなんでしょうね、この人のボーイソプラノ時代の録音を聞きましたが、なんつーかいわゆる天使の声って感じでした。
いまじゃあんな声は出ないけど、ああいう歌い方が身に付いちゃったんでしょうね。
絵も描けるし何でも出来すぎ!
ではでは!
MIKAの幼少時代のオペラの音源って
どこで聴けたんですか?
どの記事に書いてらっしゃったのか
忘れてしまったのでここに書きました。
こんにちは。
オペラ音源、以前はYoutubeにあがってたみたいですけど今はない様ですね。少なくとも検索で出てこなかった記憶があります。
私はファンの方から教えてもらいましたが、その方がどこから貰ったのか分かりませんし、本当にMIKAなのかも分からないんですが、ロイヤルオペラの音源だと思います。
期間限定(2週間くらい)で下記にあげておきますので良かったら聞いてみてください。
http://www.99magpies.com/MIKAsingopera.mp3
ありがとうございます!
これ本当にMIKAかもしれないですね!
MIKAですよね。
どことなく歌い方に同じ物が感じられますよね。
声の質はもちろん違うんですけど!
ではでは