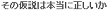いまどこ ―冒頭表示2
キーボードの2段めと3段目はなぜ互い違いになっていないの - 教えて!goo:
に答えてってな形で部分統合しようかナとも思う。
http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c11db5b33d4a1d67900e568ab0dc6273ではちょっとスレ違うと思う。
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
生産のためのエネルギーの方が、生涯発電量より多いという話は本当?
今の生産技術でなら 2~3年でペイバック
少なくとも自分を作るためのエネルギーが自分で発生したエネルギーより多かったら、全く意味が無いので普及も何もあったものでは無いはずです。
「エネルギー的にペイしない」という意見の方は、投入エネルギーは実は熱ですが、それをそのままカウントし、出力である電気もそのままエネルギーとしてカウントすると、非常に不利なことになります。
火力発電所の効率は、 40%程度、末端では 35%程度です。100Jを投入して35J取り出せるだけです。100J の熱でシリコン原石を太陽電池に変えたとし、それで作られるエネルギーは電気ですから本来比較されるべき対象は 35J でなくては不公平です。熱力学的には、熱より電気の方が同じエネルギー量でも質が高いということです。ということで、100J の熱で作った太陽電池がその寿命の間にたとえば 90J 発電したとすると、「10J 不足だ、もとが引けない」
「そのエネルギーで発電しても 35J しか出てこないのだから 90J も発電した太陽電池は約 2倍の55Jも得だ」
これは、私の邪推かもしれませんし、それだけではまだ説明がつかないほどに両者の数値の開きが有ります。でも、間を埋める一つの根拠にはなりそうです。
これは、私の邪推かもしれませんし、それだけではまだ説明がつかないほどに両者の数値の開きが有ります。でも、間を埋める一つの根拠にはなりそうです。
企業の情報として、京セラの Q&A に30MW/年の生産体制でのエネルギーベースでのぺイバック時間は 2.2年と出ています。メーカーなので確かな情報だと思います(上記のようにエネルギーベースなので、控えめの値と解釈できます)。
一方、最近(2000.11.6)出た情報では、現在の発電単価は 100円/kWh で電力料金の 4倍。そうなると、本当にペイバック時間は 2.2年かという疑問がまたまた出てきます。4倍という料金は実は会社としての人件費や維持管理費を含んでかけられる料金であって、実際の発電単価は 10円を切っています。すると、現在 10倍以上の発電単価とも言えるわけです。