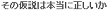いまどこ ―冒頭表示2
キーボードの2段めと3段目はなぜ互い違いになっていないの - 教えて!goo:
に答えてってな形で部分統合しようかナとも思う。
http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c11db5b33d4a1d67900e568ab0dc6273ではちょっとスレ違うと思う。
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
あだ名設計 通称設計
"幼名化仮説"が提示された。
川岸氏は "幼名化"に 何を意味させようとしているのであろうか。
こういった現象が生じたのは、明治期以後の人名の制度設定とも 関係あるのかも?
出生届け時の名が (家庭裁判所の判断を得ない限りは?)普通は 後年まで通用されつづけ 呼称とも一致し、幼名(ようみょう)/字(あざな)/諱(いみな)のような制度運用が想定されなくなったため、
出生時の子の名づけは 幼名/字/諱 を統合したものとして 名づけなくてはならなくなった。
おさなき我が子への 呼びかけの名として つい いとおしい あいらしい名をつけようとするのも 親の人情であろう。
ここで対策として、通称が 幼名にふさわしいものになるように 意図的にデザインする方法があるのではないか?
おさなごの呼称としては ○○ちゃん など 通称されるであろう。
この段階での通称呼称での運用を意識しつつ 成人後にも通用する子の名づけをデザインするのである。
如何?
みな やっていることかな?
ところで
"~太"が 多く見られるようになっているのは、
"幼名化仮説"が提示された。
仮説:近年の日本人の命名は,幼名化現象を起こしている。
川岸 克己「人名における漢字使用の変化とその誘因
Changes in the Use of Kanji for Names and the Motivation behind Such Change 」
安田女子大学紀要 41, 1-14, 2013-02-28
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009574918
- この仮説を知ったのは 次の記事"yasuoka(安岡孝一)の日記 | スラッシュドット・ジャパン"に拠る。
山下大輔、渡部絵美、そして上杉達也 | yasuoka(安岡孝一)の日記 | スラッシュドット・ジャパン http://t.co/hGWVWdMxD3
― raycy (@raycy) October 22, 2013
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
川岸氏は "幼名化"に 何を意味させようとしているのであろうか。
- 形式において 近年における命名での"~太"の多用から "幼名"化仮説を 導いた。
- 両親にとって愛らしいといった意味での "幼"名化 も傍証としているようである。
- 両親ら命名者の思考の"幼さ" (いささか浅はかさ?)の投影としての名づけ結果とも しているようである。
こういった現象が生じたのは、明治期以後の人名の制度設定とも 関係あるのかも?
出生届け時の名が (家庭裁判所の判断を得ない限りは?)普通は 後年まで通用されつづけ 呼称とも一致し、幼名(ようみょう)/字(あざな)/諱(いみな)のような制度運用が想定されなくなったため、
出生時の子の名づけは 幼名/字/諱 を統合したものとして 名づけなくてはならなくなった。
おさなき我が子への 呼びかけの名として つい いとおしい あいらしい名をつけようとするのも 親の人情であろう。
ここで対策として、通称が 幼名にふさわしいものになるように 意図的にデザインする方法があるのではないか?
おさなごの呼称としては ○○ちゃん など 通称されるであろう。
この段階での通称呼称での運用を意識しつつ 成人後にも通用する子の名づけをデザインするのである。
如何?
みな やっていることかな?
ところで
"~太"が 多く見られるようになっているのは、
- ひとつには 少子化により、 出生届け出男児の長男割合が高まっていること。
- ("~太"は 長男に名づけることが多そう。(∵太郎の太))
- さらには 長男に限らずとも "~太"と命名されることが さほどタブー視されなくなったこと