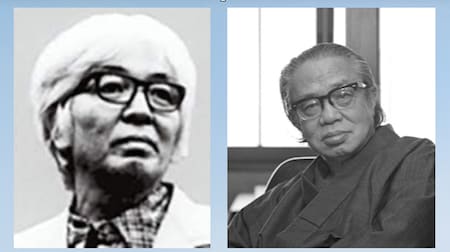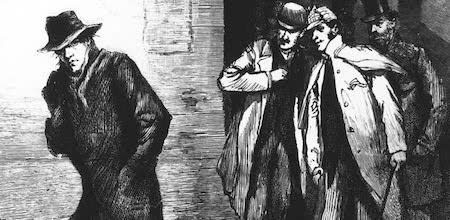久しぶりの第59弾をお届けします。取り上げるのは、「~ま」と「あとのケンカを先にする」です。お気楽に最後までお付き合いください。
<~ま>
「いきなり「~ま」って何かいな(だろう)?」と、大阪人でも戸惑われる方が多そうです。
「~ます」を例の大阪方式で、「ま」だけに短縮したものです。
こんな笑い話があります。大阪市内を路面電車が走っていた頃のことです。こんな車両でした。

東京あたりから来たんでしょうか、若い男の人が車掌に訊いています。
「この電車、道頓堀まで行くんですか?」
「行きま」と答える車掌。
「だからぁ、行くの?行かないの?」「行きま、て言うてますやんか」と、しばし押し問答があったというんですが・・・・「ます」なのか「ません」なのか、東京人が困惑したのはよくわかります。たかが「す」1音を省エネする大阪人の短縮グセにも困ったもんです。
同じ伝で「分かってます」が「分かって「ま」」、「やってます」が「やって「ま」」という具合になります。年配とか、商売をやってる方々が、もっぱらご愛用のカジュアルな言い回しです。
十分に心得てますよ、安心してください、というメッセージが「分かってま」には込められている気がします。「分かってます」とあらたまった言い方には、逆に「あんたにそこまで言われなくても」と軽いイヤミが入ってたりする(こともある)ので、ご注意ください。
「ます」が変容して、「まっせ」と「まっさ」になるのも、大阪弁です。基本的には、話し手の気軽な意志を表します。「ワテ(私)が、やっとき「まっせ」/「まっさ」」のように。
ただし、「まっせ」には、アンタに言われるまでもなく、自主的に、というちょっと恩着せがましいニュアンスも入ってたりします。
そして、もっとも大阪的な変容が「まんがな」です。「ます」が「まん」に変化し、強意、強調の「がな」が付いた形です。こんな用例になります。
「せやから(だから)、さっきから、なんべんも言うて「まんがな」。あんたの理屈は通らへんて。物わかりの悪い人でんな(ですな)」
用例からもご想像のとおり、押し付けがましく、断定的な言い方です。相手との距離感を間違わず、これが自在に使いこなせれば、大阪弁1級と認定してもいいかも。
<あとのケンカを先にする>
表現としては大阪弁ではないのですが、いかにも大阪人的発想の言い回しなので、取り上げました。私も関西で仕事をしていた時に言われた覚えがあります。
状況は忘れましたが、ビジネスの現場でこう切り出された時、「えっ、ケンカになるようなとんでもない条件を出すつもり?」と思わず身構えたのを思い出します。
ケンカ、というのは言葉のアヤです。(ケンカになりかねない)話し手にとって都合のいい条件であったり、相手にとって、なかなか飲めないような厳しい条件を最初に出しますから、覚悟しといてください、という前フリ、メッセージなんですね。
ちょっと考えると、非大阪的なやりかたです。あれやこれや、いろんな話、条件を、落ち出して、相手の腹も探りながら、落とし所へ持っていく・・・これが大阪に限らず普通でしょう。
でも、いきなり言う戦略もあります。まわりくどい話をして、時間ばかりかけるより、早く決着つけたいという意思表示です。そして、当方としては、妥協の余地のない条件提示です、という思いを強くアピールする魂胆も入っています。
いつでも、誰にでも、というわけには行きません。相手との信頼関係があり、距離感もしっかり掴んだ上で使う必要がありそうです。
銀行に勤めていた知人が、若い頃、「いやあ、社長。あとのケンカを先にしとかなあきまへんねんけど(しておかなければならないのですが)、融資限度は、〇〇〇万円でんねん(です)」などと切り出すと、たいてい話がスムーズにいった、というんですが・・・ホンマかな?
いかがでしたか?大阪弁の世界を面白がっていただければ幸いです。それでは次回をお楽しみに。