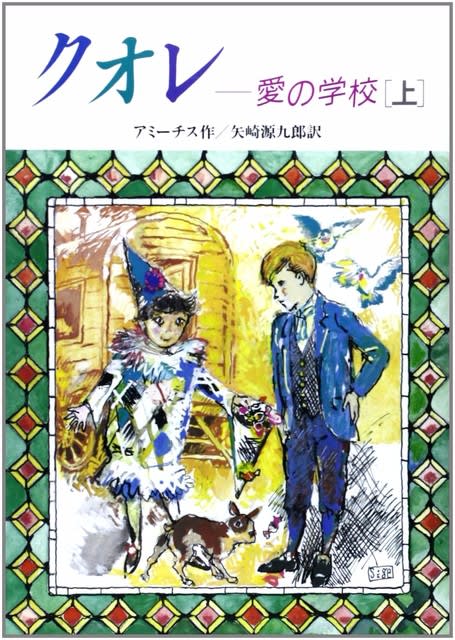
う゛う゛……物語が終わるまでまだちょっと結構(?)あるのに、ここの前文に書くこと特になくなっちゃったみたいな。。。orz
まあ、そこでちょっとまた読書感想文的な何かをというか、なんていうか(^^;)
えっと、読んだの実は結構前なんですけど、このお話の前に連載してた「ぼくの大好きなソフィおばさん」を書きはじめた頃に……パブリックスクールのこととか調べたいと思ったんですけど、なかなか検索してもその種の本というのがありませんでww
でも確かその時、「パブリックスクール」で検索して見つけた本と関連した本として出てきたのが、「クオレ~愛の学校~」という本だったんですよね。
「あ、読んだことないけど、なんか名前だけ聞いたことある~♪
 」っていう方、多いのではないでしょうか。
」っていう方、多いのではないでしょうか。わたしも、昔の『ハウス食品~世界名作劇場』的な、そういう系のお話なんじゃないかなと漠然と想像してて(歳がバレるww笑)……まあ、『世界名作劇場』ではアニメ化してなかったと思うのですが、わたしてっきり、クオレって人の名前、男の子の名前だとばかり思っていたんです。
んで、この健気な男の子が、周囲の逆境をものともせずに、友達と協力して何かする的な(笑)、そんなお話を軽くタイトルから妄想してました。。。
いえ、わたし完訳版のほうを読んだんですけど、とてもとてもとーっても良いお話でした


そしたら、ありましたねえ。本の後ろに「全国学校図書館協議会選定」って(笑)
実際、巻末で解説を書いておられる上野山賀子さんも、「すこしお説教くさいところがあるかもしれませんが」と書いておられるのですが、わたしもこれは思いました(^^;)
なんていうか、すごく「道徳的」と言いますか。物語のほうは、エンリーコというミラノの小学四年生の男の子の書いた日記(イタリアで新学期のはじまる10月から翌年の7月まで)、そしてその日記の間に、毎月1話先生が課題としてだす物語と、エンリーコの家族(お父さんとお母さんとお姉さん)の意見が挟まっているという形で綴られていきます。
お話全体を通して、「お道徳くさい」ところがあって、わたしも「あ~、ものすごくいいお話だけど、この長い物語を面白がって読む子は、今のこのご時勢では少ないだろうな~
 」という印象でした。
」という印象でした。何分、年代のほうも1870~80年代とか、そのくらいだと思うので(クオレがイタリアで出版されたのは1886年)、今からもう百年以上も昔の学校物語って、あんまり興味持つ子、いない気がするんですよね(^^;)
でもそのかわり、主人公のエンリーコと同じくらいの歳の子供にとっては、「教育」ということについてこうしたことが大切で、必要不可欠だ……といったエッセンスがぎゅっ☆と詰まっているという意味で、まるで宝石のような本だとも思います

タイトルの「クオレ」というのは、「愛」とか「真心」という意味で、本を読むと、そのことが人生で一番大切なことなんだよ……ということが、色々と形を変えて語られています。
この本、出版された当時イタリアでも物凄く売れたそうですが、おそらく当時のその頃の読者さんが胸を打たれ、感動で涙を流した……その同じ感動を味わいながらも、その後百年以上の過ぎた「今」の現代人であるわたしが読むと、また別の意味で胸の痛くなる本でもある気がするんですよね。
本の中で語られているような、先生たちの自己犠牲的な愛、そうしたものがあまりに薄れてしまったように感じる今の日本の学校(もちろん、あるところにはあると思うんですけど^^;)、子供のほうでもそんなに先生に対して尊敬を払っていないという現実……でもそれでいて、出版後百年以上が過ぎた他国人のわたしが読んでも感じることの出来る、心あたたまる優しい感情……こうした「愛」とか「真心」といったものは、今から千年前も千年後も、その「核」となる部分は大切なものとして絶対変わらないだろうということ……。
ちょっとこれ以上書くと長くなりますので、「クオレ」のことについてはまた次回にまわしたいと思いますm(_ _)m
それではまた~!!

聖女マリー・ルイスの肖像-【28】-
一方、ケイティ・オーモンドのほうはあまり写真撮影のほうが思わしくなく、どこかがっかりした顔つきで、撮影スタジオのほうから出てきていた。そんな彼女の前で嬉しそうにするのもどうかという気がして、ココは顔つきを引き締めていたものである。
「ケイティのお陰で、面接のほうは大分落ち着いて受けることが出来たわ。ありがとう」
「ううん。わたしだってココに撮影される時のコツみたいなこと、教えてもらったんだから、おあいこよ。ただ、わたしの場合撮影直前の付け焼刃じゃまるでダメでね……まあ、それなりになんとなく写真を撮ってもらったみたいな感じかな」
――結果については、一週間以内に郵送で通知するとのことで、合格でも不合格でも、どちらでも返事だけは来るということだった。この日の夜、ココは終始上機嫌で、夕食の席でもずっとオーディションの話ばかりして、まるで興味のないランディとロンを辟易させていたものである。
「最初はすっごく緊張したけど、終わってみたらほんと、すごくいい経験になったわ。それに、一回くらい受けてダメでも、大したことじゃないもの。それより、五万人の中から写真で選ばれた五百人ってだけでも、実際大したものよね」
「そうかな。俺はそういうオーディションだのミスコンだの、あんまり感心しないな。っていうか、大人の金もうけのための道具みたいなものだろ?」
ランディが珍しく、兄らしい賢い意見をしたため、マリーは少しばかり驚いた。というより、そうした考え方も確かにあると思ったのだ。
「ふふん。あんたは見た目がおデブちゃんだものね。モデルなんて絶対死んだって無理よ。っていうか、負け犬のひがみにしか聞こえないっていう感じ」
「そんなことないさ。ドラマにだって太った子供の役ってのはたまに必要になるだろ。俺だって、テレビに出ようと思ったら、早食い選手権だの、何かそんなので出れるかもしれない。だけど、俺はココみたいに虚栄心が強くないっていうそれだけさ」
「言ってなさいよ。あんたがもしデブの専門誌のオーディションでも受けて合格したっていうんなら、わたし、その時にはなんだってしてやるわよ」
ランディとココがいがみあっているのをよそに、ロンはマリーに向けて『ほら、言ったでしょ、おねえさん』といったように目でサインを送っていた。実をいうと、ココがキッズモデルのオーディションを受けると聞いた時、ランディとロンの示した反応というのはまったく同一のものだった。そんなのでもし万一、最終審査にまで残ろうものなら、ココの鼻はすっかり天狗になって、天高く聳えることになるだろうというのだ。『ココがもし今以上に高慢ちきで虚栄心が強くなったら、それこそ大変だよ』と、ふたりとも声を揃えてそう言うのだった。
「ねえ、おねいさん。ミミもオーディション受けられる?」
「えっとね、ミミちゃんはまだ六歳だから……あ、でもそうよね。六歳の子でも受けられるオーディションって、もしかしてあるのかしら?」
ココとランディの言い争いがだんだん激しくなってきたため、マリーが話を変えようと、ふたりの会話に入りこもうとした時――折りよく、イーサンが帰ってきた。オーディションに出かける前、アルマーニのスーツを着た兄の姿を見て、目がすっかりハートマークになっていたココだが、再びスーツ姿の兄を見て、「キャーッ」とばかり、兄の元まで駆けていく。
「ココ、オーディションのほうはどうだった?」
「もうバッチリよ!!あれでもし三次審査に進めなかったとしたら、それはもうわたしの実力不足とかなんとかいうより、モデルがわたしの天職じゃないとか、何かそういう啓示だとでも思うしかないわ」
「すごいな。そんなにうまくいったのか」
イーサンはマリーのほうを見、彼女もまた嬉しそうに微笑むのを見て、ほっとした。おそらく守備のほうは相当うまくいったものと見える。
そしてココがまた一から順にオーディションの様子を説明しだすのに辟易したランディとロンは、食事の皿を片付けると、早々に五階のほうへ上がっていった。また、受付のところで<76>のネームタグを受け取った時から、すごくいい予感があったという話から彼女は写真撮影、面接がどんな感じだったかなど、順に話していったわけだが――唯一、イーサンにはロンとランディがいた時にはしなかった話をした。
「でね、そのケイティがタヌキじじいって呼んでた人なんだけど、わたしには特にこれといって何も意地悪な質問とかしなかったのよ。そのかわりね、あのおっさん、マリーおねえさんのこと、穴があくんじゃないかってくらい、じいいいいっと見てたの。なんかすっごくやらしい感じ。だからね、おねえさんを見るのに忙しくて、わたしには意地悪な質問をし忘れたんじゃないかって思うのよ」
「なんだ、マリー?あんた、中年のタヌキに知り合いでもいるのか?」
食事のほうは当然済ませてきたとのことで、代わりにマリーはイーサンにいつも通りコーヒーを淹れていた。
「べつに、あの審査員のおじさんはわたしのことなんて見てなかったと思うわ。ココちゃんの気のせいじゃないかしら?」
「ううん。絶対見てた。だってわたし、他の四人の面接官の視線は自分のほうにビシバシ感じたけど、あのタヌキじじいだけは唯一違ったのよ。あのフォトグラファーのお兄さんだって、わたしのことにかこつけて、本当はおねえさんの写真が撮りたかったんじゃないかしら。まあ、そのお陰でわたしは助かったんだけどさあ」
そう言ってココは、撮影スタジオでもらった例のポラロイド写真をイーサンにも見せた。プロが撮っただけあって、なかなか良く撮れていると、イーサンにしてもそう感じる。
「なんにしても、色々とうまくいったみたいで良かったな、ココ。実は結婚式の間も、おまえがオーディションでうまくやってるかどうかと、そんなことを時々考えたりしてたんだ」
「そうなの!?じゃあ、なんだか悪かったわね、イーサン。でも、そんなふうに心配してくれたってだけですごく嬉しいわ。花嫁のクリスティンだけじゃなく、ブライズメイドのキャサリンもすごく綺麗だったでしょうねえ。わたしも見たかったなあ」
「ココ、おまえもいつか誰かのブライズメイドになったり、あるいは自分が結婚するかして、そういう経験が出来るさ。だが、そうしたら俺は父親のかわりにヴァージンロードを歩かなきゃならんだろうなあ。そう考えるとちょっと寂しい気のするのが不思議だな」
「やだあ、イーサン。何言ってるのよ!わたしまだ九つなんだから、そんなのまだまだ先の話よ」
そう言いながらも、敬愛する兄に対して愛情がこみあげ、ココは兄のことを屈ませると、その頬にキスをして慰めた。それから、「おねえさんも、今日はほんとにありがとう!」と嬉しそうに言って、ココはダイニングを出ていった。
「あんたも、負担の大きい役回りを任せて今日は悪かったな。もしこのオーディションにココが受かったとしたら、三次審査には必ず俺がついていくようにするから……」
「ええ、ほんとに。ココちゃんの頑張りでうまくいったのは良かったんですけど、やっぱり三次審査っていうのはわたしには荷が重すぎますもの。イーサンが一緒なら、ココちゃんもわたしが一緒についていくより心強いでしょうし」
――だが、実をいうとココは二次審査に合格し、三次審査に進むことが出来たものの……その前に学校のほうで大きな問題が起きた。というのも、ケイティ・オーモンドは二次審査止まりだったため、三次に進むことの出来たココとの間に溝が出来てしまったのだ。
ケイティがあまりにはっきりした態度で無視してきたため、ココにしても(そういうことか)とすぐに察しはついた。けれど、ケイティのやり方があまりに露骨だったせいもあり、ココは何人かの女生徒の強烈な同情を受け、クラス内で孤立するといったことはなかった。兄のランディのクラスの、オリヴィアとエミリーの場合とは違い、ココとケイティとは勢力を二分することもなく、ココは自分を慕ってくれる他の女子グループの子たちと仲良くし、ケイティは前と同じ自分の取り巻きと仲良くするという、何かそうしたことになった。
とはいえ、ココはこのことがショックだった。最初はお互いに、ただ軽い気持ちで応募したオーディションだった。けれど、ココはケイティと「もし芸能人になれたらどうするか」、「モデルになれたら……」、「女優になれたら……」と、そうふたりで想像して色々なことを話すのが楽しかった。それなのに、その夢が現実のほうに少しばかり近づいたかのように思われた時、突然何か大きな精神的亀裂が入ったように感じた。
『ケイティはココに嫉妬してるのよ』と、みんなは口々にそう言って慰めてくれた。でもココにはそんなことより、ケイティと彼女のグループ――ココがもともと所属していたグループ――が、自分に対し色々言っていることに対して傷ついたのだ。『あの子がおねえさんっていつも呼んでる人、本当は義理のお母さんなのよ』、『ココのお父さんとは五十いくつも歳が離れてたんですって』、『えーっ!?信じらんなーいっ!!』、『なんでも、財産目当ての結婚だったらしいわよ』……それまで、そんな話は誰もおくびにも出さなかったはずだ。けれど、もしかしたら自分が知らなかっただけで、みんな陰ではそんな話をずっとしていたのかもしれない。
この日、ココは家に帰り着くなり、「ただいま」とも言わず、真っ直ぐ自分の部屋にいって閉じこもった。屋敷のドアを開けると、例の妖精の鈴の音がシャララアンと鳴り、リビングのほうからは甘いお菓子を焼いた匂いが漂ってくる。いつもなら、ココもそんな小さなことだけで、当たり前のように幸せを感じた。けれど、この日はどうしてもダメだった。心が石のように重く、そうした心的疲労によって何もしたくないとしか思えない。
ドアの鈴の音で、マリーにはロンかランディかココのうち、誰かが帰ってきたとわかっていた。そして子供たちが毎日真っ先にやってくるのはダイニングのほうなため、その気配がまるで訪れず、怪訝に思った彼女は廊下のほうを見た。すると、階段のほうを黙って上がっていくココの姿が見える。
(学校で、何かあったのかしら?)
そう察したマリーは、一度エプロンを脱いだ。というのも、ランディのくれたひまわり模様のエプロンをココは「ダサい!」と決めつけており、さらにはそのポケットにぬいぐるみを突っ込んだ状態で自分の友達の前に姿を見せるなど、言語道断だとよく言っていたからである。
もちろん、この時ココは学校帰りに友達を誰か連れてきていたわけではない。それでも、マリーはココの意気消沈した様子から、彼女に「何かあったらしい」と察していたのだ。
「……ココちゃん、どうかしたの?」
部屋のドアをノックしても返事がなかったため、マリーはそっと中の様子を窺った。すると、窓敷居のところに顔を突っ伏して、ココが泣いている姿が目に映る。
「ケイティのことね?」
そう聞くと、ココは何度か頷いた。おねえさんのことをケイティや元の仲間が色々言っていたことを、ココは彼女のせいにするつもりはない。何故といって、おねえさんは自分にも他の兄妹にもとても良くしてくれるし、根本的な問題はそういうことではないと、賢いココにはよくわかっていたからだ。
「今は一次的に気まずかったとしても……」
「ううん。一時的にとか、あれはそういうんじゃないよ!!」
ココは服の袖で目頭を拭うと、顔を上げて言った。
「べつに、ケイティじゃなくたって、友達は他にもいるからいいけど……わたし、なんでオーディションなんか受けようと思ったんだろ。もしケイティが落ちて、自分が三次審査に進むって最初からわかってたら――こんなことになるってわかってたら、あんなオーディションなんかどうでもよかったのに。おねえさん、ケイティは違うんだよ。もちろんわたし、モニカやカレンのことも好きだよ。でもケイティはあの子たちとは少し違うの。勉強もすごく真面目にするし、ピアノも弾けて、将来のことも色々ちゃんと考えてて……仲間外れにされちゃったけど、本当はすごくいい子なの。ねえ、わかる!?そういう子がわたしのこと、仲間外れにしたんだよ!」
ココはもう一度わああっ!!と泣きだすと、マリーに身をもたせかけた。ココがこんなふうに泣くのは、クイーンユージェニーホテルでのあの時以来だったので、マリーとしてもその時のことを思いだし胸が痛んだ。
「意地悪なタヌキじじいにわたしは何も意地悪なこととか言われなかったって言ったら……それはお父さんがその芸能プロダクションの人と知り合いだったからじゃないかって……他にね、わたしがお父さんが六十くらいの頃に出来た子だとか、色々……」
「ま、まあ……」
あまりのことに、マリーも驚いた。マリーの目から見たケイティ・オーモンドというのは、見るからに優等生的な少女だったため、そんなことを本当に彼女が言ったとは、俄かには信じられないほどだった。
「だからね、わたし、あまりのことに呆れちゃった。むしろね、ケイティにとって、三次審査に進めなかったっていうのは、そのくらい悔しいことだったんだって思ったの。もしわたしが逆の立場なら、そりゃ悔しいことには悔しかっただろうけど、だからってケイティのことを仲間外れにしようとか、そこまでのことは思わないもん。だから、あの子とわたしとではそもそも格が違うんだって、そう思うことにしたの」
「そうね。おねえさんもとても残念だと思うけど……仕方ないわね。おねえさんにはケイティが本当はどう思ってるか、そこのところはわからないけど……きっとケイティは今ココちゃんとまともに顔を合わせて冷静に話すとか、出来ないんじゃないかしら。ランディが、自分のクラスの女の子の派閥争いのことを話してたことがあったけど……」
「うん。でもわたし、そこまでしようとは思わないな。もちろんね、正しいのはわたしのほうなんだから、ケイティにやり返してやろうと思えば、出来ないこともないよ。だけど、わたしにはそんなこと、どうでもいいことなの。おねえさんにはわたしが何言ってるかわかんないだろうけど、それはね、わたしがそういうふうに思えるのはね、イーサンやおねえさんがいてくれる、そのお陰なの」
ココは大きな目にたまった涙を拭うと、マリーが差し出したティッシュで、洟をひとつ大きくかんだ。一度泣いて話を聞いてもらったら、かなりのところスッキリした。
「だって、そうでしょ。そんなことしても、イーサンもおねえさんも喜ばないってわかってるもん。それよりね、わたしのほうで何もしないで、毎日明るく学校に通って、他の友達と楽しくしてたほうが――あの子にはよっぽど効き目があるよ。ほんと、可哀想な馬鹿な子!わたしみたいに可愛くてお金がいっぱいあって、たくさん色々物を持ってる子と仲良くしないだなんて……でも、今度は別の子にその恩恵に与らせてあげるつもり。そしたらね、ケイティなんかといるより、ココと一緒のほうが何かとお得なだけじゃなく、とっても楽しいみたいになるんだから!」
「まあ、ココちゃん……」
あまりの立ち直りの早さに驚くのと同時、マリーはココと一緒になって笑った。
「そうね。ココちゃんは正しいわ。おねえさん、お友達のことでは何もしてあげられないけど……でも、三次審査の前にまた新しくお洋服買いにいきましょう。二次審査の時より、今度はもっと豪華なお洋服のほうがいいかもしれないものね」
「うん。この間の時のオーディションでさあ、まわりの子がどれくらいのレベルの格好してくるかとか、ある程度わかったでしょ?だからね、今度はこういうドレスがいいんじゃないかとか、もうなんとなくイメージしてるのよ。あんまり機をてらいすぎてもダメだしー、でもあんまり地味すぎても子供らしくないもんね。ああ、今度のお休みが今から楽しみだわ!」
――この時以後、ココはケイティの話はしなかったし、マリーも彼女のことを持ちだすのは避けるということにしていた。夜になってふたりきりになった時、イーサンはこの話を聞いてやはりマリー同様残念がった。ココが今も仲良くしているモニカやカレンといった子は、このまま三人仲良くしていった場合、いつか頭カラッポのお化粧オバケ、そして話すことといえば男の子のことだけ……といったようになる気がしたが、ケイティは優等生でココにもいい影響を与えてくれそうだと思っていたからだ。
そしてこの約半月後の十一月上旬、ココは二次審査に向かう時以上に緊張した面持ちで、イーサンと一緒にタクシーでオーディション会場となっているホテルまで出かけていった。マリーと一緒だった二次審査の時は、ココは緊張を誤魔化すためにずっとしゃべってばかりいたが、この時はずっと寡黙に口を閉ざしたままだったのである。
いつもはおしゃべりなココが黙りがちなことで、イーサンとしても調子が狂ったが、それだけ妹がこのオーディションに懸けているのだろうと思い、自分も気を引き締めることにした。だが、受付を済ませてオーディションの控え室に通された時、イーサンはかなりのところ驚きに包まれた。
というのも、バレエのチュチュに身を包んだ子は、部屋の隅のほうでシェネの動作をしているし、他にイヤホンで音楽を聴きながら激しくジャズダンスを踊っている子など、とにかく個性的な子が多かった。彼は兄として、妹もかなりのところ人目を惹く容貌をしているとは思うが、かといってココに何か特技があるかと言われれば、何も思いつかないというのが現状だった。
「ココ、この場の空気に呑まれるなよ。おまえは二次審査の時みたいに、おまえらしくしていたらそれでいいんだから」
そう言ってイーサンは妹のことを慰めようとしたが、実をいうとかく言う彼自身はといえば(こりゃもうダメだな)などと思っていたかもしれない。廊下のほうからは、その自慢の喉を披露しようというのだろう女の子が、「♪あ~ああああ~」などと発声練習している声が聞こえる。他に、新体操のリボンをくるくる回す子がいたり、世界びっくり人間よろしく、物凄い体の柔らかさを発揮している少女がいたりと……正直、ココはもしや<正統的美少女>ということで残されたという、それだけではなかったのかという気が、イーサンはだんだんしてきた。
(いや、他の美少女コンテストの最終グループに残った子たちだって、そういう子が結構いるものな。ココだって、最後まで諦めさえしなければ……もしかしたらもしかするぞ)
と、その一方で、イーサンはあるひとつのことが気になってもいた。五人いたオーディション審査員のうち、芸能プロダクションの社長が、ケイティにしたような意地悪な質問をしなかったという話だ。そのかわりに、この芸能プロの社長はマリーのことをじっと見ていたという。実はその件についてイーサンは、少しばかり思い当たるところがないでもなかった。
彼とココの父親――ケネス・マクフィールドは、数えきれないほどのモデルや女優と浮き名を流し、愛人にしていた。そしてケネスの狙う女性というのが大体、世間に実力派として知られる女優であるとか、何かヒット作に出たことのある女優ではなく、いわゆる二流とか三流、あるいはそれ以下でくすぶり、アダルトビデオに出演して大金を稼ごうかどうか迷っている……といった手合いの女性たちであった。こうした女性たちの所属している芸能プロダクションにケネスは知己が結構おり、金と引き換えに紹介してもらうといったことが、実際よくあったらしい。
もしそのオーディション審査員の、芸能プロダクション社長とやらがケネスの知り合いだとしたら、ココが彼の娘だと気づいた可能性もある。その場合、以前儲けさせてもらった縁から、『あの娘のことは三次審査に進ませておけ』と命令したということもありえるかもしれない。そして何より、そう考えたとすれば、そのタヌキじじいがマリーのことをじっと見ていたという理由も頷ける。何故なら、あの遊び人のケネス・マクフィールドが最後に結婚した女ということは……もちろんそういう女に決まっているではないかという、そうした思い込みからだ。
ココが緊張ではち切れんばかりの時だというのに、イーサンはマリーとは違い、実に呑気なもので、だんだん暇になってきた彼はまわりの様子を眺めつつ、余計なことを考えだした。
(そうか。そう考えた場合、やっぱり俺が三次審査についてきて正解だったな。果たして、『俺にも大股開きしてくれたら、娘さんを最終選考に残してあげましょう』なんてことがあるのかどうか……いやいや、これは子供のオーディションだぞ。流石にそんなこと、倫理的にあっていいわけがない)
イーサンがそんなくだらないことを考え、そしてふと隣の妹のことに目を戻すと、ココが突然彼のブルーグレイのズボンをぎゅっと握りしめてきた。彼は今日、それほど派手ではない、カルバンクラインのスーツにネクタイという格好だったのだ。
「どうした、ココ?」
「お兄ちゃん、わたし……なんかもう帰りたい」
妹のか細い声を聞いて、イーサンはもう一度周囲の状況を確認した。薔薇色のチュチュを着た娘は、なおもバーレッスンのようなことを繰り返し、ジャズダンスの娘はそんな彼女を威嚇するようにリズムに乗って踊っている。まるで、今からすでにオーディションは始まっているとでも言わんばかりだ。外の廊下からは相変わらず「♪あ~ああああ~」だのいう声が聞こえ、世界びっくり少女はありえない形に体を折り曲げ、ポーズを取っている……しかもそんな子が、何十人となくひしめきあっているのだ。
もちろん、ココのように保護者の隣でただじっとしてる少女というのもたくさんいたが、みなココに負けず劣らず可愛らしい容貌で、隣にいる母親同様、マリー流の言い方をするとしたら、実に「ビッ」とした格好をした子ばかりだ。
だがここで、イーサンの中では迷いが生じた。いかな状況であれ、「最後まで諦めずにやり切る」ということを、ここで妹に教えておいたほうがいいのではないか、ということである。それに、ここで逃げだせば、ココ自身があとあとまで一生後悔するという可能性もなくはない。
「ココはそれで、後悔しないのか?」
「ううん。イーサンが今考えてること、わたし、わかってるよ。まわりの空気に呑まれてもうダメだと思ったから帰りたいとか、わたしが言ってるのはそういうことじゃないから……このことで、どうしてあの時止めてくれなかったの、なんてイーサンのことをあとから責めたりもしない。ただ、もうわたし、家に帰りたいの」
「…………………」
ココはもともと勝ち気な子であり、自分で最初にこうと決めたことを途中で投げだすような子ではない。だが、そういう性格の妹が「家に帰りたい」と言っているのだ。イーサンは、もう一度だけ「本当にこれでいいんだな?」とココに聞いた。すると彼女が頷き、胸のところからネームタグを外したため、イーサンは受付の係員に「棄権します」と言って妹と一緒に外へ出た。
「こんなことなら、自分の車に乗ってくれば良かったな。ココ、何か食いたいもんないか?帰りに少し、何かうまいもんでも食ってから帰ることにしよう」
イーサンがそう言うと、ココは通りの角にあるハンバーガー屋の看板を指差した。
「わたし、ハンバーガーとポテトが食べたいな。おねえさんの作ってくれるハンバーガーも最高だけど、たまーにマクドナルドとかで食べたくなるの。イーサンはそういうことってない?」
「ふうん。ココはあんな安いもんでいいのか。まあ、確かに俺もたまーにマクドナルドのハンバーガーなんかが無性に食いたくはなる。それじゃあ、そこに寄ってくか」
「うん!!」
緊張の呪縛から一気に解放されたココは、実に子供らしい無邪気な笑顔でそう応じた。それでイーサンはそちらに向けて歩きつつ、(本当にこれで良かったんだろうか)と思い、ハンバーガーショップでチーズバーガーを食べる妹に、最後にこう聞いていた。
「だけど、急に一体どうした?二次審査を突破できたって、あんなに喜んでたのに……」
「そうなんだけどね」と、ココはナプキンで口許を拭きながら言った。「こんなことのためにケイティと友達として駄目になっちゃったんだなあって思うと、なんか虚しいなあと思って。わたし、最初はね、こう思ってたんだ。絶対に三次審査も突破して、ケイティに目にもの見せてやるって。だから、すごく張り切ってたんだけど……なんか、実はね、ケイティとオーディションの最終選考にお互い残ったらどうするかとか、モデルや女優になるっていう夢が叶ったらどうするかとか、そんな話をしてきゃあきゃあ騒いでることのほうが楽しかったみたい。それとね、イーサン。わたし、このオーディションを受けた理由がもうひとつあるんだ」
「どんな理由だ?」
フィレオフィッシュを食べながら、ポテトをひとつ口に放りこんで、イーサンはそう聞いた。
「イーサンにね、自分の妹を自慢に思ってもらいたかったの。ほら、なんかの拍子に『俺の妹は実はモデルをしてるんだ』なんて言えるのって、なんか格好いいじゃない。わたしにとってイーサンは自慢の兄だもの。ユトレイシアの大学院に兄は在籍してますとか、ユトレイシア・ガーディアンズで戦ってたんですとか、そう言える機会があるたんびに、顔が高慢ちきに輝きそう」
そう聞いて、イーサンは思わず笑った。ロンとランディは妹のオーディションに最後まで不賛成であり、最終選考になんて万一残ろうものなら、高慢ちきになってどうしようもないだろうという話ばかり繰り返していたからである。
「俺はこんなに可愛い妹がいるってだけで、十分今も自慢だし、誇りにも思ってるさ。ただ俺は、このことでおまえが、あの時オーディション受けてれば今ごろ自分はティーンズモデルとして活躍してただの思って後悔しなけりゃいいがって、そのことが心配なだけだ」
「うん。なんかね、わたしもここのところ色々考えてたんだ。ケイティのグループからわたしが弾かれた時、他の子たちはすごくわたしに同情してくれたわけだけど……まあ、もし万一、あの三次審査を突破して最終選考に残ったとして――その時にこの子たちがわたしから離れていかない保証はないなって思ったの。イーサンは男だからわかんないだろうけど、ほら、女ってそういうとこあるのよ。実際、ケイティだって今はクラスの女王気取りだけど、先はわかんないわ。ロンやランディが言うみたいに、わたしが自分で気づいてないだけで、高慢ちきなのがいつも顔にでるとしたら、そのうち今仲良くしてるグループの子からも仲間外れにされるかもしれないし……」
「おまえ、もしかして朝からそんなこと考えてたのか」
「うん、そう。わたしがずっと黙ってたのは、緊張とかいうよりも、そっちのことを色々考えてたからなの。でね、あのオーディションの控え室に通された途端、思っちゃった。『ああ。こりゃもう駄目だ』って」
お互い、まったく同じことを考えていたらしいとわかり、ココとイーサンは互いに顔を見合わせて笑った。
「まあなあ。それに、三次審査では、オーディションの審査員が五人から十人に増えるんだろ?」
「そうなんだよね。なんかもうそういうプロの人たちの目にさらされて赤っ恥かく勇気もなくて……もちろんね、最後までやれるだけやっても良くはあったんだよ。でもわたし、あのジャズダンスの女の子みたいに、まわりの子全員を敵視してギンギンになるとか、そこまでの気持ちは自分にはないなって思ったもんだから」
イーサンはまたもう一度笑った。
「だよなあ。バレエのチュチュ着た子のことを始終睨みまくってたもんな。それに、確かに綺麗な子とは思うけど、あんな派手なチュチュとか着る勇気、ココならあるか?」
「どうなんだろ。わたしももしかしたら、小さい時からバレエとかやってたら、大して気にしなかったかもね。なんにしても、演劇のテストとかさせられたりするんだろうから、控え室に入った時点で恥かしいとか思ってるようじゃ、それだけで負けなのかも……」
ココはイチゴシェイクをずずずっという音をさせて最後まで飲みほし、「はあ~っ!」と大きな溜息を着いた。
「とにかく、肩の荷が下りてよかった!ごめんね、イーサン。せっかくの休日に、こんなくだらないことにつきあわせちゃって」
「べつにくだらなくはないさ。俺はな、ココ。将来おまえが何になろうと、どんな職業に就こうといいと思ってる。ようするに大事なのは、ココがいつどこで何をしていても幸せだったり楽しかったり、人生に喜びがあるってことが大事なんであって――俺に自慢に思ってもらうためになりたくもない職業に就くとか、そういうことじゃなくな、おまえにとっての人生が明るくて素晴らしければ、俺はそれでいいのさ。まあ、将来デザイナーになりたければ、服飾の専門学校のほうへ進学するとか、なんでもココの思ったとおり、好きなとおりにして生きていったらいい」
「うん!!」
「じゃあまあ、そろそろ帰るか。早く帰らないと、あのおねえさん、『今ごろココちゃんはどうしてるかしら。大丈夫かしら、心配だわ』だの思いながら、ずっとそわそわしてるだろうからな」
イーサンがマリーの物真似をして、裏声を使ったのでココは笑った。少しだけ似ているところがおかしい。
「あのおねえさんさあ、絶対変だよねえ」
帰りのタクシーの中で、車窓の景色を眺めながら、ココがポツリと言った。
「だって、そうじゃない?二次審査の時もそうだけど、自分のことみたいにわたしのこと、心配しちゃってさあ。いくらおねえさんが心配しても、結局がんばるのはわたしなんだよとか、そういうことを言いたいわけじゃないよ。わたしにはね、ちゃんとわかるの。このことであとからわたしがゴネたりしたら嫌だから、それで一生懸命心配してるとか、そういうんじゃないの。むしろ血の繋がってるイーサンのほうがさあ、わたしの隣で退屈そうにあくびとかしてるのに……おねえさんね、二次審査の時、わたしのためにすごーくすごーく一生懸命だったの。わたし、一生忘れない」
「そうか。見抜かれてたか」
そう言ってイーサンは笑った。子供というのはまったくあなどれないものである。
「うん。でもそこがイーサンのいいところだもん。っていうか、わたし的にはほんとはそのくらいのほうがいい。でもね、なんかおねえさんには悪かったなと思って。結局、三次審査で棄権するんだったら、あの二次審査の時のおねえさんのがんばりはなんだったのかっていうことになるじゃない?それに、ケイティと仲が悪くなったことで、心配もかけちゃったしな。イーサン、世の中のお母さんっていうのはみんな大変だね。わたし、将来的に自分が結婚しても、子供なんか絶対欲しくないな」
(そんなことを言っても、いつかはおまえも何故かそんなことになるのさ)とは言わず、イーサンはココのことを自分のほうに抱き寄せると、頭のてっぺんあたりにキスした。この歳にして、自分で髪を巻いてセットできる小学生というのはどのくらいいるものだろうと、イーサンとしてはまったく感心せざるをえない。
イーサンとココがまるで思ってもみない時刻に帰宅したため、マリーだけでなくロンとランディも驚いていた。だが、オーディションを棄権したと聞いても、がっかりした様子を見せたのはマリーひとりだけで、他の兄はふたりとも、薄情にも「そうしておいて正解だよ」としか言わなかった。
「大体、うちのクラスの女子もそうだけどさ、女の子ってのはバカだよな。そんなくだらないことのために仲違いしたりして……俺たち男にしてみたら『そんなことどうでもいいじゃねえか』ってことで揉めたり喧嘩したりするんだもんな」
ランディのこの言葉には流石にココもムッとしたらしく、「あんただってこの夏休み、ネイサンと揉めたり喧嘩したりしたんじゃなかったっけ?」と言い返してやった。ランディは急所でも刺されたように、ぐっと黙りこまざるをえない。
この時、マクフィールド家はランチの時間だったわけだが、ハンバーガーを食べてお腹がいっぱいだったイーサンとココは、それぞれコーヒーとミルクティーを飲むだけにしておいた。マリーはイーサンと同じように「ココちゃんがそれでいいなら、いいんだけれど……」としか言わなかった。そして、「今晩はご馳走にするつもりだったけど、どうしようかしら」と、少しの間ぼんやりする。
「おねえさん、それ、わたしのために作って!わたしもケーキ作ったりするの、手伝うから」
「そう?実はもう下準備のほうはしてあるのよ。でも、ココちゃんが帰ってくる夕方までに仕度すればいいかなって思ってたの」
――この日、珍しくココは午後中マリーのことを手伝って、色々とお菓子を作ったり夕食の準備を手伝ったりした。バナナブレッドやストロベリーマフィンやガトーショコラ、豆腐入りのドーナツなどなど……夕食のほうはココの大好きなサーロインステーキにお寿司だった。ケネス・マクフィールドが日本食のチェーン店を経営していた関係で、そちらの店のほうから日本食の食材が定期的に届くのだった。
「マリー、おまえよく米の握り方なんて知ってたなあ」
ダイニングに入った時、酢飯の匂いが鼻孔に漂ってきて、イーサンは驚いた。ロンとランディとミミも、興味津々といったように顔を輝かせている。
「ネットにそういう動画があるんですよ。あとは見よう見真似っていうのと、あとマキズシっていうんですか?海苔の上にご飯のせて、それぞれ自分の好きな具材をのせて巻いたりとかどうかなって思って……」
子供たちがみんな「やりたい、やりたーい!!」と言ったため、マリーはタッパの蓋を開けて、細長く切ったきゅうりや、マグロやサーモンなど、色々な具材を並べるということにする。マリーはマリーで、寿司を適当な形に握ると、その上にもともとパックに入っている寿司ネタをそれぞれ順番にのせていった。今日のお祝いのために、特別にそのようにしてもらっていたのだ。
サーロインステーキのほうは、イーサンが焼いた。こちらも店で出している高級な肉なので、美味しいのは間違いない。寿司とステーキ、そして食後にはケーキもあったことで、この日、子供たちはお腹がはちきれんばかりにいっぱい食べた。大きな盥に炊いたご飯をたっぷり入れたにも関わらず、酢飯のほうは最後、一粒も残らなかったほどだった。
「おねえさん、これ、絶対また作って!!」
ランディはそうせがみ、ミミは口のまわりを米粒だらけにし、ココとロンは食後、リビングのソファで苦しいお腹を抱えて横になっていた。マリーはそんな子供たちの楽しそうな様子を見て喜び、イーサンは彼女が満足そうにしているのを見て嬉しかったというわけだった。
「あ~、もうわたしお腹キッツい。明日からちょっとダイエットしなきゃ」
「何言ってんだよ、ココ。一日くらいたらふく食べたからって、明日から普通の食事に戻せば、どうってこともないだろ」
ロンとココはそんなふうに話しつつ、少しふらつきながら自分の部屋のほうへ戻っていった。ランディは酢の入った瓶をじろじろと眺め、「なんでこれを米に入れるとこんなに美味しくなるんだろ!」と最後まで不思議そうに眺めまわしていたものである。
「それにしても、自宅で寿司が食えるとは俺も思わなかったな」
ランディも自分の部屋のほうへ上がっていくと、イーサンは後片付けをはじめたマリーにそう言った。それから、食事の間ずっと飲んでいた白ワインに炭酸を混ぜたグラスを、マリーのほうに差しだす。
「あ、あの……わたし、お酒は……」
「いいから、一口だけでも飲めよ。それで受けつけなければ飲まなければいい」
マリーはイーサンに強く勧められるあまり、断れなかった。それで、細身のグラスに手を伸ばすと、一口だけ飲んでみる。
「……おいしい」
「だっろー?あんた絶対食わず嫌いなんだよ。ああ、この場合は飲まず嫌いか。たまに酒でも飲んで息抜きしないと、あんた潰れちまうぞ。まあ、今日はココのオーディションがあったからな、それで色々ご馳走を作る準備をしてたってのはわかるが、もっと適当だったり、たまに手抜きだったりしても全然いいんだよ」
「ココちゃん、これで本当に良かったんでしょうか?」
一応、お菓子作りを一緒にしていた時に、オーディションを棄権した理由についてはそれとなく聞いていた。『今はね、他の子たちもみんな、わたしのこと可哀想がってくれてるからいいけど、結局最終選考まで残ったりしたら、それもどーなのかなーっていう、そういうこと。おねえさんにはわかんないかもしれないけど、女子ってそういうとこあるでしょ?キッズモデルになんかなったりしたら、ケイティだけじゃなく他の子にもやっかまれるかもしれないし……そういうこと考えるとね、わたしは自分ではこれで良かったと思ってるんだ』――と、ココはそう言っていた。
「まあ、おそらくココの判断は正しかったろうな」
夕食をあんまり食べすぎてしまい、すっかりお腹のくちくなったミミは、「おねえさん、ミミねむくなったちゃったよ」と言って、いつもより早く就寝していたので、今はふたりきりだった。そして、ワイングラスを片手に、マリーとイーサンは向かいあっていたわけだった。
「控え室に入った瞬間から、バレエのチュチュを着た子だの、バトントワリングの練習をしてる子だの、そんな子が部屋中にいっぱいいたからな。ココにはああいう種類の特技は何もないし、特別演技力や歌唱力があるってわけでもないから、ココ自身、『こりゃもうダメだ』ってすぐ思ったらしい。あと、あんたも聞いてるだろ?ケイティのグループから外されて、他の子たちが同情してくれたまでは良かったけど、女ってのはビミョーな生きもんだから、もし最終選考に残ったりしたらどうなるかわからないとか……まあ、ココはココなりに色々考えて決断したんだ。俺も『後悔しないな?』とは念を押すように二回くらい聞いておいた。だけど、本人がこれで良かったって言ってるんだから、大丈夫だろう」
「だといいんですけど……」
マリーはもう一口だけ白ワインを飲み、後片付けの続きをした。この時イーサンは、ココが『二次審査でおねえさんが自分のためにがんばってくれたこと、一生忘れない』と言っていたのを伝えようとして――どういう言葉で伝えたものだろうかと迷った。ふたりが一緒にケーキ作りをしているところを見ていて、気持ちならば通じていると思ったため、最終的にイーサンは新聞を読むふりをしながら黙りこむということになる。
(実際、変なもんだよな。キャサリンとも別れて、俺はフリーになったわけだし……もっと積極的に口説いたっていいはずなのにな。マリーのことをメシに誘おうにも、何故か自然とそれは『子供たちも一緒』ってのが前提になるし。映画に誘っても『じゃあミミちゃんの好きな○△なんてどうでしょう?』ってことになりそうだからな。実際よく考えてみると打つ手が何もない)
だが、それでいてイーサンはやはり幸せなのだった。マリーがマクフィールド家にやって来るまで、イーサン自身はこの屋敷が<家庭>だと感じたことはほとんどない。確かに「家」ではあるが、それは建物として、入れ物としての「家」なのであって、家庭というわけではない……何かそんな感じだった。けれど、マリーが来てからここは彼にとってもすっかり寛げる安らぎの場所になっている。
そしてイーサンはこの日も――マリーが何か考えごとをしているらしい様子でキッチンで手を動かしているのを、時折じっと眺めやっていた。こういう時、彼はいつも『あんた、俺のことをどう思う?』と聞こうとしてどうしても聞くということが出来ない。
(何分、『あんたは今のこの状況で、本当に俺に対して何も感じるところがないのか!?』なんて、おかしな聞き方も出来ないしな。俺のほうであとから気まずくなることなく、マリーの気持ちを聞けるのが一番とはいえ、そうなると……)
結局のところ、イーサンはこの日もマリーに何も言えぬまま、白ワインのグラスを空けると「おやすみ」と言って、自分の部屋に引き下がった。マリーの「おやすみなさい」という声を聞いて、彼はもう一度だけ彼女のほうを振り返る。だが、一緒に暮らしているだけに、イーサンにはマリーの横顔を見た瞬間にわかってしまった。彼女が自分のことではなく、ココかミミ、あるいはロンかランディのことを色々考えたり、心配しているのだろうという、そのことが……。
>>続く。

























