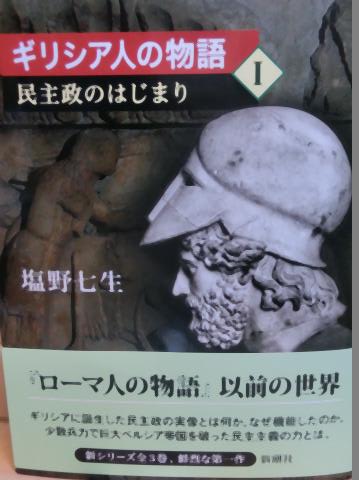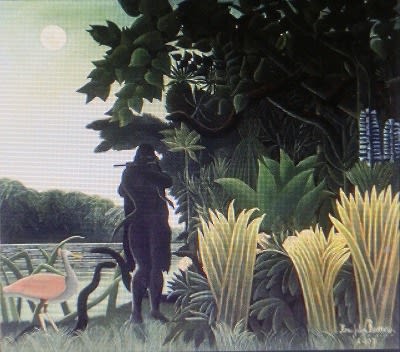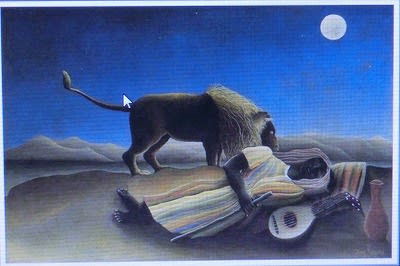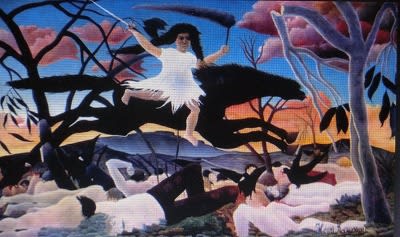ダン・ブラウンの「ロスト・シンボル」を読み始めました。
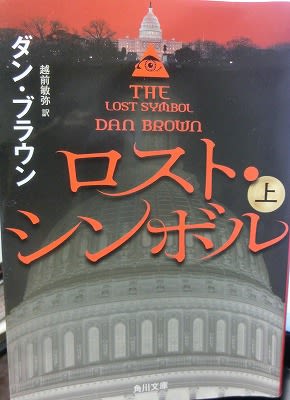
今、上巻が読み終わったところです。
ダン・ブラウンと言えば、「ダビンチコード」と「天使と悪魔」を読みましたが、この「ロスト・シンボル」は、その続きのような気がします。
なぜなら、主人公が同じで、たぶんダビンチコードと天使と悪魔での謎解きをやったことが、示されていると思うのですが、パリとローマでの謎解きという言い方で出てきました。
今度は、舞台がワシントンです。
世界最大の秘密結社「フリーメイソン」のことが出てきます。
上巻を読み終えても、全体がつかめません。
ダビンチコードの時と同じように、始めにびっくりする事件が起きます。
主人公ラングドンの知り合いの切断された手が出てくるのです。
果たして、その知り合いは、生きているのか死んでいるのか?
フリーメイソンの最高位で歴史学者のピーターソロモンの手なのです。
上中下とありますので、これから中に入ります。
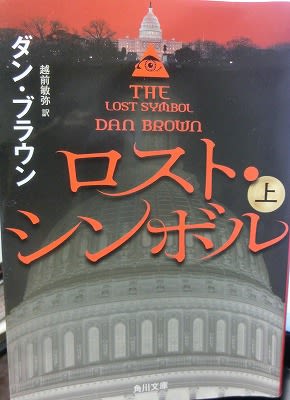
今、上巻が読み終わったところです。
ダン・ブラウンと言えば、「ダビンチコード」と「天使と悪魔」を読みましたが、この「ロスト・シンボル」は、その続きのような気がします。
なぜなら、主人公が同じで、たぶんダビンチコードと天使と悪魔での謎解きをやったことが、示されていると思うのですが、パリとローマでの謎解きという言い方で出てきました。
今度は、舞台がワシントンです。
世界最大の秘密結社「フリーメイソン」のことが出てきます。
上巻を読み終えても、全体がつかめません。
ダビンチコードの時と同じように、始めにびっくりする事件が起きます。
主人公ラングドンの知り合いの切断された手が出てくるのです。
果たして、その知り合いは、生きているのか死んでいるのか?
フリーメイソンの最高位で歴史学者のピーターソロモンの手なのです。
上中下とありますので、これから中に入ります。