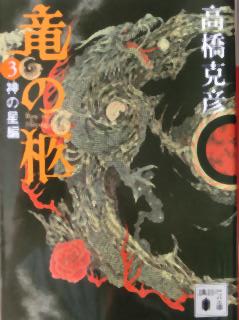又吉さんの「火花」を読みました。
漫才師の自分のことを書いていますね。先輩の漫才師を師匠と仰いで、その師匠のことを書いています。
その師匠という人は、私に言わせると、漫才を芸術にしてしまう人ですね。
芸術というのは、世間の常識からはみ出すことがあります。
現代芸術は、特に突拍子もないことをしでかします。
この師匠はその類です。
芸術の場合は、人がわかってくれようがくれまいが、構わないところがありますが、
漫才は、節度や品も必要でしょう。なぜなら、放送禁止という制約がありますから。
そして、大衆からの理解も必要です。
それがないと、漫才を主催する人から出演依頼が来ないでしょう。
いつだったか、カンニング武山が、舞台でうんこをしそうになったことがありました。
なりふり構わぬ行為です。今まで誰もやったことがないということについては、芸術です。
しかし、大衆に認められません。本当にやったら、そこで芸人生命が終わるかもしれません。
この火花の師匠は、その類のことをやりかねませんね。
最後は、胸を膨らませました。男がおっぱいを膨らませたら面白いだろうという発想です。
性転換の人がするなら理解できますが、普通の男がそれをやるということは、芸術としては面白いとしても、ユーモアを通り越していると思います。
着ぐるみを着るのとはわけが違います。大衆は引いてしまうでしょう。
他にも、いろいろ気になることがありますが、今日は、これだけ。
ただ、このように、自分の関わっている世界のことを小説にしたら、その職に就いている人でなければ書けないことが書けていいだろうなあと
思います。漫才師が小説を書いたということ、そして小説の世界では最高の賞と思われる賞を取ってしまうということ、それは凄いことだなと思いますが、
この小説は、単なる小説家には書けないものかもしれないと思いました。
漫才師の自分のことを書いていますね。先輩の漫才師を師匠と仰いで、その師匠のことを書いています。
その師匠という人は、私に言わせると、漫才を芸術にしてしまう人ですね。
芸術というのは、世間の常識からはみ出すことがあります。
現代芸術は、特に突拍子もないことをしでかします。
この師匠はその類です。
芸術の場合は、人がわかってくれようがくれまいが、構わないところがありますが、
漫才は、節度や品も必要でしょう。なぜなら、放送禁止という制約がありますから。
そして、大衆からの理解も必要です。
それがないと、漫才を主催する人から出演依頼が来ないでしょう。
いつだったか、カンニング武山が、舞台でうんこをしそうになったことがありました。
なりふり構わぬ行為です。今まで誰もやったことがないということについては、芸術です。
しかし、大衆に認められません。本当にやったら、そこで芸人生命が終わるかもしれません。
この火花の師匠は、その類のことをやりかねませんね。
最後は、胸を膨らませました。男がおっぱいを膨らませたら面白いだろうという発想です。
性転換の人がするなら理解できますが、普通の男がそれをやるということは、芸術としては面白いとしても、ユーモアを通り越していると思います。
着ぐるみを着るのとはわけが違います。大衆は引いてしまうでしょう。
他にも、いろいろ気になることがありますが、今日は、これだけ。
ただ、このように、自分の関わっている世界のことを小説にしたら、その職に就いている人でなければ書けないことが書けていいだろうなあと
思います。漫才師が小説を書いたということ、そして小説の世界では最高の賞と思われる賞を取ってしまうということ、それは凄いことだなと思いますが、
この小説は、単なる小説家には書けないものかもしれないと思いました。