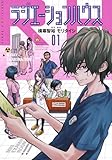医大生ブログ村、2016年8月20日注目記事ランキング。

オフ会の記事で溢れていて本当に幹事冥利につきます。自分も参加してみたい!という一般の医大生の方はこの機会に今すぐブログをはじめてみてくださいね(笑)。次回は2017年3月東京の方向で調整していきます。医大生・たきいです。
さて、本日ご紹介したいのがこちら。
 | 将棋の渡辺くん(1) (ワイドKC 週刊少年マガジン) |
| 伊奈 めぐみ | |
| 講談社 |
 | 将棋の渡辺くん(2) (週刊少年マガジンコミックス) |
| 伊奈めぐみ | |
| 講談社 |
ゆるい感じで爆笑モノ。母親に貸してあげたらケラケラ笑っておられましたが、曰く「このマンガのユルさは、うーはなちゃんのブログに通ずるものがある」とのことでした。ブログ村を読み漁り医大生ブログに精通するわが母です。
本作は将棋のトップ棋士、渡辺明の奥様によるマンガです。渡辺明はブロガー棋士ということで(渡辺明ブログ)昔から有名で、その影響でわたくしもブログサービスにgooブログを選びました。渡辺明が使っているくらいなら当分はgooブログ潰れないんじゃないかという気がして。
かつての渡辺明ブログには「嫁が書く。」というコーナーが不定期であって、奥様ご登場となるわけですがいい味だしていて非常に好きでした。今では有名になられて独自のブログを持たれていますが「嫁が書く。」の魅力たるや。
「医大生・たきいです。」というこのブログも卒業したら名前的に更新できなくなるので、いま密かに狙っているのが結婚して育休をとって子育てブログを始めるというもの。それが実現したら「嫁が書く。」コーナーも作ろう。結婚相手も見つかっていないのに妄想だけが広がります。笑
ちょうど今宮城県の実家にいるので、渡辺明と一緒に撮った写真があったような気がしたので探してみました。

渡辺明(左)と中学生・たきい(右)
痩せてんな、俺。
(昔の写真見始めたらキリがなくなった人(笑))