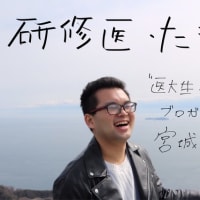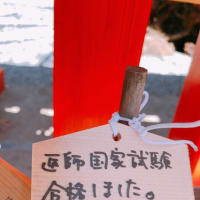朝から運動頑張ると午後の眠気がひどいです。医大生・たきいです。
社会科見学もかねてのサイクリングを7月の課題にしようとしている。意外にも大学のまわりには史跡が多い。今日は金次郎像でお馴染みの二宮尊徳ゆかりの場所へ。

高校生のときに日本史を選択したくらい日本史が好きなので、歴史の類には興味がある。二宮尊徳は180cmオーバーの大男で、70過ぎまでご存命だったらしい。パワフルな人間だ。勉学を好み、夜も欠かさず書物を読み耽っていたという。火をともすのがもったいないと怒られるほどで、勉学のために自分でなたね油を買って明かりをとっていたというから驚きだ。恵まれた時代に生を授かりながらも怠惰な自分が恥ずかしい。
廃れた農村の復興が、二宮尊徳青年期の一番の課題であったらしい。天保の大飢饉を予知して救ったエピソードは初めて聞いたが驚いた。しかしそうした功績も一朝一夕に築かれたものではなく、毎日の生活に根ざしているのではないかと筆者は考えた。
尊徳の一日の生活は午前4時に始まる。試験前にその時間に寝ることなら筆者もよくあるが、それは起きる時間なのだ。それから「廻村」するのだという。村を歩き回って村人たちに声をかけていたらしい。それも一日中。これに地域医療のヒントが隠されているのではないか。
二宮尊徳はちょうど天保の改革の水野忠邦と同時代を生きた。薪水給与令が出たころには幕臣として仕えたらしいが、中央での仕事を好まなかったという話もあるらしい。地域に出たかったのだという。現代の医学生に例えるならば、都内有名病院でスーパー外科医を目指すというよりも、地域医療をやってみたい派ともいえようか。
二宮尊徳が復興した村々も、もともとそこの出身というわけではなかったらしい。ところが、その村に受容され、年貢の収入も増加し、人口も増加し、住みよい村へと変わっていったのだという。その秘訣が「廻村」に違いない。役人としてではなく、医者としてでもなく、その地域の住民のひとりとなることでそのコミュニティに溶け込むことができる。今ではよく聞く話だが、尊徳先生はすべてお見通しだったに違いない。
こんな話を資料館のおじさんにつかまって
(地元でもサイクリングで史跡めぐりしてみたくなった人(笑))
↓今日も一発、よろしく頼む↓
にほんブログ村