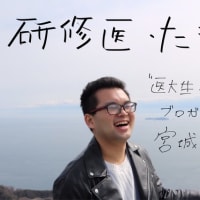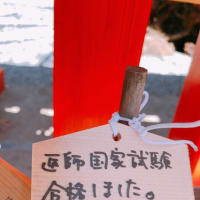二日連続のバイトはややつらいところでございます。医大生•たきいです。
さて、今日の学校はチュートリアルとか大学によってはPBLと言われるらしいもの。受動的に講義を聞く普段とは異なり、いわば机上のお医者さんごっこで、平たく言えば病気当てゲームである。班での話し合いが求められる。普段の退屈な講義よりは楽しい。
身体の問題を解決するのが医師の役割なのだという。盤上の問題を解決する職業もある。それを、棋士という。医師と棋士。なんだか似ている部分もある気がする。筆者は将棋しか指せないので、ここでは話を将棋棋士に限定しよう。
「棋は対話なり」という言葉がある。将棋の指し手を選ぶ際には、相手の指し手をよく見るべきで、さらには相手との呼吸が大事だという教えだ。将棋は達人の境地になると、将棋を指すのがあたかも会話をしているような感覚になるのである。独り言のような将棋を指している筆者はまだ修行がたらぬ。独りよがりではいけないわけだ。医者もこの格言から学ぶべきことがあるはずで、問診の際にこのことを気に留めるべきだ。今日のチュートリアルでチューターの先生から「解釈モデル」という言葉を教わったが、まさしくそれである。相手との考えにおける差異を小さくする必要がある。それには会話や対話が重要だ。
将棋の駒組には、王将の守りが弱いとか、攻めの陣形の理想型を模索する考えが序盤では特に重要である。駒の配置を大局観に置換し、プロブレムをあげるわけである。医者も同じく、患者から病歴聴取した際に聞いた言葉を医学概念に置換し、プロブレムをあげていくわけだ。そのプロブレムリストを説明できる疾患は何かと、疾患の「知識」から類推し、診断は下される。棋士にも「疾患の知識」に相当するものをもっていて、それは定跡と呼ばれる。「こうなればこう指せ」という教えのことだ。因みに「定跡」とは将棋用語であり、「定石」だと囲碁用語になる。
普段の講義は臓器別での系統講義だ。臓器別というのは、将棋で言えば戦型別である。普段は退屈な講義も、定跡の勉強なのだと言われるとまだ少しはやる気がでる。藤井猛という天才的なプロ棋士があるが、「定跡を身につけるのは、初心者がある程度まで上位者と互角に戦うことができるためにあるものだ」というようなことを発言している。初心者こそ定跡を学べという意味か。基本が大事というわけだ。医者も勉強することで、初期研修医もベテラン医師も同じところで仕事ができるわけである。定跡の勉強と言われると、積極的に勉強しようかという気にはなるから不思議なものだ。
医師と棋士を比較してみたら、将棋好きの自分としては医師の仕事の中身が大局的に理解できた。医師と棋士には言葉の響きだけではなく似た部分がある。さらには確信した。全ての道は将棋に通ずるのだ。日本国民ならすべからく将棋を学ぶべきだと信じてやまない。
(自分にはプロ棋士になれるほどの頭脳を持ち合わせていないと小学生のときに気づいたのが人生ではじめての挫折だった人(笑))
↓今日も一発、よろしく頼む↓