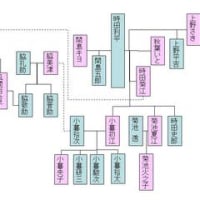すべてのリンゴの木で病気が発生、700本あるリンゴの木が病気でやられた。害虫も来る、害虫とはリンゴの木にとっての害虫であり、害虫を食べる虫が益虫、益虫は害虫に少し遅れてやってくるそうだ。そして害虫も益虫もそれぞれが生き残るようにお互いを調整するかのように数が一定になると言う。無農薬にして8年目、始めて一本の木に7つの花が咲いて小さな2つのリンゴがなった。次の年にはすべての木に花が咲いた、この8年間、近所からは害虫の発生源と言われ、「かまど消し」とののしられ、稼ぎがないので農家なのに食うものにも困り、子供たちの給食費にも事欠いた。地震は出稼ぎに出て働く日々を送った。それでも無農薬・無肥料を諦めなかった。
木村さんは理科系人間だ、観察、実験、機械があれば分解、これが成功の土台になっている。害虫はどのようにしてどこに卵を産むのか、卵はどのように孵化するのか、リンゴは時間がたつとどのように腐敗するのか、無農薬リンゴの腐敗はどのようになるのか、すべて実験して仮説を証明している。
機械が大好きなのに、大型の撒布機を使わず、リンゴの根を守るために手で撒布する手間を惜しまない、根っからの農業従事者、つまり百姓である。百姓とは百の仕事があるという、そのことが根っから好きなのだ。リンゴの木と話をする、人は気が違ったのかと思ったと言うが、木村さんは本気だ。リンゴは育てるのではなく、リンゴがなるのを手伝っているのだという。土と木と太陽の力がなければ野菜も果物もできない、人間がしていることはその手伝いをさせてもらっていて、果実を頂戴しているだけ。米や野菜の自然栽培は難しくないという。リンゴが難しいのは栽培の歴史の中で農薬に頼りすぎてきたためだという。
福岡伸一さんの『世界は分けてもわからない』で書かれていたことと同じことを木村さんも行っている。科学は小さな分野にわかれて専門的な研究を進めているが、自分は自然全部を相手にしているので専門分野などはない。木村さんが自殺をしようと山には入ってみたドングリの木は自然の中で土や虫、他の雑草とともにたくましく生きていた。これが木村さんの気付きだったのだ。リンゴの木も木が持つ力と自然があれば立派に生きていけるのだと。リンゴの木の下に生えている雑草を刈り取ることは必要なことと考えていたが、それを止めたらリンゴの木が元気になった。雑草があればミミズが増えて、暑い夏の日にも草の下の温度は20度、裸の土の温度は30度にもなり、リンゴの木を傷めているのだという。人間が自分の理解だけで農業をするからうまくいかない、人間が自然を壊しているのだ。
カロリーベースでの日本の食糧自給率は4割だという統計データがあるが、出荷金額ベースでは65%であり、世界で5位だという本があった。日本の農業も木村さんのような観察と実験、自然の力を利用した農業、そして地産地消の精神があれば状況はもっと変わるのではないか。金儲けのための農業ではなく、人間が人間らしく自然と共生できる生き方、木村さんが言いたいのはそう言うことではないか。
リンゴが教えてくれたこと (日経プレミアシリーズ 46)