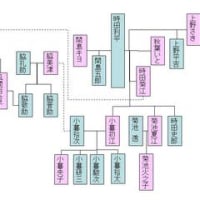著者の加藤は満州事変の特徴を次のようにまとめる。
1. 相手国の指導者不在を衝いておこされた。
2. 政治関与を禁止された軍人により主導された。
3. 国際法への抵触を自覚しつつ、しかし国際的非難を避けるよう計画された。
4. 満蒙の概念を絶えず拡大させた。
1. 当時、中国は蒋介石、張学良、共産党、孫文の後継者などが勢力を争い国としての中央政府が定かではない状態であった。しかし一応蒋介石は国民政府トップであり中国を代表していた。その蒋介石の首都南京不在のタイミングを衝いたのである。
2. 当時全国至る所で開かれていた「時局大講演会」では軍人が窮余の農民の暮らしに触れ解決策として満蒙の沃野を頂こうではないか、これで農民の皆さんも五反地主から10町歩の旦那衆になれる、と説いていた。有名な陸パン(陸軍パンフレット)もこのシナリオだ。もちろん満州でのきっかけそのものは関東軍が引き起こした。
3. 幣原喜重郎は英米との摩擦を避ける努力をしていた。国連規約、九カ国条約、不戦条約に抵触しないような解釈を探っていたとも言える。それが張学良はその悪政により満州民衆の支持を失った、という理屈である。結果はリットン調査団による報告書を不満として国際連盟脱退にいたる。天皇も外務省も脱退までは考えていなかったのに、熱河省侵攻が決定的な引き金になってしまったこと、当時意識していた日本人は少なかった。
4. 満州と満蒙は違う。英語ではManchuria、満蒙というと当然ソ連との摩擦が生じる。東部内蒙古と呼ぶ熱河省も含む広大な地域へと拡大していった。
外務省の官僚たちの力のなさもあったと思うが、当時の陸軍のこうした勢いは陸軍自身でさえも持てあましていたことも伺える。政策決定が若手の課長クラスで決められ、首脳たちはそれを追認する、というかたちでどんどんことが進んでいったからである。
この本にはあまり現れないが、昭和16年に太平洋戦争が開戦するまで、さまざまな出来事の節目に現れる言葉統帥権、上記のような陸軍の欲望は「統帥権」ということばで守られたと考えられる。政府も、そして統帥権保持者であるはずの天皇自身さえもが関与できない力学が統帥権には働いていた。関東軍の暴走を支えたのは、国際世界への無知、自分を知らない無知、果てしない欲望、そして明治憲法の欠陥であった。
満州事変から日中戦争へ―シリーズ日本近現代史〈5〉 (岩波新書)