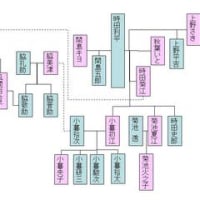最初の章がその漢語の解説である。漢語とは字訓ではなく字音で読まれる語だそうだ。これがどうも分かりにくい説明なのだ。訓読みなのか音読みなのか、考えたことがあまりない。分かりにくい例として「絵画」「会議」と「絵」「会釈」が挙げられている。「カイ」は漢音で字訓、「エ」は呉音で字音だそうである。家にかかわる言葉で漢語は廊下、風呂、便所、天井、二階、椅子、箪笥、座布団、障子、音訓組み合わせが座敷、客間、台所、本棚、建具、家賃、和語は押入れ、と言われればそうかなとも思う。
この「重箱読み」「湯桶読み」などの音訓マゼコゼは意外に多い。「手」がつく言葉には手金、手酌、手職、手数、手製、手代、手帳、手錠、手配、手本、手練手管、などたくさんある。さらに「場」の付く語では場所、場面、役場、宿場、工場、飯場、修羅場、鉄火場、停車場、現場、相場、帳場、職場、賭場、馬場、温泉場、愁嘆場、などなどいくらでも出てくる。これらも時代を経ると変わってくる。昭和の戦前は運動場(ば)が、昭和後期には運動場(じょう)になり、いまではグランドとなっている。
中国では1979年の改革開放路線以来、多くの外来語が入ってきたという。その中でも日本からの外来語は同じ漢字を使っているので、中国でも外来語とは知らずに使われていたり、少し意味が違って使われているものも多いらしい。「登校」中国では小学1年生の第一日、「写真」とはエロ写真のこと。空巣は年寄りだけの家、同じ意味でも使われているのが「少子化」、上下水道とは別に「中水」とは飲料にはならないが洗浄などには使える水。中古車は同じ意味。物流、職場、OL、人脈、健康、積極など。
ところで、日本語の「的」は英語の"tic"を音訳したものだということ、本当だろうか。合理的、科学的、積極的など。「中」は英語の現在進行形で、工事中、授業中、故障中など。「点」はポイントから、問題点、到達点、要点、弱点など。「性」を名詞の後ろにつけると、生産性、安全性、公共性などとなる。面、力、界、式など色々あるようだ。これらを明治以降日本に留学していた中国人学生が本国に持ち帰って使い始めるのが最初だそうだ。
大変情報量の多い本である。読んでいて消化しきれないくらいだが、ためになるだろうと思って読んでいると寝てしまっていることが多い。というのも、私は横になってベッドで寝る前に本を読むことが多い。その際に学生時代から愛用しているものに「読書機」がある。もう40年以上もお世話になっているということになる。学生時代は、読みだしたら面白くてやめられず、手がだるくなるので買ったものだが、その内に、冬には布団から手を出さずに読めるので、寒い冬にもいつまでも本が読めることに気がついた。
時を経て、今では冬でも部屋が暖かくなり、年も取って読み始めてもすぐ寝てしまうことが多くなった。この本はその典型例で、面白いと思うのだが、すぐ寝てしまう。おかげで、読み終わるのに時間がかかってしまった。つまり読んだ最初の方は皆目覚えていない。忘れないためにこのような読書録を書いているのだが、書いておこうと思うすでにその時点で忘れているとは、なんということであろう。年は取りたくないものだ。