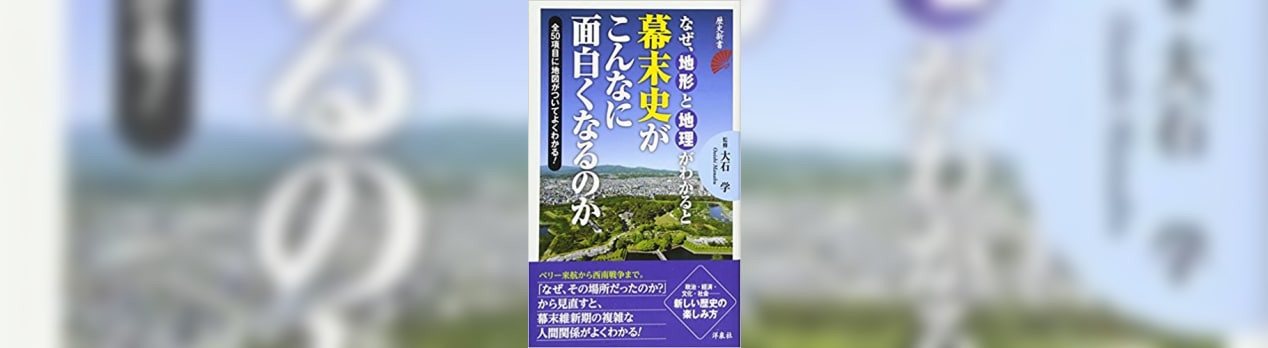幕末の50のエピソードを地図と地形図とともに紹介した一冊。
ペリーが江戸湾に深く侵入できなかったのは、当時の万国公法では領海沿海部三海里(5.5Km)と決まれていたからで、浦賀奉行所与力の中島三郎助が「内海への立ち入りを認めない」と主張したから。
築地が海外から来た人たちへの居留地となったのは、明暦の大火災で本堂を消失した本願寺の移転先として造営された土地に未利用地が多くあり、海軍軍艦操練所もあったが、これも焼失。その跡地にできたのが築地ホテル。教会やミッション系の学校も多く集まった。立教や青山学院の発祥の地でもある。
淡路島が兵庫県に編入されたのは、徳島藩筆頭家老稲田氏が尊皇攘夷派、本家蜂須賀氏が佐幕派だったためいざこざを起こし、徳島藩からの分離を主張。結果として廃藩置県では兵庫県側となる。
富岡に製糸場ができたのは、初代場長尾高惇忠が候補地を選定するに当たり、上州での養蚕生産高、高崎、吉井での石炭埋蔵、中山道の脇往還としての交通の便、地元地主による理解からの土地確保の容易性があった。
多摩地方から多くの新選組員が輩出したのは、もともと八王子千人同心街道沿いであり、幕府への忠誠心が強く、千人同心の子孫であることのプライドを持っている人物が多かったから。近藤勇のスポンサーとなった名主小島鹿之助や佐藤彦五郎、組員の中核となる土方歳三、井上源三郎、沖田総司、山南敬助、原田左之助、永倉新八などが集結した。
印象に残ったのが、備中松山藩の山田方谷による藩政改革成功の秘訣。それまで、江戸時代に重宝された製鉄による鉄製品の流通が出雲往還、大阪経由だったのを高梁川、玉島港経由にしたため、ナニワ商人による中間マージンを削減できた。7年で借金10万両を返済し、さらに10万両の貯蓄をした、これなどは地図を見れば一目瞭然、記憶にも残ります。それにしてもそれまではナニワ商人、そんなに儲けていた、というお話。
地図を見ながら記事を読むと、視覚記憶が同時に入力されるので記憶に残りやすいからだと良く分かった。なるほど、地図と地形図を見ながらの読書は良い。