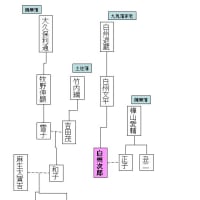初老は40歳から始まると考えてください。つまり老いという非常に緩やかな坂を下りはじめること、これが誰にでもおこる老化現象で、その坂の先では体や精神が今の皆さんのように思うようにはいかず、場合によってはいうことをきかなくなるという状況になるのです。
自分も将来は介護の対象になるということです。「安楽病棟」の若い看護士は、介護経験を通して数十年前と現代の介護を取り巻く状況の違いについて次のように分析をします。
1.昔は頭脳と体がほぼ同時に老衰を迎えた。ここ数十年で医療技術が進歩し、寿命が延びて体は長生きになったが頭脳はその体の長寿についてきていない。脳医療の進歩が重要である。
2.時代の変化が早くなり、親と子、孫の価値観が甚だしく違うようになってきたため2―3世代同居が難しくなってきている。昔は時の流れが緩やかであり、価値観の相違による世代間の相克も今ほどには顕在化していなかった。
3.上記2の結果として、世の中に沢山いる高齢者に若者が気を配らなくなってきている。同居する老人がいれば町で出会った高齢者に席を譲る、手を引いて交差点を渡るなどの行為や思いやりが自然に出てくるはず。
確かに、核家族化とか都市集中による住宅事情変化などという新聞記事に書かれていること以外にこうした側面があることに気づかされました。
もう一つは人間の尊厳問題です。介護が必要となる状態には誰でもがなるわけではありませんが、身体的な問題とともに精神面での問題が原因となるケースがあります。その一つがいわゆる認知症です。症例は本当に様々で、進行度合いや既往症、その方の性格、家族との関係などが組み合わさって対応には個別のケアが必要とされるのですが、多くの老人を同時に預かる施設としてはどうしても一様な対応にならざるを得ないのが現実です。「目は疑り深く、耳は信頼を呼ぶ」という認知症の例もこの本ではあげられています。目は良くて耳が悪い老人は同居人を疑う傾向があり、耳は良く聞こえて目が不自由な方は同居人を信頼する、というもの、ありがちな話です。自宅での介護の苦労も、教科書通りには行かないこと、またこうした個々の状況が突然変化して家族の手に余ってしまう、というところにあります。
しかし、こうした認知症といわれる老人にも人間としての尊厳が必要であり、実際に面倒を見ている家族の気持ちは大きく揺れ動きます。「安楽病棟」ではオランダにおける安楽死への対応の説明もあり、安楽死をオランダではLife terminating(生命終結行為)と表現、重篤認知症患者に適用するというもの。ここまで進んでしまって良いのかという問題提起であり、実際に介護をされている方には身を切られるような話だと思います。オランダのような割り切りが必要な時代が日本にも来るのか、それは行き過ぎなのか皆さんも考えてみてください。
安楽病棟 (新潮文庫)