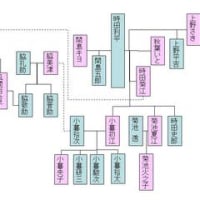今は「資本主義という名の幽霊が世界をさまよっている」という時代だと筆者は言う。アメリカや日本だけではなく、アラブやアジア、ヨーロッパなど国境を超えて資本主義は次の市場をもとめてさまよい歩く。市場は石油、食料、金融など様々だ。これまでもてはやされたアメリカ式のマーケティングやマネジメント、金融工学は本来利益が出るはずのないものに儲ける幻想を作り出し、サブプライムローンのような問題を作り出した、という天才的詐欺、問題はそのつけを国民の税金でまかなっているという点。
登山には下山がつきもの、インド哲学には人生にも学生期、家住期、林住期、遊行期の4つの時期がある、青春、朱夏、白秋、玄冬ということになる。いつまでも無限に成長する人生はないのであって、折り返し点に差し掛かったときそれを覚悟することが必要。徒然草では「死は前よりしもきたらず、かねて後ろより迫れり」、誰でも死ぬときには一人なのです。
日本人は和魂洋才といい、洋魂をもつことはできない。神仏習合は日本の誇るべき文化だと考えるべき。日本人は昔から山や森を敬い、あらゆるものに精霊を見るという山川草木悉有仏性は日本人の勝れた感覚である。欧米流の自然保護、ではなく、動物植物にはそれぞれ魂がやどり、人間も自然の一部であるという東洋的考えが重要なのではないか。禅宗でも浄土宗でも言われる「自他一如」、天寿には逆らえない。ブッダは80歳、法然も80歳、親鸞は90歳、蓮如は85歳まで行きた、当時の平均寿命から考えれば驚異的である。
痴呆老人を介護する家族は大変だが、沖縄では痴呆老人は悠々と穏やかに周りから尊敬されながら幸せに生きている、という。意識が薄れ動作が緩慢になることはマイナスではなく、周囲がそういうことを嫌悪するからトラブルになるのだと。「子供笑うな昨日の自分、年寄り笑うな明日の自分、成長と老化は一体である、ということ。
自分自身にも良く考えたい言葉であると同時に、こういう人間の覚悟、これからの日本を象徴するような著作でもある。
人間の覚悟 (新潮新書)