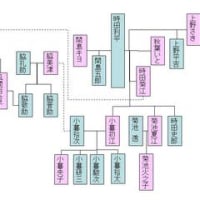当時の日本では一般外国人は開港地の10里以内の外国人遊歩地域しか行けなかったため、スイス外交使節団のエメェ・アンベールに随行、江戸市中撮影を行なった。その後も外交使節団に随行して富士吉田や箱根、京都、長崎も撮影、長州と四国艦隊との砲撃戦を現地に赴いて写真取材している。
その頃の写真は湿板写真で、撮影現場で硝子板で感光板を作り、感光板が薬品で濡れたまま撮影、その後、その場で現像もしなければならない、というシロモノであった。戦争の現場や、幕末には攘夷思想の武士による外国人殺害の危険があるなかでの撮影だったことを考えれば、よくこれだけの写真を撮影したものだと感心する。また、撮影機材は一人ではとても運搬できるものではなく、撮影自体も一人では無理だったという。おまけに動いている対象物は写らないため静止画を撮ることになる。つまり撮影対象に撮影されることを意識させ数秒間の静止を要請した上での撮影である。
しかしそうして撮影された日本の風景や人物の写真は日本について表面的に紹介するだけではない、長い滞在の中での撮影だったことが評価されて高く売れたという。
印象的な写真としてあげられるのは、イギリスの外交官リチャードソンが島津藩の大名行列に遭遇した時に下馬しなかったとして斬殺された「生麦事件」の現場である、当時の生麦の写真。現在の生麦からは想像もできないほどの田舎の一本道である。乗馬で散策していたイギリスの外交官が日本人の行列に出会ったとしても、のんびりと見物していてもなんの不思議もないようなのどかな風景である。
愛宕神社からみた江戸のパノラマ写真、どちらの方向も平屋建ての建築物しか見当たらず、高いのは浅草寺五重塔と火の見櫓だけである。江戸の町のどこからでも富士山が望めたというのもうなずける。
横浜は根岸の海岸を不動坂からみた写真、美しい根岸湾にいくつかの藁葺き屋根が並んでいる。今の港の見える丘公園や外人墓地の反対側となる場所だが、外国人達がこの辺りに住みたがった理由がわかるような美しさである。その根岸には外国人のための競馬場もあったとのことで、その写真もある。
鎌倉の鶴岡八幡宮の一の鳥居から見た若宮大路、今はない二の鳥居も見えてなかなかの写真である。大仏の写真では大仏の膝の上に座っている観光客もたくさんいて自由な感じである。寂れた感じがする江ノ島も良いが、清水の次郎長の生首写真は生々しい。
もう二度と戻ってこない「逝きし世の面影」である。