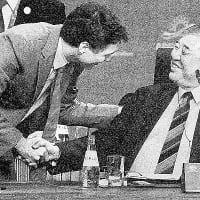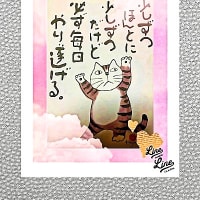現在、『北海道新聞』[釧路・根室]面に、<国立公園20年釧路湿原のカルテ>と題する連載記事が掲載されている。6月12日の第5回は、「都市開発診断〈上〉道路建設生物脅かす」という大見出しの記事に、地図と写真が添えられている。問題の道路は、釧路市街西部の鶴野から、釧路湿原国立公園の南端に沿って東へ進み、国道391号線を跨いで、国道44号線と国道272号線の分岐点に至る16.8キロである。
上の写真は、別保公園北側で行われている、釧路外環状道路の工事現場である。台地状の山間部を深く掘り下げ、道路の法面を、縦に凹凸のあるコンクリート板に、六尺間隔で横方向に崩落防止の金属杭を打ち、砕石で覆う工事が行われている。大雨による土砂崩れを防ぐ最新の工法なのだろう。道路工事が始まる前は、このあたり一帯は、ミズナラ・アオダモ・ヤチダモなどの広葉樹とトドマツとの自然混交林だったが、いまは、道路工事 による自然破壊で、無惨な姿を晒している。これが破壊でなくて何なのか。
による自然破壊で、無惨な姿を晒している。これが破壊でなくて何なのか。
記事によると、釧路開建では、「開通すれば、道東の基幹産業にも、国のためにも重要な役割を果たす道路」と、その必要性を強調している。しかし、工事関係者が、この道路の西側半分が、釧路湿原の生態系を破壊し、東側半分が、豊かな森林の生態系を破壊することを知らないわけがない。将来、北海道横断自動車道とつながって、どれほどの経済効果があるか。そして、どれほどのものが失われるか。環境省の果たした役割も含めて、釧路開建の主張をしっかりと記憶して検証しようではないか。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事