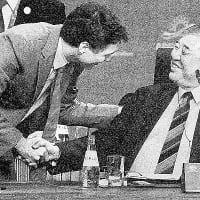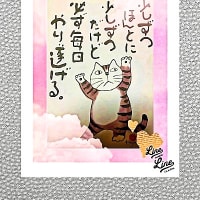平成21年5月までに、国民が刑事裁判に参加する裁判員制度がスタートするが、この制度には、不明な点や疑問に思う点が多々あるので、3月10日に釧路地方検察庁にパンフレットをもらいに行った。守衛から受け取るつもりだったのが、思いもかけず二階の企画調査課まで案内され、コーヒーまでごちそうになる羽目になった。
説明会の希望があれば、担当係が出向いて説明をするので、是非利用してほしい、といわれ、すっかりびびってしまった。ブログのネタにするなどと、本音が言える雰囲気ではない。パンフレットをもらって這々の体で引き上げた。
制度の仕組みは、なるほど図示されたとおりで、簡単に理解できるが、裁判員が参加する仕事の内容については、謳い文句が綺麗事過ぎるのではないかと思われる。3月4日付『北海道新聞』第28面〈第2社会〉に、新潟弁護士会が反対決議をしたことが報じられている。見出しに「全国に波及か」とあるが、それはないだろう。しかし、「重大な欠陥が多く、実施の強行は暴挙」という弁護士会の主張は、国民の多くが感じていることである。
最高裁では、審理期間は三日程度で、裁判員の負担は大きくないとPRしているが、そんなに簡単に考えてよいのか。裁判員が裁くのは、殺人などの重大犯罪に限定され、量刑には死刑も含まれる。裁判員の心理的負担が大きくないわけがない。実施については、拙速を避け、国民の意見を十分聞き入れるべきだろう。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事