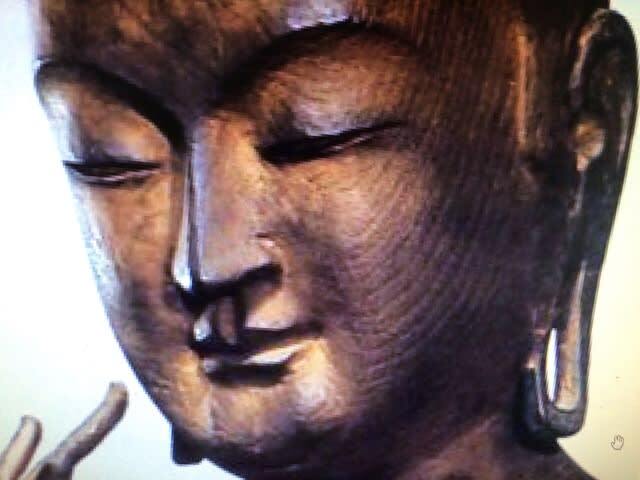勝者は 桃太郎であり 時の勢力であり 正義である
桃太郎伝説では 桃から生まれた桃太郎が
暴れまわる鬼を退治に 鬼が島へと鬼を退治に行くのが 昔話しの ストーリーですね
しかし 勝てば官軍 負ければ 賊であり 鬼なのです
現代の社会にも似ていますぞ
東條大将のことを この前も書いたが 東條大将は 負け戦の 責任者なので もののふの将として戦争敗北の責任をとって 悪者になって下さった
遺書でも 陛下や犠牲者に対して 申し訳ない事
その責任は ご自分 この大将にあることを 述べておられる
死んで償っても償いようもないとも申されております
しかし されど戦勝国が 戦勝国の裁判官が 敗戦国の責任者 大将を裁判で裁くことには 納得はしておられなかった
ワシが生まれたのが 昭和31年で 物心がついたのが昭和35年くらいだと思うが その時代 東條大将は
悪者扱い(鬼)であったと ワシはそう思っていました
子供時代とは言えども相済まないことだったと思います
もしも 桃太郎が 万が一にも鬼側に 敗北をきしていましたら
今の日本も 全く 変わった日本になっていたのかも 知れないですよね
吉備国には 元々 温羅うら(元々 吉備国におられた 渡来系豪族 製鉄技術を持った集団だとも思える)
・温羅は鬼にされてしまっている
そのもっと昔から 吉備国は 多分 朝鮮半島や 大陸との深く 交易も多い それらの人も住みついた(渡来人が多く住んだ 気候も瀬戸内気候で 水も豊富 金属も山から 採れた と 思う)が あったと
ワシは空想している
桃太郎の鬼退治は
西暦で言うと2~400年の辺りなのか?
-----どうかは 解からない
温羅(うら)は 朝鮮半島の戦いに敗れて
その昔から 渡来人の多く住む 瀬戸内の岡山に
大きな船団を組んで現れたのかも 知れません
百済の王子らしい…いや そうではなく新羅かも?
しかし 百済の王子ならば その時期 滅亡の時期とは矛盾するの????
ヤマト朝廷と吉備国の戦争 実際はあったのだろうか?
温羅(うら)鬼が 岡山 吉備の人々に 実は嫌われていないようにも 感じる所が あります
それと~ 日本での 鉄の製造の起源を 調べていくと どうも ワシの考えていた時代より まだ古い 2000年ほども 現在から 前の時代のようです
中国自動車道を走ると 『美作国建国1300年』と 大きな看板が目に付くの
今 それって やっているみたいですね
ヤマトによって 岡山北部も 支配下に置かれた という年代となるのでしょうかね
その 暫く前 数年なのよ うちの家に 神が現れたという時期 時代が ・・・そうなる
ワシ所の先祖が その時代に 住み着いたのか
それとも 朝廷のご支持で この地に来たのか これは
まったく読めないところ
これ以上は 多分 遡ることは 困難な事
古墳の作られた 時期を辿る くらいしか 思いつかない
しかし 運が良いというか 1300年も 家を遡れるなんて まれな事だと思い 幸せ者ですよね(ワシのこと)
歴史ロマンに ただいま バタ屋とうない とても凝っています 自分の出自を 見つけようとしていますのです
神社の歴史を 調べたらば かなり 解明されるのが
日本の歴史のような気がしますが
どこの神社も 自分の都合で 語られますので 歴史は かなり 人の意思で捏造も可能な 感じもうけますが
全てが嘘だとは言えない
桃太郎伝説でも 単純に ああ そうなんだ と 納得をしてしまうと・・・
敗れた側から 見れば また 違った見方 歴史もある の だろうと思うの です
1300年前から 2000年前の辺りの時代で どのような戦いや 話し合いが 部族間で なされたのだろうか?
その辺りでは 大陸から どのような経路で 文化 文明が この日本にもたらされたのか 興味深々 東内まこと
吉備国は とにかく ヤマトからも
かなり警戒された実力のある国家だった
というのは 間違いない
ヤマト朝廷に 嫁を何度も 出していることも史実のようですし
東は兵庫県加古川から西方
西は東広島辺りまでの勢力圏
東西には300km 程にも なろうという巨大な国家だった
四国の一部も その勢力は あったと思う
そして 舟で移動するにも 良い場所で 外洋の四国沖合いを航海するよりも 瀬戸内に沿って
関門から 舟で移動するほうが 完全に安全だと思う
歴史研究の方で 瀬戸内は 危険度が高かった と書かれておられる方もいますが どう考えても 瀬戸内海が完全に安全航海だろう
水深が 時代によっては 浅かった という 地球の気候変動のことを 書いておられる学者さんも いてましたが 外洋より 瀬戸内は安全航行は可能だと思う
しかし 岩に座礁するようなことはあっただろう
また 瀬戸内の島々には 海賊のような集団も 住みついたとも空想できる
百済(くだら)滅亡の 前後も 多くの 大陸からの人々が 日本を目指して 渡来してきたと空想している
だってね 対馬から 朝鮮半島の先っぽまでは
48kmなのよ 実は かなりの行き来があったと 考えてもよい
また対馬には 神社がとても多いの 神社が多いと言う事は
その昔から 対馬は日本であった 朝鮮半島の一部にまでも 日本人は 進出していたと考えています
一時は 遼東半島にも いったかも 知れない
今の 大連付近だね
1500年前後? 前の時代だよ
元寇(げんこう)の時代は まだ ずっと その後です
西暦1274年だから
740年ほど 今からは 過去のことや
ワシのやってるのは
1300年から2000年前の時代の空想ですねん
お宮の勤めを 100代もやっている家もあるので 一代が15年としても 1500年以上?続く 神主もおられると思う
それは 出雲系になるのかも知れないね
出雲の国は たぶん かなり 昔からある
鳥取県の遺跡でさ 古い時代の刀剣が 数100本も まとまって出土してる のんです
これって2000年近く それ以上も前の年代になるのか? もっと調べて見ないと ワシは まだよく知らない
ここで 鉄製の刀剣が出てくるのんじゃ
若狭湾 福井県辺りまでも 出雲の力は あったと考えてるんや ワシ
天橋立 あの辺りの 港を見ていると なんか ここにも 渡来人が 舟できたら 住みつきたい と思えるような場所じゃないか と 空想します
ワシ あの湾内 数年前に クルーズのボートに乗せてもらって一周したんや あそこへもならば ワシでも 住みつきたい と考えますね
そこにも お宮さんがあったが 御参りしたが その頃は今よりも 完全に 興味が薄かったので 神社の名前も由緒も調べず でしたが この辺りの探索も また やってみたいと思っている
そうじゃ
温羅伝説を 深く 掘り下げていくと
西暦4世紀頃より 西暦7世紀頃の 朝鮮半島には
地図の左に 百済でしょ
その右に新羅 って国
その両国の 真中 南 端っこに 小さな伽耶国(かや)
って国もあったようでして
その3カ国の 上に 高句麗があった とされています
新羅(しらぎ)から 出雲の国へ まず 先に渡来人が来たのかも 知れませんね
新羅は 660年に百済を滅ぼし
その後 668年には 高句麗を
当時の中国(唐)と組んで戦争し 滅ぼした
そういうことで 600年台の後半には かなり大陸から 日本へ人が流入したと推測しても まったく 自然である
じゃあ (温羅うら)
は どちらの国の人 なのか?
新羅の羅のようにも 思える
鬼が島の鬼の立場の人 ですよ
今年は 宝塚歌劇が 100周年で桃太郎伝説だ そうだ
ワシは歌劇には興味は全くないのですが 桃太郎となると おもろい ですね どのようなストーリーなのでしょう
桃太郎を 深く 考えると 日本の歴史 の矛盾 そのまんま なので 作者は かなり歴史を調べねば 書けないと 思いますね
吉備国には 吉備津神社と 吉備津彦神社が すぐ 近くに 建っている のは 何故 なのか とか 考えると
ヤマト朝廷と 吉備国の 関係 そして 出雲も からんできて すさまじく 難しいのんです
美作の ワシの里の付近は 2000年前の 古墳も 村落の跡も 出土していたましたり その当時から 稲作をし
鍛冶屋も あったような形跡があちこちで でている
鍛冶屋というのは 鉄を熱して カマを作ったり 矛や刀剣をつくたり
鐘のような音のでるようなモノも 作れたんだ
その当時としては 最新兵器を持っていたと考えても間違っていないと思う
近畿地方よりも 少し 時期が 早いか 同時期かも 知れないですよ
この前 交野市 と書いたのは ここも多分 鉄 鍛冶屋 鉄鉱石 かも 知れない
大阪府交野市 古代 鍛冶 などと 書けば 交野市の歴史に興味の方にも ヒットするかも 知れないですね このブログ
ワシの古代調べは 始まったばかりなので 間違ったことも 多く書いているかも 知れませんが
ワシは行動が早いので 調べていく速度も 速いとは思います
そんでな ワシは 神のから 何か 先祖がお告げを受けている血が流れているので 勘が強いのが取り得じゃ
日々は 相場の話しばっかり の バタ屋とうない やけれどもね 正月やから こんな 古代の話も 面白いよ
神宿村 大中山
とうない まこと
吉備国とは なんぜよ
以下は 昨年からのメモ書き メモ↓
09年ISO14001を認証取得しました。
09年8月末には
09年8月末には
大阪税関より 自社保有地に一般貨物保税蔵置場許可が許可され バラのスクラップ貨物を自社ヤードで通関可能な保税倉庫の許可も取得しましたので
チャーターした船に 自社保税区から直接の積み込みが可能な 全国的にも珍しいリサイクルセンターとなっております
(中国向け輸出ライセンス有)
関西一円片道300Km半径ぐらいが収集範囲です
廃棄物処理(大阪市と高槻市に2つの産業廃棄物中間処理工場)の
廃棄物処理(大阪市と高槻市に2つの産業廃棄物中間処理工場)の
マニフェスト発行も可能な中間処理業者です。
0120 535319(ゴミゴミ行く) が 屑 買取の連絡先です 072-678-1112 ㈱トーナイ名古屋周辺から関西一円可能
■『陰陽五行と日本の民俗』からのなかで,『鉄山秘書要約』を次のように解析している。
「七月は申(サル)月であるから, 金屋子神は申月申刻に天降りされた。申は金気の始め, また七日の七も七赤金気で, 金気の象徴。次ぎに西方に向かって白鷺に乗って行かれたというが, 西・白・鳥はいずれも金気である。このように時間・空間・色彩・十二支において,金気ずくめの金屋子神は,「土生金」の理で,土が二つも重なっている桂の木に止まり,最上の呪物土気である死体,それも生類の霊長としての人間の死骸を最も好まれる。それらすべて一部の隙もない五行の理の応用であり,反映であって,昔の日本人が如何に五行の呪術に凝っていたか,歴然たるものがある。同時に裏を返せば,そこに見られるのは自らの仕事に対するあふれるばかりの忠誠心であって,後代の私どもは深く感動させられるのである。」
このことからも,
①楢原邑に始めて「中山大神」として示現した神は,午(ウマ)の最盛期を選んで出現したことから,この神が「火」を中心とした神格と認識されたとして間違いないであろう。②一体どのような火であるか,火の種類については今のところ明確ではない。
しかし, この神が
東内(藤内)の矛殿・五座の鉾石など鉾を属性としていることからも,鉾などの武器製造に不可欠な金属溶鉱・鍛治の火(炉)を象徴していた可能性は高いと考えられる。
■ 東内(藤内の祖)に神が示現したのが慶雲三年,丙午の年の五月上旬(二の午の日)とある。二の午の日がわたしには解らない。当時は月を上・中・下旬とせず,上・下旬に二分していたものなら「二番目の午日」はおさまる。しかし,旬を原則どおり十日単位とした場合には,十二支を一巡とする午日が二度現れるはずがないのだが。この点については,是非どなたかにご教示をお願いしたい。
とにかく,この年の干支(カンシ)は丙午であって, 日時ははっきりしないが,日の方は干支の干が不明なるも支は明確に「第二の午日」と言う。ちなみに,旧暦の五月は夏の盛りの「午」月でもある。すると, この神は午の年・午の月・午の日に,白馬(午)に乗って現われたことになる。ここまで午が揃うと, 出現時間も当然「午の刻」の可能性も高いのではないか。午の刻は真昼-正午である。こういった干支にぴったり合わせた示現伝承や,五座の鉾石伝承からも,「陰陽五行思想」の濃密な土壌のなかから,この神が誕生したことは間違いない。
鉾石は五個あったと考えられ,鉾の大小は置くとして中央と東西南北の四方に,鉾が立てられたものであろう
とにかく,この年の干支(カンシ)は丙午であって, 日時ははっきりしないが,日の方は干支の干が不明なるも支は明確に「第二の午日」と言う。ちなみに,旧暦の五月は夏の盛りの「午」月でもある。すると, この神は午の年・午の月・午の日に,白馬(午)に乗って現われたことになる。ここまで午が揃うと, 出現時間も当然「午の刻」の可能性も高いのではないか。午の刻は真昼-正午である。こういった干支にぴったり合わせた示現伝承や,五座の鉾石伝承からも,「陰陽五行思想」の濃密な土壌のなかから,この神が誕生したことは間違いない。
鉾石は五個あったと考えられ,鉾の大小は置くとして中央と東西南北の四方に,鉾が立てられたものであろう
■和銅(日本の時代)
和銅(わどう)は、日本の元号のひとつで慶雲の前。708年から715年までの期間を指す。この時代の天皇は女帝元明天皇である。
· 和銅8年9月、霊亀に改元。
続日本紀 卷四には、武蔵国 秩父郡(現在の埼玉県 秩父市黒谷)から、和銅(ニギアカガネ)と呼ばれる銅塊が発見され朝廷に献上されたことを祝い、年号が慶雲から和銅に改められたと記されている。
和銅期
和銅元年2月 - 平城の地に新都造営の詔がでる。10月、伊勢神宮に平城宮造営を告げる。
☆ メモ 美作市 平福の遺跡 神宿の東500mの山 その裏がイチノタワ
古事記を読む 美作にはユダヤ人が居たのでしょうか
というブログを一部コピー 司馬遼太郎さんとも親しい方のようなの・・
「吉備古代史の未知を解く」は、間壁忠彦・間壁葭子氏の著書の名前です。両者は倉敷考古館学芸員であり、館長も勤められています地元の研究者であるだけに、内容は素晴らしいものです。外に、間壁忠彦の「石棺から古墳時代を考える」の著書があり、吉備の歴史だけではなく、石棺を通じて、全国の勢力分布を述べておられます。
すべてを紹介するわけにいきませんので、その一部を紹介しますと、「吉備古代史の未知を解く」の162ページに、「久米の子の里」と題して、奇妙な陶棺のことが書かれています。陶器製の棺おけのことです。九州では、甕を二つ合わせた形の甕棺が有名ですが、ここの陶棺は、土師質亀甲形と須恵質および切り妻家形の二種類とその他分類不明の陶棺に分かれます。全国に分布はしているらしいですが、その7~8割は岡山県に分布し、其の又、7割は美作とよばれた地名で発見されています。
「何か特別な生産にたずさわる集団と、関係がある棺ではないか、と見られている面が多い」と微妙な表現をされ、須恵器窯跡と関係、土師質陶棺の場合は、土師部との関係、鉄の生産が盛んであった土地柄、鉄生産者との関係、屯倉との関係などを挙げておられます。当然、他の人も精力的に研究し、成果を発表されておられるらしく、それらに負けられない気持ちがあったのではないでしょうか? 「久米の子の里」のページに43ページも費やされています。この項のはじめのところで、著者は「陶棺の存在に対する結論など、こうした本の上で簡単にでるものでないことを意味していることでもあるだろう」と慎重に、駄目押しをしておいて論をすすめておられます。
それに対して、私は簡単に、この陶棺はユダヤ人の棺おけで、しかもユダヤ人は絹を東郷湖まで運んでいるのだと前に述べ、それどころか、その絹はローマまで運ばれてい
るのだと書きました。この凄腕のプロをくつがえすことはとても、私には無理ですが、著者は、ここで発掘された陶棺の時代を次のように述べておられます。「この地域の後期古墳は、六世紀中頃に築造が始まり、七世紀末まで使用されており、時には七世紀中頃以降でも築造され、中には八世紀の火葬骨を追葬しているものもある」
私は、この部分が良くないのではないかと思っています。最近、岡山県で鉄を製造した遺跡が発掘されていますが、私はどれも、200年ぐらい遡らなければならないのではないかと思っています。そうしますと、古事記に書かれているスサノオが襲撃した製鉄所に一致します。(No62~65) 陶棺が発掘されたときに、なにを基準にして、使われた年代を決めるのでしょうか?
普通に考えても少し、おかしいと考えられませんか? 「六世紀中頃に築造が始まり、七世紀末まで使用されており」と書いておられますが、これですと、二代しか生活していなかったことになります。仮に北海道のように、明治時代に入植されたとします。帯広の原野では、一代が暮らすだけでも厳しかったそうですが、私の友人は、三代目で、200頭を超える乳牛を育てています。美作は三代ぐらいで逃げ出さなくてはならないような所とは思えません。それどころかずっと、子孫の方は現在も生活しておられると思います。
この陶棺は大きなもので、陶棺を作る技術がなかったのではないでしょうか? 陶棺は、6~7世紀と固定しているために、また、歴史に詳しいために、ユダヤなどの発想はとんでもないものだと思います。
岡山県英田郡美作町平福から発掘された切妻形の陶棺には、寒羊と思われる尻尾の太い二匹の羊を連れて羊の顎ひげを触っている人物が描かれているそうです。これは日本にはいなかった動物と思われます。子羊は聖書にでてくる神の使いだそうです。又、寒羊は、イスラエルが原産でユダヤと関係がありそうです。が知識として知っていたので、描いたのかもしれません。よって、描いた人は異国の人であったと考えていいと思います。…….
「吉備古代史の未知を解く」は、間壁忠彦・間壁葭子氏の著書の名前です。両者は倉敷考古館学芸員であり、館長も勤められています地元の研究者であるだけに、内容は素晴らしいものです。外に、間壁忠彦の「石棺から古墳時代を考える」の著書があり、吉備の歴史だけではなく、石棺を通じて、全国の勢力分布を述べておられます。
すべてを紹介するわけにいきませんので、その一部を紹介しますと、「吉備古代史の未知を解く」の162ページに、「久米の子の里」と題して、奇妙な陶棺のことが書かれています。陶器製の棺おけのことです。九州では、甕を二つ合わせた形の甕棺が有名ですが、ここの陶棺は、土師質亀甲形と須恵質および切り妻家形の二種類とその他分類不明の陶棺に分かれます。全国に分布はしているらしいですが、その7~8割は岡山県に分布し、其の又、7割は美作とよばれた地名で発見されています。
「何か特別な生産にたずさわる集団と、関係がある棺ではないか、と見られている面が多い」と微妙な表現をされ、須恵器窯跡と関係、土師質陶棺の場合は、土師部との関係、鉄の生産が盛んであった土地柄、鉄生産者との関係、屯倉との関係などを挙げておられます。当然、他の人も精力的に研究し、成果を発表されておられるらしく、それらに負けられない気持ちがあったのではないでしょうか? 「久米の子の里」のページに43ページも費やされています。この項のはじめのところで、著者は「陶棺の存在に対する結論など、こうした本の上で簡単にでるものでないことを意味していることでもあるだろう」と慎重に、駄目押しをしておいて論をすすめておられます。
それに対して、私は簡単に、この陶棺はユダヤ人の棺おけで、しかもユダヤ人は絹を東郷湖まで運んでいるのだと前に述べ、それどころか、その絹はローマまで運ばれてい
るのだと書きました。この凄腕のプロをくつがえすことはとても、私には無理ですが、著者は、ここで発掘された陶棺の時代を次のように述べておられます。「この地域の後期古墳は、六世紀中頃に築造が始まり、七世紀末まで使用されており、時には七世紀中頃以降でも築造され、中には八世紀の火葬骨を追葬しているものもある」
私は、この部分が良くないのではないかと思っています。最近、岡山県で鉄を製造した遺跡が発掘されていますが、私はどれも、200年ぐらい遡らなければならないのではないかと思っています。そうしますと、古事記に書かれているスサノオが襲撃した製鉄所に一致します。(No62~65) 陶棺が発掘されたときに、なにを基準にして、使われた年代を決めるのでしょうか?
普通に考えても少し、おかしいと考えられませんか? 「六世紀中頃に築造が始まり、七世紀末まで使用されており」と書いておられますが、これですと、二代しか生活していなかったことになります。仮に北海道のように、明治時代に入植されたとします。帯広の原野では、一代が暮らすだけでも厳しかったそうですが、私の友人は、三代目で、200頭を超える乳牛を育てています。美作は三代ぐらいで逃げ出さなくてはならないような所とは思えません。それどころかずっと、子孫の方は現在も生活しておられると思います。
この陶棺は大きなもので、陶棺を作る技術がなかったのではないでしょうか? 陶棺は、6~7世紀と固定しているために、また、歴史に詳しいために、ユダヤなどの発想はとんでもないものだと思います。
岡山県英田郡美作町平福から発掘された切妻形の陶棺には、寒羊と思われる尻尾の太い二匹の羊を連れて羊の顎ひげを触っている人物が描かれているそうです。これは日本にはいなかった動物と思われます。子羊は聖書にでてくる神の使いだそうです。又、寒羊は、イスラエルが原産でユダヤと関係がありそうです。が知識として知っていたので、描いたのかもしれません。よって、描いた人は異国の人であったと考えていいと思います。…….
凄いことを 書いてあると思うのん
楢原の神宿 出自の とうない まこと
この人の原稿なのかな?
他でも 検索が掛かるの
以下コピー
美作では兵隊に守られて天皇一族はいたようですが、ユダヤ人も一緒にいたようです。しかし、
天皇家の勢力が強かったのですが、713年に美作を分離した理由は、それまで、中国人の勢力が美作の範囲だけ確実になったのではないでしょうか?
これと同じように、天皇の勢力が強かった丹波においても、中国人の勢力が強くなった丹後だけが分離されたのではないでしょうか?
天皇家の勢力が強かったのですが、713年に美作を分離した理由は、それまで、中国人の勢力が美作の範囲だけ確実になったのではないでしょうか?
これと同じように、天皇の勢力が強かった丹波においても、中国人の勢力が強くなった丹後だけが分離されたのではないでしょうか?
· 和銅3年3月 - 藤原京から平城京に遷都。藤原氏、興福寺の造営を発願する。
· 和銅4年10月 - 蓄銭叙位令を定める。
· 和銅5年1月 - 太安万侶により古事記 完成、撰上。
· 和銅5年9月28日 - 出羽国を建てる。
· 和銅6年4月3日 - 丹後国 美作国・大隅国を建てる。
☆官稲混合による正税とは 年貢というか 稲穂を集める役目 駅起稲 神税 西暦700年過ぎの頃