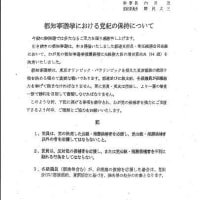愚者の自覚で 連帯感の再構築を [下]
1201年、「修行しても煩悩を抑制できない我が身は地獄へ往(ゆ)くしかない」と比叡山で苦しんでいた29歳の親鸞は山を下り、「極楽往生には専ら『南無阿弥陀(なむあみだ)仏』と唱えればよい」と説く69歳の法然の弟子となる。
親鸞は、法然の主著である『選択(せんちゃく)本願念仏集』の書写を許され(許されたのは数人)有力な弟子の一人となるが、1206年に京都東山の鹿ケ谷にあった法然の弟子の安楽・住蓮(じゅうれん)の草庵で後鳥羽上皇が寵愛していた松虫・鈴虫が出家し、上皇の逆鱗に触れるという事件が起こり、翌年、安楽・住蓮は死罪、法然は讃岐に、親鸞は越後に流されたため、親鸞は35歳までの五年余りの間だけ、法然の傍で教えを受けたことになる。

平安時代には空海の教えを受けた嵯峨天皇が818年に出した死刑停止の宣旨により810年の「平城太上(へいぜいだいじょう)天皇の変(薬子(くすこ)の変)」に際し薬子の兄の藤原仲成が死刑になってから1156年の「保元の乱」の折に平忠正や源為義が斬首されるまで346年も公的な死刑が執行されず、これは近代以前の世界に例のない事実なのだが、僧が死罪にされるほど上皇の怒りは激しかったのである。
1200年、鎌倉幕府によって既に専修念仏は禁止されていた。万人の平等(全ての人間は凡夫である)を説く法然の仏教は為政者にとって受け入れ難いものであったと思われる。
親鸞は越後に流された後、暫くして関東に移り、63歳の頃に京都に戻って晩年は著述活動と関東の門弟との間の手紙のやりとりなどで過ごし、90歳で入寂する。
現存する親鸞の手紙は80歳代に書かれたものが殆どであるが手紙には「浄土宗の人は愚者になって往生する」などの法然の言葉が度々登場する。
また、親鸞の主著である『教行信証して日本に興し、阿弥陀仏が選択された本願をこの悪世に広めた」と法然を讃たたえている。
親鸞が生涯に亘(わた)って法然の教えを伝えようと努めたことがよく分かる。
日本史の教科書では法然が開いた浄土宗と親鸞が開いた浄土真宗があると教えられるが、親鸞がいう真宗というのは法然が開いた浄土宗のことであり、自身が浄土宗と異なる真宗を開いたという意味ではない。
また現在の浄土宗はもともと法然の弟子の弁長を派祖とする浄土宗鎮西派と呼ばれる一派にすぎない。
現在の浄土宗と真宗は共にもともと法然の浄土宗の一部なのに、法然・親鸞の仏教を一体的に説かずに法然と親鸞の違いを強調しているのは誠に残念である。
『歎異抄』の「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや(善人でさえも往生を果たすのだ、ましてや、悪人が往生を果たすことはいうまでもない)」も親鸞独自の言葉ではない。
これは法然から親鸞へ、親鸞から唯円へと伝えられた人間観を端的に示すもので、他人事として、あの悪人こそが往生しやすいと言っている訳ではなく、この文の続きを読むと「阿弥陀仏の根本の願いは私ども悪人を成仏させる点にあるのだから、他力をたのむ悪人こそが正真正銘、浄土に生まれて必ず仏となる種の持ち主なのである」と書かれている。
つまり、自身を悪人、自己中心的な愚か者と自覚した人こそが、他力(阿弥陀仏)を頼み、往生成仏する人だという意味なのである。
仏教では、愛は地球を救わない。自己愛、家族愛、愛国心が他者や隣人との争い、他国との戦争の原因である。
愛は喜びをもたらす、生きてゆく原動力であると共に、苦や悲しみに身を置く種となる。
近年の日本では家族愛だけを大切にしすぎてきたことが、地域住民のつながりを壊し、最後の頼りの家族に理解してもらえず、仏や死別した肉親に浄土から拝まれている自分であることが信じられないので、孤立感を持ち、絶望して自暴自棄になる方が多いという現実を生み出していると思う。
法然・親鸞は、生涯、人間は自己中心性から逃れることができないが、自身が自己中であることをよく自覚して生きることが大切だと説いた。
専修念仏の僧が凡夫人間観と阿弥陀仏の慈悲を説き続け、「俺も自己中な阿呆(あほう)やけど、お前も自己中な阿呆やな」という上方漫才に示される愚か者同士の共感を広げ、凡夫が互いに笑い合い、時に不条理と出合わねばならないことを悲しみ合いながら、殺された家族も阿弥陀仏の浄土で菩薩や仏となっておられることを御遺族が信じていただければ死刑のない日本に戻れるのではないかと夢見ている。合掌
------------------------------------
かじた・しんしょう 京都・鹿ケ谷の法然院貫主。1956年、京都市生まれ。大阪外国語大ドイツ語科卒。きょうとNPOセンター副理事長。著書に「法然院」(淡交社)「ありのまま~ていねいに暮らす、楽に生きる~」(リトルモア)など。
1201年、「修行しても煩悩を抑制できない我が身は地獄へ往(ゆ)くしかない」と比叡山で苦しんでいた29歳の親鸞は山を下り、「極楽往生には専ら『南無阿弥陀(なむあみだ)仏』と唱えればよい」と説く69歳の法然の弟子となる。
親鸞は、法然の主著である『選択(せんちゃく)本願念仏集』の書写を許され(許されたのは数人)有力な弟子の一人となるが、1206年に京都東山の鹿ケ谷にあった法然の弟子の安楽・住蓮(じゅうれん)の草庵で後鳥羽上皇が寵愛していた松虫・鈴虫が出家し、上皇の逆鱗に触れるという事件が起こり、翌年、安楽・住蓮は死罪、法然は讃岐に、親鸞は越後に流されたため、親鸞は35歳までの五年余りの間だけ、法然の傍で教えを受けたことになる。

平安時代には空海の教えを受けた嵯峨天皇が818年に出した死刑停止の宣旨により810年の「平城太上(へいぜいだいじょう)天皇の変(薬子(くすこ)の変)」に際し薬子の兄の藤原仲成が死刑になってから1156年の「保元の乱」の折に平忠正や源為義が斬首されるまで346年も公的な死刑が執行されず、これは近代以前の世界に例のない事実なのだが、僧が死罪にされるほど上皇の怒りは激しかったのである。
1200年、鎌倉幕府によって既に専修念仏は禁止されていた。万人の平等(全ての人間は凡夫である)を説く法然の仏教は為政者にとって受け入れ難いものであったと思われる。
親鸞は越後に流された後、暫くして関東に移り、63歳の頃に京都に戻って晩年は著述活動と関東の門弟との間の手紙のやりとりなどで過ごし、90歳で入寂する。
現存する親鸞の手紙は80歳代に書かれたものが殆どであるが手紙には「浄土宗の人は愚者になって往生する」などの法然の言葉が度々登場する。
また、親鸞の主著である『教行信証して日本に興し、阿弥陀仏が選択された本願をこの悪世に広めた」と法然を讃たたえている。
親鸞が生涯に亘(わた)って法然の教えを伝えようと努めたことがよく分かる。
日本史の教科書では法然が開いた浄土宗と親鸞が開いた浄土真宗があると教えられるが、親鸞がいう真宗というのは法然が開いた浄土宗のことであり、自身が浄土宗と異なる真宗を開いたという意味ではない。
また現在の浄土宗はもともと法然の弟子の弁長を派祖とする浄土宗鎮西派と呼ばれる一派にすぎない。
現在の浄土宗と真宗は共にもともと法然の浄土宗の一部なのに、法然・親鸞の仏教を一体的に説かずに法然と親鸞の違いを強調しているのは誠に残念である。
『歎異抄』の「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや(善人でさえも往生を果たすのだ、ましてや、悪人が往生を果たすことはいうまでもない)」も親鸞独自の言葉ではない。
これは法然から親鸞へ、親鸞から唯円へと伝えられた人間観を端的に示すもので、他人事として、あの悪人こそが往生しやすいと言っている訳ではなく、この文の続きを読むと「阿弥陀仏の根本の願いは私ども悪人を成仏させる点にあるのだから、他力をたのむ悪人こそが正真正銘、浄土に生まれて必ず仏となる種の持ち主なのである」と書かれている。
つまり、自身を悪人、自己中心的な愚か者と自覚した人こそが、他力(阿弥陀仏)を頼み、往生成仏する人だという意味なのである。
仏教では、愛は地球を救わない。自己愛、家族愛、愛国心が他者や隣人との争い、他国との戦争の原因である。
愛は喜びをもたらす、生きてゆく原動力であると共に、苦や悲しみに身を置く種となる。
近年の日本では家族愛だけを大切にしすぎてきたことが、地域住民のつながりを壊し、最後の頼りの家族に理解してもらえず、仏や死別した肉親に浄土から拝まれている自分であることが信じられないので、孤立感を持ち、絶望して自暴自棄になる方が多いという現実を生み出していると思う。
法然・親鸞は、生涯、人間は自己中心性から逃れることができないが、自身が自己中であることをよく自覚して生きることが大切だと説いた。
専修念仏の僧が凡夫人間観と阿弥陀仏の慈悲を説き続け、「俺も自己中な阿呆(あほう)やけど、お前も自己中な阿呆やな」という上方漫才に示される愚か者同士の共感を広げ、凡夫が互いに笑い合い、時に不条理と出合わねばならないことを悲しみ合いながら、殺された家族も阿弥陀仏の浄土で菩薩や仏となっておられることを御遺族が信じていただければ死刑のない日本に戻れるのではないかと夢見ている。合掌
------------------------------------
かじた・しんしょう 京都・鹿ケ谷の法然院貫主。1956年、京都市生まれ。大阪外国語大ドイツ語科卒。きょうとNPOセンター副理事長。著書に「法然院」(淡交社)「ありのまま~ていねいに暮らす、楽に生きる~」(リトルモア)など。