Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas [Official Video]
「猫」 各駅停車
SEKAI NO OWARI「Hey Ho」
Lou Rhodes - One Good Thing
(ちんちくりんNo,61)
話が一段落したところで、「あ、もう社に戻らないと、じゃあね。次は僕の方から連絡するよ」そう言い残して七瀬社長はテーブルの上に一万円札を置き、立ち上がった。少し間が空いてしまって、「支払いには多すぎる」僕は言いかけたが間に合わなかった。七瀬社長はすでに階段を降りてしまったのか姿が見えなくなっていた。「大丈夫。いつもそうだから」かほるはいつまでも七瀬社長がいなくなったのであろう方向を見ている僕にそう声をかけ笑った。「ここね、ケーキもね、美味しいの。食べよ」ハイハイわかりました。おススメでたのむよ。
それにしても、人生こんなにも物事が上手く進んで良いものだろうか。僕の小説を気に入ったとはいえ、僕自身は全くの無名。素人といってもいい。いくらそういう新人を育てたいとはいっても、リスクは相当のものだ。そのようなリスクを負って迄もこの僕を使うのか。本当にこれは現実のことなのだろうか。白昼夢か・・・。僕は未だ「自己暗示」にかかりきっていなかった。いくら暗示を繰り返したところで、完全には信じられない。つまり自分を信じきれていないのだ。“自信”それがこれからプロの作家を目指す上で絶対に必要になるだろうことを僕は感じずにいられなかった。
そんな中、ふと思い出したのは、七瀬社長が会話の中で、新しい文芸雑誌は新人だけではなく、既存の作家も一人書いてもらうと言ったことだった。「勿論商業誌であるからには売らねばならない。だから、“薫りいこ”にも書いてもらうことになっている」
薫りいこ、というのは当代随一の流行作家であった。その十年ほど前に何らかの新人賞をとったことが始まりだったかと思う。その後、見る見るうちに世間に注目され、十年のうちに出した本は全て十万部以上売れ、百万部まで達成した本もあった。何故そんなに売れたのか。筆力やストーリー性もさることながら、彼女或いは彼が覆面作家であったということも影響したかと思う。その実像は徹底的に伏せられ、経歴も写真も男か女かさえも衆人には知る術がなかった。
その薫りいこに書いてもらえるのか。中小出版社が初めて出す文芸誌に?どういった経緯があったのだろうか。僕は非常に驚いたのだが、七瀬社長にはその説明を拒むような雰囲気があったので、気になりながらも訊けずじまいになってしまった。かほるはメニューを眺めている。すっきりした表情だ。勝手にしたことを詫びてきた時とは明らかに違う、生涯最後の断捨離をし終えた満足感のようなそんな気持ちが顔に表れていた。僕はやおら立ち上がり、テーブルを回って七瀬社長が場を去り、空いた向かいの席に移った。かほるの顔が正面にあった。
「どうしたの」
「いや、空いてるしこの方が話し易いと思って」
「そう」
かほるがメニューを脇に置いて、丁度皿を片しに来た店員に「ティラミスを二つ」と注文し終えるのを待ってから話を続けた。
「それで、ちょっとさ・・・」
「なに」
「薫りいこが書いてくれるって言っていただろう?」
「ああ、そうね。そう言ってたけど、それが?」
「・・・ちょっと失礼かな、と思うんだけど何で売れっ子の薫りいこが、大手でもない出版社のしかも初めて出す文芸誌に書いてくれるのかと思ったんだよね」
「それは、叔父さんと約束していたからよ。龍生書房を立ち上げてからの約束だもの」
「約束・・・。そうか、薫りいこはデビュー前から社長の知り合いだったということか」
合点がいった。そしてもしかしたら、薫りいこというのは社長が育てた作家なのかもしれないと思った。と同時に別の疑問が沸いた。
「何故、それを知ってるの。叔父と姪の関係とはいえさすがにあの薫りいことの関係を、社長が?かほるに?」
「あら、知ってて当たり前よ。だって薫りいこは叔父さんの姉さんなんだから」
さらあ、と言われて最初は「叔父の姉さんだからなんだよ」と思った。でも、かほるとの関係はと考えたら、かほるは週刊誌並みの暴露をしたんだってことに気がついた。
「かほる・・・、かほるのお母さんって薫りいこなの?」
「そうよ。それが何か」
全く動じることなくあっさりとかほるは応えた。
「猫」 各駅停車
SEKAI NO OWARI「Hey Ho」
Lou Rhodes - One Good Thing
(ちんちくりんNo,61)
話が一段落したところで、「あ、もう社に戻らないと、じゃあね。次は僕の方から連絡するよ」そう言い残して七瀬社長はテーブルの上に一万円札を置き、立ち上がった。少し間が空いてしまって、「支払いには多すぎる」僕は言いかけたが間に合わなかった。七瀬社長はすでに階段を降りてしまったのか姿が見えなくなっていた。「大丈夫。いつもそうだから」かほるはいつまでも七瀬社長がいなくなったのであろう方向を見ている僕にそう声をかけ笑った。「ここね、ケーキもね、美味しいの。食べよ」ハイハイわかりました。おススメでたのむよ。
それにしても、人生こんなにも物事が上手く進んで良いものだろうか。僕の小説を気に入ったとはいえ、僕自身は全くの無名。素人といってもいい。いくらそういう新人を育てたいとはいっても、リスクは相当のものだ。そのようなリスクを負って迄もこの僕を使うのか。本当にこれは現実のことなのだろうか。白昼夢か・・・。僕は未だ「自己暗示」にかかりきっていなかった。いくら暗示を繰り返したところで、完全には信じられない。つまり自分を信じきれていないのだ。“自信”それがこれからプロの作家を目指す上で絶対に必要になるだろうことを僕は感じずにいられなかった。
そんな中、ふと思い出したのは、七瀬社長が会話の中で、新しい文芸雑誌は新人だけではなく、既存の作家も一人書いてもらうと言ったことだった。「勿論商業誌であるからには売らねばならない。だから、“薫りいこ”にも書いてもらうことになっている」
薫りいこ、というのは当代随一の流行作家であった。その十年ほど前に何らかの新人賞をとったことが始まりだったかと思う。その後、見る見るうちに世間に注目され、十年のうちに出した本は全て十万部以上売れ、百万部まで達成した本もあった。何故そんなに売れたのか。筆力やストーリー性もさることながら、彼女或いは彼が覆面作家であったということも影響したかと思う。その実像は徹底的に伏せられ、経歴も写真も男か女かさえも衆人には知る術がなかった。
その薫りいこに書いてもらえるのか。中小出版社が初めて出す文芸誌に?どういった経緯があったのだろうか。僕は非常に驚いたのだが、七瀬社長にはその説明を拒むような雰囲気があったので、気になりながらも訊けずじまいになってしまった。かほるはメニューを眺めている。すっきりした表情だ。勝手にしたことを詫びてきた時とは明らかに違う、生涯最後の断捨離をし終えた満足感のようなそんな気持ちが顔に表れていた。僕はやおら立ち上がり、テーブルを回って七瀬社長が場を去り、空いた向かいの席に移った。かほるの顔が正面にあった。
「どうしたの」
「いや、空いてるしこの方が話し易いと思って」
「そう」
かほるがメニューを脇に置いて、丁度皿を片しに来た店員に「ティラミスを二つ」と注文し終えるのを待ってから話を続けた。
「それで、ちょっとさ・・・」
「なに」
「薫りいこが書いてくれるって言っていただろう?」
「ああ、そうね。そう言ってたけど、それが?」
「・・・ちょっと失礼かな、と思うんだけど何で売れっ子の薫りいこが、大手でもない出版社のしかも初めて出す文芸誌に書いてくれるのかと思ったんだよね」
「それは、叔父さんと約束していたからよ。龍生書房を立ち上げてからの約束だもの」
「約束・・・。そうか、薫りいこはデビュー前から社長の知り合いだったということか」
合点がいった。そしてもしかしたら、薫りいこというのは社長が育てた作家なのかもしれないと思った。と同時に別の疑問が沸いた。
「何故、それを知ってるの。叔父と姪の関係とはいえさすがにあの薫りいことの関係を、社長が?かほるに?」
「あら、知ってて当たり前よ。だって薫りいこは叔父さんの姉さんなんだから」
さらあ、と言われて最初は「叔父の姉さんだからなんだよ」と思った。でも、かほるとの関係はと考えたら、かほるは週刊誌並みの暴露をしたんだってことに気がついた。
「かほる・・・、かほるのお母さんって薫りいこなの?」
「そうよ。それが何か」
全く動じることなくあっさりとかほるは応えた。

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


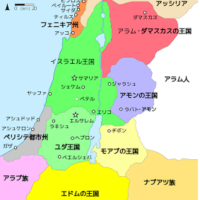






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます