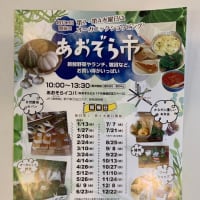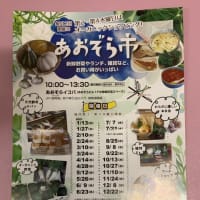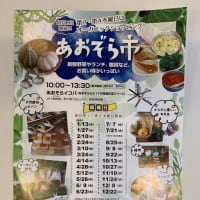【良い春を迎えるための冬養生】
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年12月1日 - 09:51
一つ、早く寝てゆっくり起きる
一つ、意思も活動も活発にするのを控える
一つ、汗を極力かかないようにする
自然界と同じように、人も『冬は閉じて護る』これが基本です。心も体も積極的にならなくて良いで… twitter.com/i/web/status/9…
冬三月,此謂閉藏,水冰地坼,無擾乎陽。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年12月1日 - 09:52
早臥晚起,必待日光。
使志若伏若匿,若有私意,若已有得。
去寒就溫,無洩皮膚,使氣亟奪。
此冬氣之應,養藏之道也。逆之則傷腎,春為痿厥,奉生者少。
が冬の養生法です。
というのは冗談で、こちらに訳をかいてありますので、ご参考ください。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年12月1日 - 09:53
中医学的冬の養生法~気持ちも心も穏やかに~ - ミドリ薬品 店長ブログ - ミドリ薬品 | 北海道北見市 | 漢方専門 | 皮膚病 不妊症など専門スタッフが対応 midoriyakuhin.com/index.php?go=z…
え?冬でも汗かいて温めたほうがいいんじゃねのかよ?
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年12月1日 - 09:54
という人も、間違ってますから、こちらを読んでくださいね。
中医学的冬の養生法~気持ちも心も穏やかに~ - ミドリ薬品 店長ブログ - midoriyakuhin.com/index.php?go=z…
身体を温める食べ物
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年12月1日 - 10:28
薬味では、しょうが、ナツメグ、シナモン、八角、フェンネルシード、唐辛子など
果物や木の実には、栗、クルミ、桃、サクランボなど
魚介などでは、鮭、ウナギ、エビなど
肉類は、羊肉、鹿肉、牛肉、鶏肉など
調味料は、… twitter.com/i/web/status/9…
人は誰しも平等に歳をとりますがが、老いるのが早い人とそうでない人がいます。これは生命力の源である『腎』の充実度の違いと中医学では考えます。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年11月30日 - 18:46
歯や骨が弱い、髪の毛が白い・薄い、精力が減退する、尿の出が悪くなる、足腰が弱いなどが若いうちから見られる方は要注意。
そのほか、目の下にくまがあったり、目に力がなかったり、髪が細くて弱かったり若白髪だったり、脱毛が多かったり、顔が黒ずんでいたり、耳周りの湿疹が多かったりするのは腎の弱りと考えます。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年11月30日 - 18:47
腎の弱さを補うには、①よく歩き、足腰を鍛える、②黒いもの、ぬめりのあるものを食べる、③冬はしっかり防寒して、汗をできるだけかかないようにすることが大切です。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年11月30日 - 18:48
エスカレーターよりも階段、通勤時電車も立って、黒豆、わかめ、イカ、海老、なまこ、タコ、牡蠣、山芋など加熱して摂りましょう。
時間医学とは「時間生物学」という生物の生体リズムを研究する学問の考え方を、医学分野に取り入れたものです。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年12月1日 - 14:12
1日24時間の間にそれぞれの臓器が集中的に働く【高期】とその後、約2時間休憩して回復する【低期】の2つに分け、体や内臓はそれ… twitter.com/i/web/status/9…
時間医学で分かりやすいのは肺です。肺が一番元気なのは明け方3時~5時の間です。そのため登山家はしっかり寝て早朝5時に出発するより、3時に出発する方が元気が出ると言います。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年12月1日 - 14:16
また喫煙者や喘息の方が朝、咳が出るのは肺が夜中のうちに仕事を終え、余分な物を外へ排出しようとするからです。
長年一日一食。という有名人の方も何人かいますが、一般的には、日に数回の栄養補給が必要です。熱エネルギーは受精時に両親から授かったもの以外は、全て飲食物から賄います。原料が入ってこなければ作れなくて当たり前d( ̄- ̄;)特に。朝は前日の夜から数時間補給してないので食餌は不可欠です。
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 16:50
飲食物は口→胃→小腸と消化が進み、小腸で人体に必要なものとそうでないものを分別し、必要なものが脾に運ばれて、生命活動に必要なものに作り変えられます。冬は寒さで熱エネルギーを消耗しやすいだけでなく、春に向けて貯えも必要な季節。食餌は… twitter.com/i/web/status/9…
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 16:53
脾胃が虚弱だと、一度にたくさんのものを消化吸収したり、必要なものに作り買えることができません。食後、お腹の脹り・倦怠感・眠気・頭がぼーっとする・能率が下がるという場合は脾胃虚弱の可能性があるので、5~6回に分けて食べると、脾胃に負担を掛けず、効率よく消化吸収できます。
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 16:55
生もの・冷たいものは、物理的に熱エネルギーを消耗させて体を冷やします。人体は37℃前後でうまく機能するようにできていますが、体温より低い温度のものを摂ると、消化吸収するために一旦37℃まであっためるので、ここで熱エネルギーの消耗が… twitter.com/i/web/status/9…
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:11
一日に成人が呼気・大小便・発汗その他で消費する水分は約2リットル。食餌を三食摂っていると、食餌だけで1リットルは賄えます。つまり。液体として必要なのは残りの1リットル。肉体労働や空気の乾燥で消耗した場合でも倍も3倍もは必要としませ… twitter.com/i/web/status/9…
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:15
体が冷えると水分の吸収にも時間が掛かります。のどの渇きや口の乾燥があって水分補給をしても、体が冷えていると吸収に時間が掛かるため、渇きが癒えるにも時間が掛かり、このタイムラグのせいで水分を過剰に摂取してシマウマ。そして。その過剰分は体を冷やします(T_T)
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:17
こたつや入浴で体があったまっていても、体温より低いアイスや果物を摂ると、折角あったまったのに内側から冷やして熱エネルギーを消耗します。特に。夜は体が休む時間で代謝や血行も低下する時間。冷え症が気になるなら我慢も必要(*^_-)b pic.twitter.com/6GI3BtuYgm
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:19
もうひとつ。中医学では、飲食物にも寒熱の属性があると考えます。体を温める温熱性、体を冷やす寒凉性、どちらでもない平性があり、当たり前ですが、冷え症にとって寒凉性のものはNG!晩秋~冬が旬の鴨・かに・ほうれん草・柿・りんご、通年ある… twitter.com/i/web/status/9…
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:26
食餌内容が一食で寒凉性に偏らないようにすることが大事デス。例えば。副菜でほうれん草を摂るなら、主菜は温性の鶏肉・羊肉・牛すじ・えびにしたり、生姜やこしょうなど温熱性の薬味やスパイスを効かせるなどで('-^*)ok
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:33
【冷え症を改善する食生活】
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:38
●食餌を三食摂る
●消化吸収が悪い場合は、一回量を少なく、5~6回に分けて摂取
●人肌以下の温度のものは食べない
●必ず加熱調理する
●のどの渇きや乾燥がなければ水分摂取は控える
●一食で寒凉性に偏らな… twitter.com/i/web/status/9…
消化が悪い原因にひとつに脾胃の熱エネルギー不足があり悪循環のパターンも。
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年11月30日 - 17:50
また。朝起きられなくて時間がない。というのも、実は熱エネルギー不足で、起きるための体温・血圧・心拍の上昇がうまくできず、覚醒できてないからかも。 twitter.com/iskra_kawagoe/…
お餅はじめ餅米製品は、寒暖差・気圧変化&風・乾燥&湿気などの気候変化や、環境による人体への影響を防御する体表のバリア・衛気(えき)を強化します。いわば。城門を強固にし、強力な門番を増員する感じで今の時期にグー(*^_-)b
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 14:18
但し。… twitter.com/i/web/status/9…
餅米製品NGは、かぜ・感染症・炎症・かゆみ・むくみ・ストレスなど、病気の原因になる邪気や、不要な熱、湿気、病理産物の停滞などがある時。
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 14:23
かぜだからたんと食べて体力つけよーとか思って、力うどんとかお汁粉とか摂らないようにネ(`_´)bその他の症状も悪化したり、長引いたりします。
アトピー性皮膚炎など炎症やかゆみを伴う症状を悪化させるものに、餅米製品・スパイシーなもの・鶏肉・羊肉・牛肉・えび・たちうお・うなぎなどがあります。これらは温熱性、発散もしくは補うはたらきが強く、症状を悪化させます。 pic.twitter.com/oBpUnZCzCH
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 14:32
まだ30日寝ないとお正月にはなりませんが、お正月にお雑煮やお節料理が食べられないのは可哀相、ほんの一口ならいいかも、と摂った一口のお餅やえびなどで、症状を悪化させる事案は毎年あります。アレルゲンにならなくても、症状悪化の引き金になるのでご注意を!
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 14:35
スパイシーなものは体を温めるのではなく、寒さを散らしたり、温めて発散・発汗・代謝および血行の促進をします。一時的に温まりますが、不要なものも排泄する代わりに必要なものも消耗させます。熱エネルギーを補うのとは訳が違うので、あったまる… twitter.com/i/web/status/9…
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 20:18
ところで。辛いものには、発散や代謝&血行を促進するはたらきがあるので、ストレスなどで気血の巡りが悪くなっていると食べたくなります。食べた時は心身リラックスできますが、発汗、発散で血液や潤いを損なうと、精神が落ち着きにくくなり、却ってストレスを受けたり、怒りっぽくなります(T_T)
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 20:21
また。辛いもので一時的に熱が生じますが、この熱も血液や潤いを消耗させます。そして。余分な熱はイライラを助長させるので悪循環。
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 20:24
ストレス→辛いもの多食→必要なもの↓&ストレス↑→辛いもの多食→…エンドレス( ̄д ̄;)
忙しくなるこの時期は特に気を付けましょう。
あと。辛いの摂り過ぎると、潤いを好む肺が乾燥します。外気の乾燥も受けやすいこの時期、辛いものの多食は肺の機能低下の原因となり、のどから来るかぜを退きやすくなったり、肺と関連するお肌のトラブルや、肺と表裏関係にある大腸のトラブルにも発展。便秘とか止まらない下痢とか痔とかも注意。
— 泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2017年12月1日 - 20:26