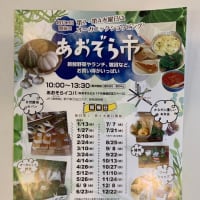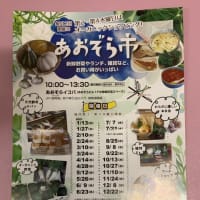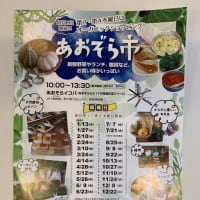【気候風土に合った食べ方をしよう】
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月19日 - 15:49
〈身体を温める食物〉
・北方地域が原産のもの
・秋冬が旬のもの
みかん、にんじん、栗、ねぎなど
〈身体を冷やす食物〉
・南方地域が原産のもの
・夏が旬のもの
なす、きゅうり、バナナ、トマトなど… twitter.com/i/web/status/9…
【旬の食材で身体を癒そう✨】
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月19日 - 16:10
・春の山菜
・夏の瓜類
・秋の種実
・冬の根菜
四季のある日本では、折々の旬の素材が届けられます。
旬の素材は美味しくてリーズナブルで最高の薬になりますよ〜☺️
自然のリズムに合わせて旬の恵みをいただ… twitter.com/i/web/status/9…
【眠れる体づくり①】
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月20日 - 13:59
血の不足(血虚)による不眠
眠りが浅い、よく目が覚める、夢が多い、朝すっきり目覚めないなどがみられるのは、このタイプの可能性が。
このタイプは放っておくと、眠れないことでイライラしたり、動悸や胸苦しさに… twitter.com/i/web/status/9…
【眠れる体づくり②】
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月20日 - 14:01
中医学で血(けつ)は、精神の安定に関与します。血が精神と魂に栄養を送ることで安定します。
そのためにはよい状態の血(ケツ≠血液)が、体内に十分にあることが重要です。
月経に加え、妊娠出産授乳など、血を消耗しやすい女性には血の不足が多いです。
【眠れる体づくり③】
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月20日 - 14:02
血(けつ≠血液)を補うには、冷たい飲食、サラダや刺身などの生もの、揚げ物、チョコなど甘いもの、唐辛子などの刺激物を避けて、鶏肉、卵、ニンジン、ゴマ、レバー、ナマコ、棗、牡蠣、黒豆、小松菜、ホウレンソウ、トマトなどを積極的に。
【眠れる体づくり④】
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月20日 - 14:05
普段から血を消耗させない生活習慣を。
・夜更かし禁物
・タバコ禁物
・目の使いすぎ禁物
・悩みすぎ禁物
この傾向が強い方はお気をつけを。
目が霞むとか乾燥するとか焦点あわないとか、最近肌や髪が乾燥して… twitter.com/i/web/status/9…
【眠れる体づくり⑤】
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月20日 - 14:24
よい血(けつ≠血液)を作るには、消化を担う脾胃が元気でなくては行けません。
食欲がない、軟便気味という方は、レバーなど動物性食品ではなく、黒ゴマをたっぷりかけるとか、黒豆煮て食べるとか、クロキクラゲをなんにでも足すとか、野菜類から摂るようにしてください。
✳︎春はデトックスの季節✳︎
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月20日 - 12:02
人も動物と同じように冬は寒さに備えて、栄養や脂肪を蓄えます。
暖かくなるにつれて代謝を促し、解毒してくれる肝臓の働きが活発になるので、冬に溜め込んだものを一気に排出するので、春は「ニキビやアレルギー、… twitter.com/i/web/status/9…
春野菜(タケノコ、菜の花、アスパラガス、タラの芽など)は強い香りや独特の苦みを持つものが多いです。香りはストレスを流し、苦味にはデトックス作用があります。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月20日 - 12:04
春野菜は冬に溜めこんだ脂肪や毒素、老廃物などを排出し、季節がら溜まりやすい… twitter.com/i/web/status/9…
春になりイライラ、火照る、のぼせ、顔が赤い、頭痛、口の渇きなどする人は陽気が体にこもってしまっています。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月20日 - 12:06
体の陽気を巡らせるために適度に運動するようにしましょう!
春にしっかり汗をかくと冬に溜めた脂肪や老廃物をデトックスでき、代謝… twitter.com/i/web/status/9…
春はデトックスの季節なのでニキビや吹き出物、湿疹、アトピーなどの症状が出やすくなります。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月20日 - 14:20
ブロッコリーに含まれる「スルフォラファン」には強い解毒作用があります。毒素はしっかり出しましょう!
ビタミンC、Eも豊富なので解毒だけでなく… twitter.com/i/web/status/9…
花粉症は突然発症する。といわれますが。中医学的には、ほとんどの場合、なるべくしてなったと考えられます。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:23
こんな体質だと、ある日突然花粉症になる可能性が…( ̄д ̄;)
①体表のバリア不足
②血液不足
③体液不足
④熱エネルギー不足
⑤肺・脾・腎の機能失調
⑥湿熱の停滞
#花粉症
①体表のバリア不足
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:27
体表のバリアを衛気(えき)といい、衛気は気候変化や環境による影響が人体に及ばないようガードし、またこれらが影響した場合、取り除くために戦ういわばガードマンのような役割を担っています。この衛気が虚弱だと、寒暖差、… twitter.com/i/web/status/9…
②血液不足 ③体液不足
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:33
花粉症で見られるかゆみなどの症状は、中医学では風や気圧変化などの外風(がいふう)が原因と考えます。血液や体液が不足すると、頭暈・痺れ・痙攣・痒みなど、風に翻弄されて揺れ動く木々のような症状が現れます。これを… twitter.com/i/web/status/9…
④熱エネルギー不足
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:37
体表のバリア・衛気の減量のひとつに腎の熱エネルギーである腎陽(じんよう)があります。熱エネルギー不足では衛気を作ることができません。また。熱エネルギー不足では全身の代謝も低下し、全体的に体力や抵抗力が虚弱になって、ちょっとした影響でも症状が強く現れます。
⑤肺・脾・腎の機能失調
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:41
体表のバリア・衛気は、脾で飲食物から作ったエネルギー&腎陽を原料に作られ、肺によって体表に発散、運搬されます。中医学では、この3つの臓腑が水分代謝にも関与すると考え、これらの機能失調は、外風の影響を受けやす… twitter.com/i/web/status/9…
⑥湿熱の停滞
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:43
湿熱とは熱を帯びた水分の病理産物です。脾胃や肝胆に停滞しやすく、目・鼻・のどの痒みなどの炎症や、鼻づまり、黄色く粘った鼻水や痰、発熱してないのに熱っぽくぼーっとするなどの原因となります。
①体表のバリア不足 ⑤肺・脾・腎の機能失調
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:48
無理な食事制限、生もの・冷たいもの・水分の過剰摂取、過労、過度の運動、房事過多、虚弱体質、加齢、かぜ・呼吸器疾患・慢性疾患の後の体力低下などが原因で起こります。
思い当たるものがあれば花粉症予備軍。
④熱エネルギー不足
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:52
①④は主にエネルギーの生成不足や消耗が原因ですが、これが更に発展すると熱エネルギー不足になります。
この他。寒さによる熱エネルギーの直接的な消耗もあります。
冷え症、寒さや冬が苦手というタイプはこれが原因かも。 twitter.com/ookawa_taiseid…
②血液不足
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 20:55
無理な食事制限、血液の原料になる蛋白質の摂取不足、辛いものの・食物繊維の過食、生もの・冷たいもの・水分の過剰摂取による脾の機能失調、血液の病理産物である瘀血の停滞、過労、過度の運動、目の酷使、心労、ストレス、虚弱体質、… twitter.com/i/web/status/9…
女性では、月経、妊娠、出産、授乳による血液の消耗もあります。妊娠したら突然花粉症になった、出産後花粉症発症という場合は、血液不足が原因の場合がよくあります。ここでケアしないと一生ものの花粉症に(>_<。)
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 21:00
③体液不足
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 21:02
無理な食事制限・偏食による原料不足、辛いもの・食物繊維の過剰摂取、脾胃虚弱による生成不足、過度の発汗・嘔吐・下痢、嚥下困難・しゃっくり・呑酸などによる摂食障害、発熱性消耗疾患、かぜの後の体力低下、外界の乾燥が原因で起こ… twitter.com/i/web/status/9…
⑥湿熱の停滞
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月20日 - 21:05
味の濃いもの・辛いもの・油っこいもの・粘っこいもの・発酵食品・酒・餅米製品の過剰摂取、ストレス、蒸し暑さの影響などが原因。
舌がボテッとして歯形が付き、黄色い苔がべっとり付いているのはこのタイプ。