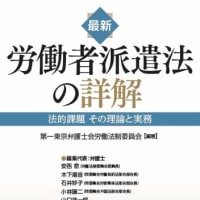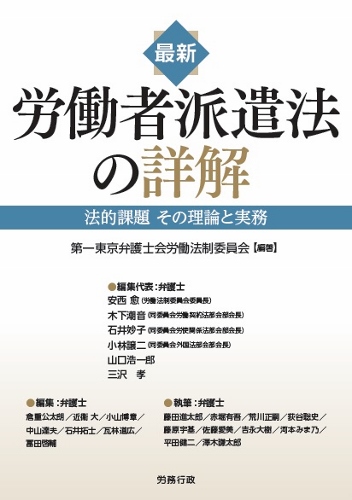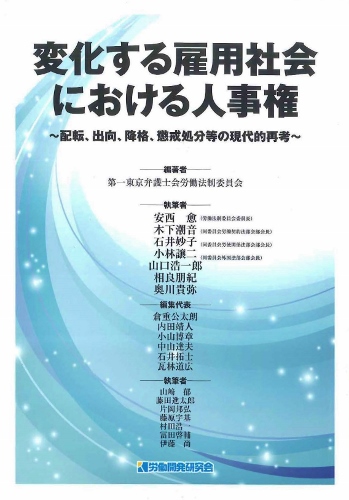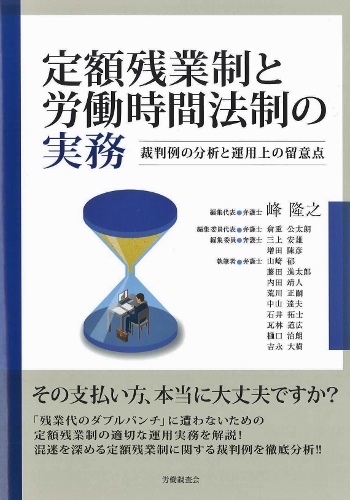Q9解雇・雇止めをした場合,労働審判・訴訟などにおいて,使用者はどのような請求を受けることが多いのでしょうか?
解雇・雇止めが無効の場合において,労働者が就労の意思があり,労務の提供をしているにもかかわらず,使用者が正当な理由なく就労を拒絶しているような場合には,就労不能の帰責事由が使用者にあると評価されるのが通常でしょうから,使用者は賃金支払義務を免れず(民法536条2項),労働者が実際には働いていない期間についての賃金についても,支払わなければならなくなります。
したがって,労働者側が解雇・雇止めの効力を争っている場合,雇用契約上の地位にあることの確認とともに,解雇・雇止め後の毎月の賃金(判決等確定までの将来分も含む。)の支払を求めてくるのが通常です。
単純化して説明しますと,このような労働審判・訴訟において,月給30万円の従業員について,解雇・雇止めの1年後に解雇・雇止めが無効と判断された場合,既に発生している過去の賃金だけで,30万円×12か月=360万円の支払義務を使用者が負担するリスクを負っており,その後も毎月30万円ずつ支払額が増額されていくリスクがあることになります。
労働者が他社に正社員として就職するなどして労務提供の意思が完全に喪失し労務の提供がなくなったと評価できる場合や,使用者が解雇・雇止めを撤回して労働者に出社するよう命じたにもかかわらず労働者が出社しなかったような場合は,当初の解雇・雇止めが無効であったとしても,以後の賃金支払義務を使用者は免れることになります。
しかし,労働者が転職せずに職場復帰を求め続けた場合や,労務提供の意思を失わないまま一時的に別の職場で仕事をしたに過ぎないような場合で,使用者が職場復帰を認めなかったような場合は,実際には全く働いていない期間について高額の賃金の支払を命じられるリスクがあります。
このため,解雇・雇止めが無効と判断されるリスクが高いケースでは,解雇・雇止めから解決までの時間が経てば立つほど,解決金の金額が高くなりがちですので,労働審判や訴訟の初期の段階で,早期に話をまとめるべきこととなります。
なお,従業員が突然出社しなくなり,会社から解雇されたと主張して,解雇予告手当(労基法20条1項)の支払を請求してくることがありますが,解雇予告手当というものの性質上,請求金額は30日分の平均賃金の金額にとどまりますので,訴訟対応の煩わしさ,解雇予告手当と同額(以下)の付加金の支払(労基法114条)を命じられるリスク,刑事罰(労基法119条1号,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)に関連する労基署(検察庁)対応の煩わしさはあっても,解雇・雇止めの無効が主張されたケースと比べて,金額面でのリスクは遙かに小さくなります。
弁護士 藤田 進太郎
解雇・雇止めが無効の場合において,労働者が就労の意思があり,労務の提供をしているにもかかわらず,使用者が正当な理由なく就労を拒絶しているような場合には,就労不能の帰責事由が使用者にあると評価されるのが通常でしょうから,使用者は賃金支払義務を免れず(民法536条2項),労働者が実際には働いていない期間についての賃金についても,支払わなければならなくなります。
したがって,労働者側が解雇・雇止めの効力を争っている場合,雇用契約上の地位にあることの確認とともに,解雇・雇止め後の毎月の賃金(判決等確定までの将来分も含む。)の支払を求めてくるのが通常です。
単純化して説明しますと,このような労働審判・訴訟において,月給30万円の従業員について,解雇・雇止めの1年後に解雇・雇止めが無効と判断された場合,既に発生している過去の賃金だけで,30万円×12か月=360万円の支払義務を使用者が負担するリスクを負っており,その後も毎月30万円ずつ支払額が増額されていくリスクがあることになります。
労働者が他社に正社員として就職するなどして労務提供の意思が完全に喪失し労務の提供がなくなったと評価できる場合や,使用者が解雇・雇止めを撤回して労働者に出社するよう命じたにもかかわらず労働者が出社しなかったような場合は,当初の解雇・雇止めが無効であったとしても,以後の賃金支払義務を使用者は免れることになります。
しかし,労働者が転職せずに職場復帰を求め続けた場合や,労務提供の意思を失わないまま一時的に別の職場で仕事をしたに過ぎないような場合で,使用者が職場復帰を認めなかったような場合は,実際には全く働いていない期間について高額の賃金の支払を命じられるリスクがあります。
このため,解雇・雇止めが無効と判断されるリスクが高いケースでは,解雇・雇止めから解決までの時間が経てば立つほど,解決金の金額が高くなりがちですので,労働審判や訴訟の初期の段階で,早期に話をまとめるべきこととなります。
なお,従業員が突然出社しなくなり,会社から解雇されたと主張して,解雇予告手当(労基法20条1項)の支払を請求してくることがありますが,解雇予告手当というものの性質上,請求金額は30日分の平均賃金の金額にとどまりますので,訴訟対応の煩わしさ,解雇予告手当と同額(以下)の付加金の支払(労基法114条)を命じられるリスク,刑事罰(労基法119条1号,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)に関連する労基署(検察庁)対応の煩わしさはあっても,解雇・雇止めの無効が主張されたケースと比べて,金額面でのリスクは遙かに小さくなります。
弁護士 藤田 進太郎