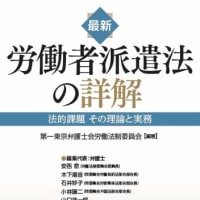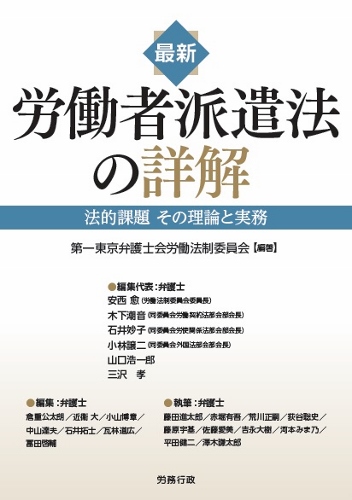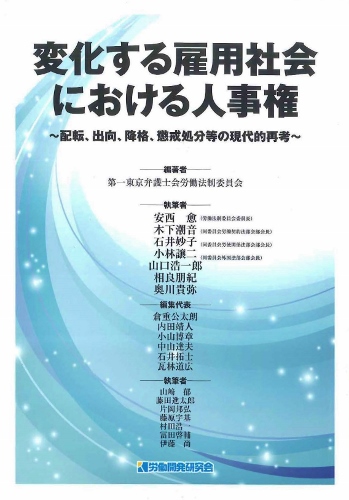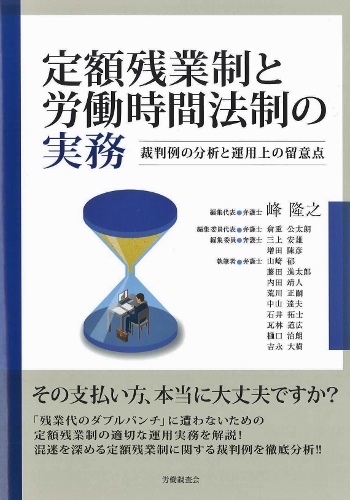Q22労働審判制度の主な特徴はどのようなものですか?
労働審判法は,
① 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)に関し,
② 裁判所において,裁判官(労働審判官)及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労使双方から1名ずつ選任される労働審判員合計2名)で組織する委員会が,当事者の申立てにより事件を審理し,
③ 調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み,
④ その解決に至らない場合には,労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利義務関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判)を行う手続(労働審判手続)を設けることにより,
⑤ 紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ること
を目的とするものです(労働審判法1条)。
労働審判手続の特徴はどれも重要なものですが,私が特に注目しているのは,①迅速な解決が予定されていることと,②裁判官(労働審判官)が直接関与して権利義務関係を踏まえた調停が試みられ,調停がまとまらない場合には労働審判が行われ,労働審判に対して異議を申し立てた場合には,訴訟に移行することの2点です。
まず,①迅速な解決という点ですが,労働者の大部分は,使用者に対して不満を持ったとしても,余程の事情がなければ,1年も2年も長期間の裁判を続けることは望まないことが多く,裁判手続を取ることを躊躇することが多かったのではないかと私は考えています。
しかし,労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結させることが予定されており(労働審判法15条2項),申立てから3か月もかからないうちにかなりの割合の事件が調停成立で終了しますので,労働者としては,利用しやすい制度と評価することができるでしょう。
これを使用者側から見れば,従来であれば表面化しなかった紛争が表面化しやすくなるということになります。
次に,②裁判官(労働審判官)が直接関与して権利義務関係を踏まえた調停が試みられ,調停がまとまらない場合には労働審判が行われ,労働審判に対して異議を申し立てた場合には,自動的に訴訟に移行する(労働審判法22条)という点も重要と考えています。
裁判官(労働審判官)と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名によって権利義務関係を踏まえた調停がなされるため,調停内容は合理的なもの(社内で説明がつきやすいもの,労働者が納得しやすいもの)となりやすくなります。
調停がまとまらなければ,たいていは調停案とほぼ同内容の労働審判が出され,労働審判に対して当事者いずれかが異議を申し立てれば自動的に訴訟での解決が行われることになりますが,訴訟で争っても,裁判官(労働審判官)が関与し,権利義務関係を踏まえて出された労働審判の内容よりも自分に有利に解決する見込みが大きい事案はそれほど多くはありません。
労働審判に対して異議を申し立てれば,直ちに訴訟に移行しますので,うやむやなまま紛争が立ち消えになることは期待できません。
訴訟が長引けば労力・金銭等での負担が重くなり,コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。
これらの点が相まって,ある程度は譲歩してでも調停をまとめる大きなモチベーションとなり,労働審判制度の紛争解決機能を飛躍的に高めているものと考えています。
弁護士 藤田 進太郎
労働審判法は,
① 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)に関し,
② 裁判所において,裁判官(労働審判官)及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労使双方から1名ずつ選任される労働審判員合計2名)で組織する委員会が,当事者の申立てにより事件を審理し,
③ 調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み,
④ その解決に至らない場合には,労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利義務関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判)を行う手続(労働審判手続)を設けることにより,
⑤ 紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ること
を目的とするものです(労働審判法1条)。
労働審判手続の特徴はどれも重要なものですが,私が特に注目しているのは,①迅速な解決が予定されていることと,②裁判官(労働審判官)が直接関与して権利義務関係を踏まえた調停が試みられ,調停がまとまらない場合には労働審判が行われ,労働審判に対して異議を申し立てた場合には,訴訟に移行することの2点です。
まず,①迅速な解決という点ですが,労働者の大部分は,使用者に対して不満を持ったとしても,余程の事情がなければ,1年も2年も長期間の裁判を続けることは望まないことが多く,裁判手続を取ることを躊躇することが多かったのではないかと私は考えています。
しかし,労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結させることが予定されており(労働審判法15条2項),申立てから3か月もかからないうちにかなりの割合の事件が調停成立で終了しますので,労働者としては,利用しやすい制度と評価することができるでしょう。
これを使用者側から見れば,従来であれば表面化しなかった紛争が表面化しやすくなるということになります。
次に,②裁判官(労働審判官)が直接関与して権利義務関係を踏まえた調停が試みられ,調停がまとまらない場合には労働審判が行われ,労働審判に対して異議を申し立てた場合には,自動的に訴訟に移行する(労働審判法22条)という点も重要と考えています。
裁判官(労働審判官)と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名によって権利義務関係を踏まえた調停がなされるため,調停内容は合理的なもの(社内で説明がつきやすいもの,労働者が納得しやすいもの)となりやすくなります。
調停がまとまらなければ,たいていは調停案とほぼ同内容の労働審判が出され,労働審判に対して当事者いずれかが異議を申し立てれば自動的に訴訟での解決が行われることになりますが,訴訟で争っても,裁判官(労働審判官)が関与し,権利義務関係を踏まえて出された労働審判の内容よりも自分に有利に解決する見込みが大きい事案はそれほど多くはありません。
労働審判に対して異議を申し立てれば,直ちに訴訟に移行しますので,うやむやなまま紛争が立ち消えになることは期待できません。
訴訟が長引けば労力・金銭等での負担が重くなり,コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。
これらの点が相まって,ある程度は譲歩してでも調停をまとめる大きなモチベーションとなり,労働審判制度の紛争解決機能を飛躍的に高めているものと考えています。
弁護士 藤田 進太郎