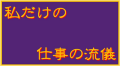「私だけの仕事の流儀」5人目は、熱い魂を持つ日本男児の登場です。
ニックネームは「吉田さん」です。
福岡市在住 38歳
現在は、介護講師として活躍中です。 はなそう屋主宰・福岡介護福祉学校
今回は、私からの半ば強制的な要望に応えて頂いて実現したインタビューでした。
私がどうしても吉田さんのお話を聞きたいと思ったのは、彼のブログを目にして、そこに書かれている事がとてもシンプルでありながら、深く考えさせられることが多かったことが一番の動機です。
これまで、ある勉強会では顔を合わせることがありましたが、二人だけでじっくりお話をするのは今回が初めてだったので、少しの緊張感と大きな期待感の中でインタビューを始めました。
私のイメージしていた通り、話を始めた途端に彼の熱い情熱が言葉に乗って心に入って来るのを感じながら、私もそれに応えようと熱い心で会話を楽しみました。
今回は、そのほんの一部を紹介します。
● これまで経験したお仕事・またはその一部
自動車整備工(約5年) 介護職(約10年) 介護講師(約4年)
● もっとも印象深い仕事と、その内容
介護士として利用者の最期をみとる時です。
私は今まで10名以上の利用者の死に向き合って来ました。介護の世界では多い方だと思います。
その中でも特に忘れられないのは、「もう今夜がヤマ」と医師に告げられていた利用者に、私は最期だと思って声掛けしに病室に赴き「また明日来るから待っててね。」と声をかけました。本当に大好きだった利用者に、1日でも長く生きてほしいという思いから出た言葉でした。
翌日、覚悟を決めて再び会いに行くと、その人は私を待っていてくれたのです。
そして、人生最後の約束を果たして下さったその30分後に、安らかに息を引き取られました。
● その仕事を振り返って、今思うこと
私は、介護の仕事は聖職だと確信していると同時に、その仕事に誇りを持っています。
介護という仕事は、人に真正面から向き合う仕事です。それは命を扱うことに直結し、時には人の死に向き合うことを意味します。
利用者の最期をみとる度に、人間の“生”を全うしようとする強烈な意志を感じてきました。
そういう瞬間に立ち会えること、人間の命を実感できることこそ、介護職が聖職である証だと思います。
● 忘れられない仕事での失敗談
介護の世界に身を投じて1年目のこと、ある女性利用者の愛情を受け止めてあげることが出来なかったことです。
99歳になるその女性は、どういう訳か私をとても気に入って下さり、会う度に「私とつきあって。」と言っては熱い視線を送ってこられましたが、当時の私はそういった時、頭ではすべてを受け止めてあげると分かっていても、実際にどういった応対をすればいいのか分からず、ただ仕事として冷静に受け流すような態度を取っていました。
しかし、その利用者がお亡くなりになり、自分の取った行動を思い返す度に、「自分は仕事(作業)はしかもしれないが、彼女に向き合ったのか?」という思いが出てきました。
彼女は、素直に愛情を口に出しては、私の気持ちを求めていたにも関わらず、私はその思いに応えるどころか、介護という作業だけをするのが精一杯だった。それは、本当に相手を満足させたことにはならないのではないか、と考えるようになりました。
今では、利用者との心のつながりを最優先に仕事に向かうことが出来ますが、そのおばあちゃんとの出会いは、今でも大きな教訓として心に残っています。
● 仕事で影響を受けた人
介護の世界では二人います。
まず、介護実習でお世話になった、カトリック系施設の生活相談員の方です。
彼女から介護士と利用者の関係性について学ぶことが出来ました。
その教えは、介護講師となった私にとって、受講者の方に最初に話す重要項目であり、セミナーや個別相談の基礎的な部分を担ってくれています。(詳しい内容は企業秘密ということで…)
そして、私が最初に介護の仕事に就いた時の先輩には、「介護のいろは」をじっくり学ぶことが出来ました。今でも、良き相談相手になって下さり、とても感謝しています。
● 仕事で楽しいと思う瞬間
利用者やその家族、さらに相談相手や受講者から、笑顔でありがとうと言ってもらえた時です。
介護の現場にいた時は、利用者の「お疲れさん!」という何気ない一言に、全てが報われるような気持ちになっていました。
● 今になって思う、仕事のために、やっておけば良かったこと
やっておけばと言うよりも、感情的な部分で「母親のような愛情」をもっと持ちたかったと思います。
先ほどの99歳のおばあちゃんとの関係も、自分がもっと母性を持っていたら、彼女を大きな愛情で包み込んであげることが出来たかもしれないと、今になって思います。
● ズバリ、仕事とは何か
仕事=プロフェッショナル
介護においては、全てを受け入れる大きく深い気持ちが先、技術だけでは追いつけない。
相手に合わせるのはプロではない。相手に徹底的に寄り添うのがプロの仕事である。
● 自分にとっての仕事の意味価値とは
仕事は自分で創るものだと思う。
私は「ゆっくりと、しかし着実に」という言葉が好きです。意志を貫くには決して焦らず、一歩、1センチ、心の決断を繰り返すことが大切だと思う。
● 未だ社会に出ていない若者へ、贈る言葉
「今ここ」の自分を感じよう。今、どんな自分になって何をするのかが重要。
そして、どんなことでも安心して語ることが出来る真の仲間を一人でも多く見つけよう。
きっとそいつが何か困った時に必ず助けてくれるし、自分も困っている仲間のために頑張れるはずだから。
★ 私だけの仕事の流儀
プロ意識を持つこと。「俺は一流だ」と自分の在り方を規定すること。
それは、自分に自信を持って行動すると同時に、自分を過信しないということ。
決して気を抜かず、深い愛情を持って仕事に向き合うことこそ、私だけの仕事の流儀です。
------------------------------
このインタビュー中、私は吉田さんから言葉と共に溢れ出る情熱を何とか受け止めようと必死になりながら、彼の介護職にかける誇りというものが、その言葉の強さ以上に熱く本物だと心に突き刺さったように感じていました。
そんな吉田さんの言う「プロ意識を持って相手に寄り添う」という言葉は、私自身に向けた熱いエールだと受け止めています。
また、彼は約2時間の話の中で、ほとんど介護現場の実情に対する愚痴はおろか、行政や制度に対する疑問や不満といった話をしなかったことも、後になってすごいなぁ~と感じた次第です。
私は当初、ある程度は現場の大変な実情の話が出てくると思っていましたが、彼の次元は既にそんな段階は通り越しており、今は介護講師としての立場から、そういう現場の受け止め方、認識の仕方を指導しているそうです。
私は仕事柄、現役の介護職の方や、辞めた方の再就職相談を受けることもしばしばあるので、自分なりに介護という現場がどれほど大変なのか、職員の方々がどれだけ頑張っているのか、頭では分かったつもりでいましたが、吉田さんの話を聞いて、そのイメージが大きく変わりました。
彼は、「介護職は聖職だ」と言い切りました。
それは、単なるプライドという言葉では収まらない、人間としての生きざまを仕事にぶつける彼の魂が籠った言葉でした。
出来れば、これから介護の世界を目指す若者たちに直接聞かせたい瞬間でもありました。
今後は、彼のような講師が多く育って行き、現場を改革してくれることを、心から願っています。
今回のインタビューで、私はキャリア支援のプロとして、介護のプロである吉田さんに尊い教えを頂きました。そして、人の人生や命と直結する現場で、日々ご活躍されている介護職の方々に改めて敬意を表したいという気持ちになり、この仕事に人生を掛けて取り組んでいる人たちの熱い思いを少しでも伝えたいという意志をもちました。
今、吉田さんは「はなそう屋」という場創りを新たに計画中で、近日にもオープンする予定だとお聞きしました。介護職に限らず、誰もが気軽に訪れ、本音でアウトプットしあいながら様々な学びを得る場にしたいと話してくれました。
私も是非参加してみたいと思っています。
話の後半に、彼は私に「こうちゃん。言い切ること、大事よ。」と笑顔で言ってくれました。
確かにその通りだと思います。
10歳も年下ですが、なんだか兄貴のような言葉にとても嬉しい気持ちになれたインタビューでした。
吉田さん、本当にありがとうございました。
最後に、彼の決め台詞を拝借して終わりたいと思います。
また会おう!!
2016.3 Youth worker・Support 「私だけの仕事の流儀」